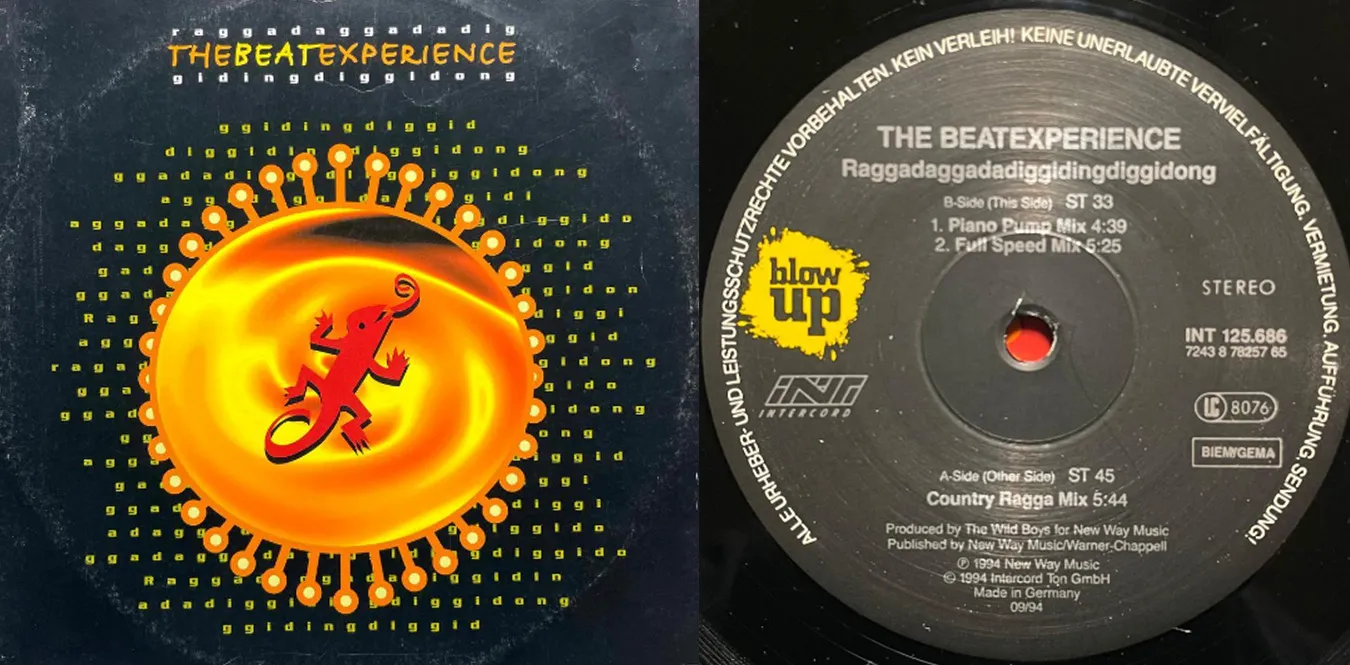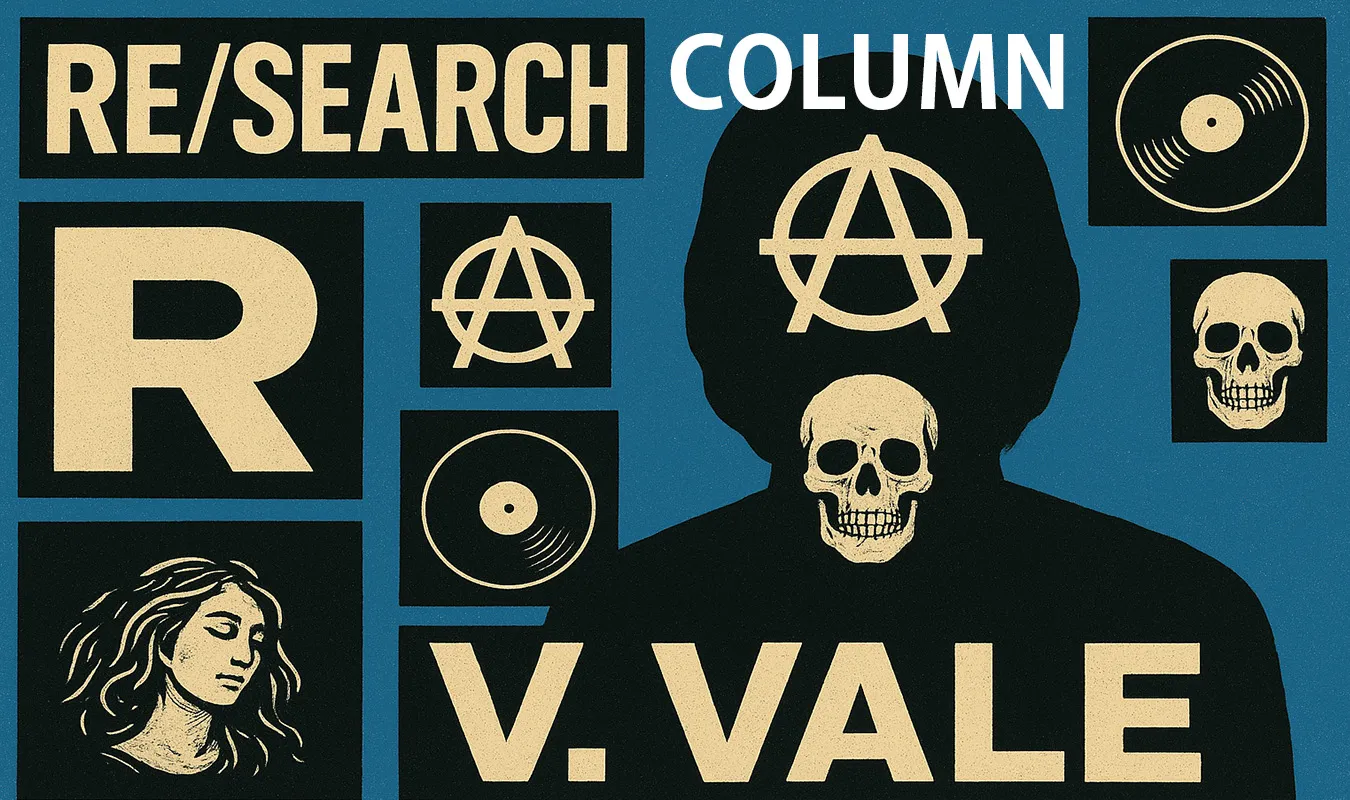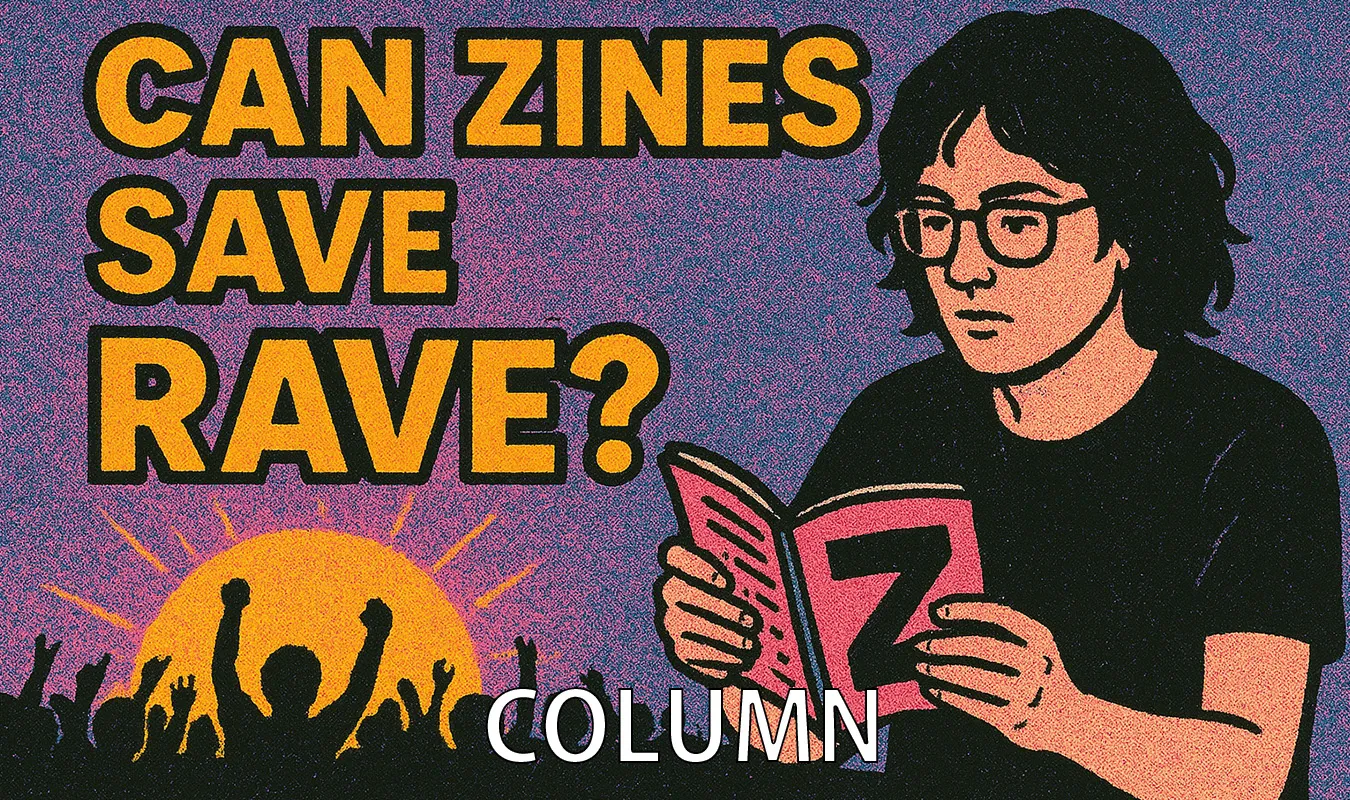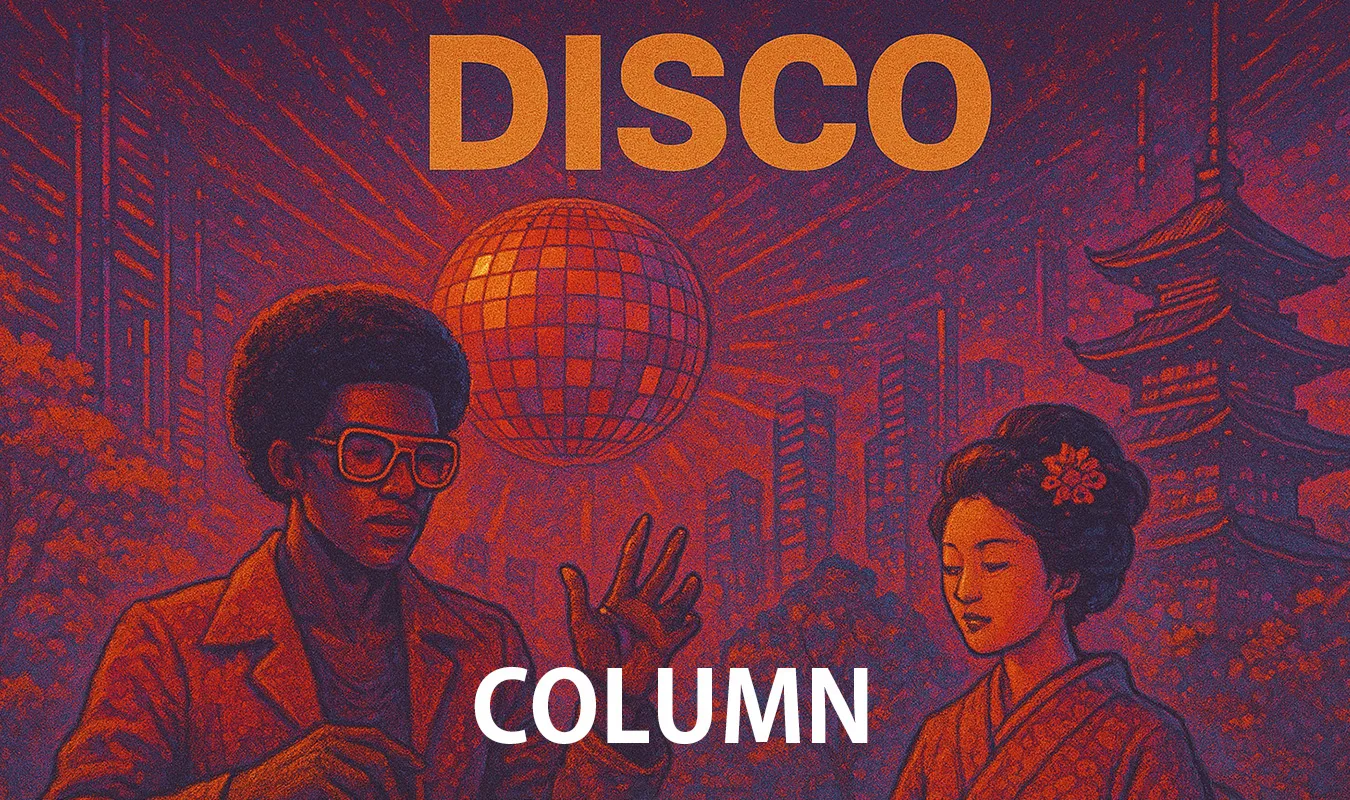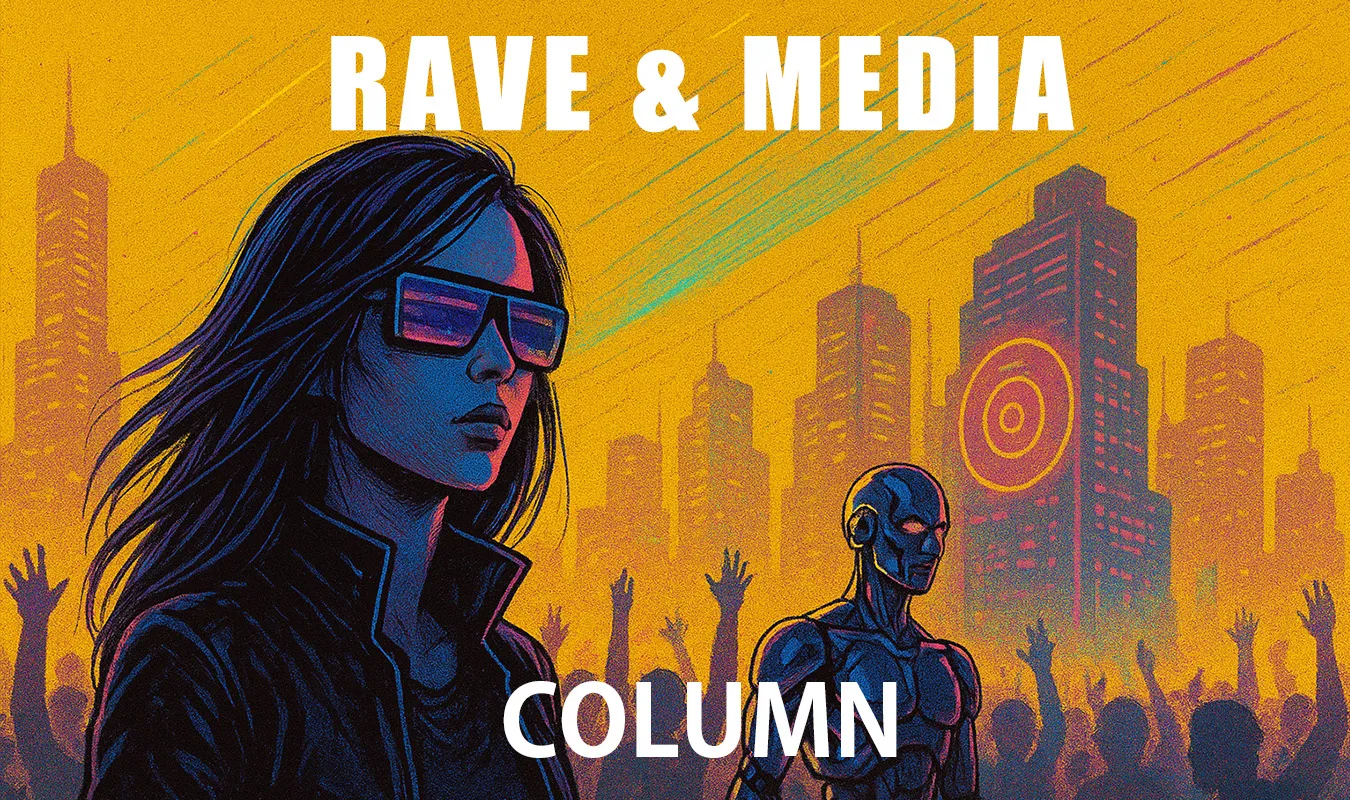
消えていくはずだった音楽
文:mmr|ジャンル:文化記録・メディア考察|テーマ:消えゆく音楽の痕跡を追う
レイヴ——それはその場限りの音と光の祝祭であり、基本的に「記録されること」を前提としないカルチャーだった。クラブでも野外でも、レイヴは「いま、ここ」で完結する体験であり、アーカイブされることなく忘却される運命にあった。
しかし21世紀に入り、YouTubeやSNS、アーカイブサイトの登場によって、「記録されなかったはずの文化」が、記録され、再評価され始めている。この変化は、メディア論的にも、音楽文化論的にも非常に興味深い。
レイヴというメディア不在の空間
● レイヴの本質は「反メディア性」
1990年代のレイヴカルチャー(とくにUK、ドイツ、オランダ、日本の地下レイヴ)は、メディアによる露出や記録を避けていた。
法的リスク(違法パーティーやドラッグ問題)
商業主義への反発(「売られる音楽」ではない)
その瞬間の「身体体験」が全て(記録より実感)
つまりレイヴは、あらゆる意味で「ライブ」だった。メディアとは距離を置くことが、美学であり、ポリティクスであった。
記録されなかった音楽文化
● 失われたものの例:
DJセット(当時は録音禁止が基本)
現場のVJ映像、照明演出
会場の空気、スモーク、匂い、温度
観客同士のノンバーバルな交感
レイヴは音源や楽譜ではなく、現象そのものが作品だった。したがって、その記録は通常の音楽アーカイブとは根本的に異なる課題を持っている。
誰がアーカイブするのか?メディアの変質
● アンダーグラウンドからの自発的アーカイブ
2000年代以降、以下のような試みが世界中で始まっている。
MixesDB、Discogs:セットリストやマイナー音源の情報集積
YouTube/SoundCloud:昔のミックステープや海賊録音のアップロード
Reddit、Forum、ブログ:当時の体験談の言語化
Zine/Podcast/ドキュメンタリー:DIY精神による保存運動
これらは、従来の音楽メディア(雑誌、レーベル、放送局)ではカバーされなかった領域を埋める草の根的アーカイブである。
クラブカルチャーの断絶と復元
● 日本でも記録が少ない理由
風営法により、クラブは“風俗営業”とされていた
写真・映像を撮ることが忌避されやすかった(特に渋谷系や六本木系)
雑誌メディア(『LOUD』『ele-king』など)も限られた範囲しか追えなかった
そのため、90年代の東京レイヴはほとんど“記憶の中”にしか存在していない。
● 近年の動き
クラブ文化保存のための市民運動(風営法の見直し)
「日本レイヴ・アーカイブ」やZineプロジェクトが立ち上がりつつある
渋谷WOMBやageHaの過去映像のアーカイブ化
海外は積極的なアーカイブ化が進行中
2007年設立の「Rave Archive」は、90年代レイヴ文化の記憶を保存・共有するアーカイブ。レイヴァーでありアーキビストの視点から、消えやすい文化を後世へ伝える。
アメリカとカナダ各地の1989〜2000年のオールドスクール・レイヴ・フライヤー・アーカイブ(Archive of Old Rave Flyers)も必見です。
デジタル時代の“非正規アーカイブ”の価値
今、私たちが頼りにしているアーカイブの多くは、「非正規」である。
・ ラベルもないミックステープ
・ VHSから取り込んだ低画質映像
・ 匿名ユーザーの記憶ベースのセットリスト
だが、それこそがレイヴの「場のリアル」を保存する最も生々しい手段でもある。制度化された文化遺産ではなく、地下で脈打つ“記憶の断片”の寄せ集めが、いま、ひとつの“文化遺産”になりつつある。
結論:記録されなかった文化をどう遺すか
レイヴは「体験の芸術」だった。それを記録し、後世に伝えることは、通常の音楽アーカイブの手法だけでは不可能である。
だが、記憶、断片、再解釈、そして“情熱”の蓄積が、それを可能にしつつある。メディアとともに育ってきた我々が、メディアを超えて「文化をどうアーカイブするか」を再考する時代がきている。
関連コラム
🔗 【コラム】 アシッド・ハウス:サウンドの化学反応と文化の変容
🔗 【コラム】 Psy-Trance(サイケデリック・トランス)の歴史と名盤・おすすめトラック10選
🔗 【コラム】 国境で変わる“ユーロの音”──イタリア、ドイツ、スウェーデン:三大制作国が生んだユーロ・ミュージックの違い