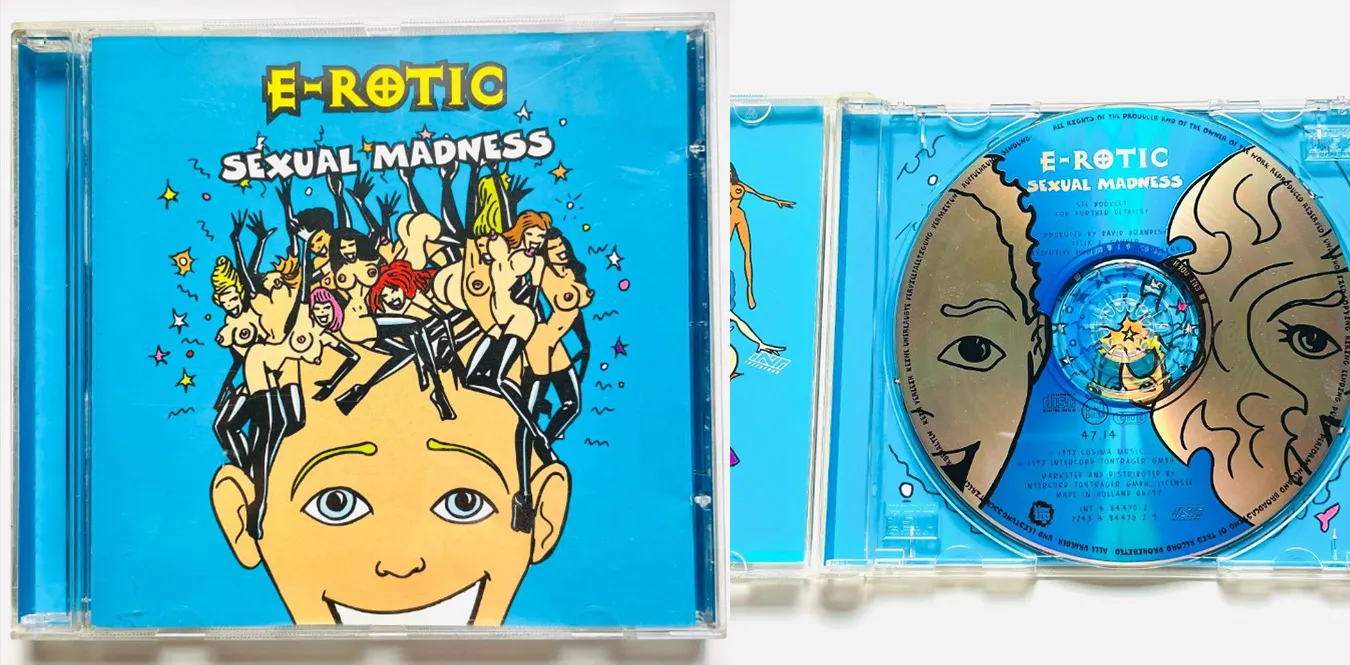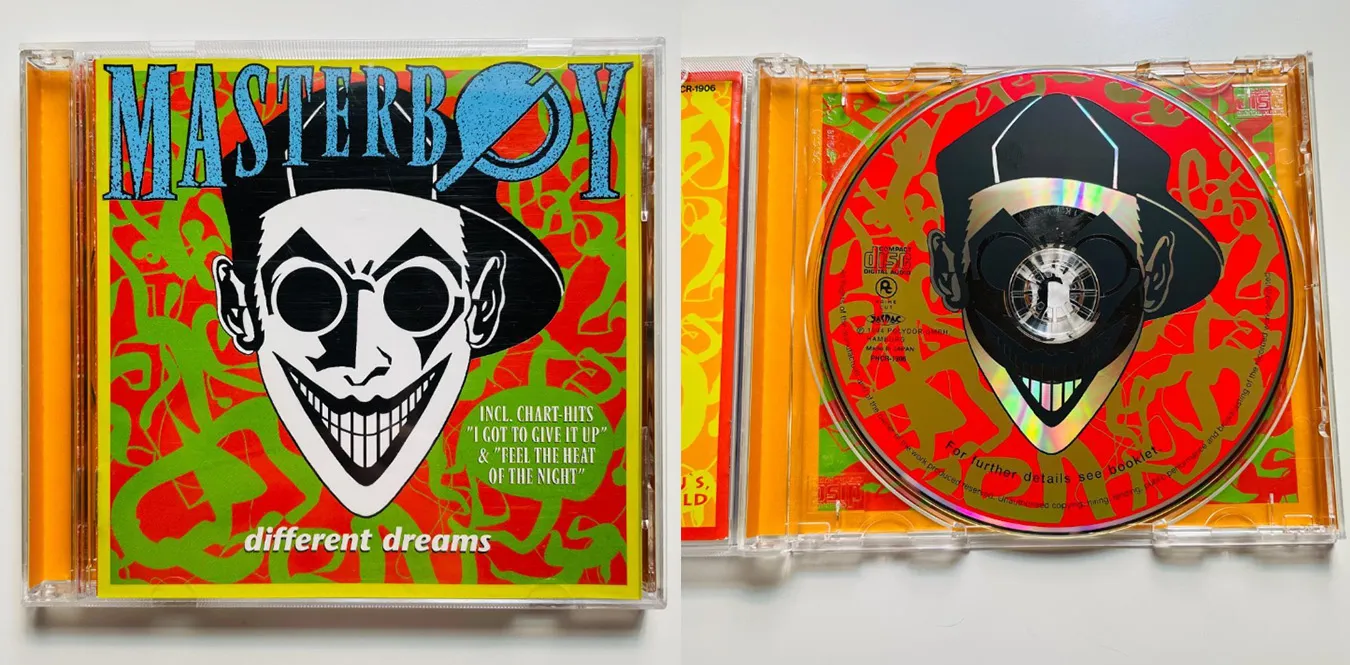ユーロはポップか?アンダーグラウンドか?
文:mmr|ジャンル:音楽文化考察|テーマ:90年代ユーロとクラブの接点を巡って
「ユーロビート」「ユーロダンス」などに代表されるユーロミュージックは、90年代のクラブやチャートを席巻したジャンルでありながら、しばしば“軽い音楽”という誤解を受ける。だがその実体は、ラジオを中心としたマスメディアと、地下で進行していたレイヴカルチャーの交差点で生まれたハイブリッドな存在だった。
この記事では、ユーロミュージックがクラブシーンと大衆音楽の間でどのような役割を果たしたかを、「ラジオ」と「レイヴ」という2つの文脈から探っていく。
ラジオとMTV:マスメディアによるユーロの拡張
● ダンスミュージックの“公共財化”
80年代末〜90年代初頭、ラジオ局は急速に「ダンスミュージック専門チャンネル」を増やし、ユーロミュージックが一般家庭へと浸透。特に西ヨーロッパでは「Radio NRJ(フランス)」「Radio 538(オランダ)」などが中心的役割を果たす。
● ユーロ・ダンスのテレビ浸透
MTV Europeの設立(1987)により、ビジュアルとセットで流通。
Real McCoy、Culture Beat、2 Unlimitedなどの高品質なMVは、アメリカの視聴者にも刺さり、逆輸入的にビルボードチャート入り。
● パラパラ、J-WAVE、スーパー・ユーロビート
日本ではJ-WAVEやBay FMが積極的にユーロをオンエア。
avexの「Super Eurobeat」シリーズと連動して、クラブとテレビCMを横断するユーロ現象を生んだ。
レイヴとサブカルチャー:アンダーグラウンドなユーロの顔
● レイヴ文化との接点
ユーロミュージックはもともと「Italo Disco」や「Hi-NRG」といったゲイ・クラブ発祥のサウンドを引き継いでいた。それが90年代に入り、レイヴカルチャーの爆発と共鳴。
ドイツ:Love ParadeやMaydayでユーロ・テイストのトラックが多数プレイ
イギリス:Hardbag、Euro-House系が90年代中盤のガラージ・セットに出現
オランダ:Speed GarageやHard Tranceとの境界が曖昧に
● ダークユーロ/ユーロトランスの発展
Commercial(商業的)な側面とは裏腹に、レイヴでは重厚なユーロ・トランスやIndustrial Euroも定着。
Cosmic GateやScooterなど、境界を突き破るアーティストが現れた。
音楽的交差点:ユーロ vs クラブ・トラックの技術的融合
| 要素 | ユーロミュージック | クラブカルチャー |
|---|---|---|
| 主体 | プロデューサー/作曲家 | DJ/オーガナイザー |
| 形式 | 楽曲単位(シングル志向) | ロングプレイ、ミックス志向 |
| 構成 | メロディ重視・AメロBメロ構造 | グルーヴ重視・展開は最小限 |
| 導線 | ラジオ、テレビ、CD | パーティ、フェス、ヴァイナル |
| 交流点 | 12インチリミックス、DJエディット、ダブミックスなどで連携 |
この2つの文化は相反するように見えても、ミックスCDやヴァイナル文化、リミックス市場を通じて緩やかに結びついていた。
交差点としての「ミックスCD」文化
● Pete Tong、Paul Oakenfold、DJ Boboなどの役割
DJとしてのキュレーションが“ユーロの選別眼”を提供
商業的パッケージでありながら、クラブ的センスが込められた選曲
● ユーロ→トランスへの橋渡し
Late 90’sにはユーロ・ダンスとトランスの接合点としてのユーロトランスが登場
ATB、Fragma、Darudeなどがポップとクラブの間を縫う音を提示
なぜ今、再評価されるのか?
2020年代に入り、TikTokやYouTubeで再発見される90年代ユーロ。その背景には、次のような要因がある。
メロディックで明快な構造が“即視聴時代”にマッチ
当時の「レイヴ感覚」が、現代のクラブ系プロデューサーにサンプリングソースとして再利用
オープンエアやフェスシーンにおいてノスタルジックでありながら機能的なサウンド
おわりに:ユーロは“ポップ”と“クラブ”の境界線で生きていた
ユーロミュージックは単なる「能天気なチャート音楽」でも、「硬派なクラブトラック」でもなかった。 その真価は、メディアと地下、メロディとリズム、システムと身体性のあいだでバランスを取り続けた音楽だったことにある。
ラジオで聴き、クラブで踊る。 それが90年代ユーロの最も“正しい”消費方法だったのかもしれない。
関連コラム
🔗 【コラム】 国境で変わる“ユーロの音”──イタリア、ドイツ、スウェーデン:三大制作国が生んだユーロ・ミュージックの違い

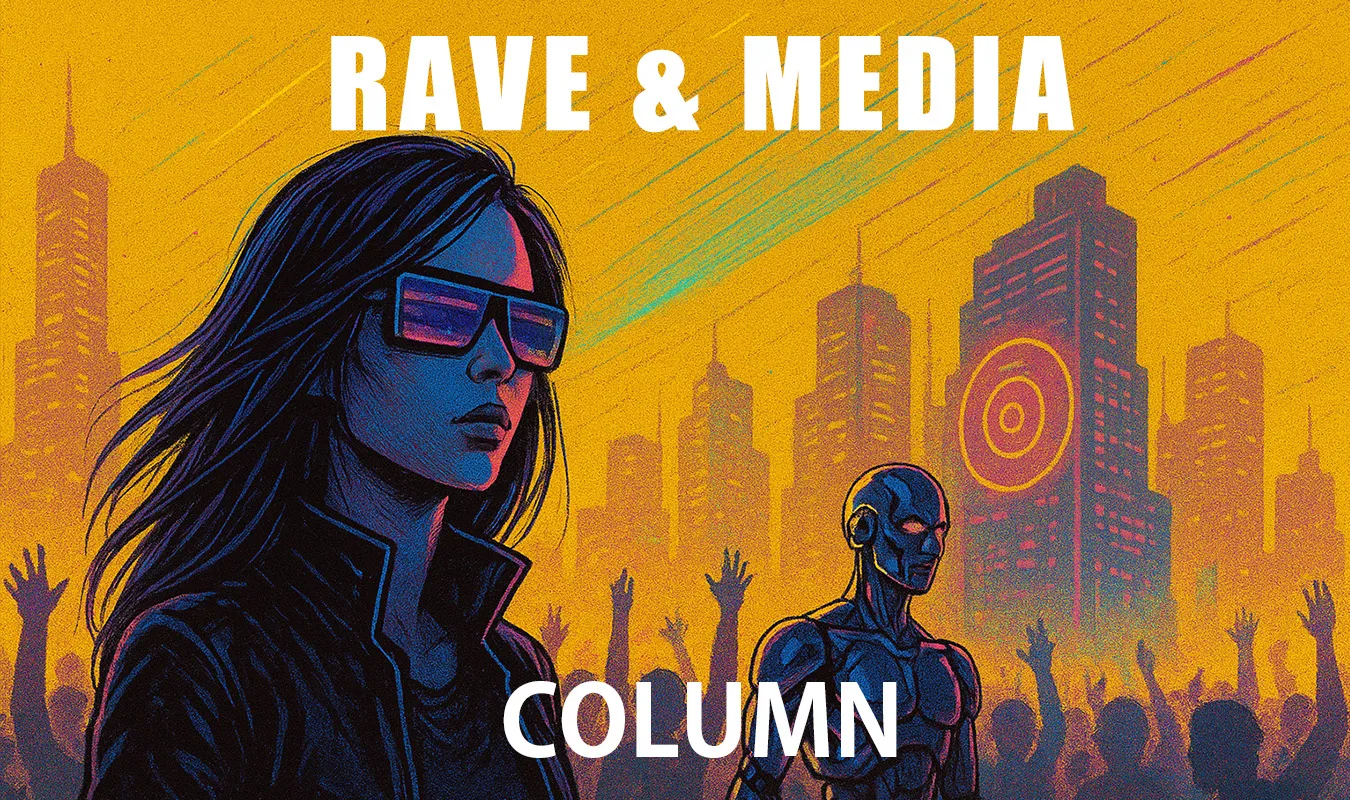

.webp)