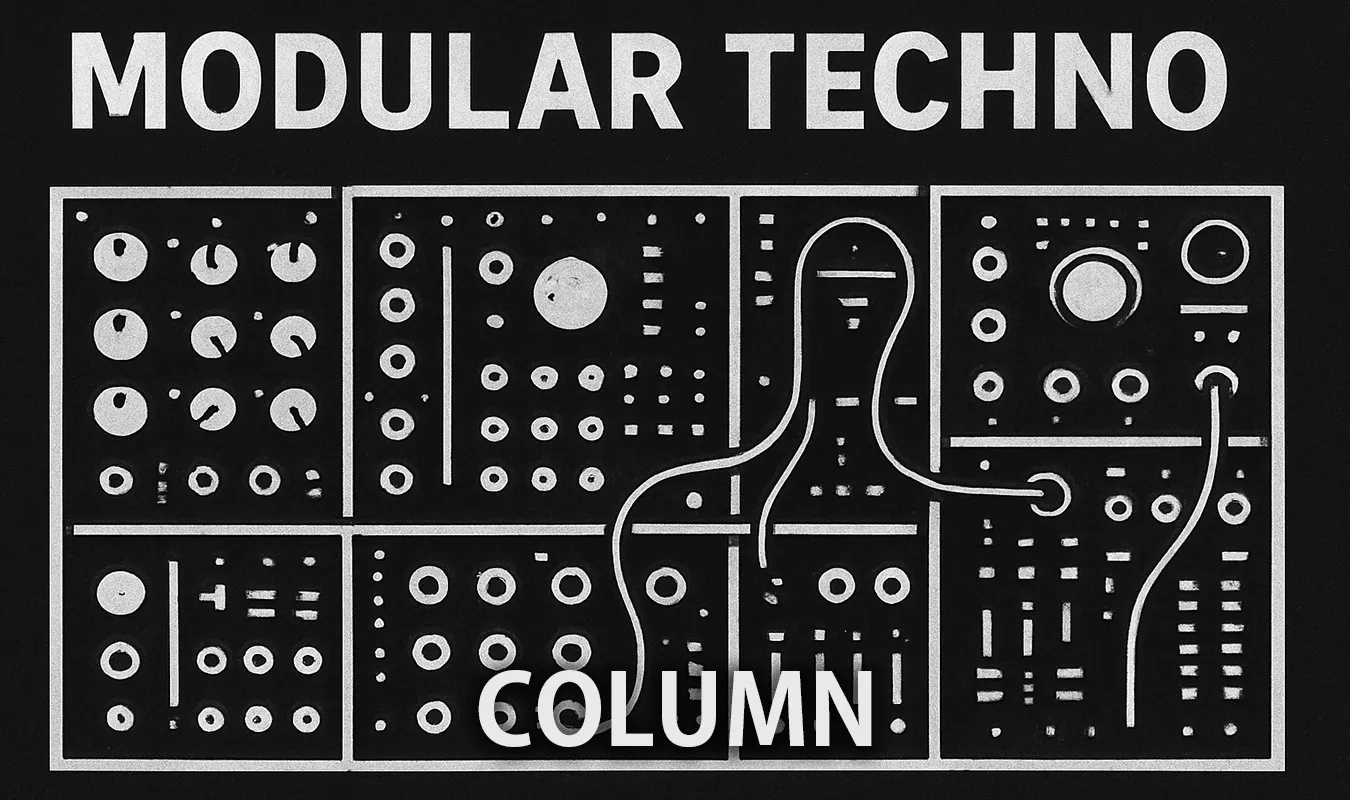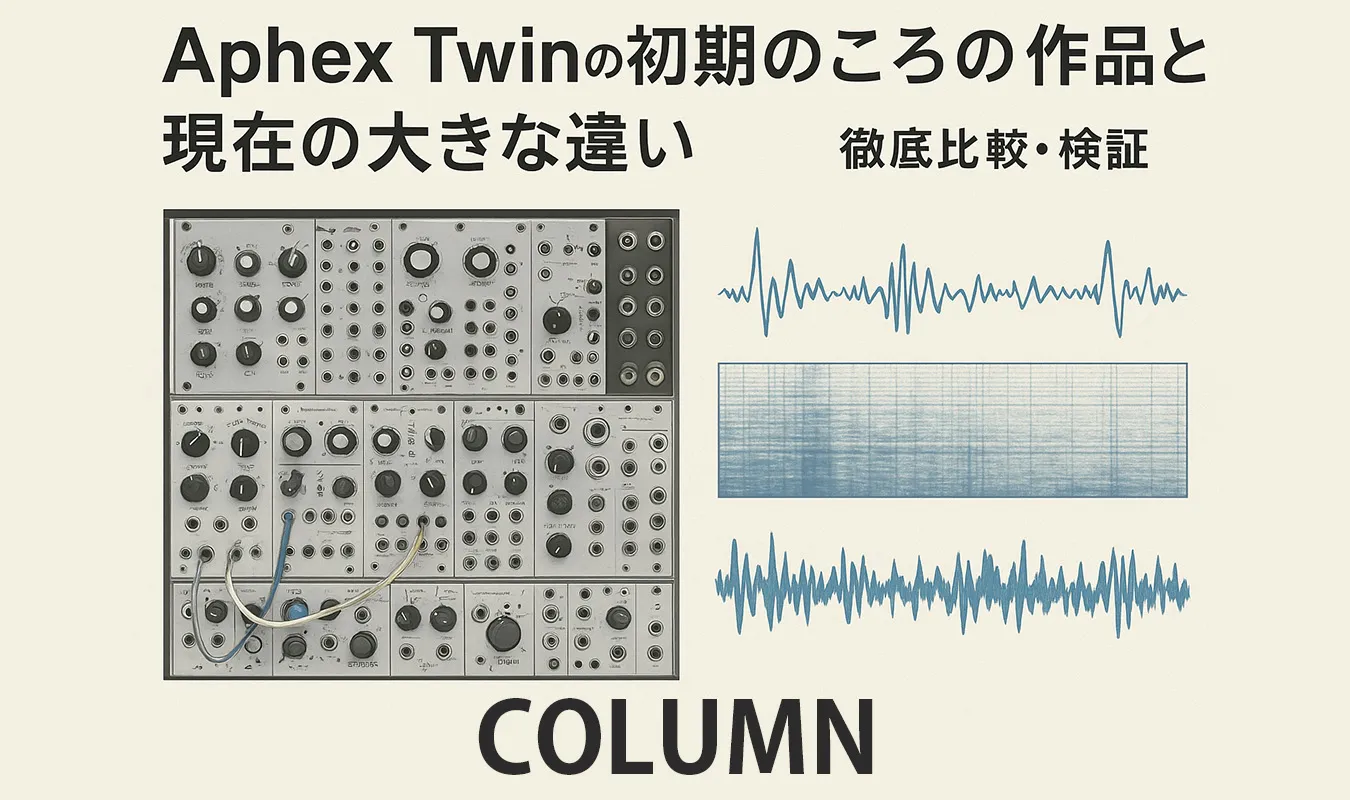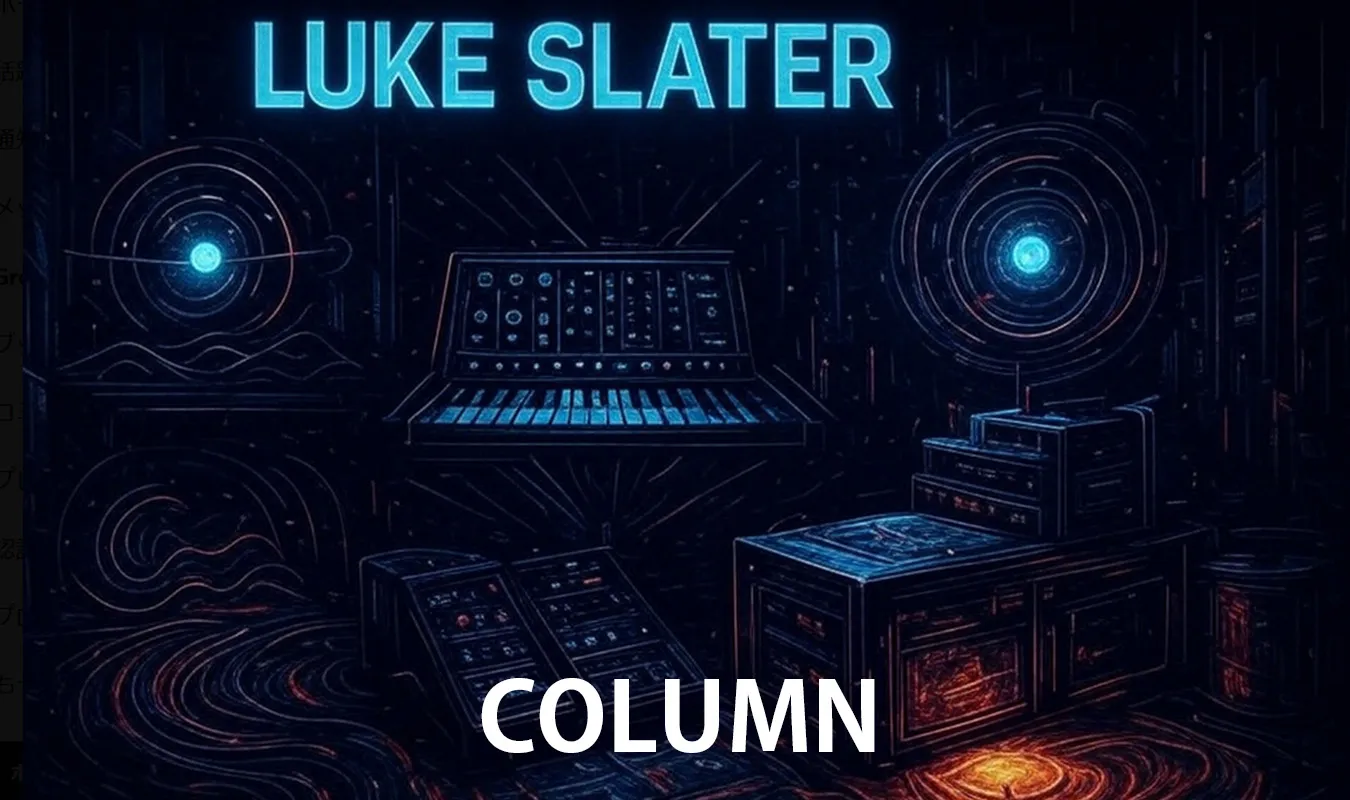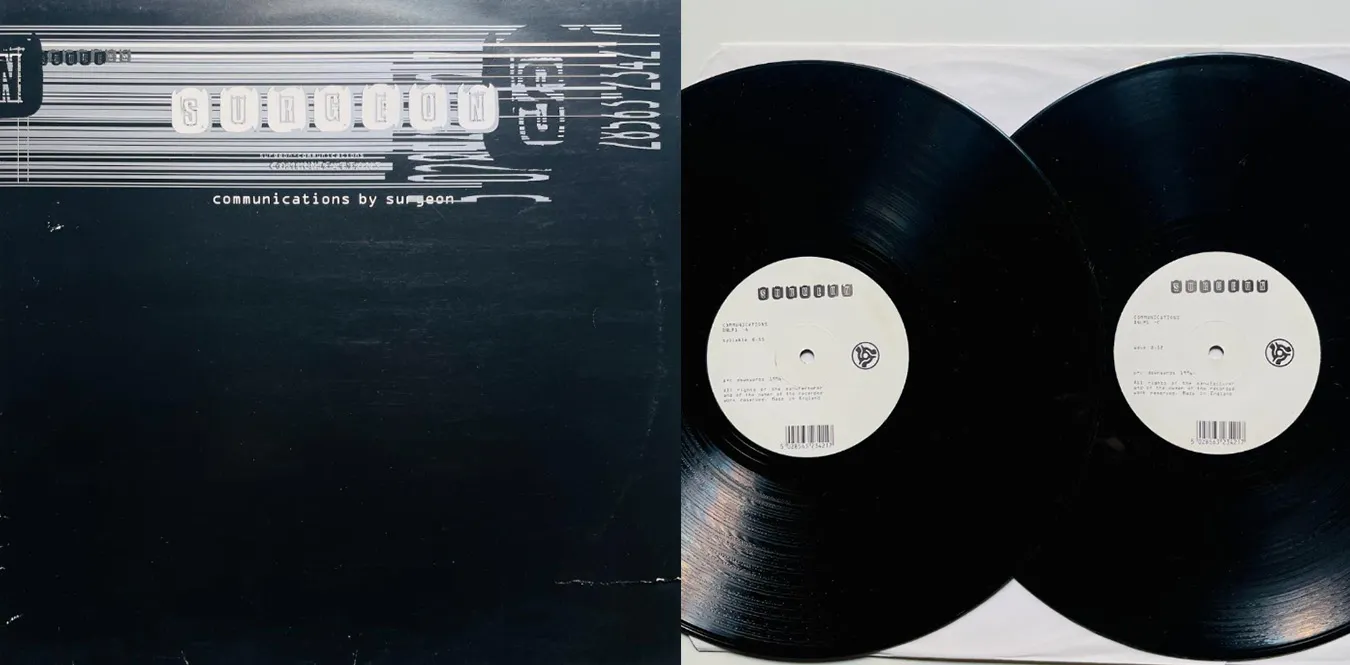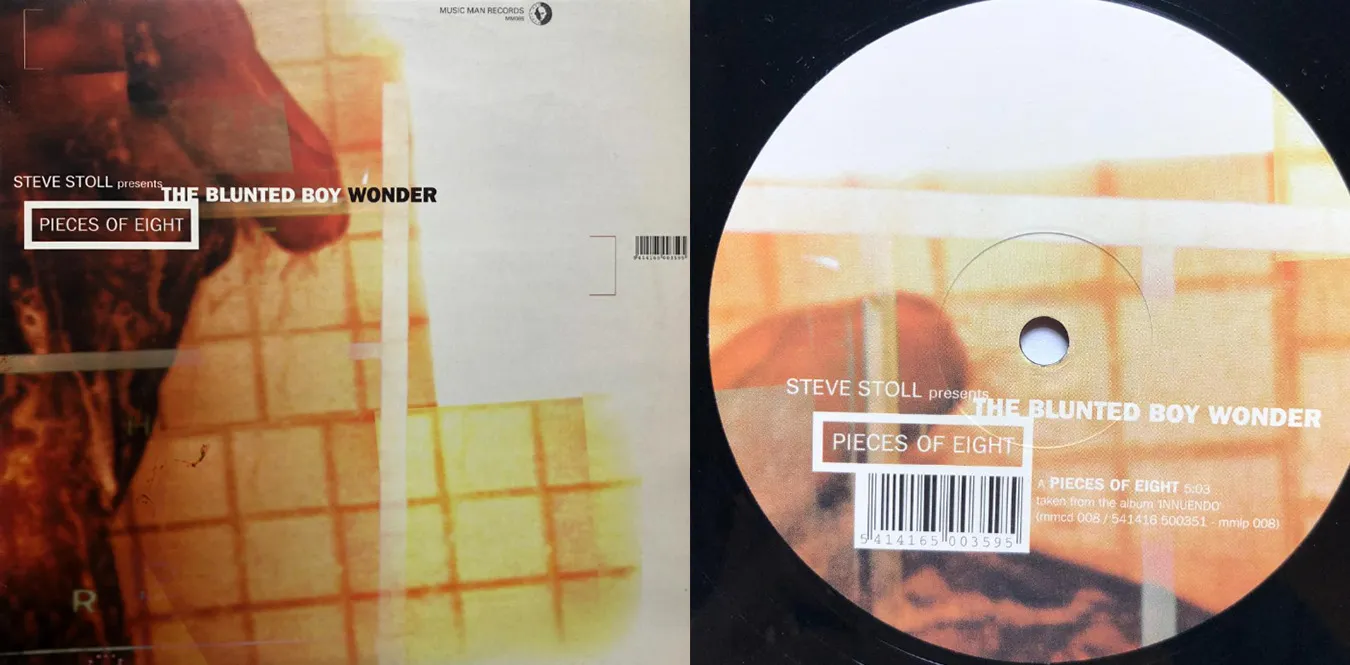序章 工場の影に育ったリズム——産業の残り香から
文:mmr|テーマ:UKの地下に根を張り続けるBlawanの冷たく、そしてなぜか人間的ビートについて
かつてイギリス北部の工業地帯は、蒸気と金属のにおいで満ちていた。
その残響を、Jamie Roberts――すなわちBlawan――は無意識に吸い込んで育ったのかもしれない。
Sheffieldから流れ出した電子音楽の血脈(Cabaret Voltaire、Warp Records、The Black Dog)は、
労働のリズムと都市の息づかいを同時に鳴らしてきた。
Blawanのビートには、鉄を叩くような打音と、湿った空気の圧がある。
それは単なるテクノではなく、産業の記憶の再生でもある。
彼がロンドンやベルリンを拠点にせず、UKの地下に根を張り続けていることも象徴的だ。
――音は、土地の重力を離れない。
そのビートは冷たく、そしてなぜか人間的だった。
Blawanの音楽は、鋼鉄の中に眠る「体温」の記録である。
第1章 Bohlaから始まる鉄の物語
2011年、R&S Recordsからリリースされた『Bohla EP』。
硬質でいて奇妙に柔らかいリズムが、クラブに“新しい重さ”をもたらした。
それは、ポスト・ダブステップの混沌から抜け出そうとするUKのクラブ・サウンドが
新たに見つけた「手触り」だった。
この頃のBlawanは、Rolandのリズムマシンやアナログ・フィルターをこよなく愛していた。
DAWの中ではなく、指先とつまみで音を掴む。
電子音を“演奏する”という身体的感覚こそが、彼の音を鉄のように熱くしていた。
第2章 “Why They Hide Their Bodies Under My Garage.”——恐怖と快楽の境界
2012年、世界のクラブ・シーンが震えた。
“Why They Hide Their Bodies Under My Garage.”
この一曲が、Blawanの名を決定的なものにした。
タイトルからして不穏。
歪んだヴォーカル・サンプルは、まるで地下室で呻く亡霊のよう。
ビートはひたすらに重く、狂気すれすれの執念で反復する。
だが、その中に奇妙な“快楽”がある。
聴く者の身体を圧迫しながら、同時に解放していく――それは恐怖と多幸が混ざり合う瞬間だった。
多くのDJがこのトラックをピークタイムに投下し、
クラブのフロアが一瞬、「暴力的な陶酔」に包まれたという。
この曲は単なるヒットではなく、
テクノに“感情なき感情”を蘇らせた象徴だった。
第3章 Karennという肉体——Pariahとの共鳴
Blawanのもう一つの顔、それがKarennである。
盟友Pariah(Arthur Cayzer)とのデュオは、スタジオというよりも「作業場」だった。
Sheworksレーベルを設立し、即興の機材ライブでヨーロッパ中を巡った。
ケーブルの山。
鳴り止まぬリズムマシン。
そこにはマシンの冷たさと、人間の汗が共存していた。
Karennのライブは「演奏」というより「鍛造」に近い。
鋼を叩く音、熱せられた空気、そして観客の体温。
すべてが溶け合う一瞬、音楽は“物質”になる。
第4章 Wet Will Always Dry——感情なき感情の記録
2018年、ついにBlawanはフルアルバム『Wet Will Always Dry』を発表した。
タイトルの示す通り、濡れて、乾く。
そこにあるのは、人間の感情の不完全な循環だ。
“Careless”“North”“Stell”――
どの曲も、冷たさの奥にわずかな温度を隠している。
金属のように無表情な音の中で、時折ふっと呼吸のような間が現れる。
そのわずかな「隙間」に、人間の感情が滲む。
音を削ぎ落とし、構造だけを残す。
そのストイックさが逆に、Blawanの“情緒”を際立たせている。
第5章 身体なきクラブ——2020年代のBlawan
パンデミックの時代、クラブは沈黙した。
しかし、Blawanの音は静かに変化していく。
“Under Belly”“Toast”などのトラックでは、以前よりも柔らかく、内省的な質感が漂う。
ハードウェアのノイズが、どこか優しく聴こえる。
クラブが閉ざされても、身体のリズムは消えなかった。
彼はモジュラー・シンセの中に“人間の呼吸”を見出した。
電子機器が心臓の鼓動を模倣する――そんな逆説的な時代の音である。
第6章 Blawanをめぐる人々と都市
Blawanの音は、ひとりの作家のものではない。
RegisやSurgeonが築いたUKインダストリアルの遺伝子、
Paula TempleやGiant Swanの暴力的なリズム、
そしてSkee Maskの繊細な粒子。
そのすべてが、彼の中で再構築されている。
ベルリンの無機質さよりも、ロンドンの湿度を。
デジタルよりも、手のひらの圧を。
Blawanは土地の重さを選び続けている。
それは、クラブが再び「場所」であり続けるための抵抗でもある。
第7章 SickElixir — 鋼鉄都市の崩壊と再生のリズム
Blawanの最新作『SickElixir』(2025)は、テクノの構造を解体しながらも、なお“人間”の存在を感じさせる稀有な作品だ。
ノイズと歪みが渦巻く中、リズムは崩壊寸前で均衡を保ち、声は意味を失って楽器へと変貌する。
“Rabbit Hole”で差し込む光、“NOS”での重低音の奔流。
その一瞬ごとに、Blawanの音は冷たさと情熱の境界線を行き来する。
背景には、友人の喪失や依存との葛藤など、彼自身の“生”が横たわる。
冷たい機械音の奥で鳴るのは、喪失と再生の呼吸音だ。
『Why They Hide Their Bodies Under My Garage.』で衝撃を与えた彼が、十余年を経て到達したのは、“破壊の中に宿る祈り”である。
テクノが抽象化し、クラブがデジタルに溶けていく今、Blawanはあえて“重力”を取り戻す。
鋼鉄都市の静脈を流れるビート。
その中で彼は静かに問う——音は、まだ人間でいられるか?
第8章 年表+ディスコグラフィー
| 年 | 作品名 | レーベル | リンク |
|---|---|---|---|
| 2011 | Bohla EP | R&S Records | Amazon |
| 2012 | Why They Hide Their Bodies Under My Garage. | Hinge Finger | Amazon |
| 2013 | Works The Long Nights | Sheworks | Amazon |
| 2018 | Wet Will Always Dry | Ternesc | Amazon |
| 2020 | Immulsion (Come To Me In Full Mix) | Ternesc | Amazon |
| 2025 | SickElixir | XL | Amazon |
付録:声の断片 — Blawanとその周辺が語る「音」と「身体」
「テクノを作るとき、僕は“曲”を作っていない。
ただ、リズムが空気を震わせる瞬間を追っているだけ。」
—— Blawan
「あの“Why They Hide Their Bodies…”を初めて聴いたとき、
クラブが一瞬“凍る”感じがした。
恐怖と快楽が同時にくる。
そんなトラックは、10年に一度だよ。」
—— Ben UFO(Hessle Audio)
「Blawanは“硬い音”の中にちゃんとした温度を持ってる。
それが他の誰とも違う。
工場で働いてるみたいに見えて、実は詩人なんだ。」
—— Pariah(Karenn)
「彼のスタジオに行くと、まず“無音”がある。
スイッチを入れる前の静寂が、すでにリズムを孕んでいる。
あの空間自体が“打面”になってるんだ。」
—— Paula Temple
「DJの現場でBlawanをかけると、
みんな一瞬“構え”る。
でも、そのあと笑うんだよ。
体が勝手に反応する。あれは理屈じゃない。」
—— Objekt
「Karennのライブを袖から見てたけど、
まるで鉄工所の中にいるみたいだった。
火花が飛んでるような音。
それでも観客の顔は、どこか優しかった。」
—— Surgeon(Anthony Child)
「クラブ・カルチャーがデジタルに溶けていく中で、
Blawanは“重力”を取り戻した。
音が地面に落ちる。
それが今、一番人間的なことだと思う。」
—— Resident Advisor ライター・コメントより
「音の中に“手”がある。
それがBlawanの音だ。」
—— 匿名DJ、Boiler Roomセット後の一言
「彼の音楽は“無機質”じゃない。
無機質を演じているだけだ。
そこに温度があることを、聴く人が感じ取る瞬間。
その一瞬のために彼は音を削っている。」
—— 音楽ライター・再構成コメント
終章 鋼鉄の祈り——踊ること、それは生き延びること
Blawanの音は、時に冷たく、時に荒々しい。 だがその奥には、確かに「人間の祈り」が宿っている。 踊るという行為は、都市のノイズの中で“生き延びる”ための儀式だ。 “Why They Hide Their Bodies Under My Garage.”がいまなお人々を惹きつけるのは、 そこに恐怖と救済の両方があるからだ。
鋼鉄のような音。 だが、聴くたびに体温が上がる。 Blawanは、冷たい世界に血を通わせるアーティストである。
「音は、身体の影だ」 ——Blawan(インタビューより)
付録:Blawanのモジュラー・セットアップ図解(2020–2025)
「すべての音は、触れることから始まる。」
——Blawan
Blawanスタジオの特徴メモ
| 区分 | 機材 | 用途 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Sequencer | Intellijel Metropolis | メロディ・リズム生成 | ハードな16ステップ感を重視 |
| Oscillator | Verbos Complex VCO / Plaits | メイン発振源 | アナログの歪みとデジタル粒子を併用 |
| Drum Synth | Moog DFAM | 金属的パーカッション | Blawanサウンドの“工業ノイズ”の核 |
| FX Chain | Analog Heat / Mimeophon / BigSky | 質感調整 | ドライブとリバーブで空間を構築 |
| Mixer | WMD Performance Mixer | リアルタイム構築 | Karennライブにも使用 |
| Recorder | RME Fireface + Ableton | 最終レコーディング | オーバーダブせず“一発録り”哲学 |
このセットアップが生む音は、完全に手作業で作られた電子音だ。 Blawanは「打ち込み」ではなく「演奏」をしている。 それゆえに、彼のテクノは“人間的な不安定さ”を残しているのだ。
「電子機器を操作するのではなく、交感する感覚なんだ」 ——Blawan(RBMA Interview)
後記
夜の街に響く重低音。
誰もがスマートフォンで音を消費する時代に、
Blawanは、“触れる音”を取り戻そうとしている。
スチールのような音の中に、人間のぬくもりがある。
その矛盾こそが、彼の存在理由だ。
「僕はテクノを信じてる。
まだ、誰かが踊ってるかぎりは。」
—— Blawan
関連コラム
🔗 【コラム】 テクノの発祥から現在まで ― 名盤と機材でたどる年代史
🔗 ドイツ・テクノ(German Techno)の系譜と現在 ― ベルリンから世界へ広がる音の美学