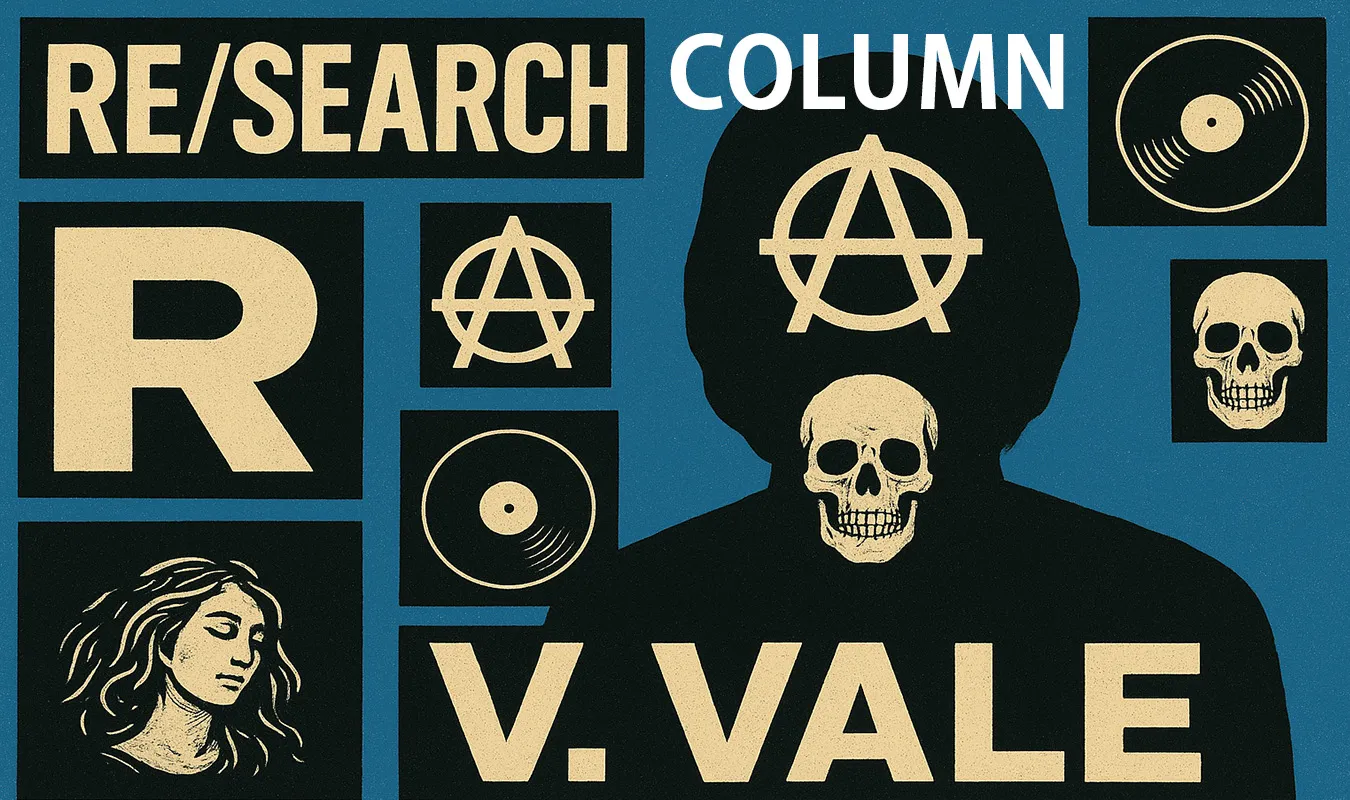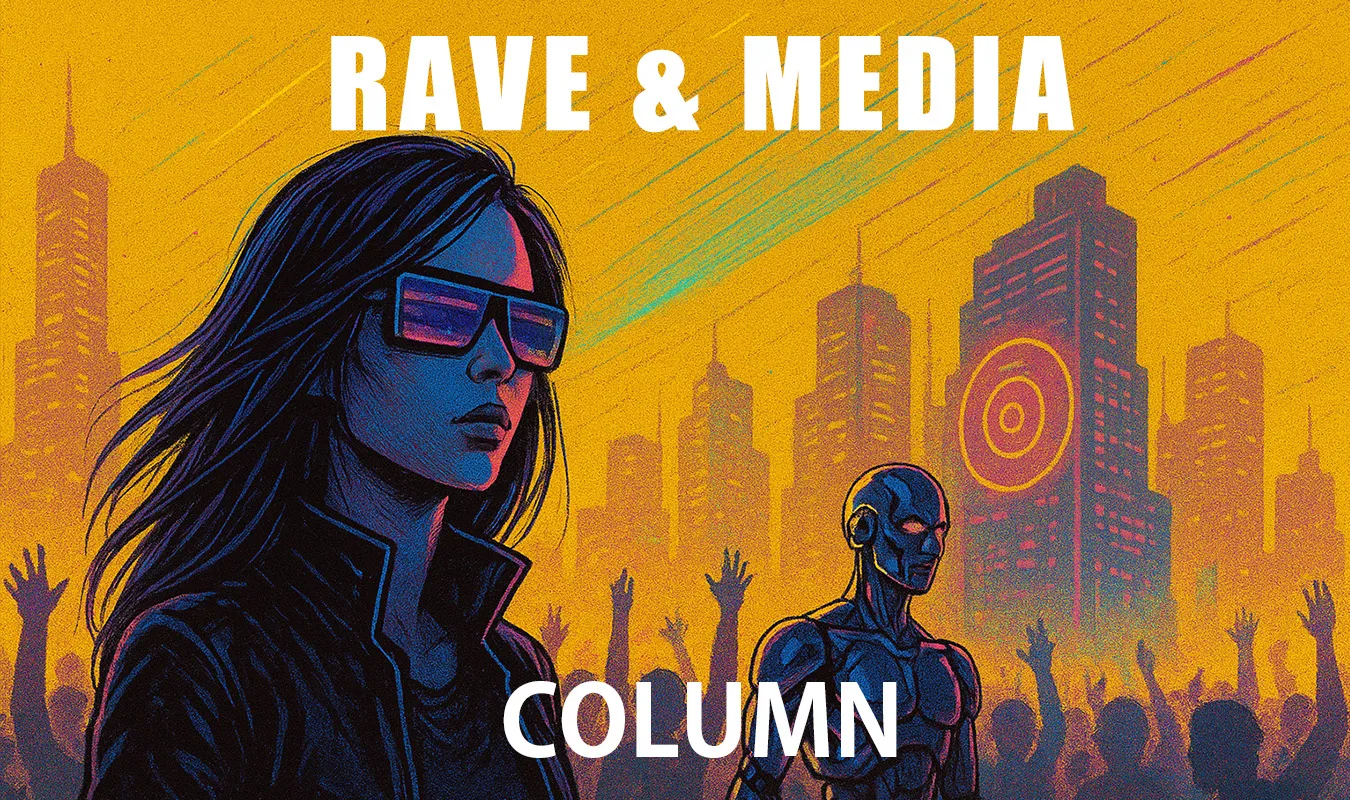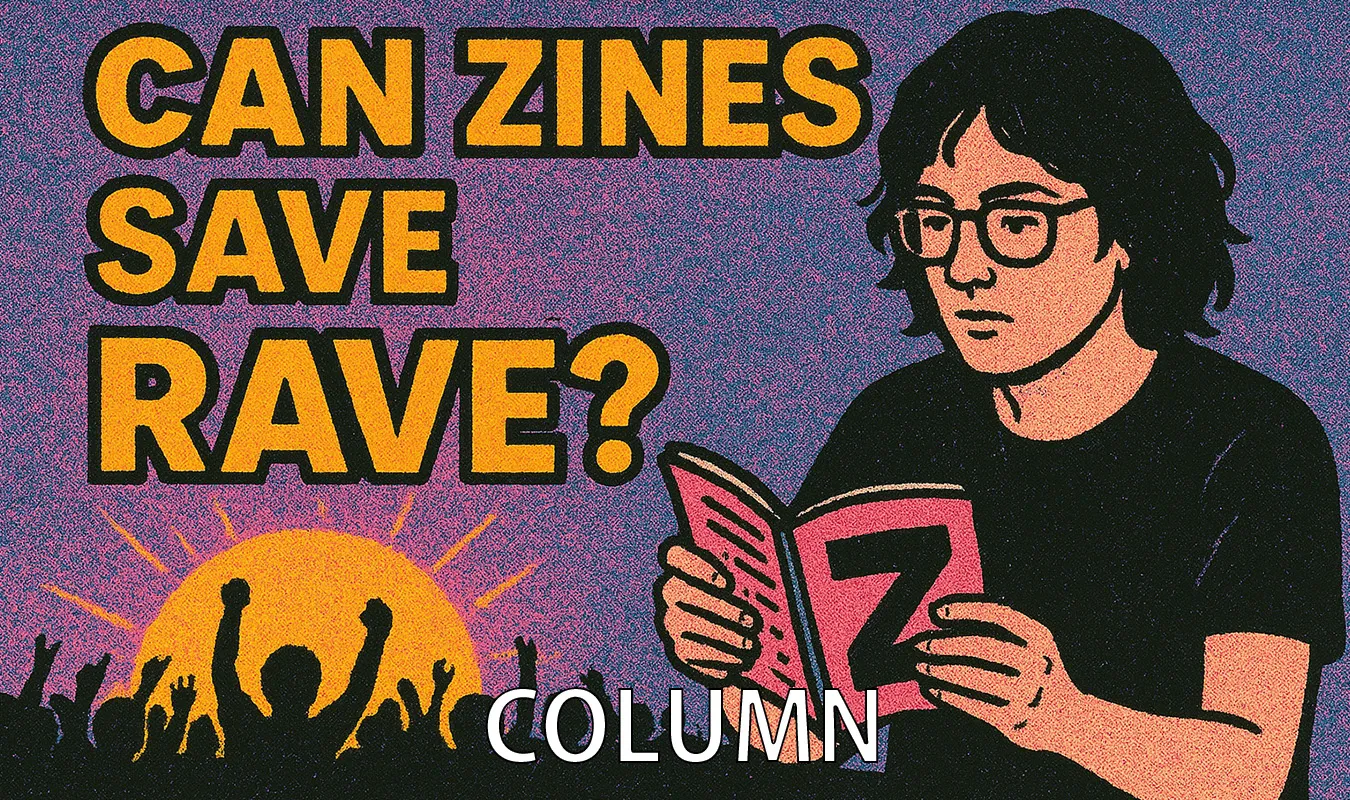
Zineは記録、Zineは表現、Zineはレイヴの延長
文:mmr|ジャンル:メディア文化・音楽アーカイブ|テーマ:記録されなかったカルチャーの保存装置としてのZine
Zine(ジン)とは、自分で自由に作る小さなメディア。90年代パンクシーンやフェミニズム運動、スケーター文化と同じように、レイヴシーンでもZineは存在してきた。レイヴは瞬間の祝祭であるが、それを記憶し、他者と共有する手段としてZineはとても有効だ。
紙に焼きつく熱狂
クラブのフロアで感じた身体の振動。郊外の林で朝まで続いた違法レイヴ。煙に包まれた赤外線の中で交わされた言葉なき共鳴。
それらは多くの場合、記録されていない。メディアに載らず、履歴に残らない。
だが今、その断片を拾い上げ、語り直す手段として注目されているのが「Zine(ジン)」というDIYメディアである。
Zineは、雑誌でも、日記でも、レポートでもない。だが、そのどれよりも“当事者の声”に近い。レイヴという本来、記録を拒む文化において、Zineは“記憶の補助装置”としての可能性を秘めている。
レイヴの記録不在という問題
レイヴは、「いま、ここ」の体験を重視する音楽文化であり、その性質上、メディアによる記録と相性が悪い。
| 記録されにくい理由 | 内容 |
|---|---|
| 写真撮影・録音のタブー | 90年代地下レイヴでは特に強く、機材の持ち込み禁止も多かった |
| 違法性・匿名性 | 警察や行政からの摘発を避けるため、記録を残さない |
| 一過性 | フロアの出来事はその瞬間限りで消える |
こうして、多くのレイヴの「本当の姿」は残っていない。音源、映像、記録がないために、文化の継承が断絶しかねない。
Zineとは何か?:個人がつくるオルタナティブな記録
Zineとは、「Magazine(雑誌)」の省略形で、誰でも自由に作れる自主制作出版物。印刷技術やWebに依存せず、紙とコピー機だけで成立する文化のかたまりだ。
Zineの特徴
- 編集者=読者=当事者という三位一体構造
- 手書き、切り貼り、コラージュなど自由な形式
- テーマは自由(音楽、政治、ジェンダー、体験記、エッセイなど)
- 商業主義とは無縁な“記録と共有”のための手段
Zineとレイヴの親和性
Zineは、記録されなかったレイヴの「体験を後から再構築する手段」になり得る。
具体例
| 手法 | 記録できる内容 |
|---|---|
| フライヤー再掲 | 当時のビジュアル文化を保存 |
| 現場のエッセイ | その場の心情・空気感を言語化 |
| セットリスト記録 | DJ名、曲順、現場の流れ |
| 危険や逸話の共有 | ドラッグ体験、検問回避、社会的緊張感 |
実例:世界のレイヴZineたち
(ドイツ)"] B --> B2["Rave Flyer Archives
(UK)"]
| 地域 | Zine名 | 特徴 |
|---|---|---|
| ドイツ | Datacide | サイコア、ブレイクコア、政治的文脈を含む批評的レイヴZine |
| UK | Rave Flyer Archives | 90年代フライヤー+パーソナルエッセイ |
デジタル全盛の時代に、なぜ紙で残すのか?
| 特徴 | デジタル | 紙(Zine) |
|---|---|---|
| 消える可能性 | リンク切れ・削除で消える可能性あり | 半永久的に手元に残る |
| コピー | 無限コピー可能 | 有限の物理コピー=“証拠物件”としての存在感 |
| 共有 | クリックで瞬時に共有 | 手渡し・郵送=身体的な儀式を伴う |
| 発信のしやすさ | 誰でも容易に発信可能 | 作るのに手間=作り手の思いが濃縮される |
レイヴが“身体的体験”であったように、Zineもまた“身体的メディア”なのである。
レイヴアーカイブ
2007年設立のRave Archiveは、90年代レイヴ文化の記憶を保存・共有するアーカイブ。レイヴァーでありアーキビストの視点から、消えやすい文化を後世へ伝える。
アメリカとカナダ各地の1989〜2000年のオールドスクール・レイヴ・フライヤー・アーカイブ
Oldschool Rave Flyer archive 1989-2000+ from all over the US & Canada
By Ernie Villalobos
結論:Zineは記録できなかった文化を継ぐ鍵
Zineは商業でも公的記録でもない。だが、それゆえに、“誰も記録しなかったはずの瞬間”を残すことができる。それは日記であり、報告書であり、証言であり、ラブレターでもある。
レイヴ文化の多くが失われていく中で、Zineという形で遺された記憶は、後世のリスナーやダンサーにとって、文化の輪郭を再発見する貴重な断片となるだろう。