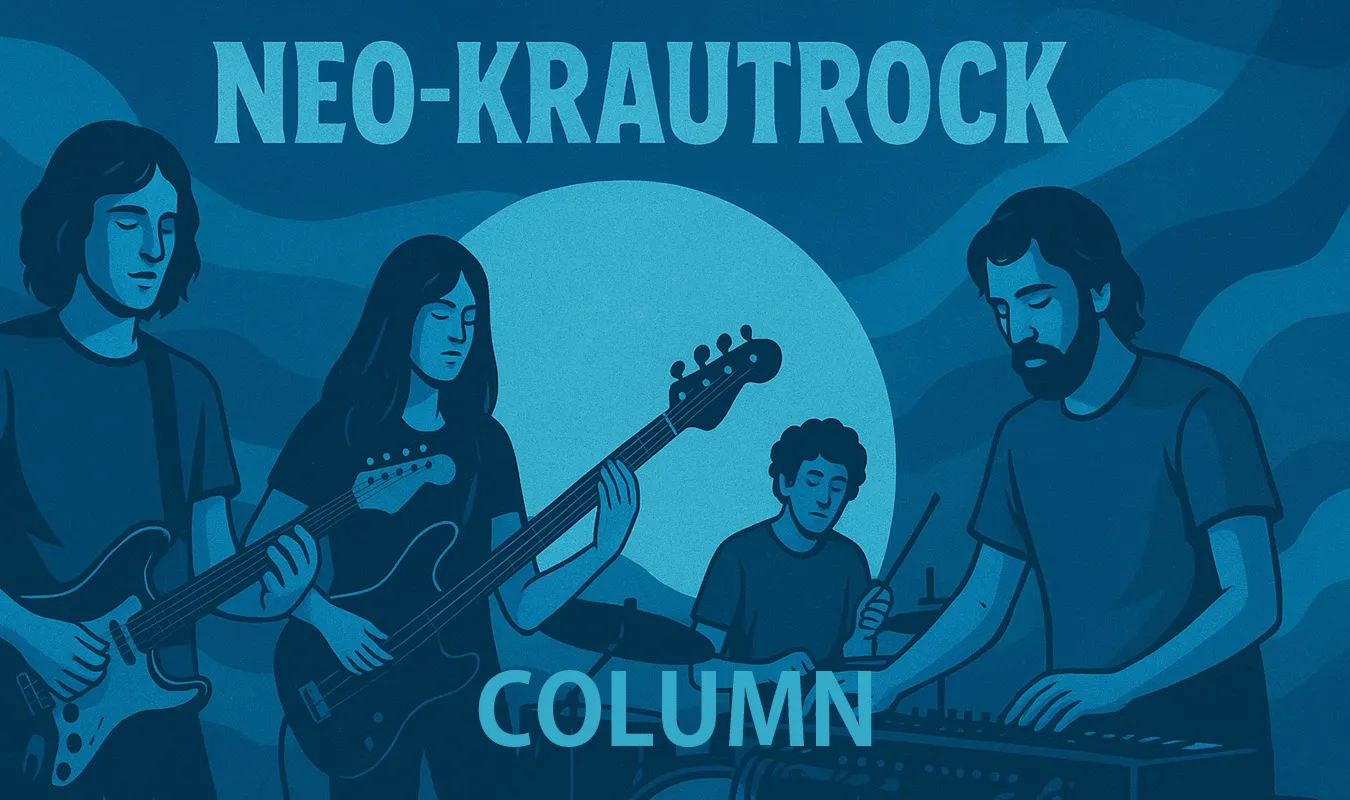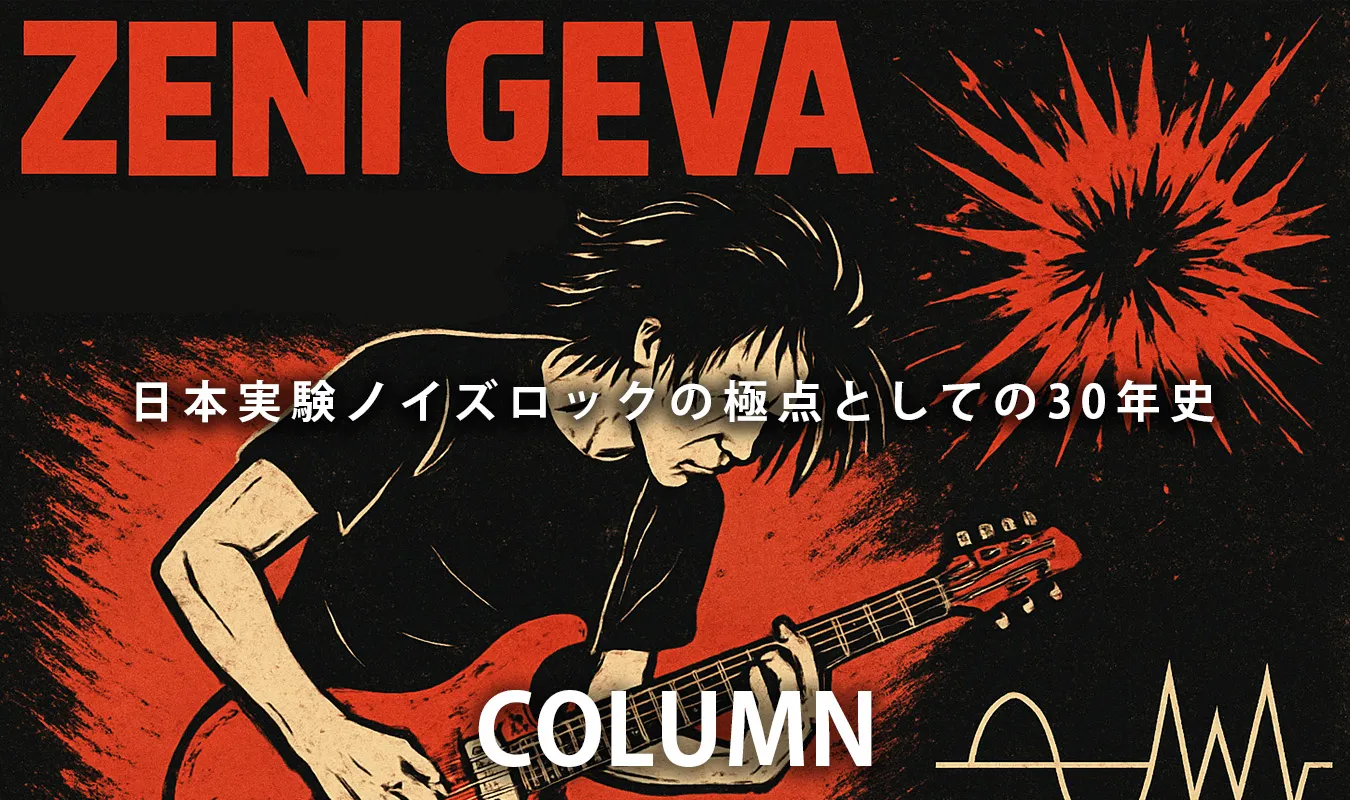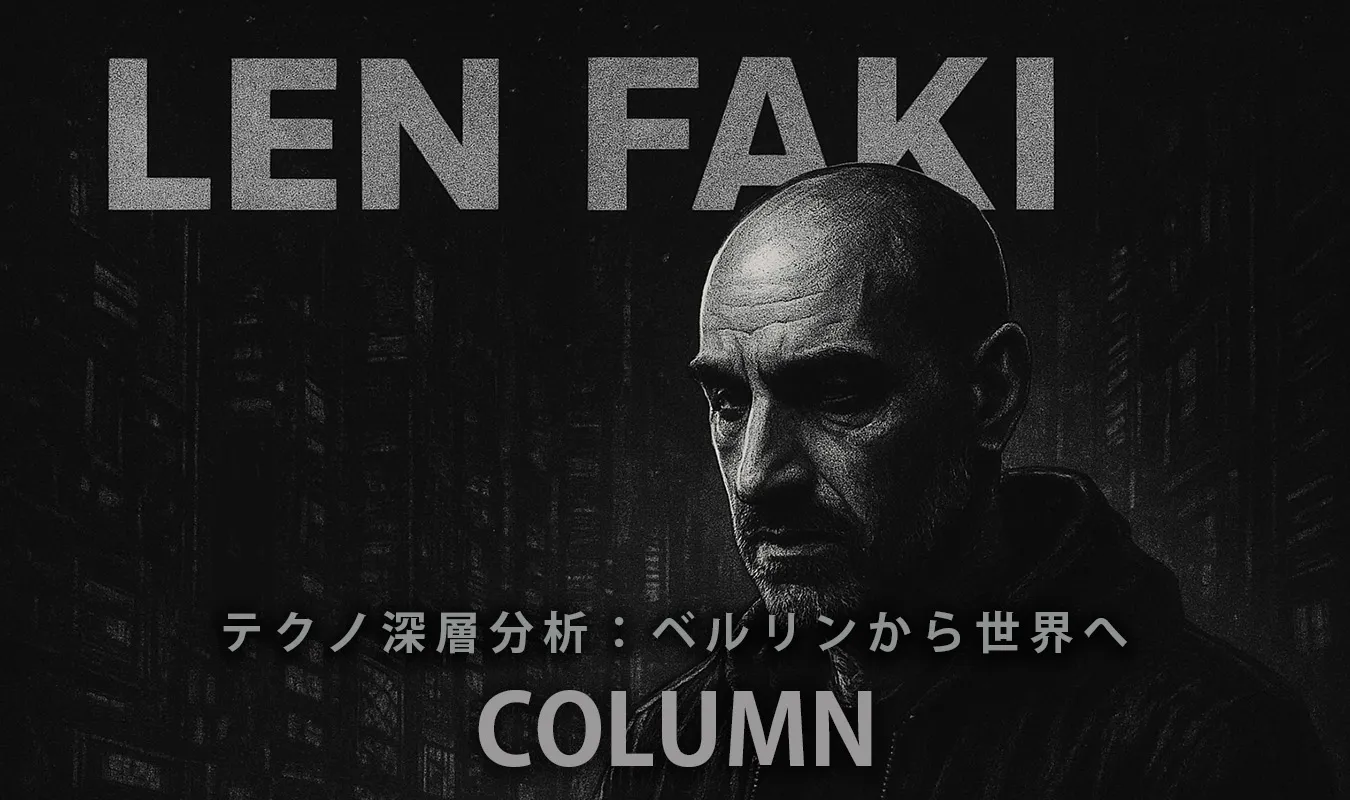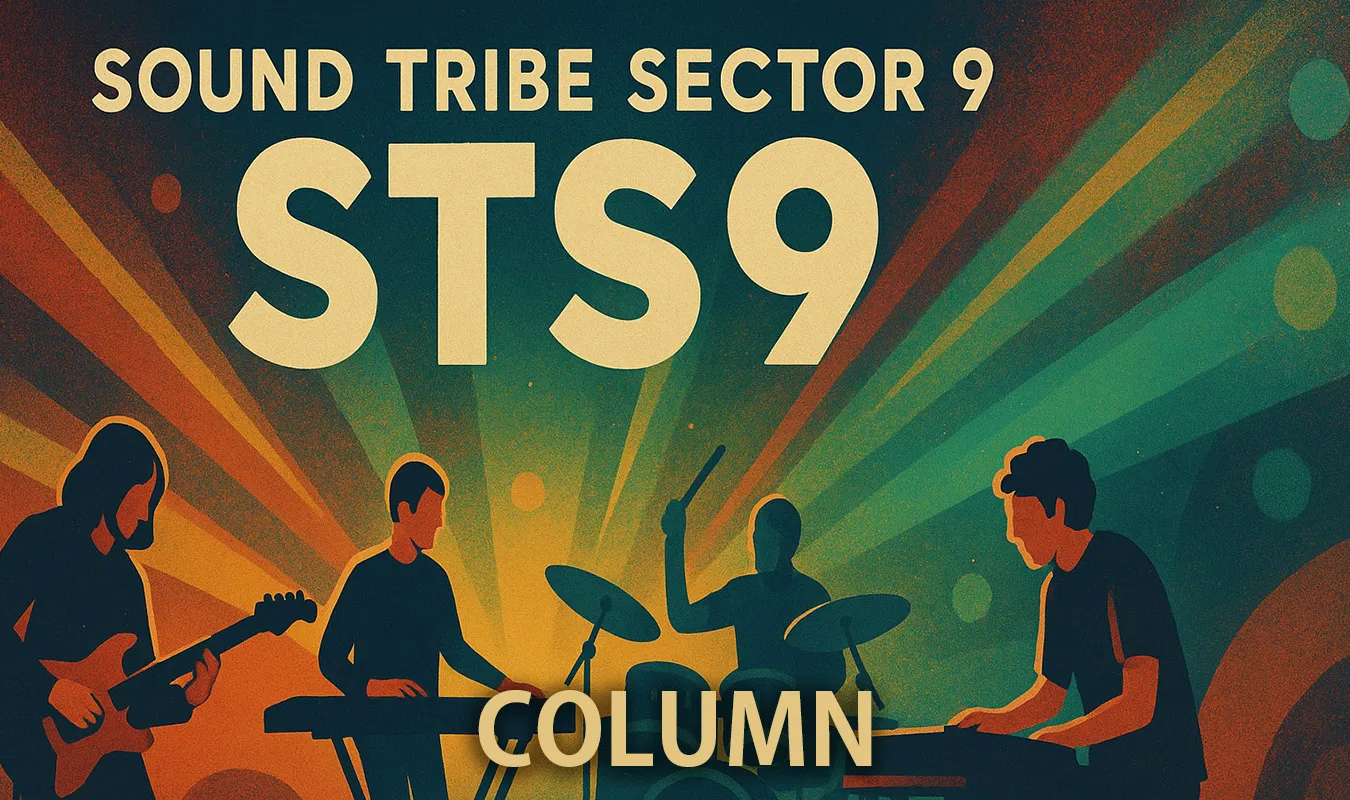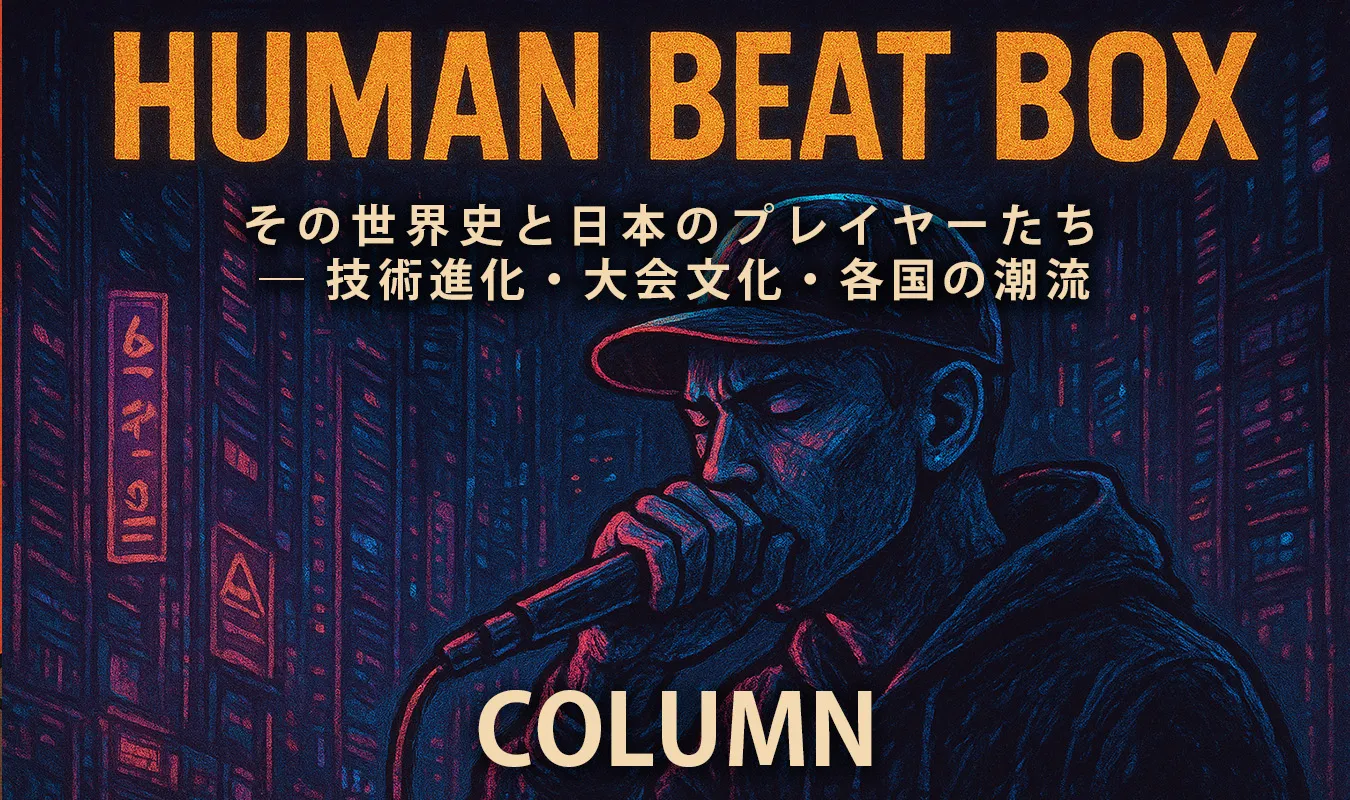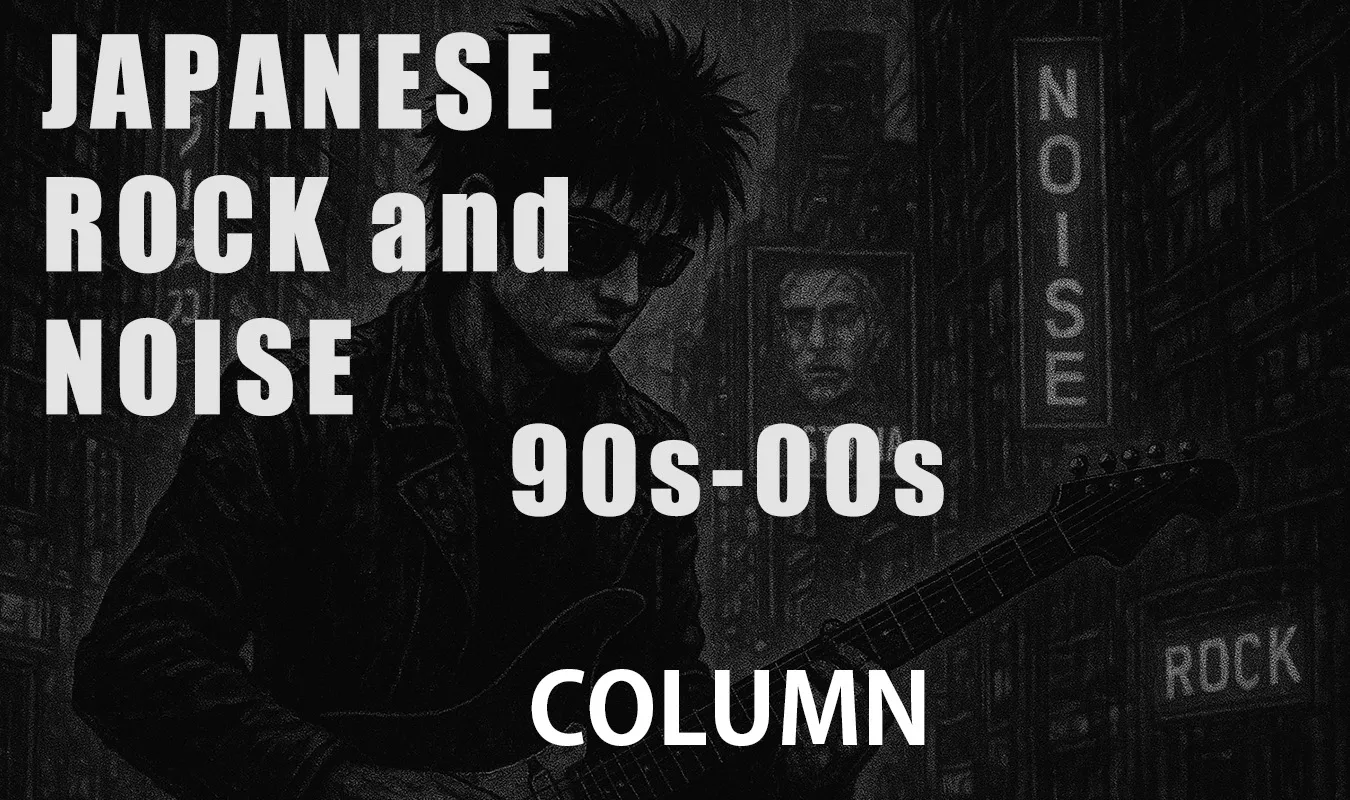
90年代〜2000年代の日本アンダーグラウンド・ロックとノイズの交差点
文:mmr|テーマ:1990年代から2000年代の日本のアンダーグラウンド音楽シーンの世界的な注目
1990年代から2000年代は、ノイズ・ミュージックの最盛期であると同時に、オルタナティブ・ロックやアヴァンギャルド・パンクとの交差点としても機能しました。
特に灰野敬二、メルツバウ(Merzbow)、非常階段、Melt-Banana、Boredoms、暴力温泉芸者といったアーティストは、既存の音楽ジャンルを破壊し、新たな表現領域を切り開きました。
日本アンダーグラウンドの熱狂
灰野敬二率いる Fushitsusha、秋田昌美の Merzbow、山塚アイと山本精一のBOREDOMS、インキャパシタンツや暴力温泉芸者といったグループは、従来のロックやパンクの枠を破壊し、ノイズと実験精神を融合させた音世界を築きました。
またこの時期は、インディーレーベルの台頭、国際的なフェス出演、アメリカやヨーロッパのアンダーグラウンドとの交流も加速。さらには映画やサウンドトラック制作、後年の AI音楽生成 にまで影響を及ぼす先鋭的な活動が展開されました。
シーンの特徴
- 灰野敬二: フィードバックと即興演奏による「音の儀式」。
- メルツバウ: アナログ機材からラップトップ・ノイズへと移行しつつも、アニマルライツや菜食主義思想を反映。
- 非常階段: 「ノイズ・バンド」と「パフォーマンス・アート」の境界を曖昧にした存在。
- Boredoms: サイケデリックとノイズを融合させ、米国オルタナシーンにも影響。
- Melt-Banana: ハードコアの速度感とノイズ的質感を組み合わせた「ナノ・コア」。
各バンドの特徴・変遷・逸話
灰野敬二
- 特徴: ギター、ヴォーカル、フィードバックを駆使した「音の儀式」。即興演奏を軸に、宗教的・呪術的とも形容される音世界。
- 変遷: 1970年代のソロ作品から、90年代以降はFushitsushaなどバンド形態でも活動。即興演奏の枠組みを超えた持続的探求を続ける。
- 逸話: ライブ前にギターの弦を全て張り替え、儀式のように音を放つことから「サウンドシャーマン」と呼ばれる。
| アルバム | 特徴 | リンク |
|---|---|---|
| Watashi Dake? (1981/再発1998) | 初期代表作。孤高の歌声とギターのノイズ的表現 | Amazon |
| Fushitsusha – A Death Never To Be Complete (1997) | 圧倒的即興演奏とフィードバックの海 | Amazon |
Merzbow(メルツバウ)
- 特徴: 「ノイズ・ミュージック」の代名詞。アナログ機材のカオティックな轟音から、90年代後半以降はラップトップへ移行。
- 変遷: 80年代はカセットテープ作品、90年代にCDリリースで国際的評価。2000年代には「環境保護」「アニマルライツ」を音に込める。
- 逸話: アルバム『Pulse Demon』は海外で「最も聴き続けられないアルバム」と呼ばれつつ、ノイズの金字塔とされる。
| アルバム | 特徴 | リンク |
|---|---|---|
| Venereology (1994) | ノイズ+デスメタル的要素。エクストリームの極み | Amazon |
| Pulse Demon (1996) | ハーシュノイズの決定盤。金属的轟音が持続する圧倒的作 | Amazon |
| Merzbeat (2002) | 4/4ビートとノイズを融合。クラブ的感覚を持つ異色作 | Amazon |
非常階段
- 特徴: 世界初の「ノイズ・バンド」。ノイズ演奏に加えて過激なパフォーマンス(食品投げ、火花、裸の乱舞)で伝説化。
- 変遷: 80年代に活動開始、90年代にはライブ・アルバム中心で記録される。2000年代以降はアイドルとの共演など実験的活動を展開。
- 逸話: ライブで「鶏を解体する」といった行為が海外メディアで大きな議論を呼び、社会的スキャンダルとして扱われた。
| アルバム | 特徴 | リンク |
|---|---|---|
| 蔵六の奇病 (1980) | 初期の暴力的ノイズの記録 | Amazon |
| 雑音伝説 (2014) | メルツバウ、インキャパシタンツのメンバーが全て参加し、非常階段とのセッション音源 | Amazon |
Boredoms(ボアダムス)
- 特徴: ノイズとサイケデリック、ハードコアを融合。アート性とカオスを同居させたバンド。
- 変遷: 初期はノイズ・パンク的、90年代に『Super æ』『Vision Creation Newsun』でポリリズムとサイケ志向へ。
- 逸話: 2007年7月7日にNYブルックリンで「77 Boadrum」を開催。77人のドラマーを指揮する伝説的イベント。
| アルバム | 特徴 | リンク |
|---|---|---|
| Pop Tatari (1991) | ノイズとハードコアの狂気的融合 | Amazon |
| Super æ (1998) | サイケ・ポリリズム的な中期代表作 | Amazon |
| Vision Creation Newsun (1999) | スピリチュアルでサイケな音像 | Amazon |
Melt-Banana
- 特徴: 超高速ハードコア+ノイズ。ヴォーカルYasuko O.のキュートで切り裂くような声が特徴。
- 変遷: 90年代初期に結成、Steve Albiniのサポートで海外進出。2000年代はより電子的で構造的なサウンドに変化。
- 逸話: 海外ツアーでジョン・ゾーンに絶賛され、アメリカのオルタナシーンで「日本の最速バンド」としてカルト人気を獲得。
| アルバム | 特徴 | リンク |
|---|---|---|
| Speak Squeak Creak (1994) | 初期代表作。爆発的スピードのナノコア | Amazon |
| Charlie (1998) | 構成が整い、楽曲性が増した中期の名盤 | Amazon |
| Cell-Scape (2003) | エレクトロ要素を導入した新境地 | Amazon |
年代別おすすめアルバム
| 年代 | アーティスト / アルバム | 特徴 | リンク |
|---|---|---|---|
| 1991 | Boredoms – Pop Tatari | アヴァンギャルド・ノイズとロックの狂気的融合 | Amazon |
| 1994 | Melt-Banana – Speak Squeak Creak | 初期代表作。爆発的スピードのナノ・コア | Amazon |
| 1996 | Merzbow – Pulse Demon | ハーシュノイズの頂点。ラップトップ以前の最重要作 | Amazon |
| 1998 | 灰野敬二 – Watashi Dake? (再発) | 70年代録音だが90年代以降に再評価 | Amazon |
| 2017 | 非常階段 – Destroy Noise Symphony | パフォーマンス的ノイズの集大成 | Amazon |
シーンの相関図
FAQ — 日本アンダーグラウンド・ノイズシーンについて
Q1: 90年代と2000年代でシーンはどう変わった?
A1: 90年代は革新的な実験が爆発した時期、2000年代は海外からの再評価とリイシューが進んだ時期です。
Q2: 初心者が聴くならどの作品がおすすめ?
A2: Boredoms『Super æ』やMerzbow『Merzbeat』は比較的入りやすい入門盤です。
Q3: ノイズとロックはどう結びついた?
A3: サイケデリックやパンクの影響を背景に、轟音と即興を融合させた新しい表現が生まれました。
Q4: サウンドトラック制作やAI音楽生成とどう関係する?
A4: 実験的サウンドは映像作品に独自の緊張感を与え、AIの生成音楽研究にも応用可能な構造を提示しています。
まとめ
90年代〜2000年代の日本アンダーグラウンド・ロックとノイズは、単なる音楽ジャンルではなく、文化的実験場でした。灰野敬二の儀式的演奏、Merzbowの機材的進化、非常階段の破壊的パフォーマンス、Melt-Bananaの疾走感、Boredomsのサイケ・ノイズ融合は、世界の音楽史に残る唯一無二の表現です。
関連コラム
🔗 【コラム】 日本のロック史:メインストリームとアンダーグラウンドの交差点