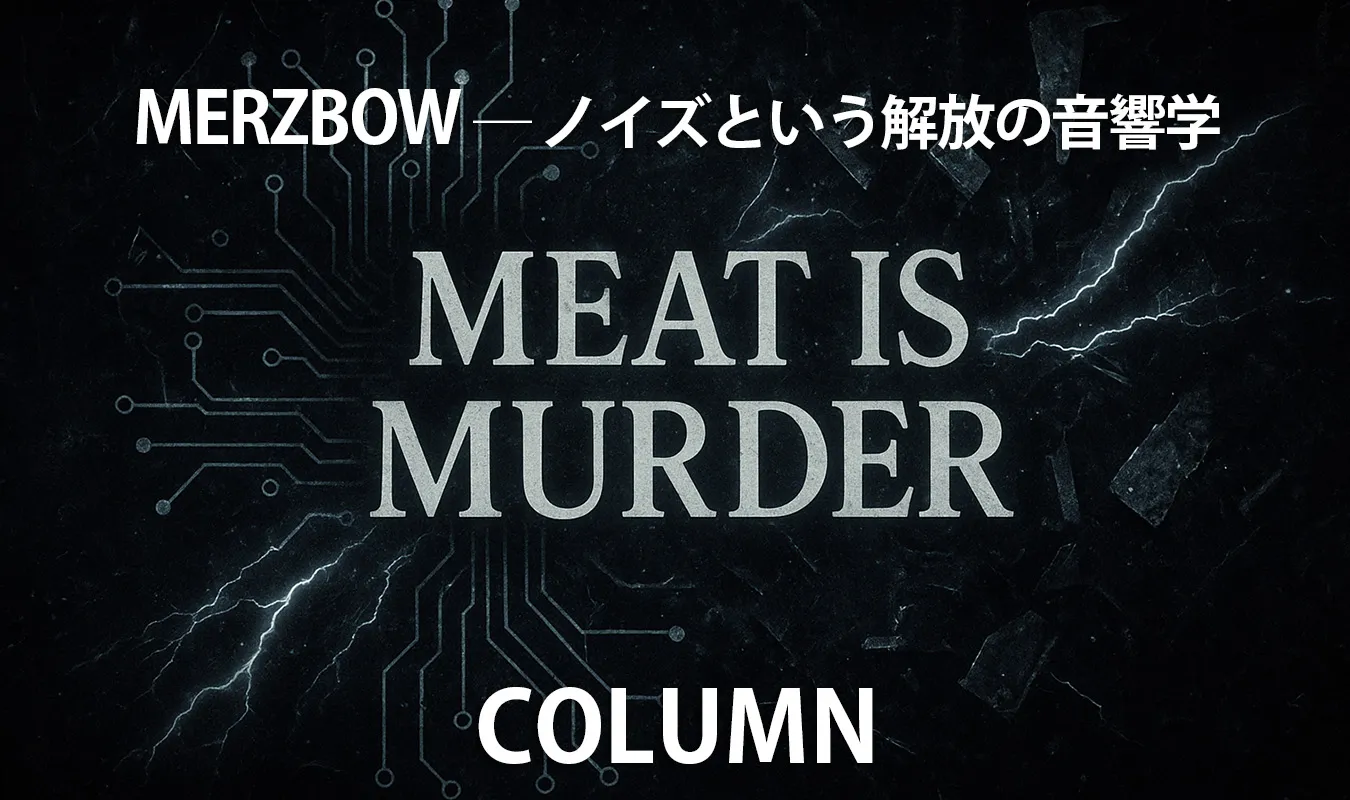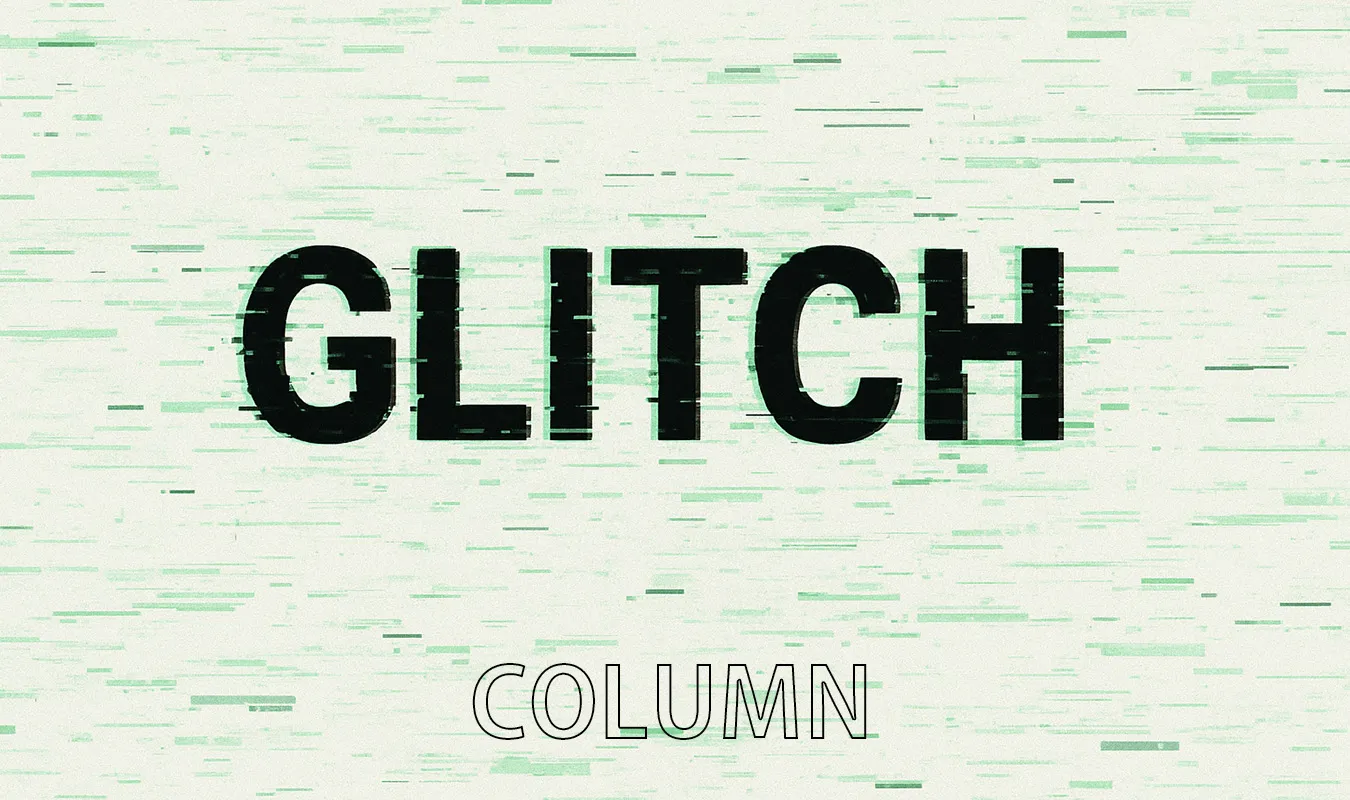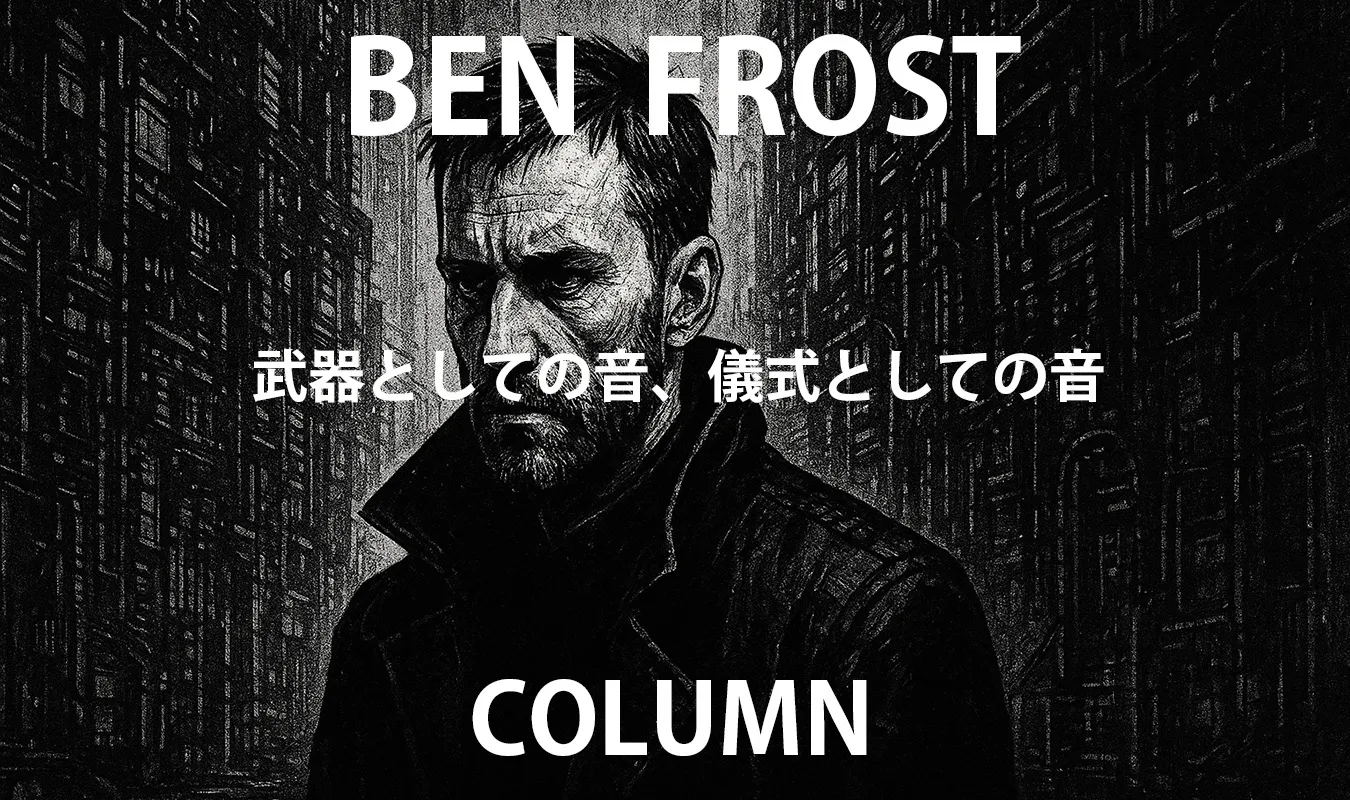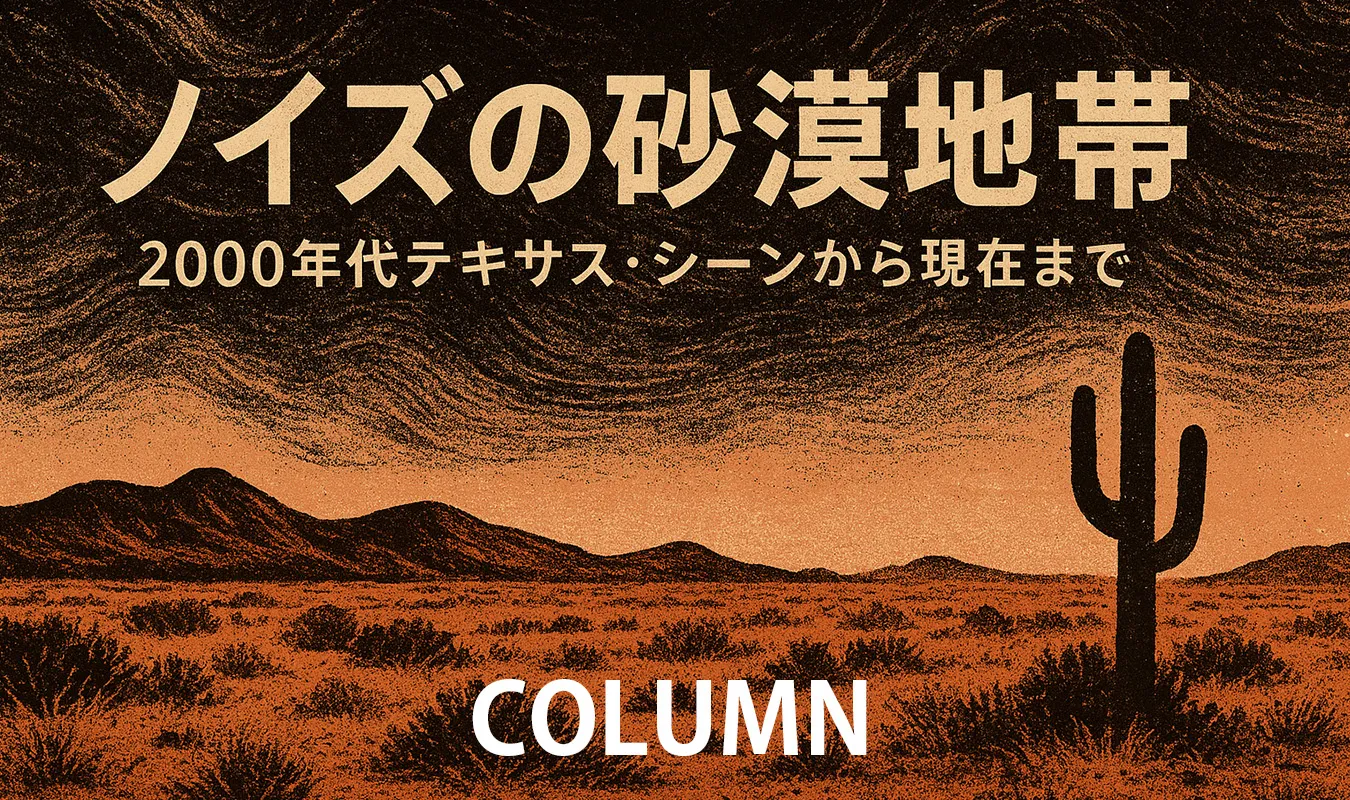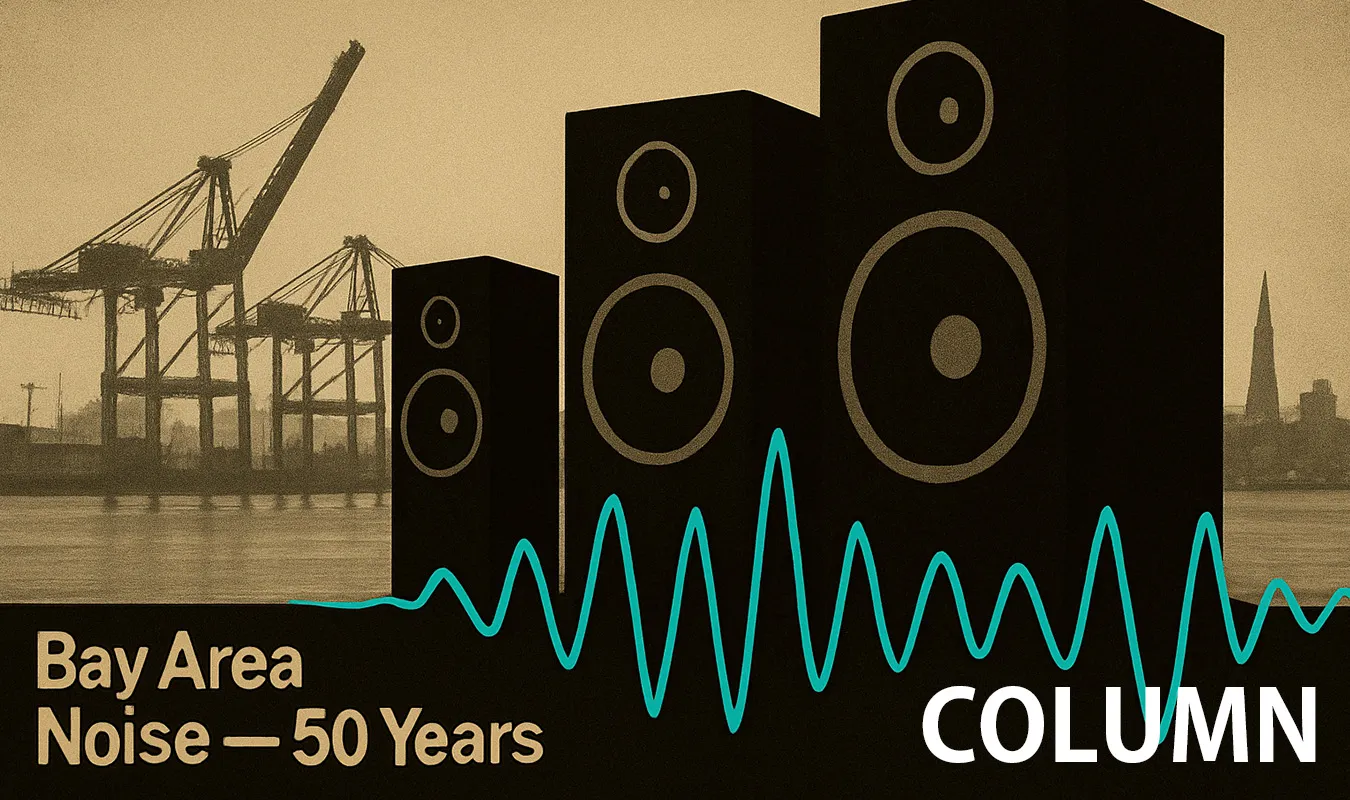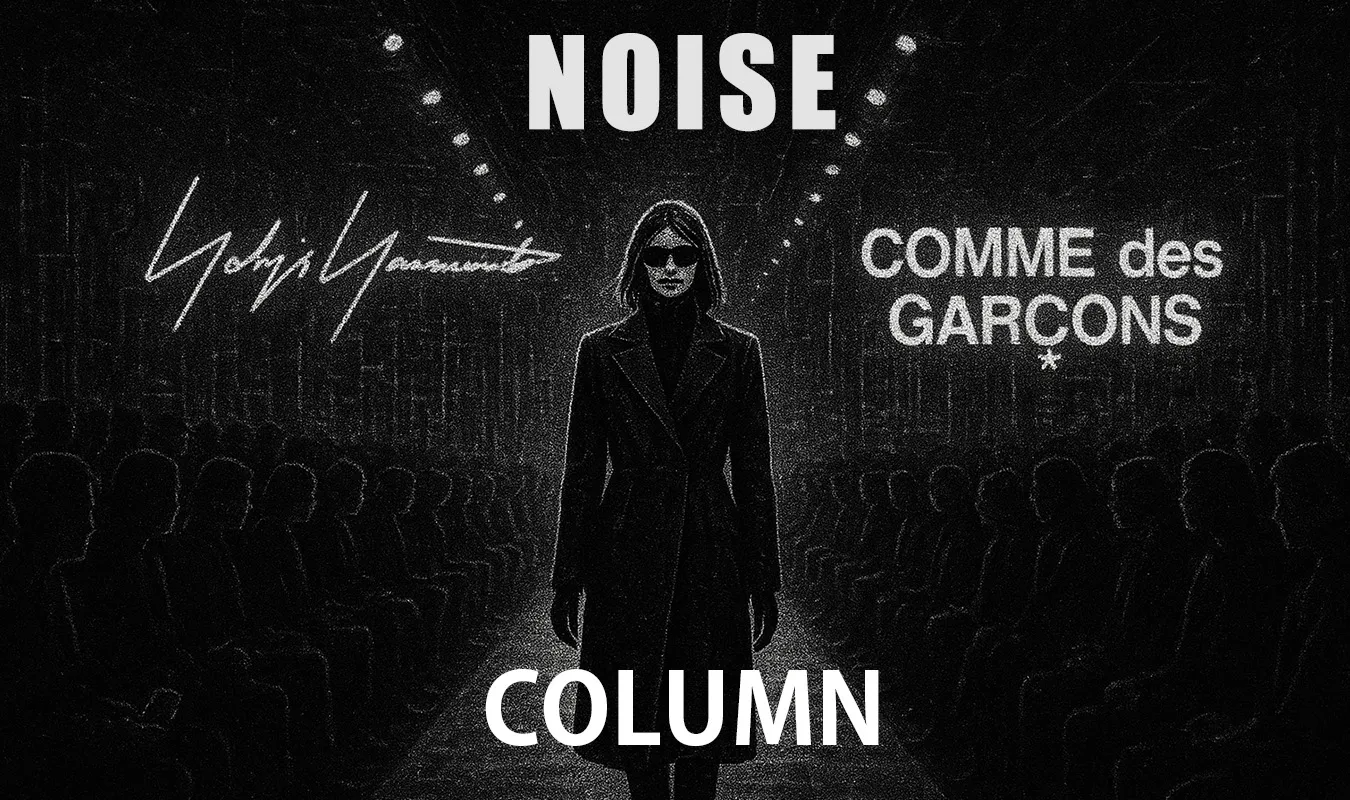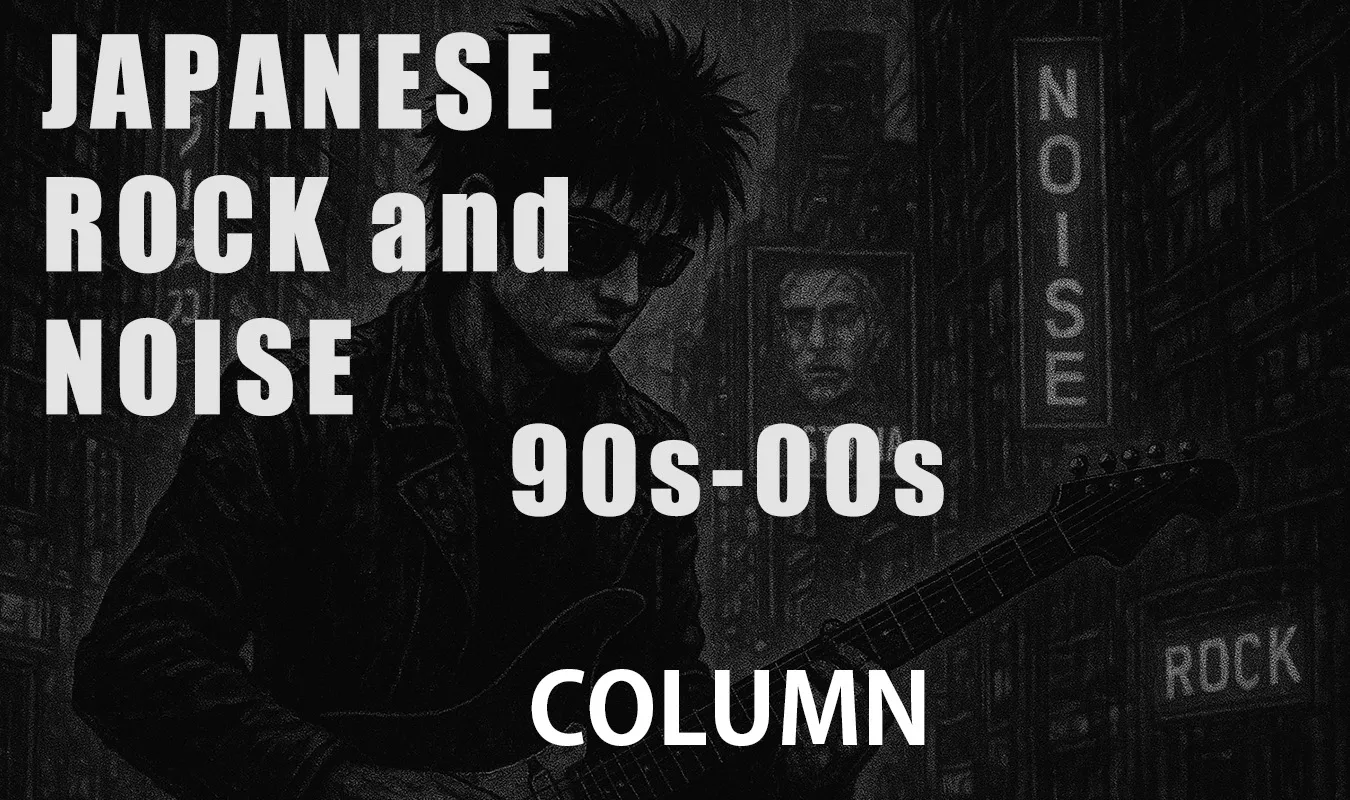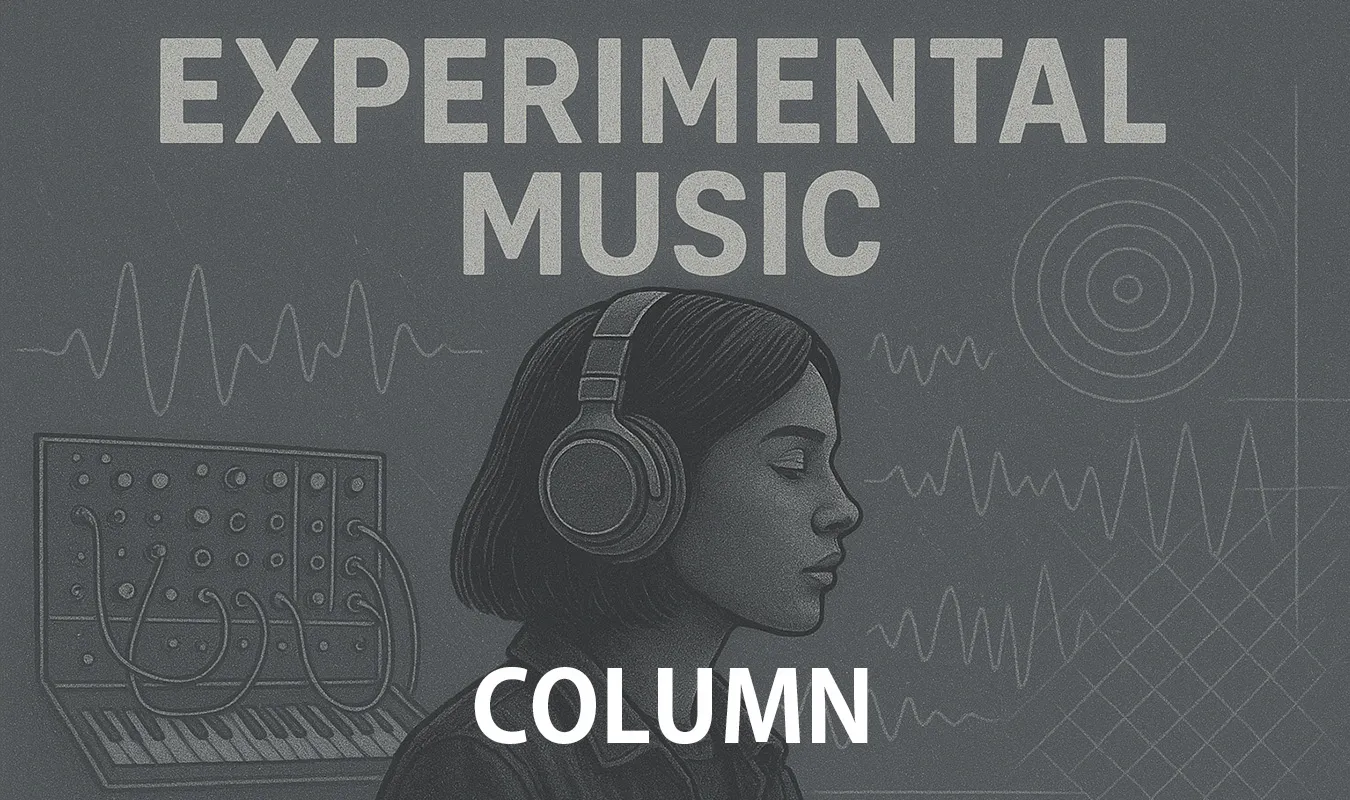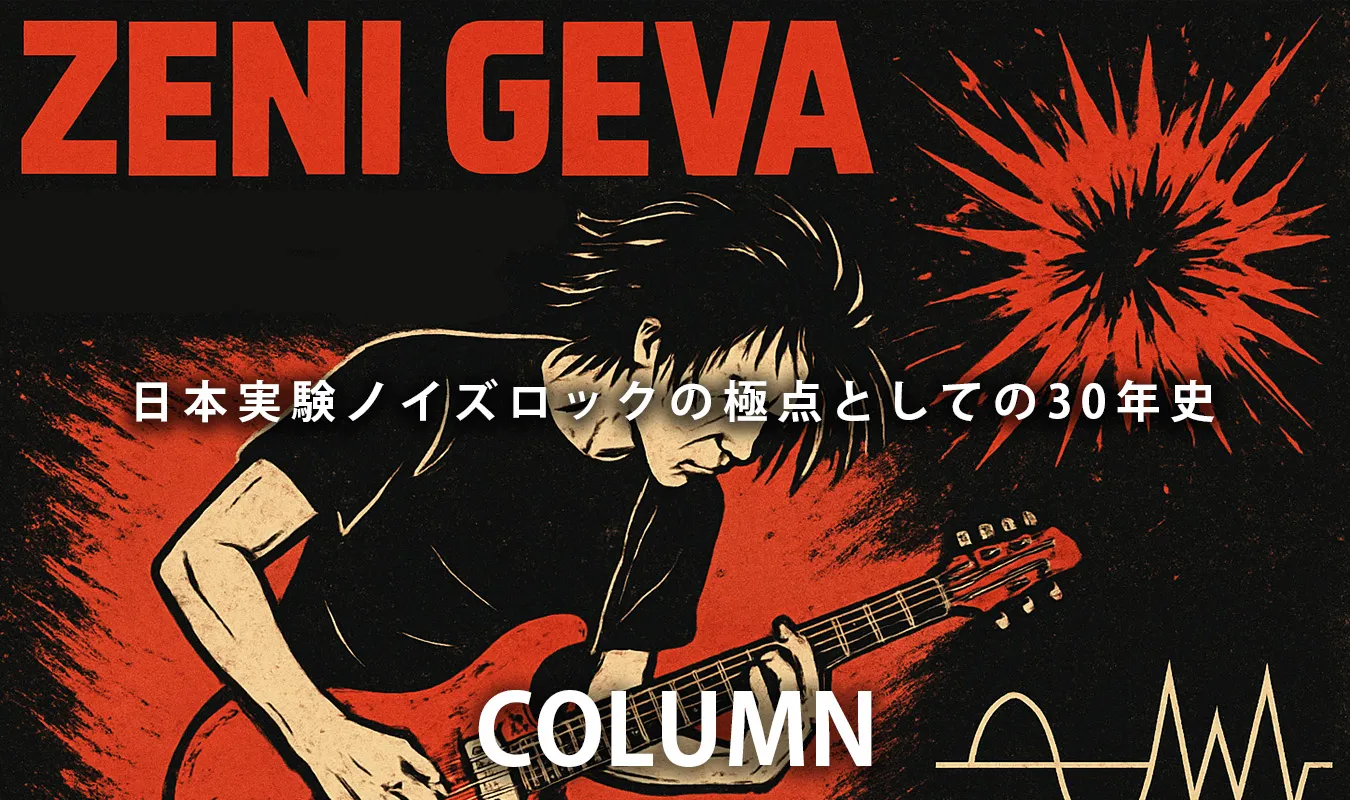
イントロダクション
文:mmr|テーマ:暴力性・精密性・構造美が交錯するサウンドの変遷を読み解く
Zeni Geva(ゼニゲバ)は、日本の実験ノイズロック/ハードコアの歴史において、極めて特異な位置を占めるバンドである。1987年に結成されて以来、そのサウンドは一貫して暴力的でありながら、同時に驚くほど構築的で、精密に計算された数学的リズムを内包する。リーダーである KK Null(Kazuyuki Kishino) が持つ広範な音響哲学は、バンドの核を成し続け、国内外のアンダーグラウンド・シーンに強烈な影響を与えてきた。
彼らの音楽には、ノイズ、金属的ギター、破壊的ドラム、反復構造、そして電子音響的テクスチャが多層的に積層する。1990年代から現在まで断続的に活動を継続してきた Zeni Geva の歩みは、日本のノイズ文化と海外アンダーグラウンドの結節点として極めて重要だ。
1. 結成期(1987–1990):暴力と構造の原点
Zeni Geva の結成は 1987年。中心人物は KK Null。彼は YBO2 など前身活動ですでに実験性の高い音楽性を確立しており、ノイズ/ハードコア/前衛音楽の横断的な知識を持つ人物だった。
初期メンバー
- KK Null(Vo/Gt)
- Fumiyoshi “NP” Suzuki(Gt)
- Ikuo Taketani(Dr)
- Elle(Vo)
バンド名は「Zeni(銭)」と、ドイツ語の「Gewalt(暴力)」の語感が由来とされ、“Money Violence”=貨幣と暴力 という社会的な概念が埋め込まれている。
初期作品
- How to Kill(1987)
- Vast Impotenz(1988/Cassette)
初期作品では、ノイズロックとハードコアを基軸としながら、後に特徴となる 反復構造・破壊的リフ・数学的変拍子 の萌芽が既に見られる。
1988年には 田畑満(Mitsuru Tabata) が加入し、ギターの質量は一段と増した。以後、田畑は長期にわたって Zeni Geva の音の柱を担う。
2. 飛躍(1991–1995):アルビニとの出会いと国際的評価
1991年、Zeni Gevaは大きな転機を迎える。それはアメリカのエンジニア/プロデューサー Steve Albini との協働である。アルビニはその録音哲学によって、生々しく、空間の空気をそのまま刻むレコーディング手法で知られる。
『Total Castration(1991)』
アルビニ録音による初のフルレンス作。
Zeni Geva の暴力性と、アルビニの乾いたダイレクトな音響が完璧に噛み合い、海外で強い評価を獲得した。
『Desire for Agony(1993)』
- アメリカのレーベル Alternative Tentacles(Jello Biafra 主宰)からリリース
- 海外ツアーが本格化
- 同時期に EP やシングルを多数発表(Nai-Ha、Disgraceland など)
ライブ活動の拡大
1992年頃からアメリカ・ヨーロッパのライブを精力的に行い、イギリスの John Peel セッションにも登場。Peel が Zeni Geva の音楽性を高評価したことで、国際的知名度がさらに上昇する。
『Freedom Bondage(1995)』
再びアルビニを迎えて制作された重要作。
音響・構造・暴力性が最もバランスよく統合されたアルバムとされる。
3. 実験の深化(1996–2001):長尺化、電子化、構造美の追求
1996年にはドラマーの入れ替わりが起こり、Blake Fleming が短期間在籍。その後、藤掛正隆(Masataka Fujikake)が加入し、Zeni Geva のリズムはより複雑・高速・多層化した。
構造的音楽性の強化
この時期、Zeni Geva の曲は長尺化し、16分を超える曲を含む構造的な作品が増える。
- 複数のパートが分岐しながら再収束する
- ギター2本による対位法的リフ
- Nulltron など電子装置の使用拡大
『10,000 Light Years(2001)』
- 電子的テクスチャの増加
- ノイズ/金属質ギター/変拍子/電子音が重層的に絡む
- 1980〜90年代期とは異なる、音響彫刻としての Zeni Geva
バンドはこの時期に音楽的成熟を極めるが、同時に Null のソロ活動や他プロジェクトが増え、バンドとしてのリリース間隔は空いていく。
4. 休止と再起(2002–2009)
2002〜2004年には海外ライブを収めた作品がリリースされるが、バンドとしての活動は停滞する。
- Last Nanosecond – Live in Geneva 2002(2004)
- メンバーは各自の活動へ
- KK Null はノイズ/電子音響/コラボレーションで世界的に活動を拡張
2009年:再結成
長い停滞の後、吉田達也(Ruins)の再加入を機に、本格的な再結成が行われる。
Zeni Geva にとって吉田の加入は、再び強烈なインパクトをもたらした。
5. 第二期 Zeni Geva(2010–):再評価と世界的再注目
『Alive and Rising(2010)』
- 2009年のラインナップによるライブ音源
- 吉田達也の変態的ドラム、Null & Tabata のギター対峙が圧巻
以降、アジア・ヨーロッパでのライブ活動が再始動。
ノイズ/メタル/ハードコア/前衛音楽シーンからの再注目が高まり、Zeni Geva はその歴史的価値を改めて評価されている。
6. Zeni Geva の音楽分析
6-1. リフ構造の特徴
- 低音リフの反復
- 対位法的に絡む2本のギター
- 途中で突然折れる構造、カットアップ的転調
- 非4/4拍の執拗なループ
6-2. ドラムの役割
- 初期はハードコア寄り
- 90年代は数学的・ポリリズム化
- 吉田達也加入後は激烈かつ変拍子的アプローチ
6-3. テーマ性
- 「貨幣」「暴力」「支配」「身体」「解体」など
- リリックは抽象的、象徴的
6-4. プロダクション
- Steve Albini による録音作品群は、Zeni Geva の代表的音響美
- 生々しいダイナミクスとギターの金属的倍音が際立つ
- 後期は Nulltron などデバイス導入で電子音響が増大
7. 日本アンダーグラウンド史での位置づけ
Zeni Geva は「ノイズ × ハードコア × メタル × 実験音楽」という組み合わせを、日本でほぼ唯一無二の形で成立させたバンドである。
- 1980年代ノイズ文化(非常階段、Merzbow、YBO2)
- 1990年代の国際的ノイズムーブメント
- 2000年代以降の実験音響・エレクトロアコースティック
これらを横断する存在として、国内外双方で評価され続けている。
年表(Zeni Geva 主要年表)
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1987 | Zeni Geva 結成。How to Kill 発表。 |
| 1988 | Vast Impotenz(Cassette)。田畑満が加入。 |
| 1990 | Maximum Money Monster 発表。 |
| 1991 | Total Castration(Albini録音)。海外ツアー開始。 |
| 1992 | Live in America を発表。 |
| 1993 | Desire for Agony(Alternative Tentacles)。 |
| 1995 | Freedom Bondage(Albini録音)。 |
| 1996 | ドラマー脱退・交代。Blake Fleming → 藤掛正隆。 |
| 2001 | 10,000 Light Years 発表。 |
| 2004 | Last Nanosecond(Live 2002)発表。 |
| 2009 | 吉田達也が再加入し再結成。 |
| 2010 | Alive and Rising(2009 Live)発表。 |
ディスコグラフィ+時代区分チャート
How to Kill"] --> B["1990 Maximum Money Monster"] B --> C["1991 Total Castration
Albini録音"] C --> D["1993 Desire for Agony
Alternative Tentacles"] D --> E["1995 Freedom Bondage"] E --> F["2001 10,000 Light Years"] F --> G["2004 Last Nanosecond (Live 2002)"] G --> H["2009 再結成"] H --> I["2010 Alive and Rising"]
結語
Zeni Geva の歴史は、 「暴力」×「構造」×「実験」 の三要素が、30年以上にわたって交互に、あるいは同時に膨張し続けた軌跡である。
商業性とは無縁のまま、しかし世界のアンダーグラウンド・ミュージックから確固たる評価を獲得し続けている稀有な存在。それが Zeni Geva であり、その中心には常に KK Null の音響思想があった。
今なお彼らの音楽は古びず、むしろ現代のノイズ/メタル/実験音楽の枠組みを先取りしていたことさえ明らかである。 本稿が、Zeni Geva を再発見するきっかけとなれば幸いである。
YouTube Podcast
※このPodcastは英語ですが、自動字幕・翻訳で視聴できます