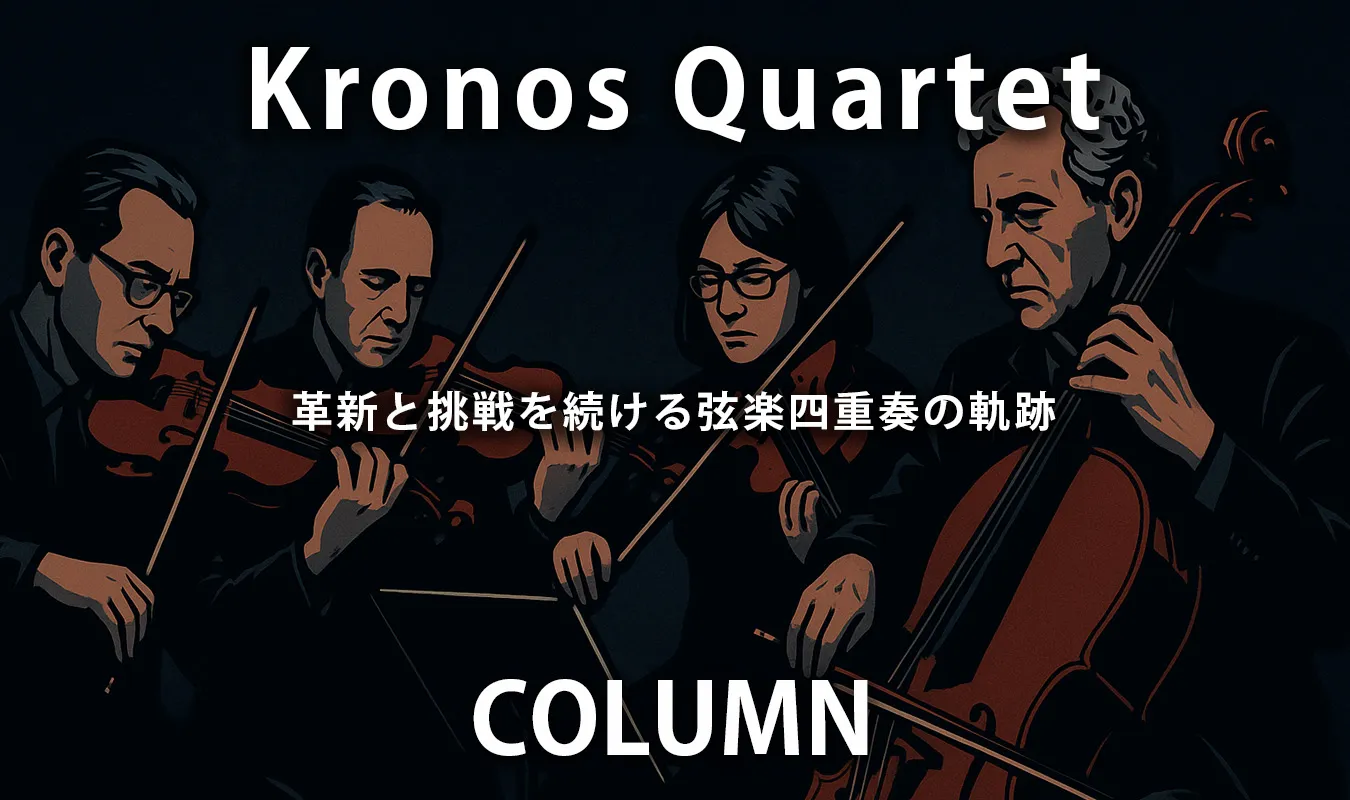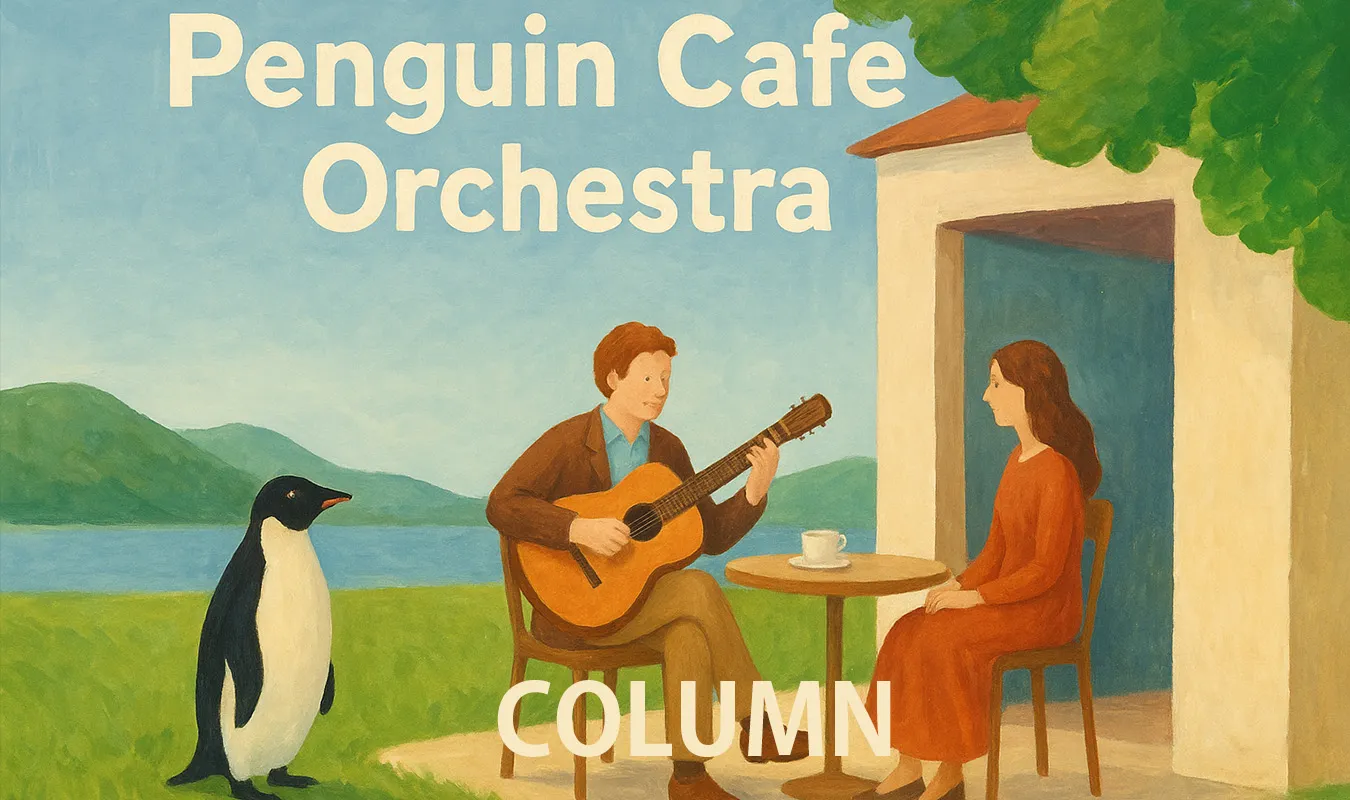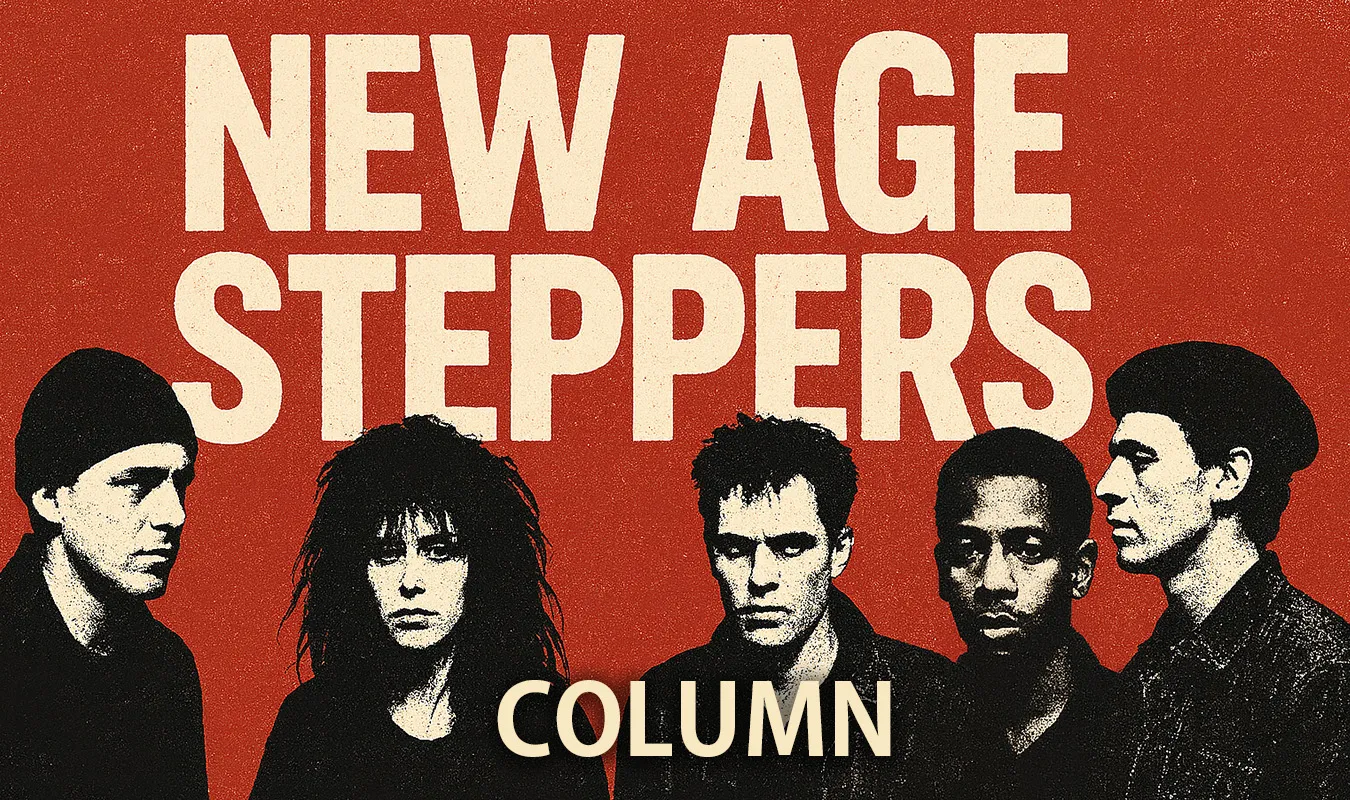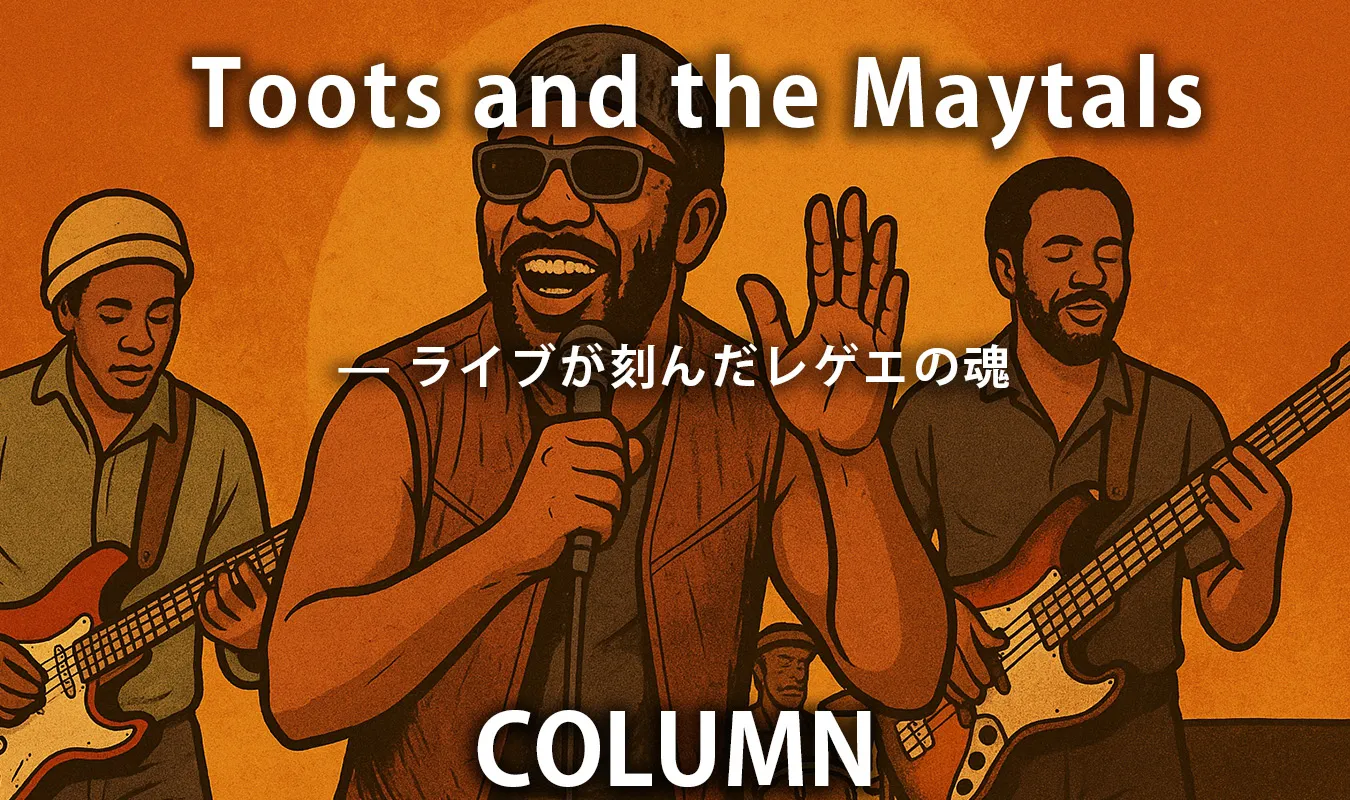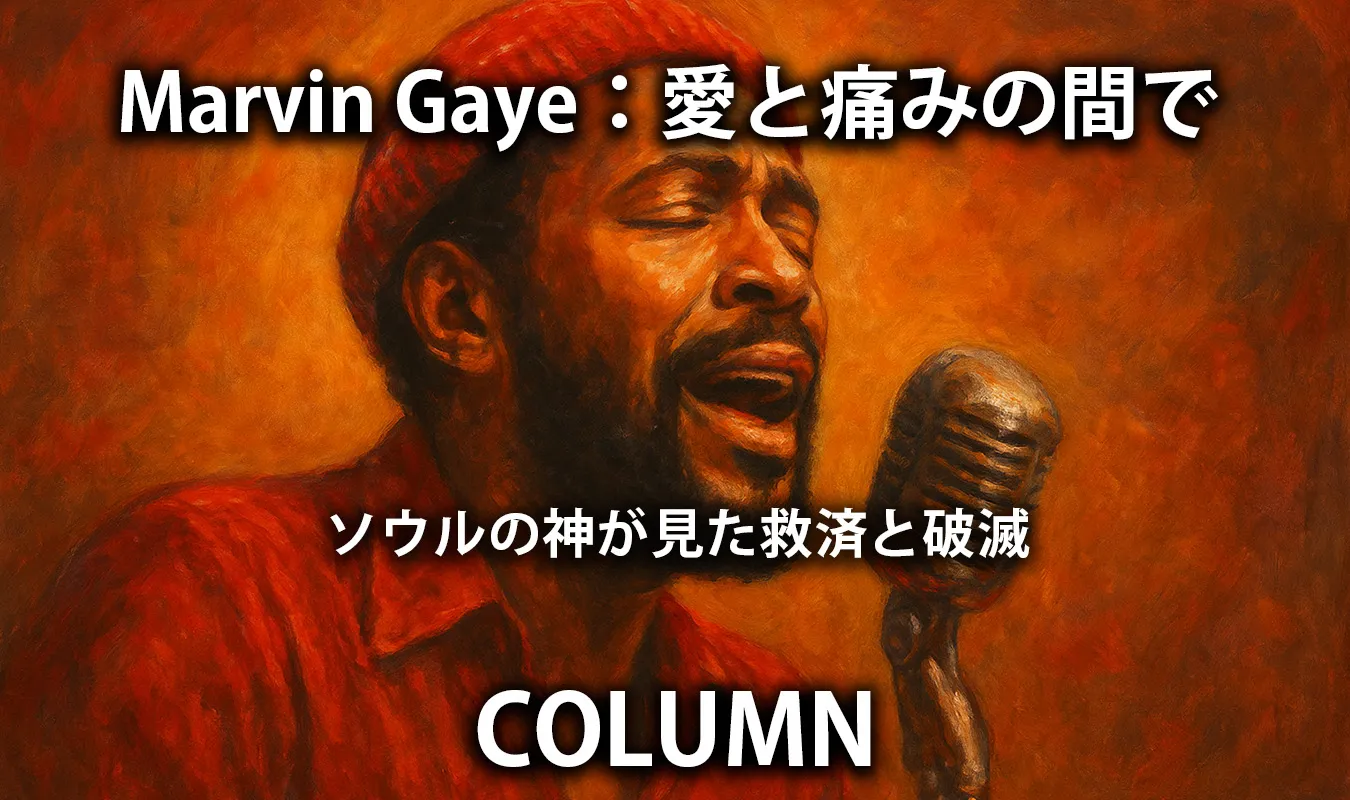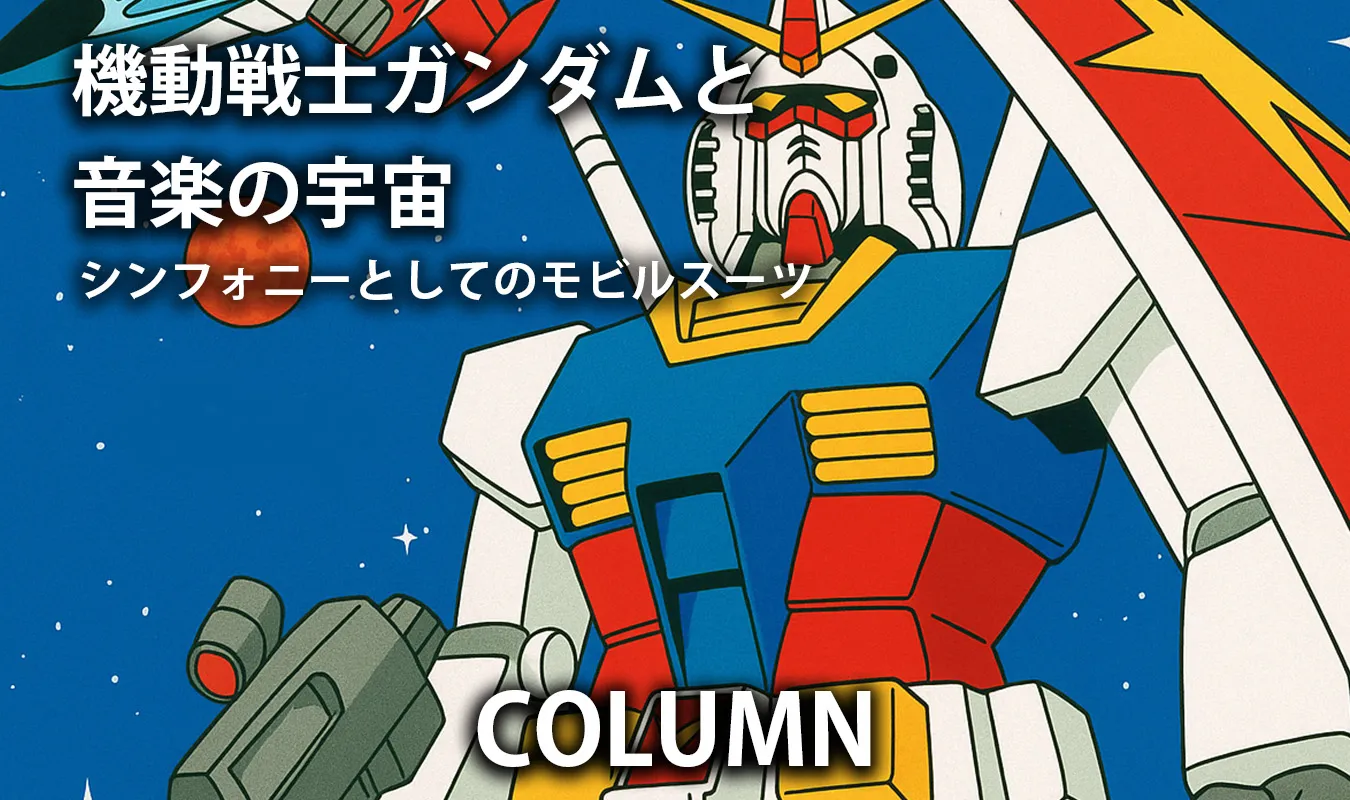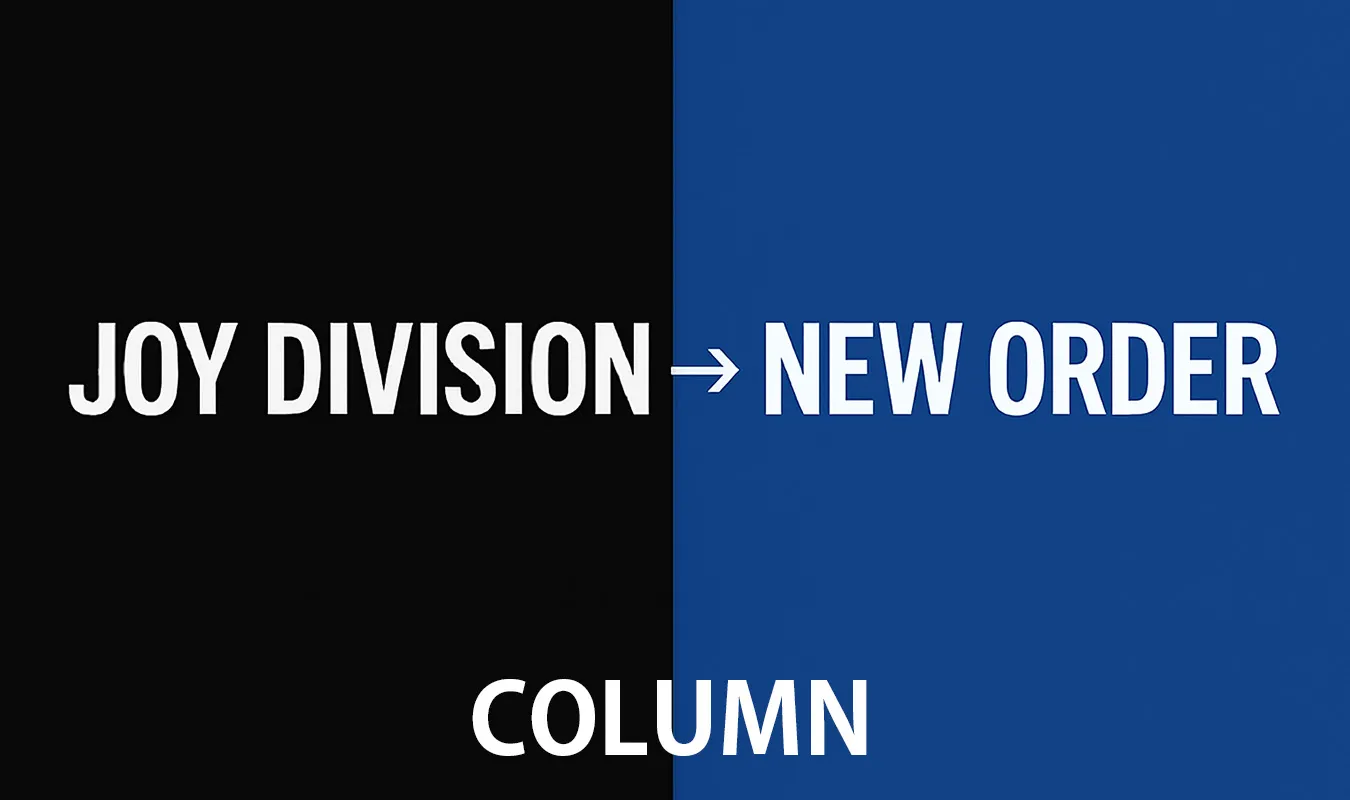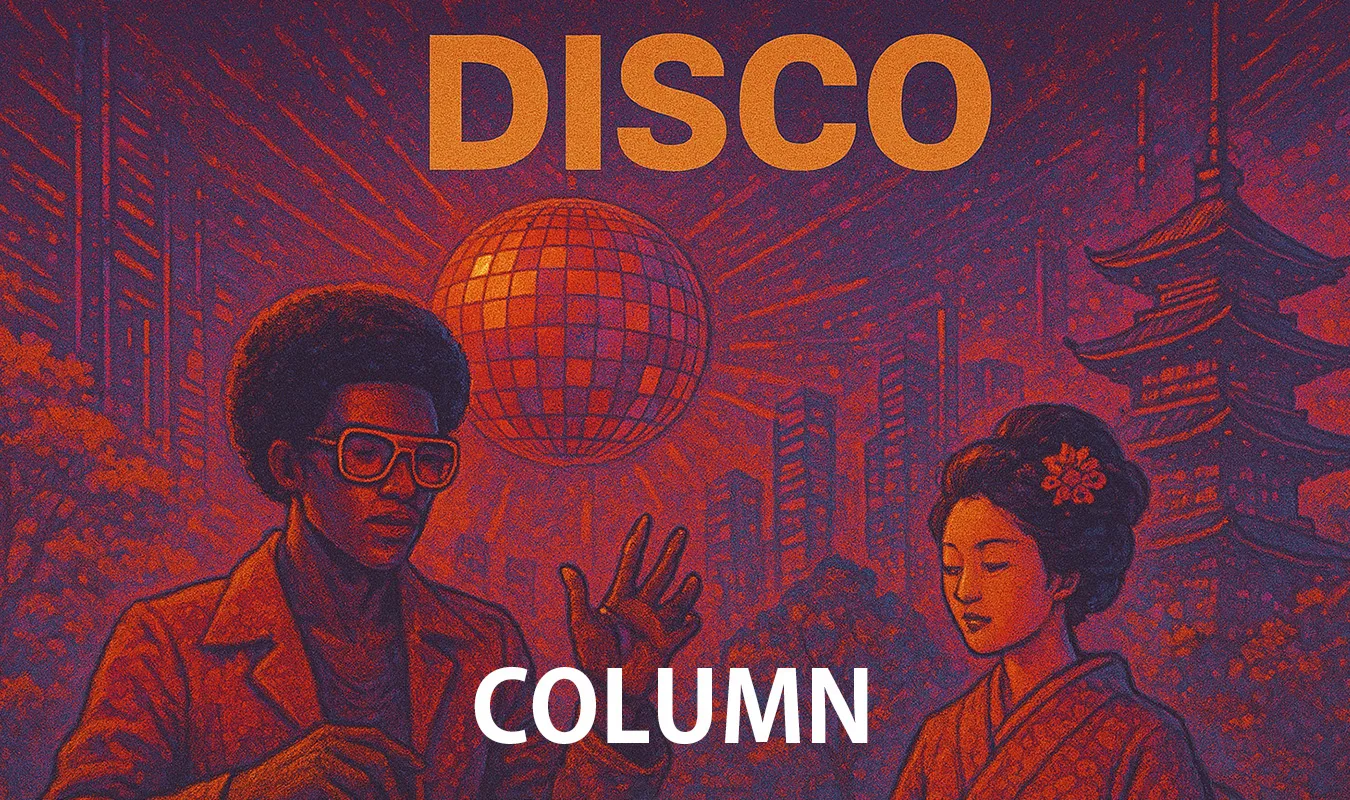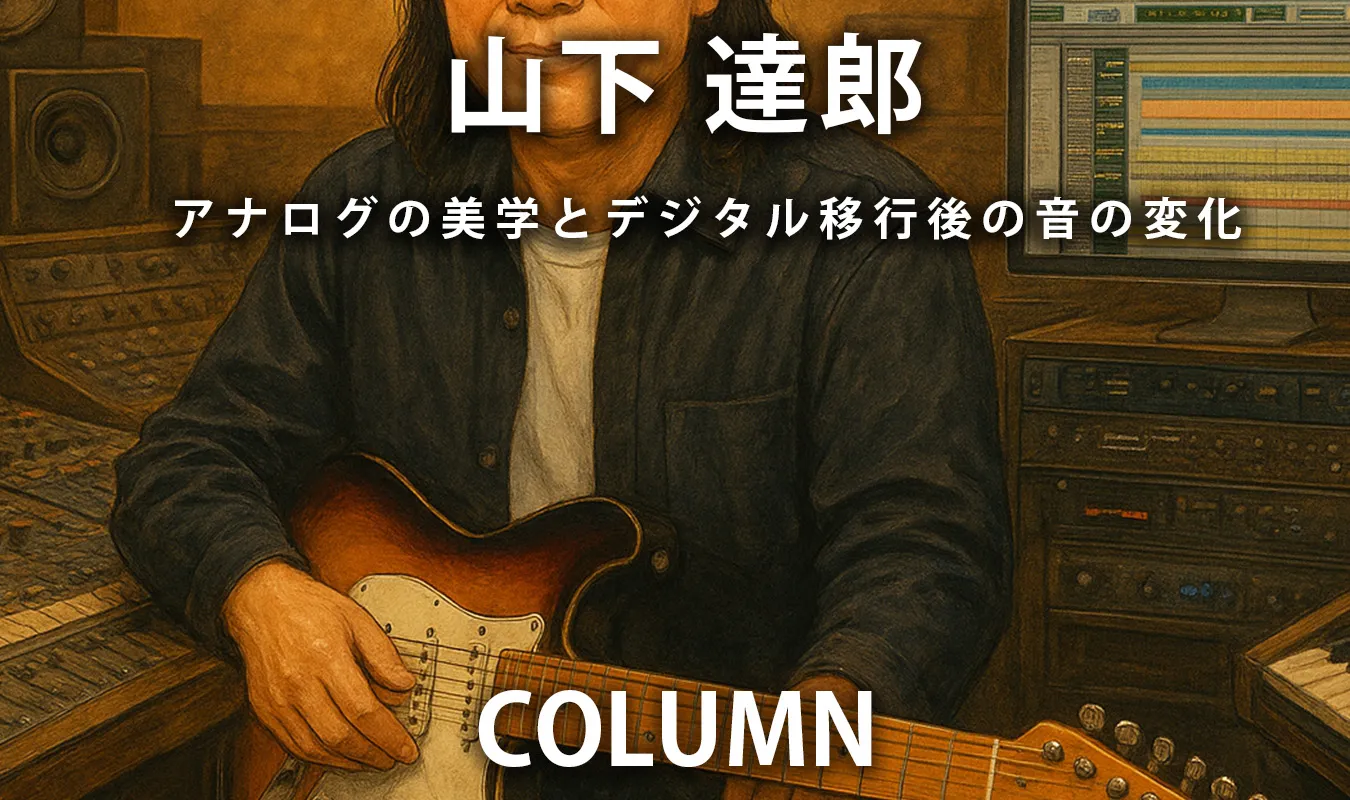
制作環境・機材・録音手法・スタジオ文化・媒体仕様
文:mmr|テーマ:シティポップ時代から最新作まで、「録音の人」が貫いたサウンド哲学について
日本のポップミュージック史において、山下達郎はボーカリスト・作曲家であると同時に、日本屈指の「録音作者」である。
彼のアルバムを貫いているものは、時代によって変化する流行や音楽ジャンル以上に、録音技術、媒体、音響思想である。
特に、
- アナログ・テープ時代の徹底した音作り
- デジタル録音/デジタル機器導入後の慎重な変化と選択
- シティポップ時代のスタジオ文化との関係
- 近年のリマスターにおける哲学の一貫性
これらの変遷は、単なる音質の違いではなく、日本のポピュラー録音史そのものを映し出している。
1. 1970年代:アナログ・テープ黄金時代と山下達郎の基礎形成
■ シュガー・ベイブ(1973–1976)
山下達郎の音楽観は、この時期のロック/ポップスのアナログ録音文化の中で形成された。
- 録音媒体:アナログ・マルチトラック・テープ(2インチ、主に16〜24tr)
- スタジオ:日本の黎明期スタジオ(ビクター、日音、CBSソニーなど)
- 音楽的背景:ブライアン・ウィルソン、フィル・スペクター、スタックスなどアメリカ録音文化への深い傾倒
この時代、達郎はすでに「録音技術こそが音楽の根幹」という思想を固めていたと語っている。
■ 『SONGS』(1975)の音の特徴
- セルフ・コーラスの多重録音
- ドラムのデッドなルームサウンド
- ホーン/ストリングスの生録音
- アナログ特有の厚い中低域
アナログ特性に最適化されたアレンジと録音が、既にここから始まっていた。
2. 1970年代後半:ソロ初期と「アナログ・レイヤー」の完成形
■ 『SPACY』(1977)、『GO AHEAD!』(1978)
この時期は、達郎がアナログ24トラック録音を使い倒した時代である。
特徴:
- テープによる温度感のあるコンプレッション
- 手弾きの多重録音(ギター、キーボード、パーカッション)
- ボーカルの何十テイクにもわたるオーバーダビング
達郎は後年、「アナログは重ねるほどニュアンスが丸く収まる」と語っており、この頃の作品はその理想形である。
3. 1980–1982年:『RIDE ON TIME』『FOR YOU』
■ シティポップ時代の録音技術の頂点
1980年代初頭、日本のスタジオ技術は世界的にも高い水準に到達していた。
その中心にあったのが CBSソニー信濃町スタジオ。
▼ アナログ録音のピーク
- 使用機材:Studer A80/A800 24tr、NEVEコンソール
- リズム:生ドラム+アナログ録音
- ギター:コンプレッサーを通した温かいトーン
- コーラス:アナログ特有の「密度のある重ね」
- リバーブ:EMT 140 プレート、Lexicon プリディレイ併用
この頃の音は、しばしば「シティポップの理想形」とされる。
■ 『FOR YOU』(1982)の録音美学
達郎作品の中でもトップクラスに語られる作品。
音響的特徴:
- アナログ録音の最高峰レベルのクリアさ
- ドラムのアナログ録音が持つ「厚み」
- コーラスの密度と定位の完璧な構築
- 高音側が丸く、アナログらしい耳当たり
すべてアナログでありながら、モダンな解像度を持った稀有な作品。
4. 1980年代後半:デジタル導入期と慎重な移行
日本では1982年にCD発売。
1980年代後半にはデジタル録音機器(PCM、デジタルマルチ、デジタルリバーブ)が急速に普及し始める。
だが、山下達郎は デジタル化にもっとも慎重だったアーティストの一人である。
■ デジタルの初導入
達郎が本格的にデジタル機材を使用しはじめたのは、
- デジタルシンセ(DX7など)は導入
- デジタルリバーブ(Lexicon 224/480)は限定使用
- 録音そのものは「アナログ・テープ」を強く保持
特に以下の理由で、デジタル録音そのものを避けていた:
- デジタル録音初期は高域が硬く、奥行きが失われやすい
- アナログの重ね録りがもつ「丸み」を失うことを嫌った
- 自身のコーラス構築にはアナログの方が向いていた
実際、達郎は「アナログ24トラックが廃れた時代は音楽の危機だった」と語っている。
5. 1990年代:デジタル録音時代への突入と新たなアプローチ
1990年代に入り、業界は完全にデジタルへ移行する。
▼ 達郎はデジタル録音へ移行しつつも、基本姿勢は変えなかった
- デジタル録音採用
- ただしアナログ的な質感を保つための処理が増加
- 楽器の録音は依然として生音を多用
- コーラス重ね録りの手法は継続
■ 『ARTISAN』(1991)
- 本格的なデジタル録音時代の代表作
- 高解像度、クリアな中高域
- デジタル機材を使用しつつ、アナログ時代のコーラス技法を維持
- サウンドはシャープだが冷たくない
達郎は「デジタルでも、録り方次第で温度感は出せる」と語っている。
6. 2000年代:デジタル制作成熟期と“アナログ的デジタル”の確立
■ 2000年代の録音哲学
- 制作環境は完全デジタル化
- ただしレコーディング段階でのマイク選びやルームサウンドの重視
- 「デジタルであってもアナログ質感を設計する」
達郎は、自宅にも高品位な録音環境を構築し、
セルフ・プロデュース+デジタル+生音という独自の融合を達成する。
7. 2010年代:リマスター時代と“音の復権”
2020年代にかけて、多くのアナログ時代作品がリマスターされた。
達郎はリマスターにおいても、音の改変を極端に嫌うスタンスを明確にしている。
▼ リマスターの特徴
- 元テープを忠実に再生
- 極端なEQは一切せず
- 音圧を不自然に上げない(ラウドネス戦争を拒否)
- オリジナルの意図をそのまま伝える
結果として、近年のアナログ再発は世界的にも高評価を受けている。
8. 2020年代:最新作〜アナログ回帰の時代
現代ではアナログ盤の需要が再び高まっている。
達郎は、デジタル全盛の中で次のような姿勢を貫く:
- 録音はデジタル中心
- しかしアナログ盤のリリースを重視
- ミックスはアナログ的な質感を残す
- 過度な音圧を避ける
- 高域の丸み・中域の厚さを保持
特に最新作では、「アナログの丸み」と「デジタルの情報量」が高次に融合した音になっている。
9. 年表:アナログ〜デジタル移行の流れ
10. アナログ音とデジタル音の技術的比較
――達郎作品を基準に見る音響の違い
| 項目 | アナログ期(〜1980年代) | デジタル期(1990年代〜) |
|---|---|---|
| 録音媒体 | テープ(2インチ) | PCM/ProTools |
| 音の印象 | 温かい、厚い、丸い | クリア、シャープ |
| コーラス | 多重するほどまとまる | 多重時に硬くなりやすい |
| ドラム | 低域が太く自然 | 立ち上がりが速い |
| ノイズ | 少量のテープヒス | ほぼゼロ |
| 達郎の評価 | 「音楽の理想形に近い」 | 「使い方次第」 |
11. シティポップと録音文化:なぜアナログ時代の音は“特別”なのか
山下達郎の名盤群がシティポップとして世界的に再評価された背景には、
単なる楽曲の魅力だけでなく、アナログ録音の質感と日本の1980年代スタジオ文化がある。
ポイント:
- 生ドラムとアナログ録音の相性
- 手弾きミュージシャンの高度なプレイ(林立夫、伊藤広規、青山純ほか)
- 大型スタジオの音響設計(信濃町、ビクター、オンエアなど)
- NEVE卓による中低域の豊かさ
- EMTプレートの残響文化
これら“時代に固有の条件”が、アナログ・シティポップの音を唯一無二にしている。
12. 結論:
山下達郎の音は「アナログ vs デジタル」ではなく
“録音哲学”の一貫性がすべてである
50年のキャリアを通じて、達郎の音はこうまとめられる:
-
アナログ時代:
素材と機器の限界を使いこなすことで“温度感”を極めた -
デジタル移行後:
技術の進化を受け入れつつ、アナログ的質感を保持し続けた -
リマスター時代:
歴史を塗り替えるのではなく、原音を忠実に再生するという姿勢を貫いた
つまり、
メディアや機材が変わっても、山下達郎の音の本質は変わっていない。
それは「録音技術は音楽そのもの」という、
彼が活動初期から抱き続けてきた信念の反映である。