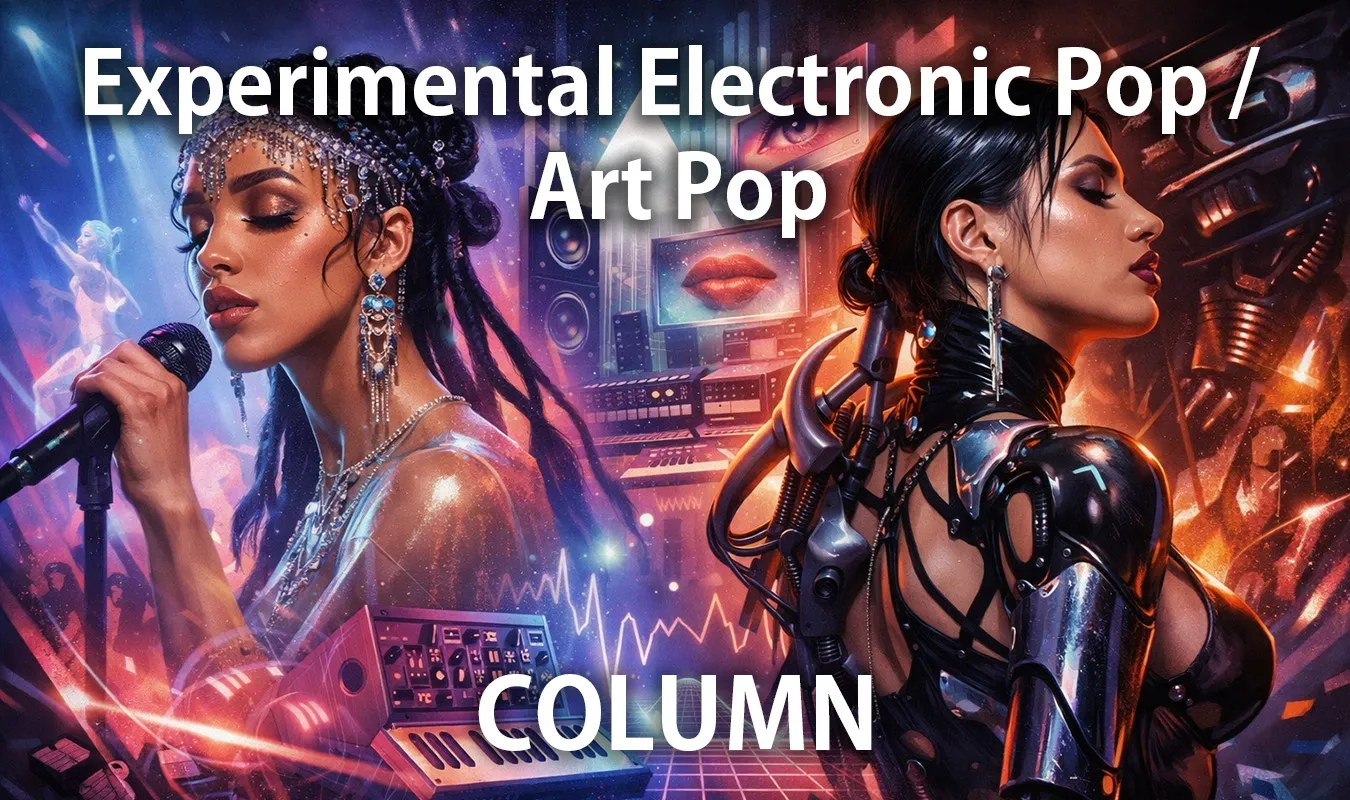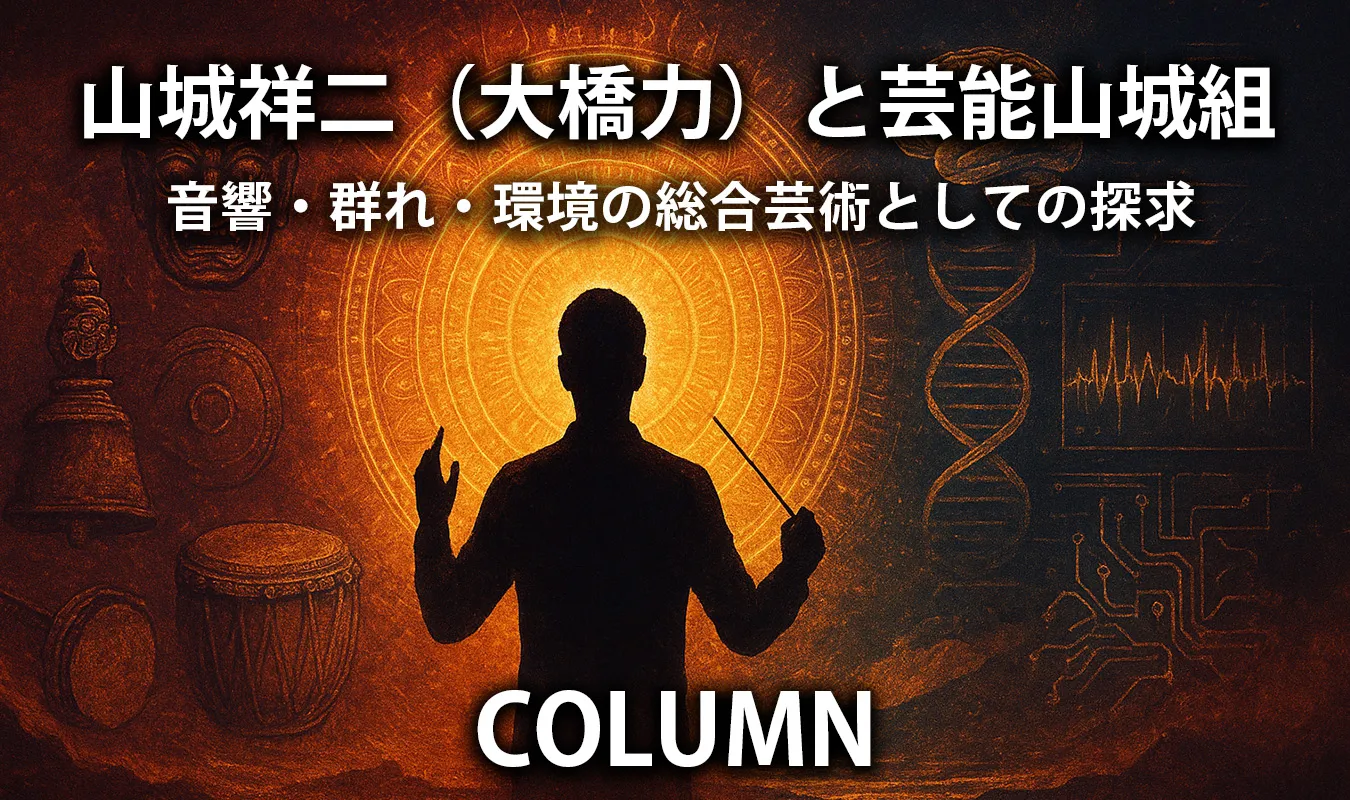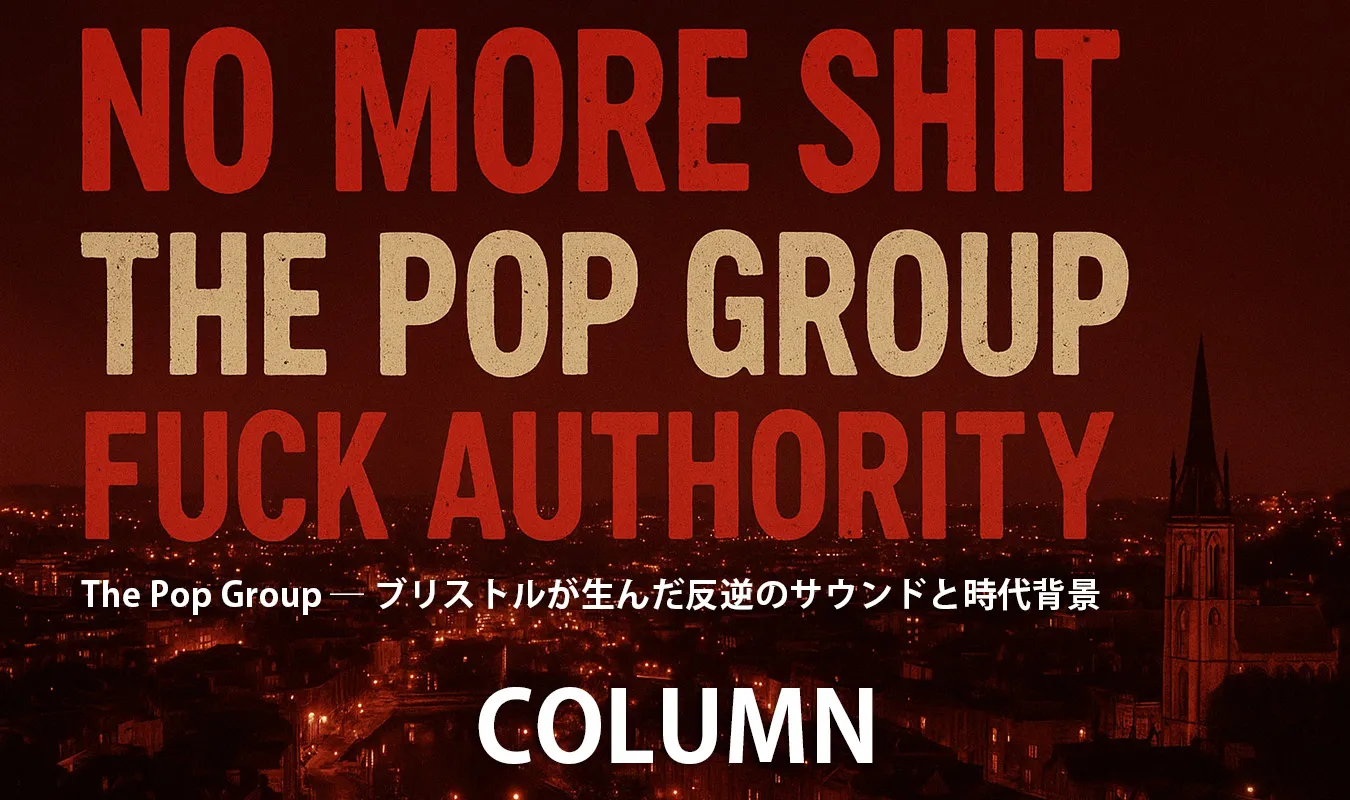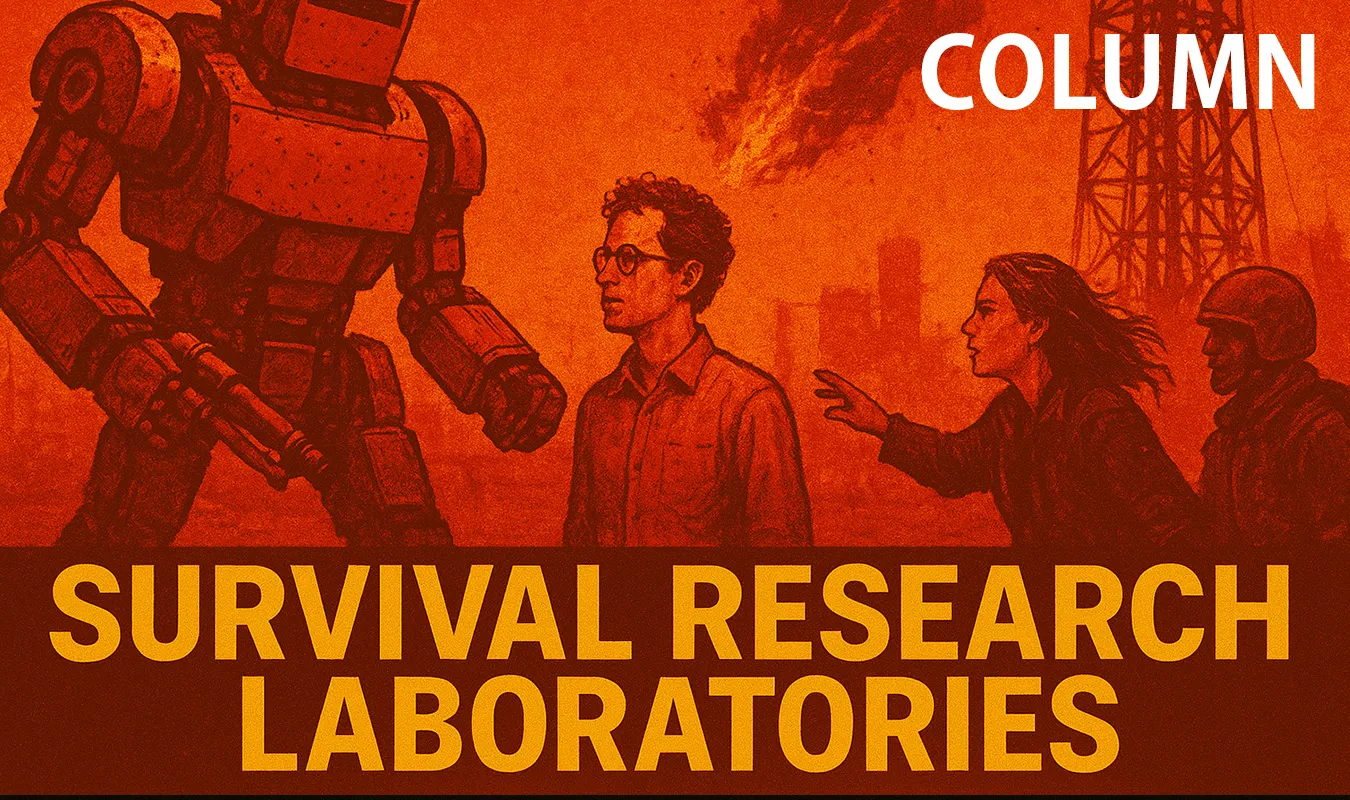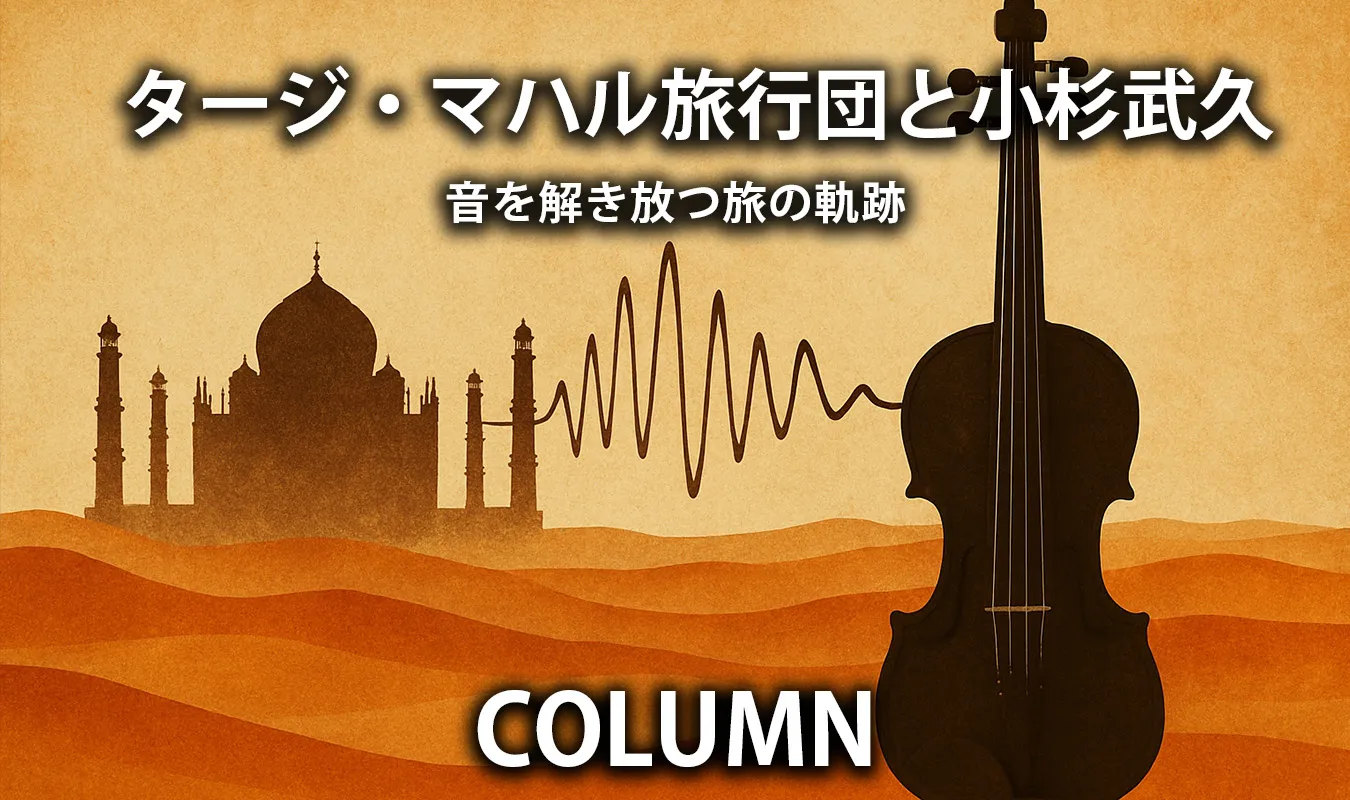
I. 1960年代の出発点:音楽の制度を超えて
文:mmr|テーマ:即興と環境音が交錯する音の巡礼 ― 小杉武久とタージ・マハル旅行団が描いた、音楽の外へと向かう旅の記録
1960年代初頭、日本の前衛音楽シーンは静かに胎動していた。
武満徹や一柳慧、湯浅譲二らが牽引した《実験工房》や《草月アートセンター》を中心に、音楽・舞踏・映像・照明といったジャンルの垣根が取り払われつつあった。
小杉武久はこの時期、東京藝術大学でヴァイオリンを学ぶ傍ら、従来の音楽の形式に限界を感じ始めていた。音を「構造」ではなく「出来事」としてとらえる視点が芽生え、やがて即興と偶然性の探求へと向かう。
“音は、演奏者の意志から離れたところで生き始める。”
— 小杉武久
II. 《Collective Music》とジョン・ケージとの邂逅(1964)
1964年、小杉は武満徹・一柳慧とともに《Collective Music》を結成する。
同年、マース・カニングハム舞踏団の初来日に際して、ジョン・ケージ、デイヴィッド・チューダーと共演。
この出来事は日本の前衛音楽史における決定的な転換点となった。
ケージが提示した「偶然性」「非意図性」の思想は、小杉にとって深い衝撃だった。
演奏者が音を「支配」するのではなく、音が自然に「現れる」状態をいかに作るか。
この問いが、小杉の生涯のテーマとなる。
III. Fluxusとの共鳴と行動の芸術(1965–1969)
1960年代半ば、小杉は国際前衛運動「Fluxus」に接近し、パフォーマンスやハプニングの領域へ踏み出す。
日常の物体を音源化し、時間や空間の枠組みを解体する行為は、従来の音楽観を根底から揺さぶった。
代表作《Music Expanded #2》《Catch-Wave》などに見られるように、
小杉は「演奏する身体」そのものを作品化し、音の発生=出来事の瞬間を記録しようとした。
この流れは後の「サウンド・アート」「環境音楽」「即興音響派」に直接的な影響を与えていく。
IV. タージ・マハル旅行団の結成(1969–1970)
1969年、小杉は新たな実験体として《タージ・マハル旅行団(Taj Mahal Travelers)》を結成。
メンバーには永井清治、飯島孝、菊地雅章(後に離脱)らが加わり、
ヴァイオリン、チェロ、電子機器、金管、声、ラジオ波などを駆使して、
“場所そのものが楽器になる”という理念を実践していった。
V. 音を旅する:インドからヨーロッパへ(1971–1972)
1971年、タージ・マハル旅行団はヨーロッパ公演を目的に出発する。
彼らの旅は、単なるツアーではなく「音の巡礼」であった。
電源もステージもない野外で、風・水・群衆・電波と即興的に共鳴する演奏を展開した。
旅程(Mermaid地図)
注記: この旅程は実際の記録・証言をもとにしたおおよそのルートであり、 各地での即興パフォーマンスは現地の文化施設・野外・学生運動の拠点など多岐に及んだ。
VI. 音の解体と拡張:即興という儀式
タージ・マハル旅行団の演奏は、通常の「曲」や「構成」を持たない。 むしろ、環境の中に音を放ち、偶然の共鳴を待つ行為に近い。
彼らはPAシステムやマイクロフォンを創造的に使用し、 空間全体を一種の「共鳴体」として扱った。 リーダーである小杉は、ヴァイオリンに接触マイクを貼り、フィードバックや電波ノイズを操りながら、 音が「発生しては消える」生態系を構築した。
VII. 《Taj Mahal Travelers – July 15, 1972》の記録
彼らの活動の頂点が、1972年に発表されたアルバム 《Taj Mahal Travelers – July 15, 1972》(CBS/Sony)である。 これはアグラのタージ・マハル周辺で行われた即興演奏のライブ録音で、 時間・空間・音響が完全に融合した「音の風景」として高く評価されている。
アルバムには、リズムも旋律も存在しない。 代わりに、風の音、電子音、声、弦の共鳴がゆるやかに交差し、 聴く者を「音の内側」に誘う体験が提示されている。
VIII. 海外活動と《Catch-Wave》(1975)
ヨーロッパ滞在後、小杉は1970年代半ばからアメリカに拠点を移し、 電子音響と即興を融合したソロ活動を展開する。 1975年の代表作《Catch-Wave》(EM Records再発)は、 ヴァイオリン、テープ・ディレイ、フィードバックを駆使したサウンドスケープ作品であり、 ブライアン・イーノやロバート・アシュリーにも影響を与えた。
IX. 後年の活動と評価
小杉は1980年代以降、マース・カニングハム舞踏団の音楽監督を務め、 ジョン・ケージの理念を継承しつつ、舞踏と音響の統合を深めた。 晩年まで「音は自然現象である」という信念のもと、即興・環境・沈黙のあいだを漂う表現を続けた。
X. 小杉武久とタージ・マハル旅行団の遺産
今日、彼らの活動は「サウンド・アート」「フィールド・レコーディング」「アンビエント音楽」など、 多様な音楽潮流の源流として再評価されている。 音を「素材」でも「情報」でもなく、「現象」として聴く態度。 それが、小杉が私たちに遺した最も重要なメッセージである。
年表
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1938 | 神奈川県横浜市に生まれる |
| 1960 | 東京藝術大学音楽学部卒業 |
| 1961–63 | 一柳慧、武満徹らと前衛的実験音楽活動に参加 |
| 1964 | 《Collective Music》結成、ケージ&チューダーと共演 |
| 1965–68 | Fluxus的パフォーマンスを展開(草月アートセンター等) |
| 1969 | 《タージ・マハル旅行団》結成 |
| 1971–72 | インド~欧州を巡る音楽巡礼 |
| 1972 | 《Taj Mahal Travelers – July 15, 1972》発表 |
| 1975 | ソロ作《Catch-Wave》発表 |
| 1977–90s | マース・カニングハム舞踏団音楽監督 |
| 2018 | 逝去。享年80。 |
ディスコグラフィー(主要作品)
| タイトル | 年 | リンク |
|---|---|---|
| Taj Mahal Travelers – July 15, 1972 | 1972 | Amazon |
| Taj Mahal Travelers – August, 1974 | 1974 | Amazon |
| Catch-Wave | 1975 | Amazon |
結語 ― 音の自由と祈り
タージ・マハル旅行団の旅は、単なる「バンドの海外公演」ではなかった。 それは、音楽という制度を超え、世界と共鳴するための精神的な旅路だった。
“We are travelers, not performers.” ― Takehisa Kosugi
彼らの放った音は、半世紀を経た今も、 空気の中、記憶の中、そして聴く者の心の奥で静かに振動し続けている。