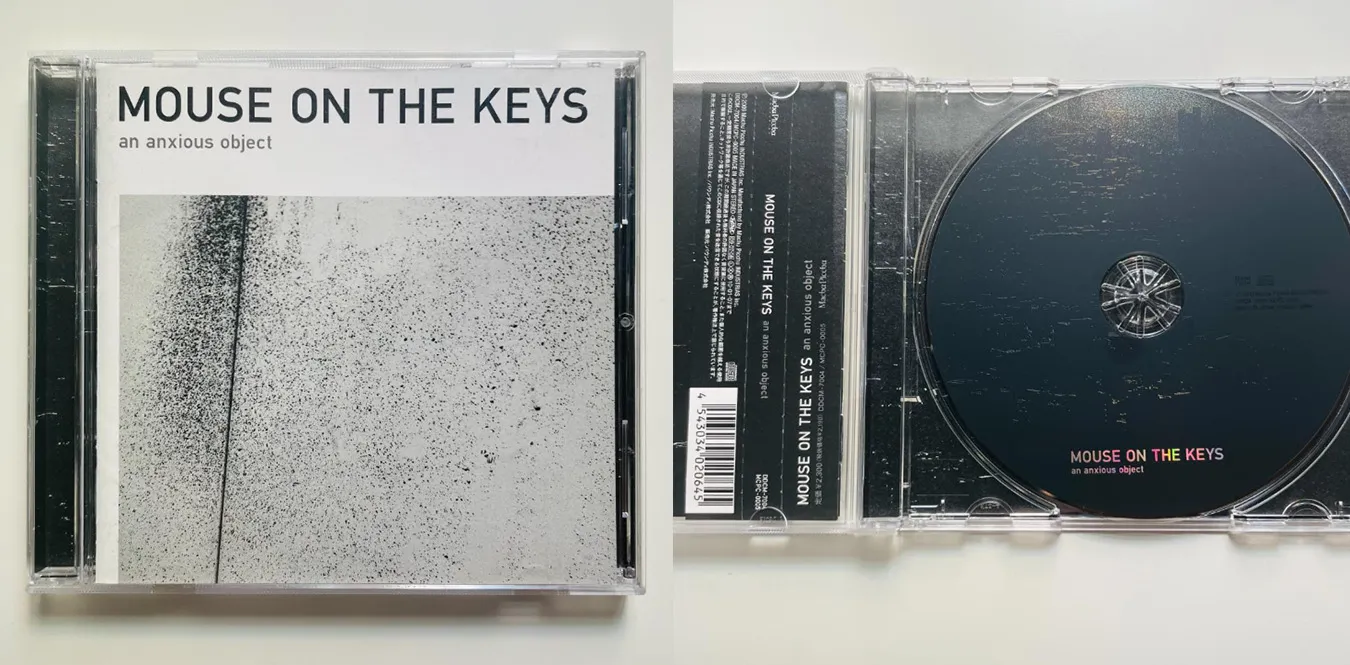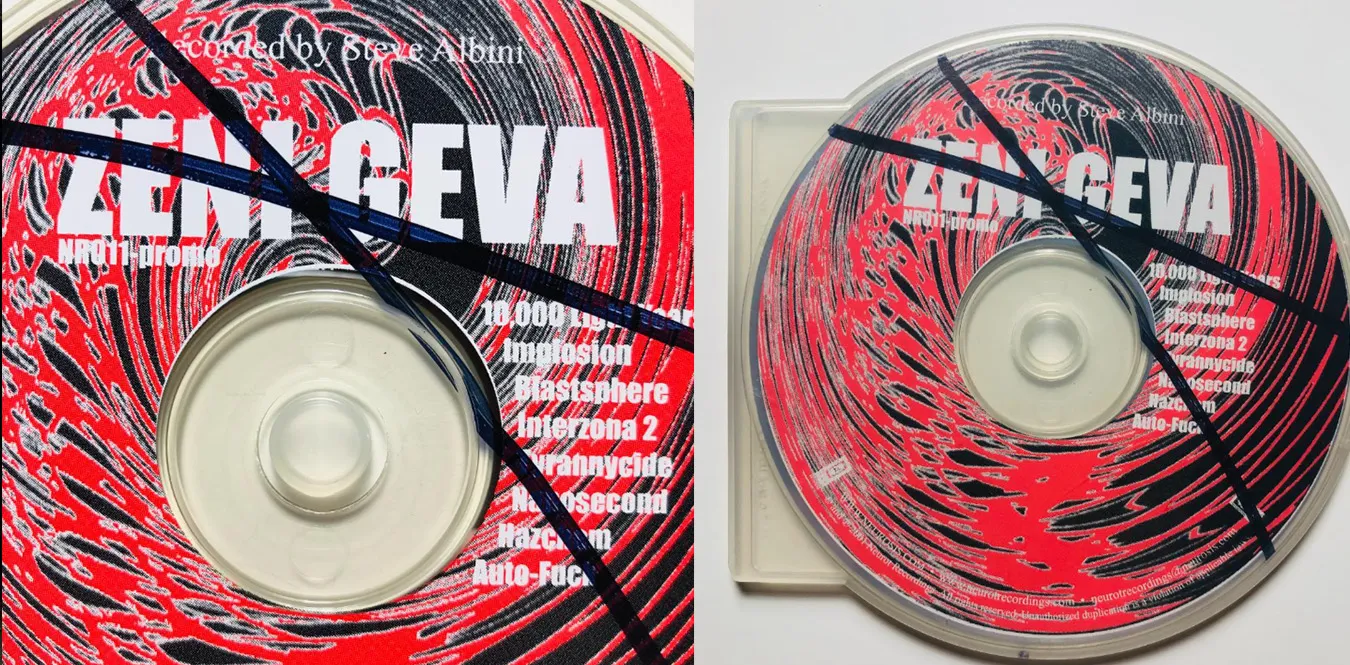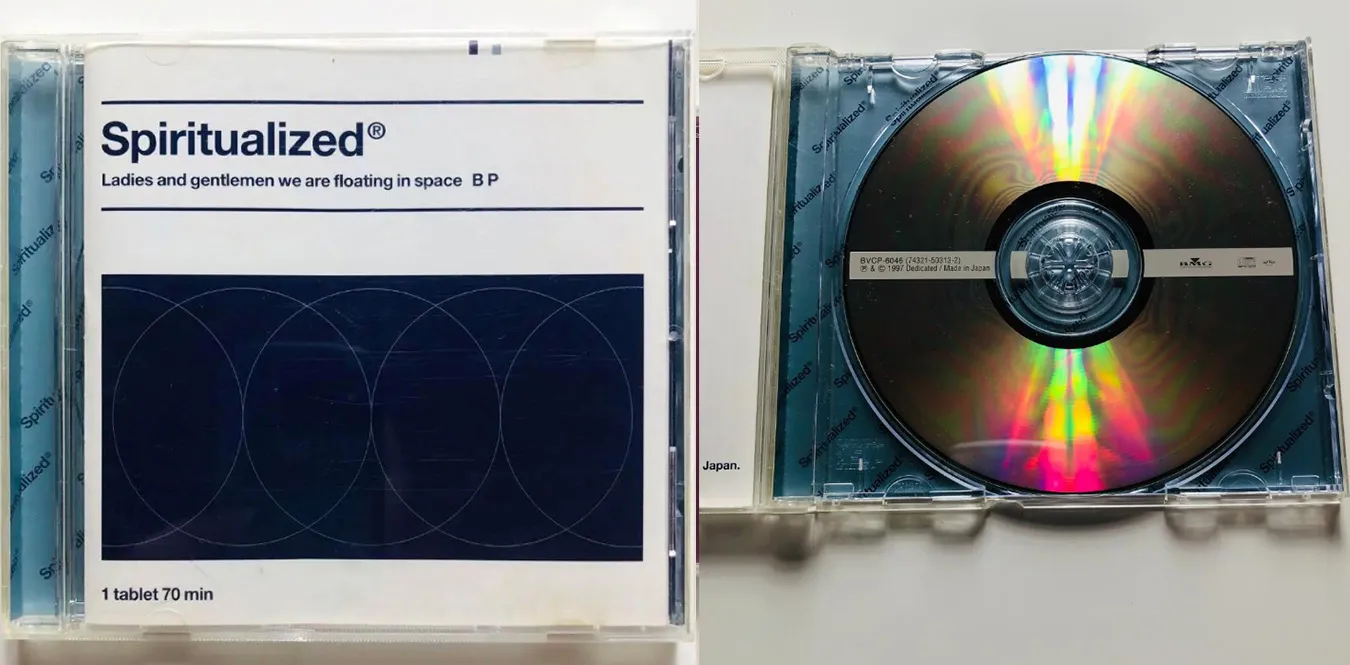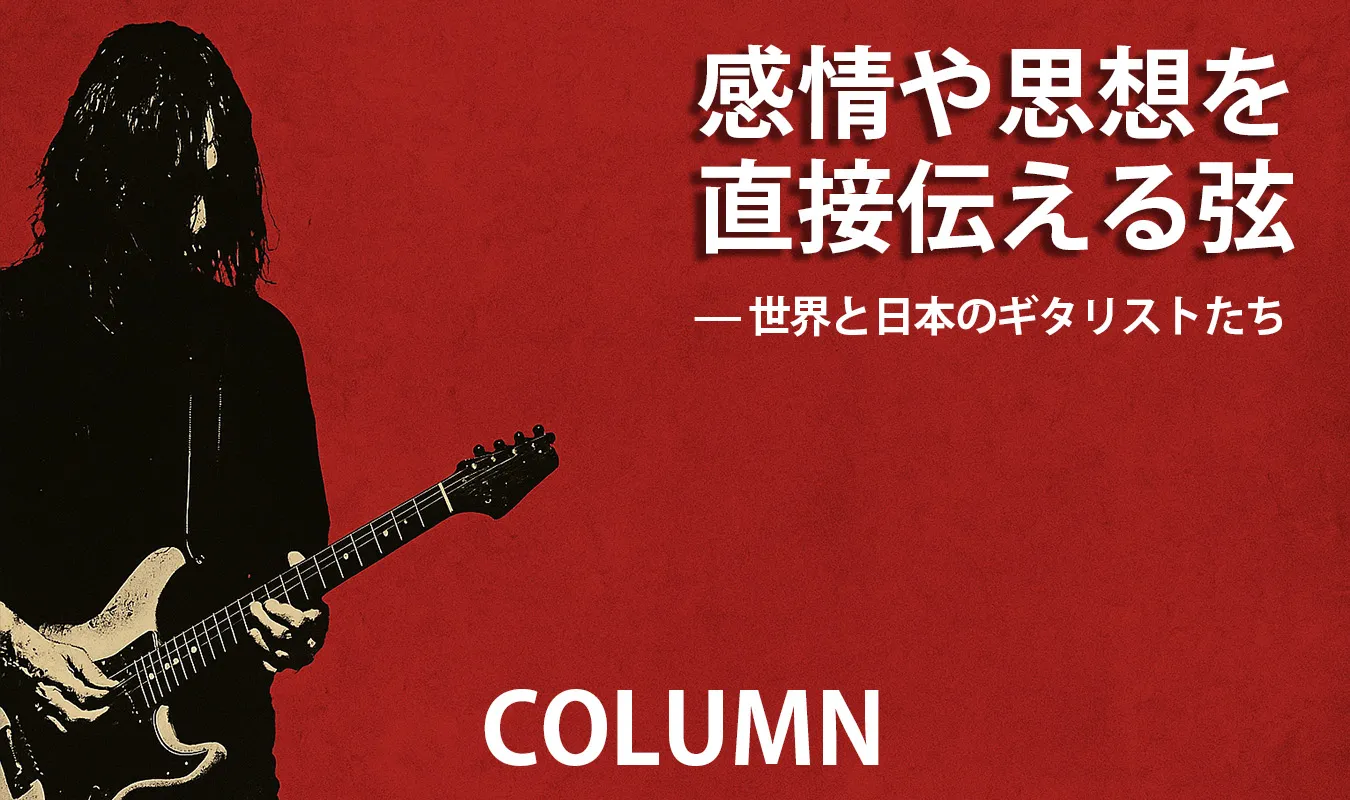
序章:ギターという“身体の記録装置”
文:mmr|テーマ:世界と日本の代表的ギタリストを年代・ジャンル・技法・思想の観点から解説
ギターは単なる楽器ではなく、20世紀以降の音楽史において、感情や思想を直接伝える身体の拡張装置として機能してきた。弦に指を触れる瞬間、音は手指の振動から生まれ、アンプやエフェクターを通じて世界に届く。ギターが生み出す音色は、その人の感情、精神状態、さらには文化的背景までも写し取る鏡のような役割を持つ。
世界と日本では、ギタリスト像は異なる。アメリカやイギリスでは、ブルースやロックが基盤となり、メインストリーム中心に進化してきた。しかし、日本では戦後のエレキブームからアンダーグラウンドのノイズ、即興、ポストロックに至るまで、より複雑で自由な発展を遂げている。メインストリームの技巧と、地下の破壊的表現が交差する地点に、日本ギターの独自性が現れる。
II. 世界篇:ギターが革命を鳴らした瞬間
1. ロックの発火点(1950〜60年代)
Chuck Berryは、リズムギターとフレーズの融合によりロックンロールの骨格を築いた。彼の右手によるカッティングはダンスビートの基盤を作り、左手のフレーズはブルース由来ながら独自の旋律を描く。Berryの音楽は、エレキギターが若者の反抗や自由を象徴する手段になることを示した。
Jimi Hendrixは、エレクトリックギターの可能性を爆発させた。フィードバック、ワウペダル、フェイザーなどのエフェクトを駆使し、ギターを「声」として鳴らした。ライブパフォーマンスでは即興と破壊的表現を組み合わせ、ギターを単なる伴奏楽器から表現の中心装置に変えた。
Lou Reed(The Velvet Underground)は、単純なコード進行や不協和音を用いて、音楽にアート的破壊性を持ち込んだ。ポップでありながら挑発的で、アンダーグラウンドの精神を内包していた。
2. 実験と反逆のギタリズム(1970〜80年代)
Robert Fripp(King Crimson)は、複雑なリズムと即興レイヤーを駆使し、プログレッシブロックにおける革新的アプローチを確立した。
Thurston Moore & Lee Ranaldo(Sonic Youth)は、特殊チューニングや準備されたギターを使用し、偶然性を作品に積極的に取り入れた。ノイズを表現手段の一部とし、ギターが旋律や和音だけでなく空間や感情を描く道具であることを示した。
Glenn Brancaはギターオーケストラを編成し、都市的な音響の表現を可能にした。多人数ギターによるハーモニーとノイズの重層構造は、後のシューゲイザーやノイズロックに大きな影響を与えた。
Fred Frithは即興演奏で偶発性を重視し、ギターの物理的可能性を最大化。ピック、弦、ボディを多様に操作し、従来の技法を超えた表現を行った。
3. 静寂と轟音の狭間(1990〜2000年代)
Kevin Shields(My Bloody Valentine)は、轟音の壁を用いたシューゲイザーの代表。フィードバックとモジュレーションで音を空間化し、音の「質感」で感情を表現する新たなスタイルを生み出した。
David Pajo(Slint / Papa M)は、静寂を構造化するポストロックの先駆。繊細なアルペジオとリズムの組み合わせで、静と動のコントラストを生み出し、物語的な音世界を構築した。
Jim O’Rourkeは、実験音響とメロディを融合させ、ジャンル横断的なギターワークを展開。音響と歌心の両立を可能にした。
Godspeed You! Black Emperorは、ギターを叙事詩の道具として扱い、長大な楽曲で都市や社会の風景を描く。
4. 現代の越境者たち(2010〜2020年代)
Mary Halvorsonはジャズ即興と抽象表現を融合し、ギターの不可能性を可能に変える。モダンジャズとアヴァンギャルドを橋渡しする存在。
Ryley Walkerは現代フォークに精神的変奏を導入し、ブルース、ジャズ、ロックを融合。ギターは物語を語るための手段であり、感情の複雑さを映す鏡となる。
Yves Tumorは、ノイズ、ポップ、身体表現を横断。ギターは声や効果音のように扱われ、楽器の枠組みを超えた表現媒体となる。
Ichika Nito / Yvette YoungはSNS世代の技巧派。複雑なポリリズム、タッピング、ハーモニー構築により、デジタル時代のギターテクニックを刷新した。
III. 日本篇:沈黙と轟音のギタリスト史
1. 戦後からエレキ黎明期(1950〜70年代)
寺内タケシは戦後日本のエレキブームを牽引。テクニカルかつエンターテイメント性のある演奏で、若者にギターの魅力を伝えた。
Charはブルースを日本語化し、日本の音楽文化におけるギター表現を拡張。独自の旋律と技巧で国内外に評価を得た。
高中正義はフュージョンや南国風メロウを融合させ、日本ギター音楽に独自の彩りを与えた。技巧と情緒の融合が特徴。
2. アンダーグラウンドの胎動(1970〜80年代)
水谷孝(Les Rallizes Dénudés)は退廃的なギターノイズとサイケデリックな演奏で、日本のノイズ/アンダーグラウンドシーンに多大な影響を与えた。
山本精一(Boredoms / Omoide Hatoba):
- Boredoms期:リズムと破壊の儀式的演奏。ノイズ・即興・サイケを融合。
- ソロ〜Omoide Hatoba期:内省的旋律とサイケデリック表現。歌心とノイズの共存を実現。
- 日本語ロックに潜む無意識的表現を体現し、後続ギタリストへの影響は計り知れない。
灰野敬二:
- 身体派ギタリストの極致:ギター、声、身体を同時に操作し、即興演奏で極限の音世界を生む。
- 技法:ピッキング、スライド、ボウ演奏、共鳴物体操作、低音シャウト、奇声、口笛など、あらゆる身体表現を統合。
- 思想:音楽は身体の延長であり、ギターは感情と精神の鏡。破壊的音色を感情表現として昇華。
- 代表作:
- 『Live at Improvised Music from Japan』シリーズ:極限即興演奏の記録
- MERZBOWとの共演ライブ:ノイズと身体表現の対話
- 山本精一とのコラボレーション:内省と破壊が交錯する即興
- ライブの特徴:
- 数時間に及ぶ長尺即興
- 身体全体を使った演奏(弦、ボディ、声)
- 聴覚だけでなく、空間感覚や身体感覚に訴える体験型パフォーマンス
- 影響:日本のアンダーグラウンドシーン全体に大きな足跡を残し、後続ギタリストや実験音楽家の精神的指標となる。
MERZBOW(秋田昌美)はノイズの純粋形態を追求。ギターや電子機器を用い、極限表現を展開。
3. ポストロックと叙情の建築(1990〜2000年代)
MONOはギターで光や祈りを描くポストロックバンド。長大な曲構造とアルペジオの叙情性が特徴。
toeはリズム構造としてのギターを探求。数学的精密さと感情表現を両立。
envyは激情ハードコアに叙情ギターワークを融合させ、独自の感情表現を確立。
Borisは轟音と多彩なジャンル融合で国際的評価を獲得。
Zeni Gevaはメタルとノイズを融合し、破壊的即興表現を行う。
4. 新世代の孤高(2010〜2020年代)
Ichika NitoはSNS世代の技巧派で、ポリリズム、タッピング、ハーモニー構築を駆使。YouTubeを通じて世界に発信。
青葉市子はアコースティックギターで夢幻的民話表現を行う。
七尾旅人はギターと歌詞を融合させ、現代詩的音楽表現を展開。
山本精一以降の影響:内向・即興・アンダーグラウンド表現を継承する若手ギタリストが登場。
IV. ギターの再定義:装置・身体・祈り
ギターは単なる楽器ではなく、自己表現の装置である。
- ペダルボードの思想:音作り=自我デザイン。個々のペダルが奏者の人格の拡張となる。
- ループ・グリッチ・DAW:拡張された“指の記憶”。単一の演奏者がオーケストラ的表現を可能に。
- 山本精一×Jim O’Rourke:京都アンダーグラウンドから世界へ橋渡し。国内外の即興・実験音楽に影響。
灰野敬二は、ギターを身体と精神の延長として扱い、音の極限で聴き手の感覚を揺さぶる存在である。即興・破壊・表現の三位一体が、日本アンダーグラウンド・ギター史における重要な座標となる。
V. 結章:鳴り止まない弦の余韻
ギターは地下から世界まで、常に自由な表現の象徴であり続けた。技術よりも、奏者の温度と思想が問われる時代が訪れている。
ギターの弦の震えは、時代を超えて鳴り続ける。
年表(1950〜2020)
ディスコグラフィー
| アーティスト | 代表作 | リンク |
|---|---|---|
| 山本精一(Seiichi Yamamoto) | 『カフェ・ブレイン』 | Amazon |
| 灰野敬二(Keiji Haino) | 『Watashi Dake?(わたしだけ?)』 | Amazon |
| BORIS | 『Gensho(with Merzbow)』 | Amazon |
| MONO | 『Hymn to the Immortal Wind』 | Amazon |
| Kevin Shields / My Bloody Valentine | 『Loveless』 | Amazon |
| Sonic Youth | 『Daydream Nation』 | Amazon |
| Chuck Berry | 『The Great Twenty-Eight』 | Amazon |
| Char(竹中尚人) | 『Smoke』 | Amazon |
| 寺内タケシ | 『エレキ・ギターのすべて』 | Amazon |
| 青葉市子 | 『0(ゼロ)』 | Amazon |
| toe | 『the book about my idle plot on a vague anxiety』 | Amazon |
| Yvette Young / Covet | 『technicolor』 | Amazon |
| Fred Frith | 『Guitar Solos』 | Amazon |