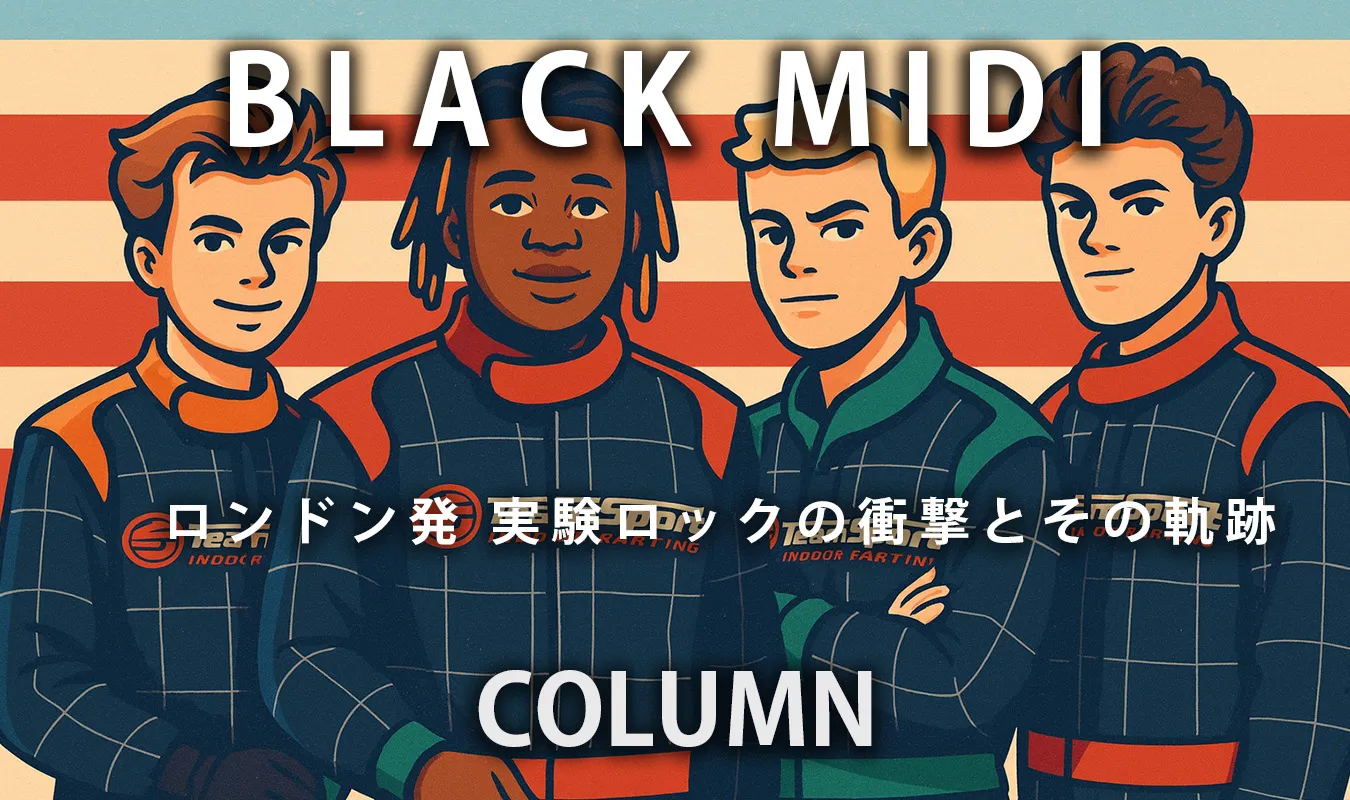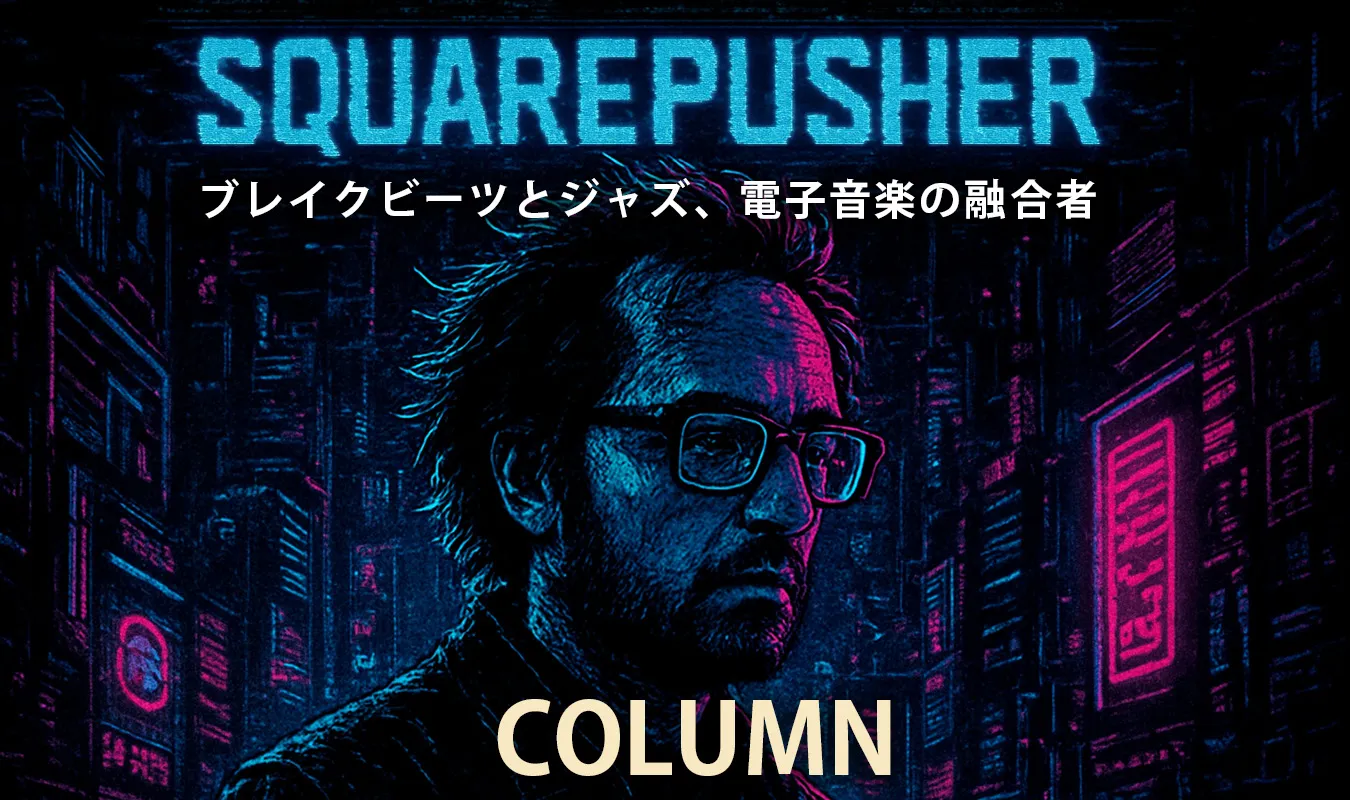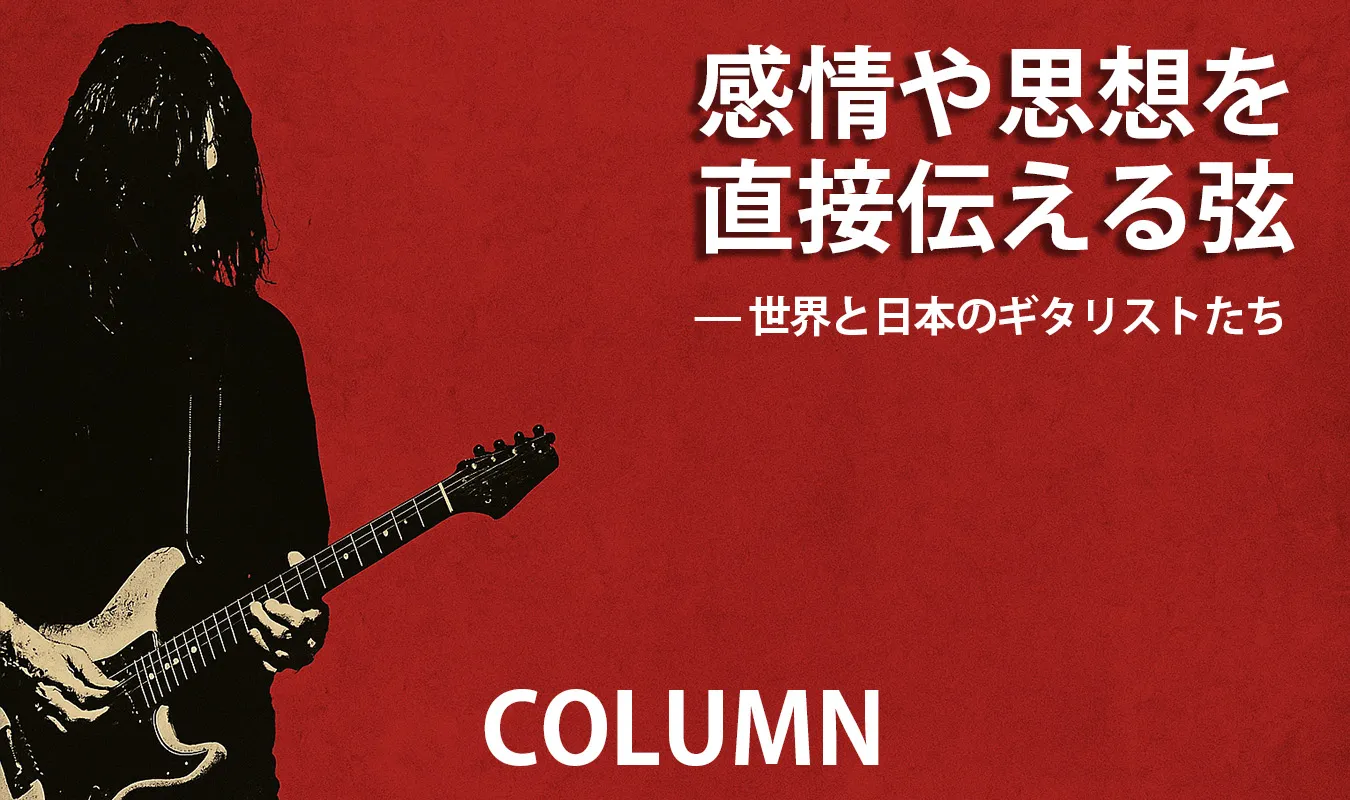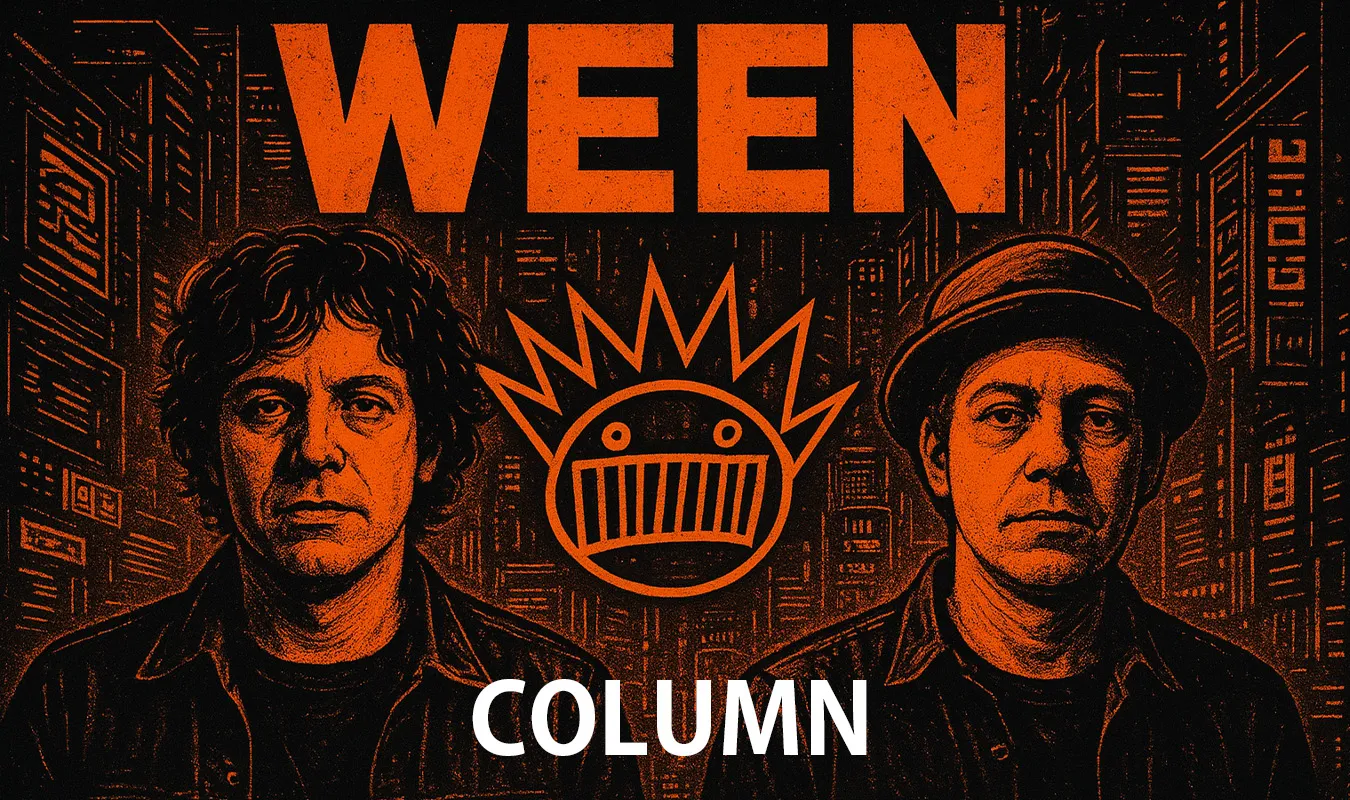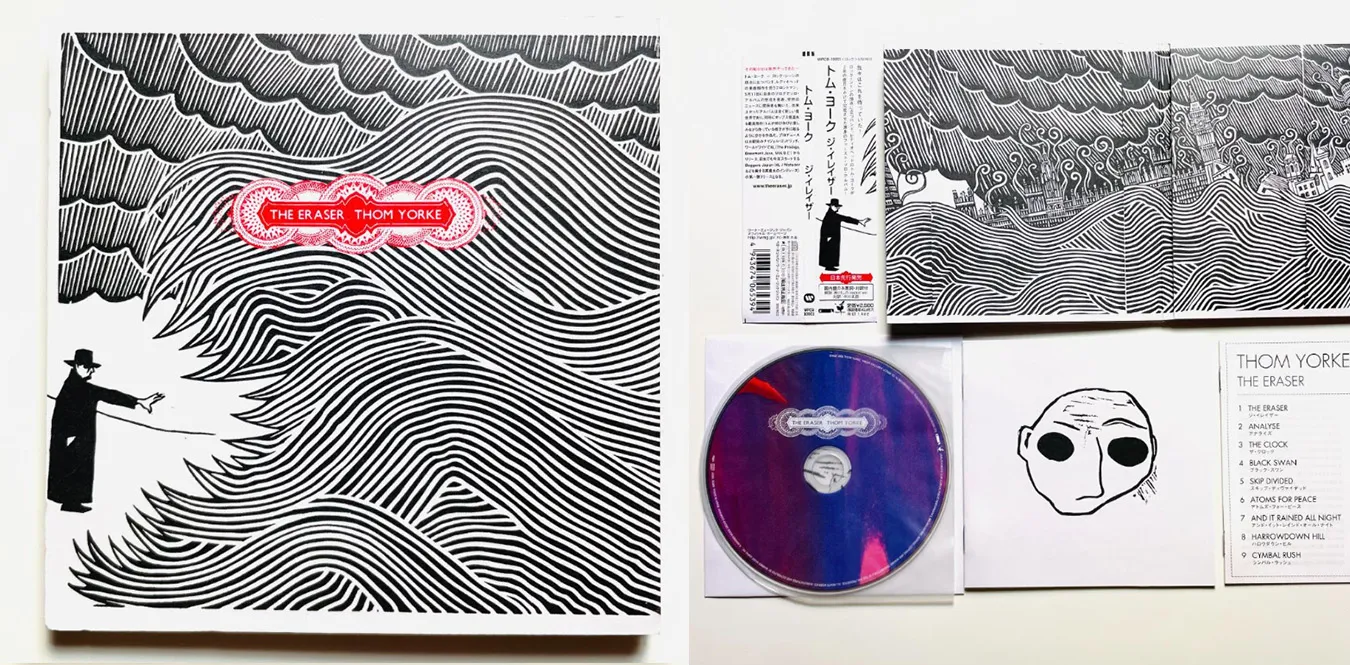世界と日本の鼓動:地上と地下をつなぐリズムたち — 沈黙と衝動、伝統と実験のあいだ —
文:mmr|テーマ:世界と日本を貫く「リズム」の系譜──地上と地下をつなぐドラマーたちの200年史
歴史の中心にいたドラマーたちの影には、地下で時代を先取りしていた実験者たちがいる。
Buddy RichやJohn Bonhamがメインステージを制覇した時代にも、どこかの倉庫や小さなジャズバーで、別の鼓動が鳴っていた。
彼らはしばしば過剰すぎ、自由すぎ、理解されにくかった。
だが、その“余白”から新しいリズムが生まれた。
アンダーグラウンドのドラマーたちは、楽器よりも「時間」を叩いていた。
それは国家でもジャンルでもない、「感覚共同体」の言語だった。
序章:リズムとは何か — 打撃と呼吸の文化史
打楽器とは、音楽の始まりであり、世界の心拍である。
アフリカの集落での太鼓は言葉の代替であり、ラテンアメリカのコンガは祈りの継承。
そして産業革命以後の都市では、それは機械のリズムとシンクロする存在となった。
ドラムセットが誕生したのは20世紀初頭。
スネア、キック、ハイハットという組み合わせが人間の手足の延長として設計され、
ジャズがそれを「即興の構造体」に変えた。
ジーン・クルーパ、バディ・リッチ、アート・ブレイキー──
彼らが叩いたのはリズムというよりも、存在そのものだった。
リズムは支配でも伴奏でもなく、バンドという共同体の“心拍”であり、
それを鳴らすドラマーは、同時に哲学者でもあった。
第1章:世界の鼓動 — リズム革命の系譜
1-1. ジャズ黄金期:アート・ブレイキーからエルヴィン・ジョーンズへ
アート・ブレイキーの「モーニン」が象徴するように、
ジャズの黄金期、ドラムは「対話」の中心にあった。
リーダーであるブレイキーはドラムを通して若手を育て、
エルヴィン・ジョーンズはコルトレーンの“宇宙的推進力”となった。
リズムは単なるグルーヴではなく、時間と空間の拡張そのものだった。
1-2. ロックの爆発:ジンジャー・ベイカーとジョン・ボーナム
1960〜70年代、ドラムは「反逆の象徴」へと変貌する。
ジンジャー・ベイカー(Cream)はアフロ・ポリリズムをロックに導入し、
ジョン・ボーナム(Led Zeppelin)は爆発的な音圧で“ドラムソロ”を芸術にした。
ボーナムの「When the Levee Breaks」におけるスネアのリバーブは、
以後のヒップホップ・ビートの原型にもなる。
1-3. 正統の軸:Buddy Rich, Tony Williams, Steve Gadd
Buddy Richはスピードの象徴、Tony Williamsは自由の象徴、Steve Gaddは精密の象徴。
彼らが築いた“ドラマーの理想像”は、20世紀音楽の骨格そのものだった。
しかし同時期に、規律から逸脱するドラムが地下で蠢いていた。
1-4. アフリカの鼓動:Tony Allenとポリリズムの革命
Fela Kutiの相棒として知られるTony Allenは、「アフロビート」を発明した男だ。
そのリズムは“反体制”の象徴であり、軍政下のナイジェリアで民衆のエネルギーを可視化した。
ドラムは政治だった。音がプロテストだった。
1-5. ヨーロッパ前衛の衝撃:Han Bennink, Christian Lillinger
オランダのHan Benninkは、ステージ上で椅子も壁も叩く。
彼にとって「音」は物体との出会いそのものだ。
ドイツのChristian Lillingerは、ポリリズムをデータ構造のように操り、現代音楽とクラブカルチャーを接続する。
ヨーロッパの実験ドラマーたちは、リズムを“哲学”として叩いている。
1-6. 北米の地下:Greg Fox, Deantoni Parks
Greg Fox(ex-Liturgy)はブラックメタルと即興の融合。
Deantoni Parks(The Mars Volta)は片手でサンプラー、もう片手でスネアを叩き、
「人間とマシンの同居」という21世紀的課題を身体で解く。
彼らの演奏は、宗教儀式とテクノロジーのあいだにある。
第2章:日本の鼓動 — 地上と地下をつなぐリズムたち
2-1. ポンタ以後 — 職人から思想家へ
村上“ポンタ”秀一が築いたのは「日本語で叩く」感覚。
しかし90年代以降、その文法を解体する新世代が登場する。
彼らは“間をズラす”ことで、音楽の重力を再定義した。
2-2. YOSHIMIO(BOREDOMS / OOIOO)とYo2ro — ドラムを宇宙へ放つ
Yoshimi Yokota=YOSHIMIOは、世界で最も自由なドラマーのひとり。
Boredomsの巨大ドラム・アンサンブル「77BOADRUM」は、都市を揺らす儀式だった。
彼女にとってドラムは打楽器ではなく、“生命の波動”である。
さらに Yo2ro は、Boredomsやその他の実験音楽プロジェクトで活躍し、
ポリリズムの縦横を自在に操ることで、YOSHIMIOの宇宙的ビートと呼応する。
Yo2roのスネアは、叩くたびに空間を変形させる力を持ち、
日本のアヴァンギャルド・ドラマーの象徴的存在として注目されている。
2-3. 内田裕也以降のロック反逆者たち:中村達也、池畑潤二
中村達也はドラムを暴力でもあり詩でもあるものに変えた。
「忌野清志郎」や「Blankey Jet City」といった文脈を超え、
身体の叫びを音として具現化した存在。
池畑潤二は、ブルースを日本語に翻訳したドラムを叩く。
そのスティックには昭和の風と反骨がある。
2-4. 実験と瞑想:山本達久、芳垣安洋、Hachito Matsumoto、灰野敬二
山本達久(坂田明、ジム・オルークとの共演)は、空気そのものを叩くような音を出す。
そのリズムは、時間が止まる瞬間を可視化する。
芳垣安洋(ROVO, Orquesta Nudge! Nudge!)は、クラブミュージック的構造と即興を統合。
Hachito Matsumoto(ex-Paellas)は、ポスト・インディーズ時代の都市感覚を叩き出す。
灰野敬二は、ノイズ、即興、祈りの境界を超えた打撃を行う。
いずれも「沈黙の中の衝動」をテーマにしている。
2-5. 新世代の流動:石若駿、Utena Kobayashi、坂本暁良、Yo2ro
石若駿は東京J-Jazzの象徴だが、millennium paradeやceroなどポップ領域も自在に横断する。
Utena Kobayashi(ブラックミディ的ポリリズム+和太鼓的構造)は、ジェンダーとジャンルを超える存在。
坂本暁良(DOWNY, MONO NO AWARE)は、静謐さと暴力の境界線を叩く。
そして Yo2ro は、Boredomsを含む現代音楽・即興プロジェクトで培った経験を踏まえ、
伝統的リズムと前衛即興の接点を現代都市に響かせる。
彼らは「個人のリズム」=世界の文法を再構築している。
第3章:リズムの未来 — 機械と肉体の新しい関係
AIドラム、MIDIトリガー、触覚デバイス。
打楽器の未来は、人間の身体性を再定義する試みでもある。
しかし、どれほどテクノロジーが進化しても、
リズムの原点は「息」と「心拍」にある。
ジェフ・ミルズが言うように、
「ドラムマシンは未来のジャズだ」。
彼のライブでは、TR-909がまるで生物のように鳴動する。
そして灰野敬二が続けるように、
「沈黙こそ音楽の一部である」。
終章:鼓動の系譜 — 世界と日本を貫く一本のリズム
世界の鼓動と日本の鼓動は、いま確実に交差している。
ニューヨークのロフト、ベルリンの倉庫、東京の地下スタジオ。
どこでもドラムは、心臓のように鳴り続けている。
アート・ブレイキーの“魂の拍”、
ジョン・ボーナムの“爆音の詩”、
灰野敬二の“沈黙の爆発”、
山本達久の“呼吸の音”、
YOSHIMIOとYo2roの宇宙的ビート。
それらは一見、異なる世界に思える。
だが、聴く者の胸に宿るリズムは同じだ。
それは「地上と地下をつなぐ鼓動」──
そして未来へと続く音楽の記憶である。
ディスコグラフィー
| アーティスト | アルバム | 年 | リンク |
|---|---|---|---|
| Art Blakey & The Jazz Messengers | Moanin’ | 1958 | Amazon |
| Elvin Jones | Live at the Lighthouse | 1972 | Amazon |
| Tony Allen | HomeCooking | 2002 | Amazon |
| John Bonham (Led Zeppelin) | Led Zeppelin IV | 1971 | Amazon |
| Ginger Baker (Cream) | Wheels of Fire | 1968 | Amazon |
| Jeff Mills | Live at the Liquid Room, Tokyo | 1996 | Amazon |
| Tony Williams | Lifetime: Emergency! | 1969 | Amazon |
| 村上“ポンタ”秀一 | Rhythm Designer | 1994 | Amazon |
| 日野元彦 | Alone Together | 1979 | Amazon |
| 吉田達也 (Ruins) | Hyderomastgroningem | 1993 | Amazon |
| 灰野敬二 | Watashi Dake? | 1981 | Amazon |
| 山本達久 | Red Oni | 2010 | Amazon |
| 芳垣安洋 (ROVO) | Pyramid | 2005 | Amazon |
| 坂田学 | One | 2016 | Amazon |
| Jim O’Rourke × 山本達久 | Simple Songs | 2015 | Amazon |
| Keiji Haino & Merzbow & Balázs Pándi | Become the Discovered, Not the Discover | 2019 | Amazon |