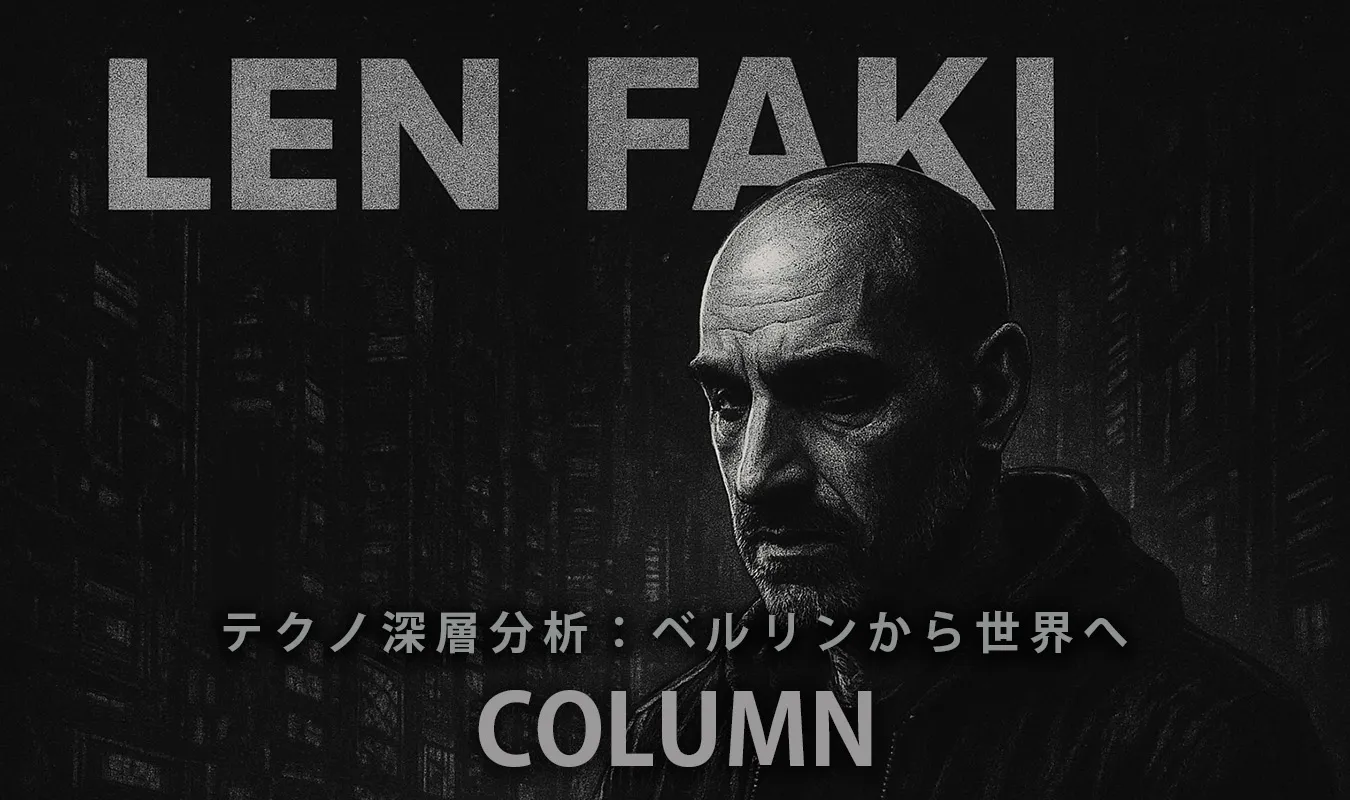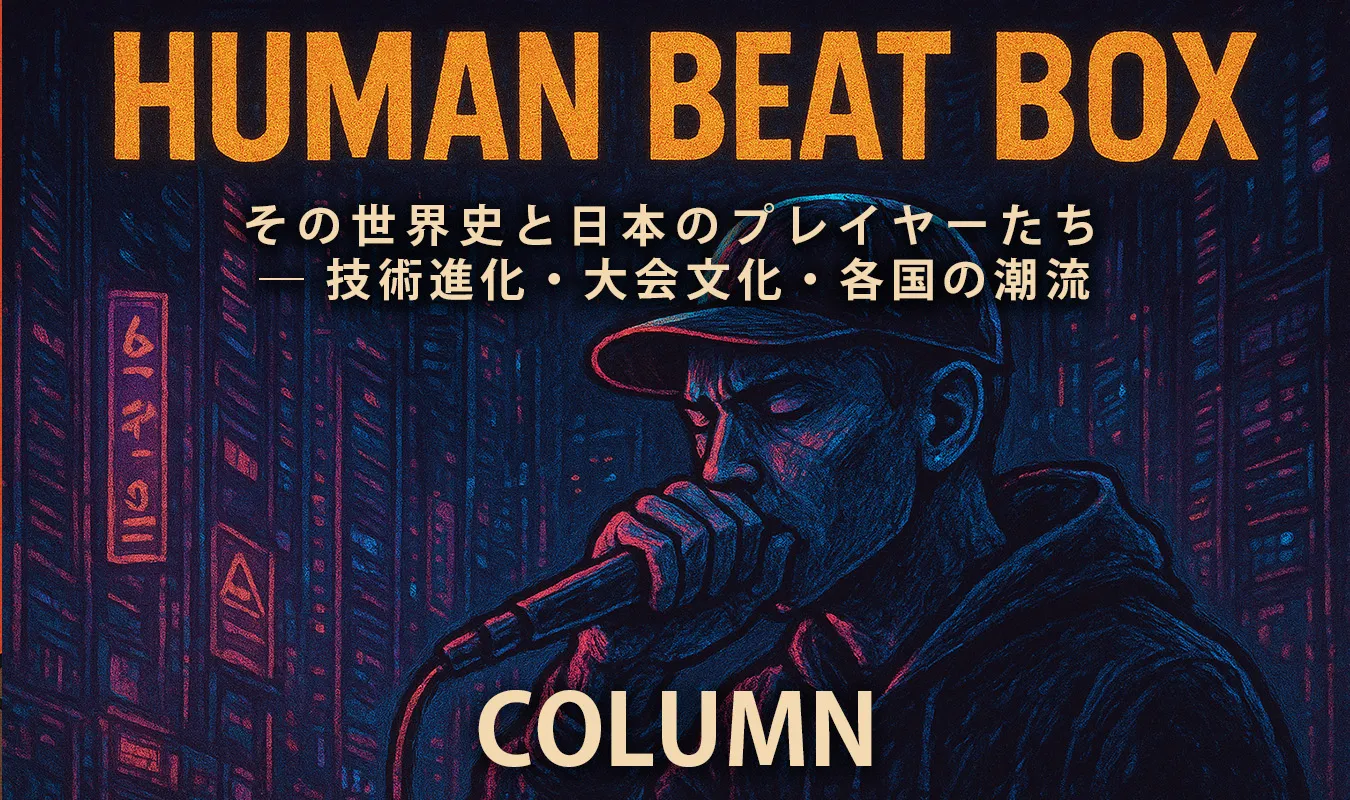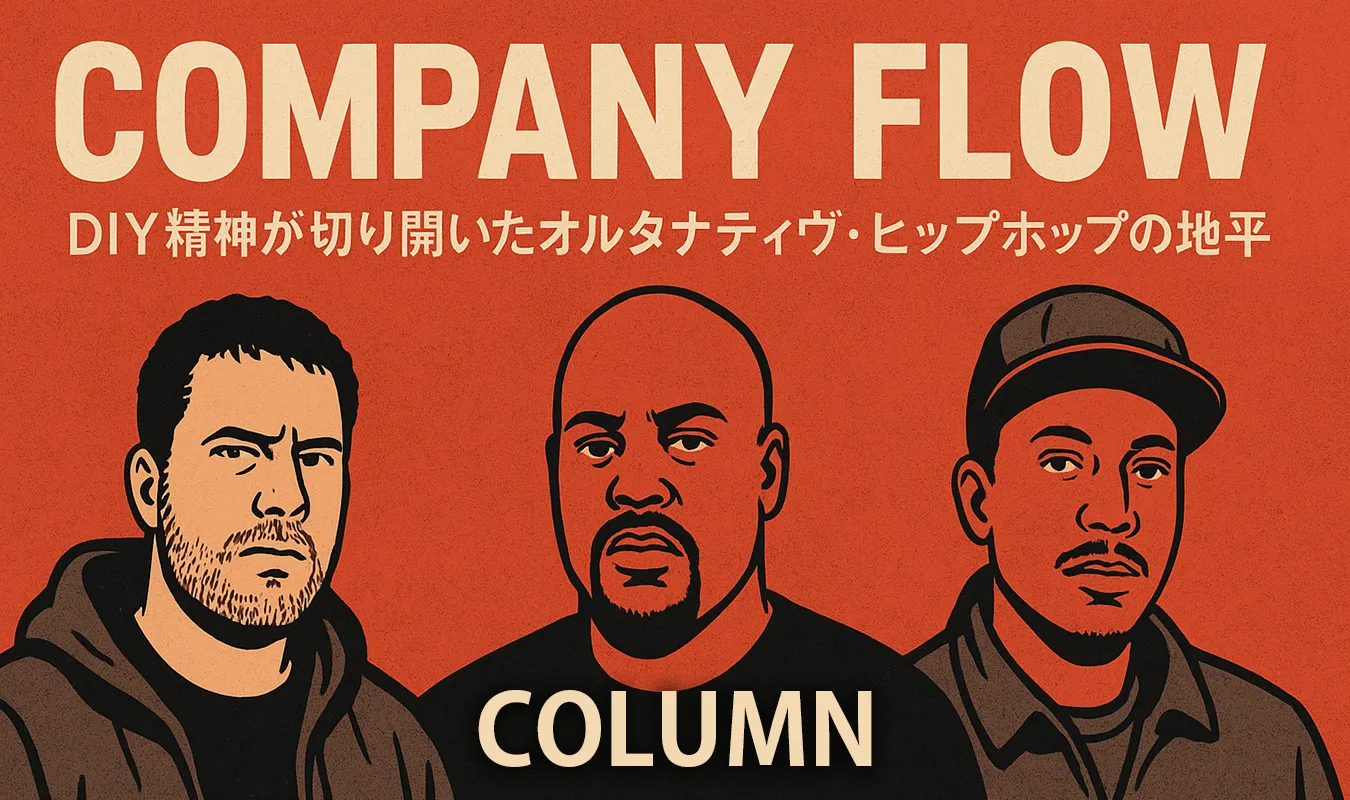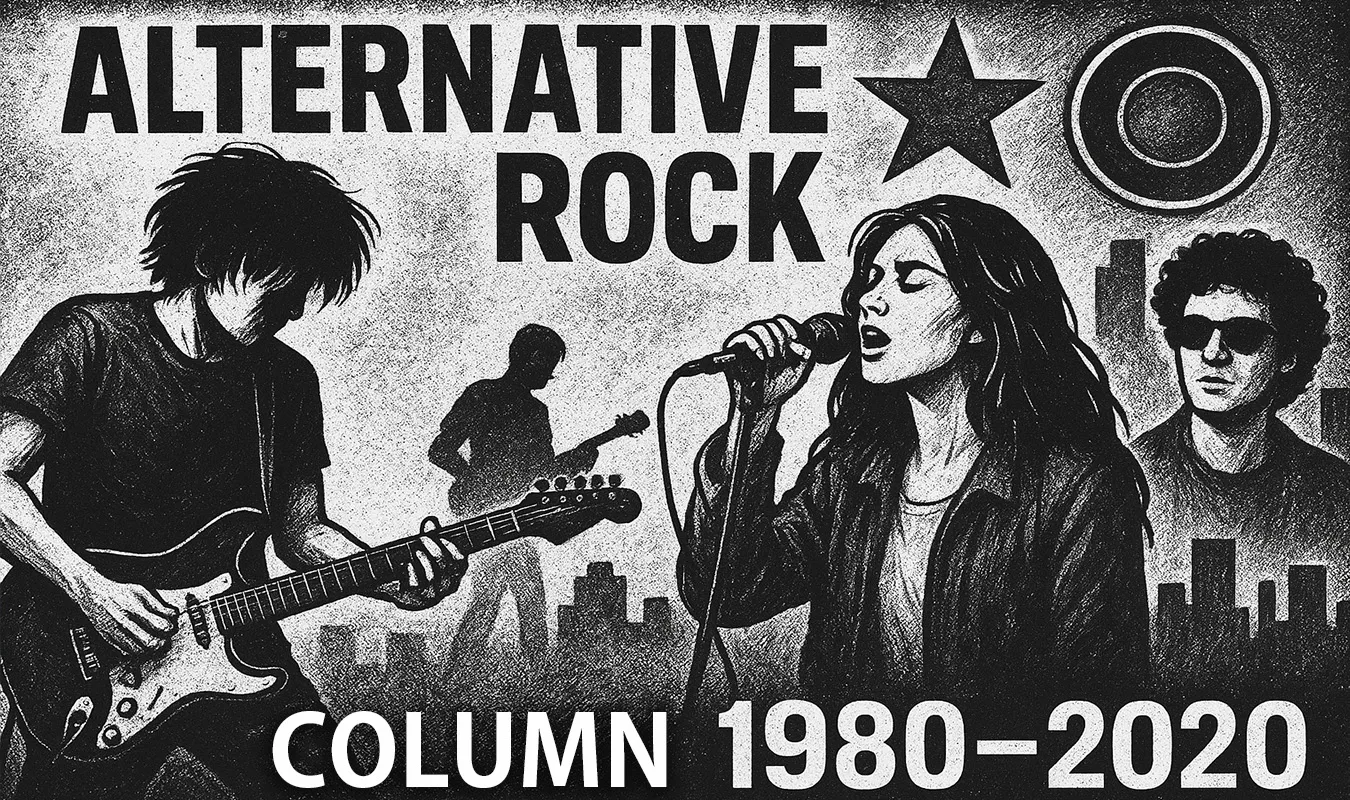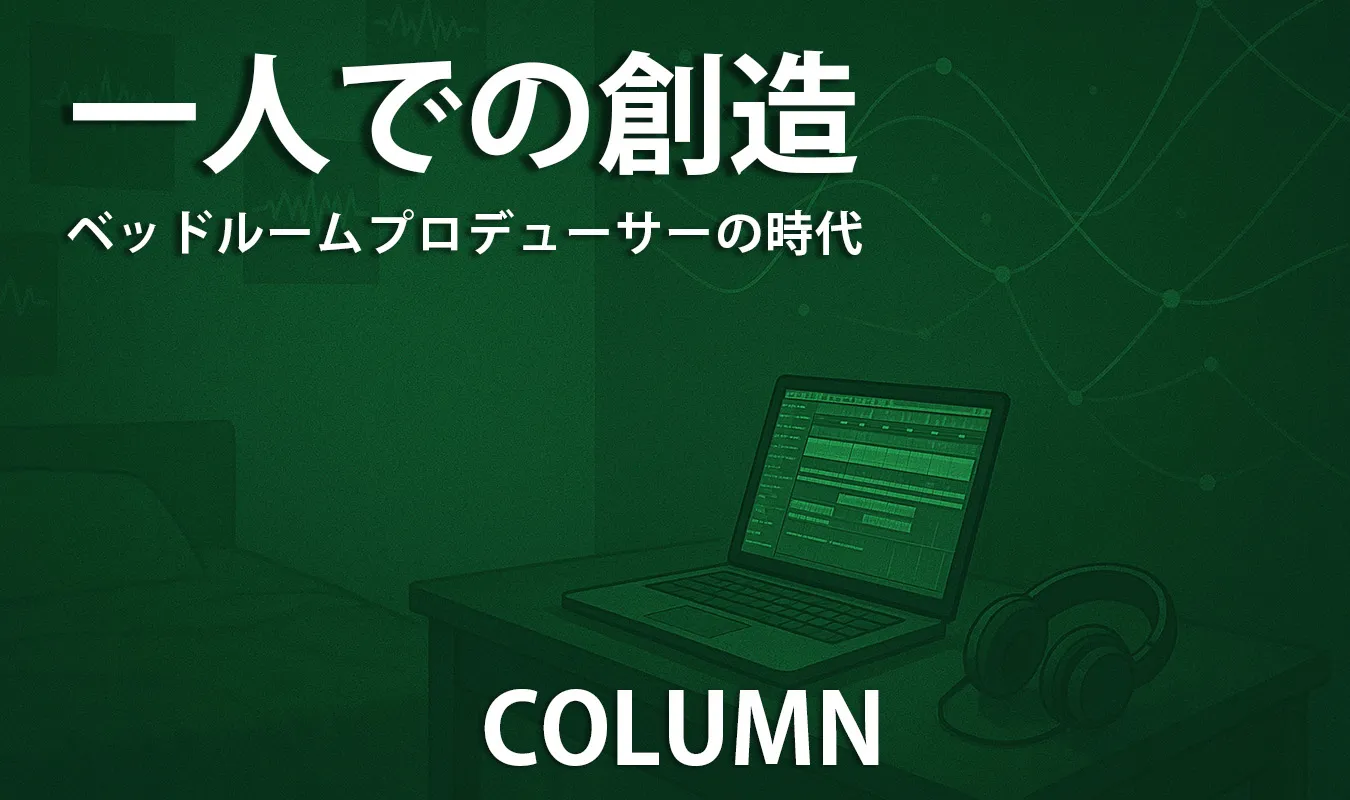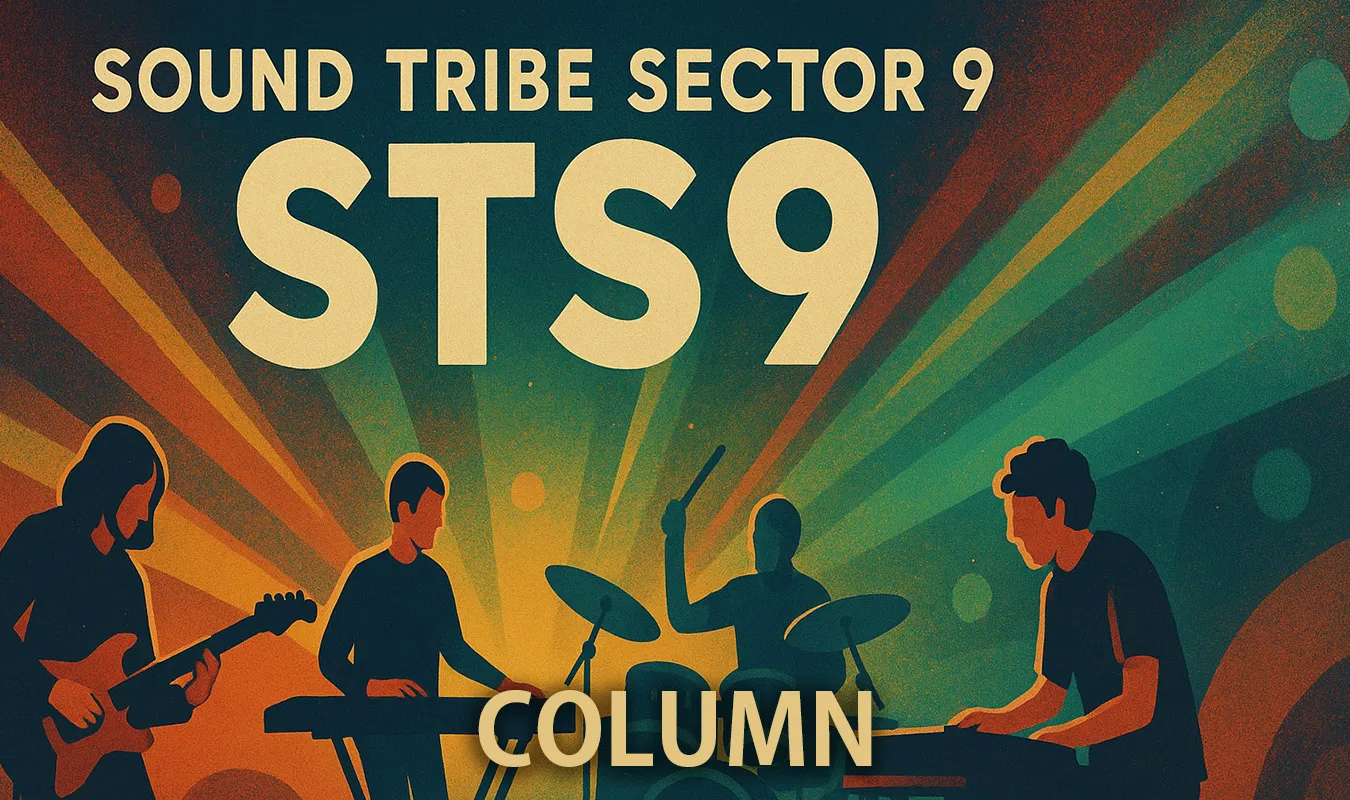
即興創作與電子音樂交叉的 21 世紀前衛現場音樂
文:mmr|主題:STS9從形成到現在的歷史、音樂特色、現場哲學、代表作品、文化社會影響
Sound Tribe Sector 9 (STS9) 被稱為“livetronica”的代表,從 20 世紀 90 年代末至今,它在美國現場場景中經歷了獨特的演變。 他們的音樂融合了即興樂隊的即興本質、電子音樂的結構和質感以及俱樂部文化的節奏,使他們不同於搖滾樂隊或電子音樂團體。
他們的立場始終是“音樂=現場空間的體驗”,他們強調自治社區的形成,從製作到巡演管理、舞台指導和社交活動。
1. 組建前的歷史(~1997):誕生於亞特蘭大周圍的“既不是樂隊也不是 DJ”風格
STS9的起源可以追溯到20世紀90年代中期,當時活躍在亞特蘭大地區的音樂家組成 “是否可以通過現場音樂營造 DJ 在俱樂部中營造的氛圍?” 據說是從這個問題開始的。
成員們有著廣泛的背景,包括搖滾、爵士、放克、電子音樂,甚至世界音樂。尤其是鼓/打擊樂團隊所強調的“律動第一合奏”,成為了從開始一直延續至今的重要核心。
1997年左右,罕見的 Electronica x 現場合奏團 這個方向成立了,並開始命名為 Sound Tribe Sector 9。
2. 1998-2002:早期作品及巡演文化適應
2-1.出道時代 ― 星際逃生飛行器 (1998)
他們1998年發行的首張專輯《Interplanetary Escape Vehicle》與現在的STS9相比,現場表演的感覺更強,混合了後搖滾般的吉他寬廣、非洲節拍般的節奏和爵士樂般的合奏。
當時,混合電子音樂和即興創作的“livetronica”樂隊,例如The Disco Biscuits和The New Deal,開始在美國興起,而STS9就被定位為這一趨勢的一部分。
2-2.與節慶文化的共鳴
在此期間,STS9積極參加當地的節日演出。 “俱樂部/節慶/現場樂隊平等相交” 我們已經確立了獨特的地位。
- 長篇即興創作
- DJ 般的循環感覺
- 具有世界觀的燈光和視頻製作
這些在當時的搖滾樂壇中並不多見,被觀眾形容為“會演奏的DJ組合”。
3. 2003-2008:成熟的電子音樂和黃金時代
3-1. Artifact (2005) - STS9 的標誌性作品
2005年的《神器》被認為是STS9的代表作。
合成器層、編程節拍和厚重打擊樂的多層結構完全使他們遠離了即興樂隊框架,進入了更加電子化的音樂方向。
代表歌曲:
- “阿特拉斯”
- “某物”
- “阿里加托”
- “東京”
- “人們”
這些都是當前歌單中經常播放的歌曲,最能體現STS9的音樂形象。
《Artifact》是一首將STS9的聲音和創造力發揮得淋漓盡致的作品,以其獨特的聲音和創新的手法在電子音樂和即興樂隊界贏得了高度讚譽。
他們的聲音融合了多種流派的元素,包括環境音樂、電子音樂、爵士樂、放克音樂和迴響貝斯。
A2的《Tokyo》被稱為STS9的招牌歌曲,經常在現場表演中演奏。
《Artifact》是STS9職業生涯中的一張重要專輯,也是樂隊歌迷的必備專輯。
曲目列表
A1. Possibilities
A2. Tokyo
A3. Vibyl
B1. Peoples
B2. Somesing
B3. Better Day
Youtube
3-2.現場安排的演變
同期的直播結構是
- 碎拍
- 慢節奏
- 類似IDM的模式
- 長篇即興創作 觀眾以“舞蹈”為前提過渡到地板/節日類型的體驗。
這裡重要的是STS9追求一種用吉他和貝斯再現“電子音樂質感”的技術。 許多部分都經過效果鏈,形成了 DAW 中的編輯思維直接反映在現場表演中的特點。
4. 2009-2014:獨立廠牌、社交活動、片場結構的深化
4-1.獨立廠牌1320條記錄管理
STS9推出了自己的廠牌1320 Records, 除了自己的工作之外,他們還支持具有相似音樂抱負的藝術家。
它的獨特之處在於它不僅僅是一個專輯製作的地方,而且還扮演著一個接近社區的角色。
4-2.社會活動及慈善文化建設
從STS9開始
- 教育支持
- 環境保護
- 當地活動 他積極參與慈善活動,例如:
也有很多演出捐贈了一部分現場門票收益,也有很多以社會問題為主題的歌曲。 尤其是《Peaceblaster》(2008)被定位為一部以政治和環境主題為背景的概念作品。
5. 2015年至今:成員變更及新階段
5-1.過渡到新系統
2014年,這位長期的吉他手離開了樂隊,並建立了以亨特·布朗為中心的新體系。 這一變化也對音樂產生了影響,更清晰、更簡約的結構變得越來越普遍。
5-2. 內部宇宙 (2016)
這張2016年的專輯更加強調合成器,並且專注於舞曲的歌曲數量也有所增加。 在現場編曲中,有很多嘗試以EDM風格重構過去的歌曲。
5-3.當前STS9
進入2020年代,STS9在保持音樂節頭條地位的同時,也舉辦自己的活動“WAVE SPELL”並加強社區活動。
6.STS9音樂特點
6-1.節奏結構:打擊樂驅動凹槽
STS9最大的特點是其以鼓和打擊樂為中心的合奏結構。 在電子音樂中,現場音樂扮演著鼓機的角色,貝斯、吉他、合成器和样本分層在上面。
- 非洲節奏
- 碎拍
- 拉丁打擊樂
- IDM細分 結合起來,徹底貫徹了“用節奏創造世界觀”的方法。
6-2.廣泛使用聲音處理和效果
為了通過現場表演再現電子樂的感覺,
- 延遲
- 活套
- 篩選
- 顆粒加工 每個儀器都積極地使用這些。
即使在現場表演期間,這也能確保聲學厚度,創造出類似於 DJ 設備的三維感覺。
7. STS9的現場哲學:佈景、燈光、社區
7-1.構建歌單
STS9每次巡演都會改變他們的演出名單,
- 開場白(世界觀介紹)
- 中場組織
- 樓層峰值
- 深沉的慢速部分
- 安可 並設計了類似於 DJ 設備結構的現場表演。
7-2.燈光/視頻:聲光一體化
燈光在 STS9 現場表演中極其重要。 一個特殊的特點是光的移動與歌曲的變化相關。 在音樂節的夜間演出中,燈光本身就像一個巨大的“舞台佈景”,增強了觀眾的沉浸感。
7-3.社區文化
STS9 的粉絲高度以社區為導向,這是即興樂隊的典型特徵。 跟團旅遊的“旅遊迷”也不少。
8.作品說明(主要專輯)
星際逃生飛行器 (1998)
它具有濃郁的早期現場音樂色彩。世界音樂的強大影響。
奉獻(1999)
即興結構和電子樂的混合體。
和平衝擊波 (2008)
基於政治和環境主題的概念作品。
內部宇宙 (2016)
這部作品更加偏向舞蹈,象徵著新的體系。
9.年表(美人魚)
10、STS9聲音的技術結構(美人魚:信號流圖)
11.文化影響力與定位
11-1。 LiveTronica 成立
STS9與The Disco Biscuits、The New Deal一起成為“livetronica”的代表, 他們建立了一種連接電子音樂和即興樂隊的新流派。
11-2。與節日文化的緊密聯繫
STS9的現場表演與節日很相配。
- 博納羅
- 電森林
- 蘇萬尼·胡拉溫 他們在“深夜”等重大音樂節上的“深夜演出”已成為傳奇。
11-3。社區藝術家的先鋒範例
獨立廠牌經營、公益活動、舉辦原創節慶等。 它也很重要,因為它展示了 21 世紀及以後的藝術家應該如何做。
12. 結論:21世紀“通過現場表演發展的樂隊”
聲音部落第 9 區是 嘗試將電子音樂的結構轉移到現場表演,同時保持樂隊形式 他是一個罕見的人,能夠持續追求這個目標20多年。
僅憑錄製的作品,音樂永遠是不完整的, 它隨著現場表演的“此時此地”體驗而不斷更新。
他們的步驟是 ** “現場樂隊能與電子音樂有多接近?” “電子音樂能在多大程度上捕捉現場音樂的活力?”** 這是一個回答這個問題的持續實驗,可以說是21世紀音樂文化本身的標誌之一。

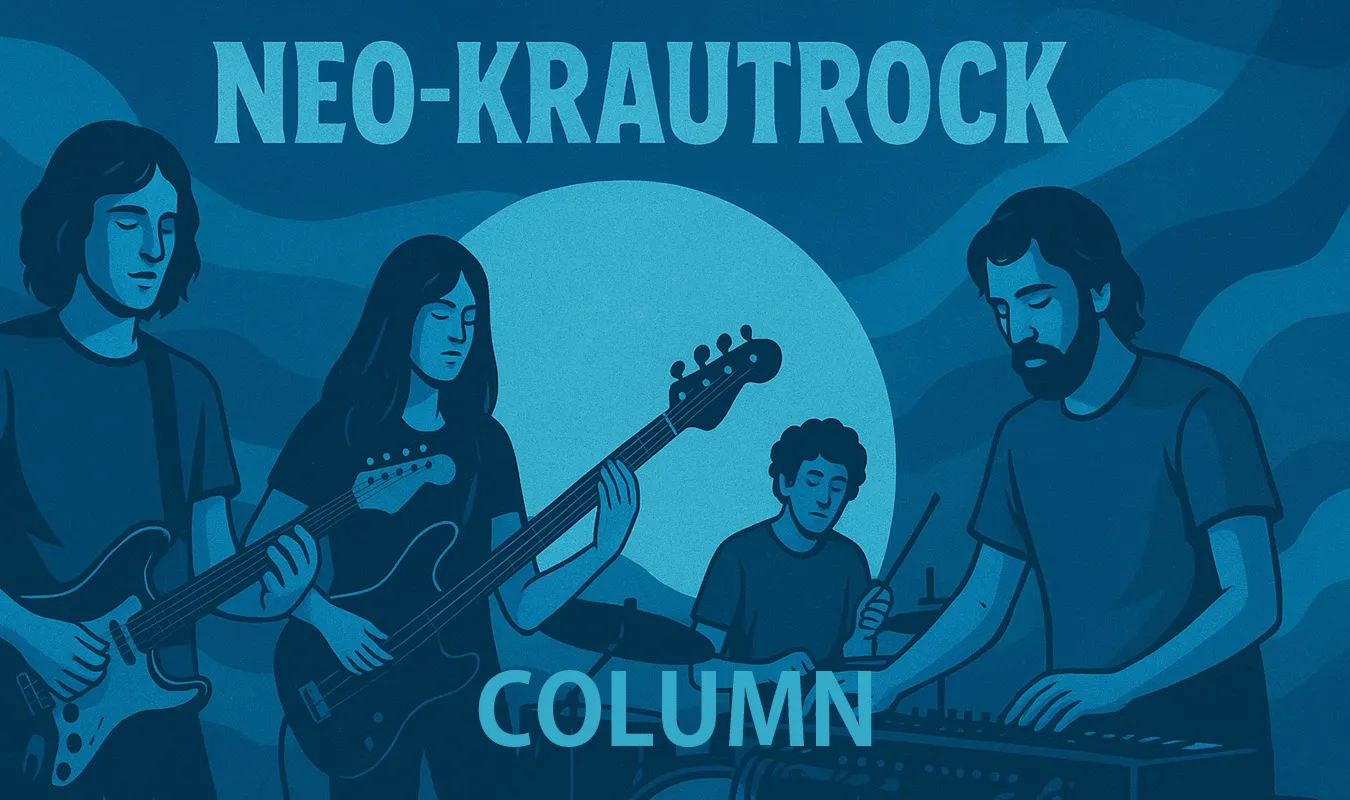

![[專欄] Dego & Kaidi 與 Sound Signature](/../assets/images/column-dego-kaidi-so-we-gwarn.webp)