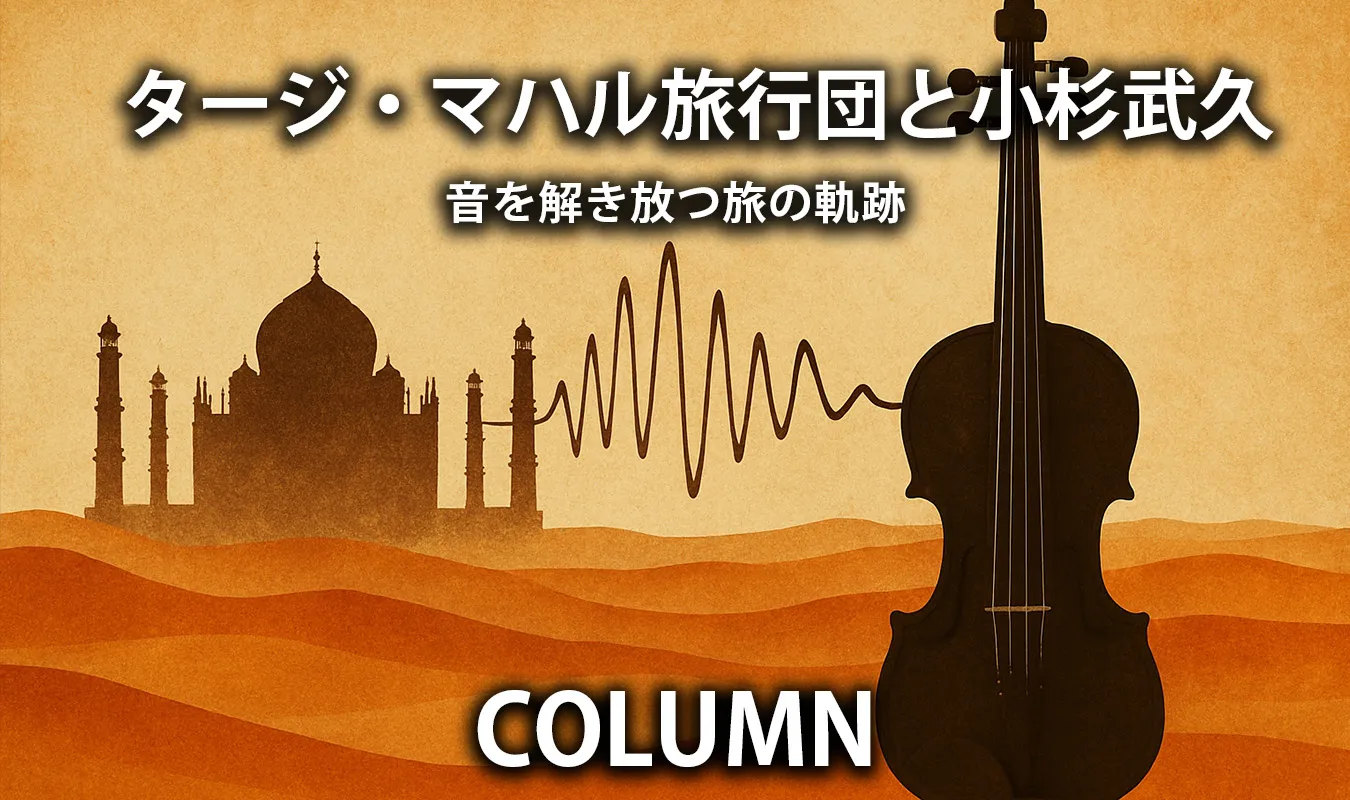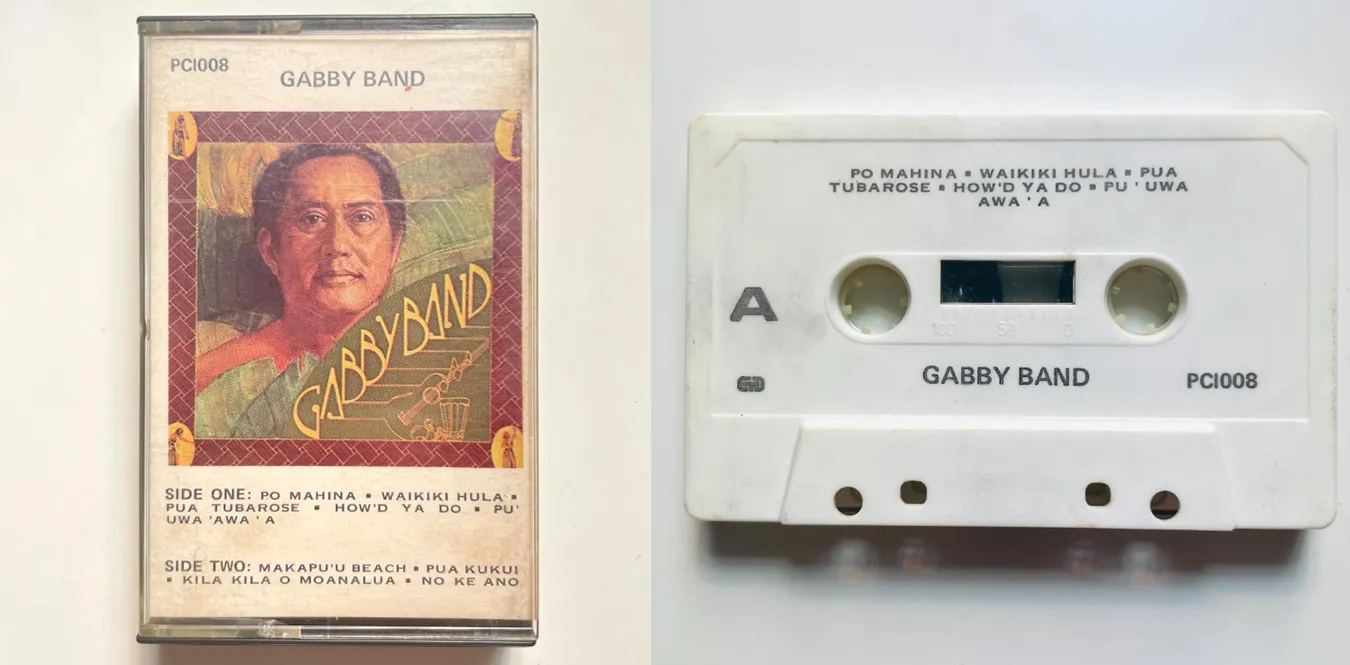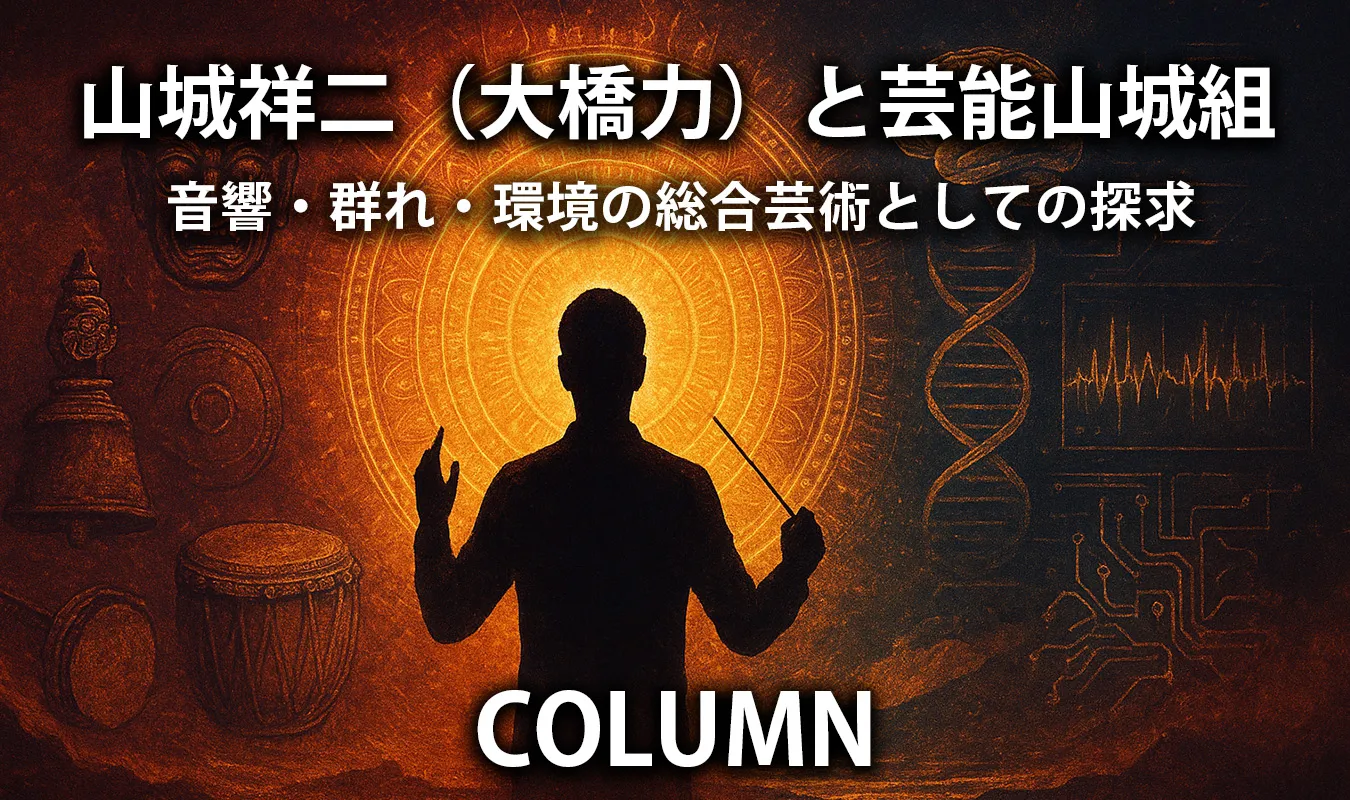
序章:電脳と原始が交差する場所 ― 山城祥二という人物
文:mmr|テーマ:1970年代初頭に結成された芸能山城組について
1970年代、日本の音楽と映像の境界で異彩を放った存在がいる。
山城祥二(本名:大橋力)。東北大学農学部農芸化学科を卒業し、生命科学・情報・音響に関心を持った彼は、科学的な思索と感性を背景に、芸術を「人間と環境の関係を探る実験」として位置づけた。
その実験の場こそが、1970年代初頭に結成された芸能山城組(Geinoh Yamashirogumi)である。
単なる音楽グループではなく、「音と人間と社会の関係を総合的に探るための共同体」として、音楽・民族学・情報理論・人類学を統合する“場”であった。
第一章:芸能山城組の誕生 ― 「群れ」としての芸術
芸能山城組の出発点は、大学・企業・職業を越えて集まった人々による「群れ(コレクティヴ)」の形成だった。
医師、教師、技術者、学生、主婦――職業も思想も異なる人々が、「音の中で生きる」という直観的な欲求を共有していた。
当初から山城は、芸術を個人の表現行為ではなく、「群れ」の表現と定義した。
そのため、彼らの稽古は単なる演奏ではなく、「音が場を生成する」プロセスそのものだった。
身体、声、空間、時間が一体となって共鳴する瞬間――それが芸能山城組の出発点である。
「音楽とは人間の意識の構造そのものだ。だからこそ、群れの音は、社会の音に通じる。」
— 山城祥二(1982年)
第二章:世界80系統の「群れの音」 ― 普遍的音楽構造への探求
芸能山城組は、1970年代後半から1980年代にかけて、
「世界80系統に及ぶ民族パフォーマンス」を実際に演奏・研究してきた。
それは単なる民族音楽の収集ではなく、「人間が群れとして発する音とは何か」という根源的問いへの探求であった。
◇ 研究・演奏対象の例
| 地域 | 音楽・儀礼 | 研究焦点 |
|---|---|---|
| インドネシア・バリ島 | ケチャ、ガムラン | 集団的トランスと時間構造 |
| アフリカ熱帯林 | ピグミーの森林歌唱 | 環境音と身体の同期 |
| 東欧ブルガリア | 女声合唱 | 不均等拍子と倍音構造 |
| コーカサス・ジョージア | 男声合唱 | 空間共鳴と社会性 |
| チベット・モンゴル | ホーミー唱法 | 喉頭共鳴と倍音分離 |
山城らは、これらを「素材」として扱うのではなく、構造・機能・社会的意義を観察し再構築した。
特にバリ島ガムラン音楽の「時間/空間を超える音響構造」は、芸能山城組の「群れ創り」「情報環境」「音の環境学」に通底している。
「人は音によって群れを形成する。群れによって音は進化する。」
— 山城祥二
第三章:『AKIRA』への到達 ― 電子と民族の融合
1988年、世界的アニメーション映画『AKIRA』(監督:大友克洋)の音楽を芸能山城組が担当。
ここで山城の音響哲学は頂点を迎える。
◇ 音響設計の理念
- バリ島ガムランのポリリズム × 電子パルス
- チベット密教の唱法 × サンプリング音声
- 都市の残響と群集音 × 空間構築的リズム
それは単なる劇伴ではなく、「音による神話構築」であり、都市と原始、未来と記憶を接続する試みだった。
『AKIRA』のサウンドトラックは、電子音楽と民族音響の融合点として国際的に再評価され、
のちの世界的アーティストたち――Aphex Twin、坂本龍一、コーネリアス――にも影響を与えた。
第四章:音の環境学 ― 「聴くこと」の科学と哲学
『AKIRA』以降、山城は芸術活動と並行して「音の環境学」という概念を展開した。
音を単なる聴覚刺激ではなく、「情報と生態の接点」として捉え直したのである。
◇ 主な著作と思想
| 書名 | 出版社/年 | 内容概要 | リンク |
|---|---|---|---|
| 『音と文明―音の環境学ことはじめ』 | 岩波書店, 2003 | 熱帯雨林の音やガムラン音楽が脳に与える活性を調査 | Amazon |
| 『ハイパーソニック・エフェクト』 | 岩波書店, 2017 | 健康と文明のあり方までを鋭く問いかける記念碑的著作 | Amazon |
ここで山城は、音を「人間と環境の通信プロトコル」として定義した。
音は記号ではなく、生態的・社会的活動そのもの――。
この思想は、後の「サウンドスケープ」や「メディア・エコロジー」研究とも共鳴する。
「音とは環境と情報のインターフェースである。
音楽とは、群れが自己を環境と同調させるアルゴリズムなのだ。」
第五章:科学者としての感性 ― 聴覚の生理と社会の音
東北大学農学部での理系的訓練は、山城に独自の分析視点を与えた。
化学・生物・環境の理解を背景に、「音を物理現象としてだけでなく、生命活動の一部」として捉える発想が生まれた。
彼のアプローチは、科学的観察と芸術的実践の往還である。
実験室ではなく、人間集団そのものを“音響系”として扱う。
そこには、生命のリズムと社会のリズムを一致させようとする「実験的倫理」があった。
「我々が聴く音とは、脳の中で再構築された世界の写像である。
だから音楽とは、世界の構造そのものをリハーサルする行為だ。」
第六章:21世紀の群れ ― 情報社会における芸能の意義
現代のSNSやAI時代において、「群れ」という概念は再び重要になりつつある。
芸能山城組の実践は、共同体的共鳴の再生を先取りしていたともいえる。
「個」から「群れ」へ。
「情報」から「共鳴」へ。
芸能山城組が1970年代に唱えた理想は、ネットワーク社会における「新しい共同体」の原型でもある。
音楽は「伝える」ものではなく、「響き合う」もの。
山城祥二が探求したのは、情報と情動のエコロジーとしての芸能だった。