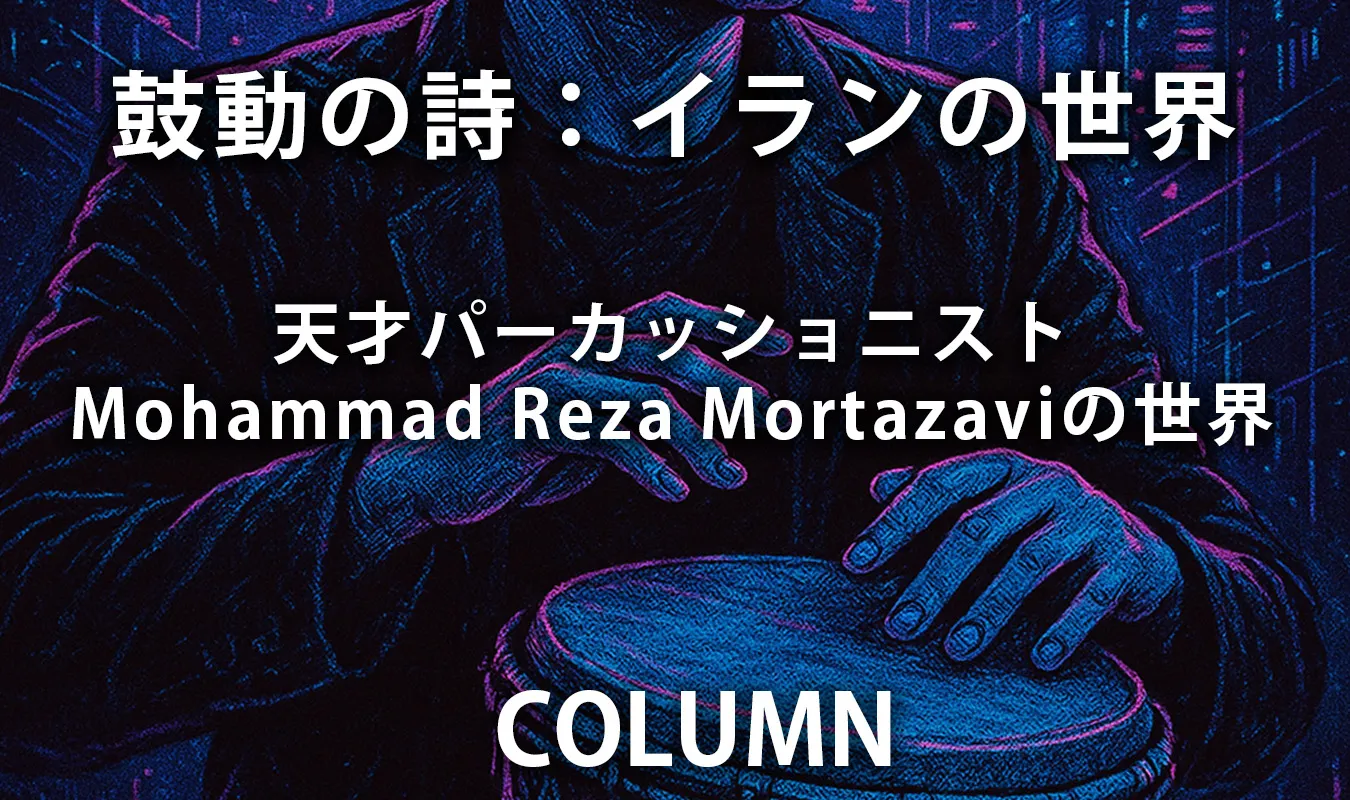
1. はじめに
文:mmr|テーマ:彼の生い立ちから現在に至るまでの歩みを丁寧に追い、彼の技術革新、哲学、コラボレーション、そしてリスナーにもたらす体験の核心を探る
モハマド・レザ・モルタザヴィは、伝統的ペルシア打楽器を現代の音楽表現において根本から再解釈した稀有なパーカッショニストである。彼の演奏は、ただのリズミックな技巧の披露ではなく、時にトランスを誘発する深い精神性を伴い、聴衆を身体的・意識的な旅へと誘う。その意味で、彼の活動は「伝統音楽と実験音楽」「東洋と西洋」「過去と未来」といった二項対立を超える、新しい音楽地平の創出として重要である。
2. 幼少期と出自
モルタザヴィは、1978年(あるいは1979年)にイランの古都 イスファハン に生まれた。 両親は音楽的バックグラウンドを持ち、幼い彼の音楽への関心を温かく見守っていたという。
6歳のとき、タムバック(英語では “tombak”、ペルシア語で tonbak または zarb)を学び始める。伝統的なタムバック奏者の師匠の元でレッスンを受けたが、わずか数年でその才能は師をも上回ると評価され、9歳の時点で「もはや教えられることはない」と師が認めたという逸話がある。
10歳にして、イラン国内で毎年開かれるタムバック競技で初優勝。以降も連続して勝利を重ね、若き才能として全国に名を知られるようになる。 この時期、彼の人生における楽器との関係は単なる趣味の域を越え、アイデンティティの核へと成長していく。
3. タムバックおよびダフという伝統楽器――その意味と背景
彼が扱う主要な楽器である タムバック(tombak/トンバック/ザルブ)は、ペルシア音楽の核心をなす伝統打楽器である。ゴブレット(杯)型の胴をもち、皮を張った面を手や指で叩く構造は、非常に豊かな音色と表現力を持つ。 多様な奏法を通じて、タムバックは伴奏だけではなくソロ楽器としての地位を確立してきた歴史がある。
また、ダフ (Daf) は大きなフレームドラムで、メタルの輪や鈴が付いていることがあり、祝祭的・儀式的な用途もある伝統的楽器だ。モルタザヴィはタムバックだけでなく、ダフも演奏対象とし、それぞれの特性を活かしたソロおよび共演を展開してきた。
彼がこれらの伝統楽器を選んだ背景には、ただの民族楽器への回帰ではなく、楽器の本質を深く探求し、そこから未知の表現を導き出す強い意志がある。
4. 青年期の才能と修業
少年期を通じて競技会での成功を重ねる一方で、モルタザヴィは単なる勝利者にはとどまらなかった。伝統奏法の技術を習得すると同時に、彼の探求心は「なぜタムバックはこう演奏されてきたのか」「まだ使われていない音はあるか」へと向かっていた。
彼は既存の教則や慣習に縛られることなく、自己流の研究を開始する。皮面の異なる場所、胴の共鳴、指の使い方、掌のポジション、爪と関節の応用など、身体と楽器の物理的な相互作用を丹念に観察・実践。これにより、伝統にはなかった新たな音響を引き出していく。
また、若くして教える立場にもなった。12歳頃から後進を指導したとされる記録もある。 教えることは、彼自身の技術を言語化し、整理する機会を与え、それがさらなる進化を呼ぶ好循環となった。
5. 技術革新:30以上の新打撃/指テクニック
モルタザヴィの最も注目すべき功績は、30以上に及ぶ自己開発による打撃および指技術である。これは単なる芸風としての目新しさではなく、タムバックという楽器の身体的・物理的可能性を根本から拡張する革新であった。
具体的には、以下のようなアプローチが含まれる:
- 異なる打点の活用:皮の中心、縁(リム)、胴(木部分)など、従来奏者が使わない場所へのアタック。
- 多様な手の部分:指先、関節、爪、手の平、親指の根、本来タブー視される部位も含め、奏者の手全体を楽器とみなす。
- ポリリズム的アプローチ:同一楽器内で複数の声部 (レイヤー) を同時に鳴らす技術。これは、たった一人の奏者によるアンサンブル的な演奏を可能にする。
- ダイナミクスの幅:極めて静かなタッチから爆発的な打撃まで、音の強弱、テンポ、密度を自在に操る。
- 共鳴操作:胴の響きをコントロールし、打撃時の余韻を設計。これにより、一打のあとに残る音の「残響」を一つの表現要素として用いる。
これらの技術は、一部の伝統的マスターから保守的な批判を受けることもあった。しかし、モルタザヴィは伝統を否定するのではなく、伝統の深みと可能性を探るという姿勢を崩さなかった。
6. ドイツ、ベルリンへの旅立ちと転機
20代前半、モルタザヴィは自身のキャリアの転機を迎える。22歳のときに初めてドイツ(ミュンヘン)で演奏し、ヨーロッパの聴衆から強い関心を引きつける。その成功は、彼に活動基盤をドイツに移す道を開いた。
やがて彼はベルリンに拠点を定め、国際舞台での活動を本格化。ベルリンはモルタザヴィにとって、実験音楽、電子音楽、パフォーマンス・アートとの出会いの場であり、彼の芸術的探求が加速する都市となった。
2003年には、600人を超える競合者の中から RUTH(ルース)賞、新人部門 を受賞。この受賞は、彼の国際的認知を決定づけるものとなった。
2010年には、彼のソロ公演が ベルリン・フィルハーモニー で行われるという夢が現実化。同年、アルバム『Green Hands』をリリース。 彼にとって、この年は象徴的なターニングポイントであり、伝統と実験の狭間に立つ彼自身の音楽アイデンティティが世界に明確に示されることになった。
7. 主要作品の分析と音楽世界
モルタザヴィのディスコグラフィは、彼の探求の進化を物語る地図のようなものだ。以下、それぞれの主要作品を深掘りしながら、彼の音楽的ビジョンと技術を読み解く。
7.1 『Green Hands』
2010年リリースのこのアルバムは、モルタザヴィの象徴的な出発点である。 伝統楽器(タムバック/ダフ)のみを使ったソロ演奏でありながら、彼の技術革新と音響設計がすでに鮮明に刻み込まれている。各トラックには、指や掌、爪などを駆使した繊細で多層のリズムが展開され、ひとつの楽器が複数の音声を持つかのような錯覚を聴き手に与える。
特筆すべきは、彼の打ち方が単に速いだけではなく、非常にダイナミックである点だ。静かなタッチの中にある共鳴、強打による鋭い切れ味、そしてその中間を滑らかに行き交うグラデーション。彼の手が皮面を滑り、胴の木を叩き、指が爪を使って跳ねるたび、異なる音色が階層的に交差し、強い存在感を持つ。
また、このアルバムの録音/ミキシングの妙も無視できない。彼の打楽器がマイクを通じて空間に再構築される際、その余韻と反響が鮮やかに捉えられており、まるで小宇宙を聴いているかのようなサウンドスケープが生成されている。
7.2 『Codex』
『Codex』はモルタザヴィがさらに自己の技術的言語を体系化し、書き記す(コード化する)挑戦のひとつである。伝統奏法と彼自身の革新的奏法の融合がさらに進み、楽曲構造が高度に練られている。彼はただ即興するのではなく、作品として設計された時間とリズムを聴き手に提示する。
このアルバムにおいては、打点の選択、リズムの周期性、反復と変化のバランスなどが非常に緻密に構成されており、演奏者自身の内的対話がそのまま外化されているように感じられる。
7.3 『Transformation』
『Transformation』は、モルタザヴィの芸術性におけるスピリチュアルな深化を示す重要な作品。彼のメディア掲載でもこのアルバムが大きく取り上げられており、彼の哲学的探求と身体性が音として開かれていく過程が明確に見える。
この作品では、タムバックのみならず、ダフや他のアコースティックな物体を使った演奏も含まれる。彼は音楽を、単なるリズムの連続ではなく、時間そのものを変容させるプロセスとして提示しており、聴く者にトランス的な体験をもたらす。
7.4 『Ritme Jaavdanegi』
Latency レーベルからリリースされたこのアルバムは、モルタザヴィの中核的テーマである「永続性 (jaavdanegi)」への深い探求を反映している。 タイトルはペルシア語の “永遠のリズム (rhythm of eternity)” を表す言葉であり、楽曲には反復、循環、微妙な変化が持続的に重なってゆく構造がある。
批評家からは、「メトロノームとは異なり、人間の鼓動 (pulse) は柔軟で固定されていない」という彼の見解が取り上げられている。 彼のライブでもこのテーマは顕著であり、彼は観客との間に「共通の拍動 (common pulse)」を作り出すことを重要視してきた。
7.5 『Prisma』
2022年にリリースされたこのアルバムは、モルタザヴィの音楽のさらなる拡張を示す作品だ。Flussbad の公演情報などによれば、タムバックとダフに加えて、鳥の笛、小型マリンバ、カリンバ、小さなシンバルなど、さまざまな音響オブジェクトが導入されている。 これにより音色の幅が広がり、より立体的で精神的な空間表現が可能になっている。
彼はこの作品を通じて、自らの演奏スタイルを “ミニマリズム + 多層性” の融合に昇華させており、技巧の華やかさよりも、音の余白、静寂と響きのバランスを探ることに重きを置いている。
7.6 最新作および今後への展望
彼の最新作 『Nexus』 (Latency) は、ベルリンで録音され、彼の新たな方向性を示す重要なマイルストーンである。この作品では、彼が従来用いてきたアコースティックな手打ち太鼓に加えてエフェクト処理やサウンド・トリートメントを導入し、彼のリズム・言語をさらに未来へと押し上げている。
「Nexus(結節点)」というタイトルが示す通り、過去と未来、伝統と革新、身体と電子音響の交差点を探る作品として構想されており、今後のライブや共演、さらなる録音活動でも中心的な役割を果たすだろう。
8. コラボレーションとジャンル横断的活動
モルタザヴィはソロ演奏だけでなく、さまざまなアーティストやジャンルとの共演を通じて、自身のリズム・哲学を広げてきた。
特に注目されるのは、エレクトロニック/実験音楽との共演だ。彼は Burnt Friedman との EP(例:Yek)で、伝統打楽器と電子ビートを融合させ、反復・循環リズムを探求。 この共演は、彼の多声音テクニックと電子音楽の構造的リズムが調和する、ユニークな融合を生み出した。
また Mark Fell などとの交流も報じられており、これは彼が実験音楽コミュニティにも深く受け入れられてきた証である。
舞台芸術との連携も彼の重要な活動の一つだ。バレエやダンス公演、劇場との協働により、彼のリズムは身体表現の中核となる。実際、彼はリンツ地方歌劇場 (Landestheater Linz) などで振付家とともに作品を作ってきたという報告もある。
さらに、世界各地のフェスティバルやワークショップにも定期的に登場し、伝統と実験の橋渡しを担っている。
9. ライブ体験 ― 身体性・精神性・トランス性
モルタザヴィのライブ演奏は、非常に身体的かつ精神的な体験である。彼の手が皮面を叩くたびに空間が震え、観客の呼吸や集中がそのリズムに引き込まれてゆく。彼自身が言うように、「リズムは精神 (spirit)、旋律は身体 (body)、身体と精神が合わさって初めて音楽になる」。
彼の演奏には、瞑想的な反復構造と、高速かつ複雑な変化パターンが混在し、聴き手はしばしば時間感覚を忘れる。テンポが緩やかになる瞬間、音が残響をともなって持続し、その持続が次第に重なって身体内に共鳴を生む。逆に、急激にリズムが加速すると、聴衆の集中はピークに達し、一種のトランス状態へ導かれる。
このようなライブ体験は、単に耳で聴くものではなく、身体で「感じる」体験だ。モルタザヴィは、演奏と同時に観客との共鳴 (resonance) を創出し、瞬間ごとに「共通の拍動 (common pulse)」を共有させる。そのプロセスは、楽器と人間、演奏と聴衆を結ぶ儀式のような側面を持っている。
10. 批評、受賞、評価の軌跡
モルタザヴィは、技術・芸術性・革新性において国際的な評価を受けてきた。2003年には RUTH 新人賞 を受賞。また、メディアからも高い関心が寄せられており、ドイツの Deutschlandfunk や Pitchfork、Hardwax、Boomkat など、多様な媒体で彼のスタイルや哲学が取り上げられてきた。
特に Pitchfork では、人間の拍動 (pulse) の柔軟性と彼の演奏するリズムの即興性が注目され、「人間らしさと時間の可塑性を体現する音楽」と評された。 Hardwax などは、彼の 30 以上の新テクニックが作り出す音の精緻さと精神的な深みに強い賛辞を送っている。
また、ライブレビューでもその身体性と精神性がたびたび強調される。Drummerszone などは、彼が使用する打点、手の部分、共鳴操作などを詳細に記述し、まるで彼の手が “音響システム” を演奏しているかのようだと指摘している。
これらの評価は、彼が単なる技巧派奏者ではなく、音楽的思想家、そしてリズムの哲学者としても高い地位を得ていることを示している。
11. 哲学・スピリチュアリティ:リズム、時間、意識
モルタザヴィの音楽を語る上で、技術以上に重要なのはその 哲学的視座 である。彼はリズムを単なる時間の区切りやグルーヴとしてではなく、精神 (spirit) と深く結びついたものとして捉えている。
彼の反復構造は瞑想を思わせ、音の持続 (sustain) や余韻 (resonance) の扱いは、聴き手を時間の中で揺らす。テンポの循環、微妙なずれ、変化と同時の持続 ― これらはすべて、彼にとって時間を「彫刻する」手段であり、その場の空間を精神性に満ちた領域へと転換する装置である。
また、彼は観客との共鳴 (共拍動) を演奏の重要な要素とみなしている。彼のライブでは、観客がただ聴く存在ではなく、その場のリズム生成に参加する被動的能動者 (co-creator) となる。彼は自分と観客の間にリズミックな対話を築き、一人で演奏していても “ひとつの共同体” の感覚を作り出す。
このようなアプローチには、伝統と現代、身体と意識、個と共鳴、静寂と躍動といった二元性を克服しようとする深い意志が感じられる。そして、彼のリズムは単なる技術の展示ではなく、自己探求、共同体、時間の意味を問う哲学的実践として立ち現れてくる。
12. 教育とワークショップ活動
モルタザヴィは若い世代への教育にも熱心である。彼はヨーロッパ(特にドイツ)でワークショップを多数開いており、タムバックやダフ、手打ち太鼓の初心者から熟練奏者まで、多様な参加者を対象として指導を行ってきた。
あるワークショップ (例:北ドイツの村 Thandorf) では、彼は「音楽は愛であり、愛には境界があってはならない」と語った。 伝統音楽界の保守主義や規則主義に対して、彼は音楽が自由な対話と探求の場であるべきだという強い信念を持っており、それを教える場でも体現している。
また、オスロのコンテンポラリ音楽祭 Ultima などでも、彼は参加者に対して「共通の拍動 (common pulse) を見つける」ワークショップを行っており、小さな手打ち楽器から身体自体を使ったリズム生成までを通じて、リズムの普遍性と包括性を探求させる。
こうした教育活動は、彼の芸術が自分自身だけのものではなく、広いコミュニティへの架け橋であることを示している。
13. 現代における位置づけと影響
モルタザヴィの活動は、現在のグローバル音楽シーンにおいて非常に特異かつ重要な位置を占めている。彼は単なる伝統音楽家でもなく、電子音楽家でもなく、純粋な実験音楽家でもない。むしろ、これらの要素を横断し、結節し、新たなジャンル/地平を切り開く存在である。
彼の演奏と作品は、以下のような影響を持っている:
-
伝統楽器/文化への再定義 彼の技術はタムバックという伝統楽器に新たな命を吹き込んでおり、伝統を守るだけでなく拡張し続ける道を示す。
-
実験音楽・電子音楽への架け橋 電子音楽プロデューサーとのコラボレーションや、リズムと循環構造の探求は、伝統と現代の接点を鮮明にする。
-
パフォーマンス芸術との融合 彼のライブには身体性、儀式性、トランスが関与し、演奏は単なる音楽公演を超えた身体・空間芸術となる。
-
コミュニティと教育 ワークショップを通じてリズムの民主化、伝統技術の伝承・変容、異文化理解を促進している。
-
哲学的・精神的問いの提示 彼の音楽は、時間、自己、共同体、意識など根源的な問いをリズムを通して提示し、リスナーを深い内省へと導く。
これらすべての要素が相互に作用し、モルタザヴィは現代音楽における「リズムの哲学者」としてのポジションを確立している。
14. 結論:未来への響き
モハマド・レザ・モルタザヴィの歩みは、伝統を再定義し、技術を拡張し、そしてリズムと意識の間の新しい対話を生み出す旅である。彼の手が紡ぐ多声音、多層リズム、持続、余韻、そしてその根底にある深い哲学は、単なるパフォーマンスを超えて、聴く者に時空間を超える体験を提供する。
彼は、タムバックという古典的な楽器をただ保存するのではなく、未来へ向けて変容させる。その変容の過程で、音楽、身体、コミュニティ、意識は交差し、新たな地平が開かれていく。
これから彼が向かう道は明確だ。さらなる技術的探求、新しい共演、未知のサウンド空間への拡張。だが、それ以上に重要なのは、彼が常に「リズムとは何か」を問い続ける存在であり続けることだ。
彼の音楽を聴くとは、ただリズムに身を委ねることではなく、自分自身の内なる鼓動と、世界の鼓動との共鳴を探す旅である。モルタザヴィは、その旅の先導者であり、地図でもあり、そして目的地でもある。
15. 参考年譜
- 1978/1979 — イラン・イスファハンに生まれる。
- 1984–1985(6歳頃) — タムバックを始める。
- 1987–1989(9–10歳頃) — 師匠を超える技術を持つと評価され、国内大会で初優勝。
- 1990代 — 数回にわたりイラン国内タムバック競技で優勝。
- 2001頃(20歳前後) — 国内外で既に高く評価される。
- 2003 — ドイツで RUTH 新人賞 (World Music Young Talent Award) を受賞。
- 2005 — Total Music Meeting (Berlin) でソロ公演・ワークショップを担当。
- 2010 — ベルリン・フィルハーモニーでソロ・コンサート。
- 2010 — アルバム『Green Hands』をリリース。
- 2011 — WOMEX (World Music Expo) 出演。
- 2013 — アルバム『Codex』リリース、その後ツアー。
- 2016 — アルバム『Transformation』リリース (Flowfish)。
- 2017 — Burnt Friedman との共演 EP『Yek』リリース。
- 2019 — アルバム『Ritme Jaavdanegi』リリース (Latency)。
- 2022 — アルバム『Prisma』リリース、新しい音響オブジェクトを導入。
- 2025–2026 — アルバム『Nexus』リリース (Latency)。
