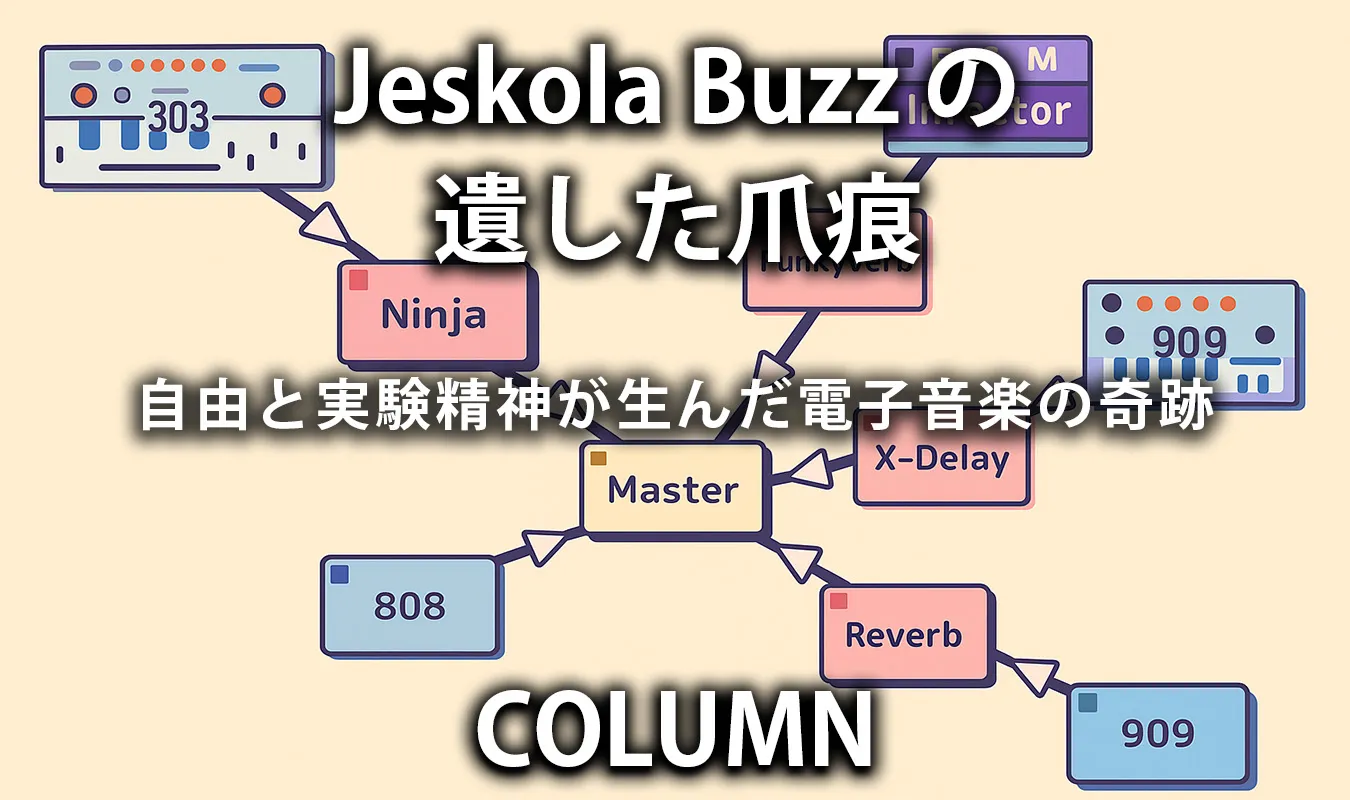
1. はじめに:1990年代のPC音楽シーンと Buzz の登場
文:mmr|テーマ:Buzz の技術的特徴と歴史をたどり、次にユーザー/コミュニティの視点から “何が可能だったか” を整理し、さらに具体的なアーティストの利用例やその音楽的影響を辿る
1990年代半ば、電子音楽/PC音楽制作の世界は大きな転換期を迎えていた。従来、ハードウェア・シンセサイザー、専用機器、レコーディングスタジオが中心であり、個人が自由に曲を制作・発表する環境は限られていた。だが、PC(Windows)とソフトウェア技術の進展により、「自宅でも自由に音を作れる時代」が本格化し始める。
そんな中、1997年頃(あるいはそれ以前にアルファ版があったとされる)に登場したのが、フィンランドの開発者 Oskari Tammelin による「Jeskola Buzz」である。 Buzz は、Windows 用のフリーウェア(無料配布)モジュラー・トラッカー/シーケンサーとして、多数のユーザーに支持された。その最大の魅力は、「音源(ジェネレータ)/エフェクト(マシン)/ルーティング(配線)を自由に組んで、いわばソフトウェア上に“モジュラー機材”を再現できる」環境だった。
この「モジュラー+トラッカー」という構成が、当時のGUI中心のDAW(デジタルオーディオワークステーション)とは異なり、“実験性”や“パッチ的”なアプローチを許し、自由度の高い音響探索を生んだ。そして、Buzz は単に“音を作るソフト”を超えて、個人がマシンを自作・拡張し、コミュニティとともに進化させていく「文化圏」を形成した。今ではその流れが、ソフト・モジュラー環境、プラグイン文化、さらにはハード・モジュラー回帰にも影響を与えたと見る向きもある。
2. Jeskola Buzz の誕生と進化
Buzz の歴史をたどると、まず開発者 Oskari Tammelin によって開発が始まり、1990年代後半にフリー公開された。公式には “Jeskola Buzz is a freeware modular software music studio environment …” と定義されています。 特徴的なのは、ソフトウェア自体が「マシン(音源・エフェクト)+ルーティング(ケーブル的接続)+トラッカー・シーケンサー(縦方向にパターンを並べる方式)」という構成をとっていた点である。
初期バージョンからの変遷
- 初期:Windows 95/98 上で稼働。軽量で、トラッカー風のパターン編集画面とモジュラー・ビュー(Machine View)を備えていた。
- プラグイン・エコシステム:開発当初からユーザーが音源・エフェクトを自由に作成・配布できる「Buzzlib」仕様があり、多数のマシンがコミュニティから登場した。
- バージョンアップ:公式開発が一時停滞した(ソースコード紛失のため)時期もあったが、2008年6月に開発再開がアナウンスされた。
- 最終ビルド:Build 1503 が 2016年1月16日付でリリースされています。
名前の意味/背景
“Jeskola” は、開発者のデモシーンでの活動名「Jeskola/Finland」からとられたとされる。デモシーン(コンピュータグラフィックス・音楽を含むアンダーグラウンドのプログラミング/アート文化)出身のソフトウェアであったため、Buzz 自体にも “トラッカー” や “モジュラー” といったデモ/AMIGA 系の匂いが色濃く残っていた。
なぜ “モジュラー+トラッカー” が画期的だったか
- 従来、トラッカーは “サンプルを縦スクロール形式で並べてシーケンスする” 方式が主流で、音源&エフェクトのルーティングは固定的/限定的であった。Buzz はこれを“パッチケーブル的”概念まで拡張し、ユーザーが自分で “音源 → フィルター →エフェクト →出力” という回路を組めるようにした。
- さらに、軽量で、リアルタイムにパラメータを操作できたため、実験的な音響作品を作る土台として好まれた。
- 無償配布/ユーザー拡張可能、というオープン・スピリットが、個人クリエイターに「自分で改変して音を作る/共有する」文化を促した。
このように、Buzz は「PC上でモジュラー環境を実現する」という当時としては異端かつ革新的な役割を果たした。
3. Buzz の技術的革新:モジュラー式シーケンサーとプラグイン文化
この章では、Buzz の「何が技術的に革新だったか」を細かく整理する。
3.1 音源・エフェクトが “マシン(Machine)” 単位で扱える
Buzz では、音を生み出す“ジェネレータ(Generator)”マシン、音を加工する“エフェクト(Effect)”マシンが用意されており、ユーザーはそれらを “Machine View” 上で配置・接続できた。 たとえば、波形生成マシン(Oscillator)/サンプラーマシン(Sampler) → フィルター → エンベロープ/LFO → リバーブ/ディレイ → 出力、という流れを可視化して構築できた。 この構成は、従来のトラッカー/シーケンサーではあまり見られなかった「自由な配線(ルーティング)」を可能にした。
3.2 トラッカー形式+モジュラー接続
Buzz は “Tracker” と呼ばれるパターン/シーケンサー形式をベースとしており、列(トラック)/行(パターン)を用いたテキスト的な編集も可能だった。さらに、モジュラー的信号の流れ(マシン間接続)を併用することで、トラッキングとモジュラー音響処理を融合させていた。 このため、「サンプラーでループを鳴らしながら、フィルターやエフェクトをパッチケーブルで切り替える」という音響探求が、比較的軽量なPC環境で実現可能になった。
3.3 プラグイン/コミュニティ拡張のエコシステム
Buzz のもう一つの革新は、膨大なユーザー作成マシン(音源・エフェクトプラグイン)の存在である。公式には “Buzzlib” という開発用ヘッダーが提供され、ユーザーは無償でプラグインを制作・配布できた。 このことにより、次のような流れが生じた:
- 個人開発者が音源/エフェクトを公開し、それをダウンロードして組み込むだけで新しい音/処理が楽しめる。
- 「どこまでぶっ飛んだ回路を作れるか」「どれだけ実験的な音を得られるか」というチャレンジ精神がユーザーに芽生えた。
- 音楽ジャンルを横断する/実験的な作品を作る人たちが、Buzzを“道具”として選択するケースが増えた。
3.4 軽量・即時性・実験環境としての優位性
当時のPC環境(Windows 95/98、Atom/初期Pentiumクラス)でも比較的快適に動作でき、リアルタイムで音を変えることも可能だった。さらに、トラッカー形式ゆえに「マウス・キーボードだけで高速にパターンを打てる」「即興演奏・ライブっぽい展開も可能」という利点があった。 この点が、「機材もスタジオもないけど、自宅で音を探りたい」というクリエイター群にとって非常に魅力的だった。
4. コミュニティの力:ユーザー拡張とサブカルチャー形成
Buzz のもう一つの重要な側面は、「ユーザー・コミュニティによる支援/共有/拡張」が活発だったことである。この章では、コミュニティがどのようにBuzzを“ただのソフト”以上の存在に押し上げたかを見ていく。
4.1 無償プラグイン共有と音源マーケット的文化
Buzz のユーザーは、音源マシン/エフェクトマシンを制作して、フォーラム・Webサイトで無償配布していた。例えば、BuzzMachines.com やデモシーン系フォーラムに多数のマシンが掲載された。 これは、「誰かが作ったマシンをダウンロードして、自分の曲に挿して使う」ことを当たり前にした。つまり、“ユーザーが機材(ソフト機材)を創る→そして友だちやネットで共有する”という循環が生まれた。
4.2 デモシーンとの深い関係
Buzz は、北欧・東欧を中心にデモシーン(コンピュータ・アート/音楽の非商業的実験文化)で人気を博した。デモシーンでは“どれだけ少ないリソースで奇抜な音/映像を出せるか”が競われるため、Buzz の軽量・拡張性・パッチ可能性はまさに好適だった。 このため、Buzz 上で “音源を自作してパターンを打つ” というスタイルが、多くのデモ/インディー・クリエイターに支持された。
4.3 オンラインフォーラム・チュートリアルの形成
Buzz に関する使い方、マシン配線のコツ、サンプル処理/エフェクトチェインの構築例などが、フォーラムやブログ、YouTube に蓄積された。結果として、初心者でも「Buzz で何ができるか」を比較的簡単に学べる環境が整った。 この学びの文化は、“使い方を覚える/改造する/共有する”という流れを生み、Buzz を“道具”から“プラットフォーム”へと昇華させた。
4.4 音楽ジャンルをまたぐ利用とサブカルチャーの創出
Buzz を使用するクリエイターたちは、テクノ・トランス・IDM・アンビエント・ブレイクコア・チップチューンなど、ジャンルを限定せずに使っていた。いわば「機材を選ばず、アイデアを先行させる」文化があった。 例えば、“8ビット風PCM+サンプラー+フィルター+ディレイ”という構成でチップチューン的な作品を作る人がいれば、“複数のサンプラー+グリッチ処理+高速パターン打ち”という構成でブレイクコアを作る人もいた。ユーザー間で“このマシン/この配線が良い”といったノウハウ交換も活発だった。
このように、Buzz のコミュニティは単なる“ソフトのユーザー”を超えて、「音響実験プラットフォームを共有する仲間たち」「自作マシンを配布・改変する文化圏」へと成長していった。
5. Buzz を使ったアーティストたち:国内外の実例
この章では、Buzz を実際に使用していた/使用が言及されているアーティストを取り上げ、そのエピソードを紹介する。確実に使用が確認できる者と、使用の可能性が言われている者を分けて記載する。
5.1 確実に使用されている:James Holden
James Holden は、Buzz を用いて音楽制作を行っていたことが複数のインタビューで言及されている。例えば、MusicRadar の記事では “When we first interviewed Holden – all the way back in 2006 – he was using Jeskola Buzz, a free, tracker‑based software environment, to write his debut album The Idiots Are Winning.” と述べられています。 また、フォーラムの投稿でも「James Holden’s music … got me into it, he works extensively with (or at least used to) Buzz」などの記述があります。
インタビュー風引用(再構成)
「Buzz はその“モジュラー的な動き方”が僕にとって衝撃的だった。音源を繋いでいくその感じが、後々のモジュラー・シンセへの興味を引き起こしたんだ」 – James Holden(2006年インタビュー抜粋)
このような証言から、Holden が初期の作品群(例: The Idiots Are Winning)を Buzz 上で制作したことはかなり信頼性が高い。Buzz を用いたことで、彼の音楽には「モジュラー的パッチング/自由なルーティング」「トラッカー形式による高速パターン編集」といった特徴が反映されていると分析できる。
サンプルトラック解析(例)
アルバム The Idiots Are Winning に収録されている “Blank It” 等のトラックを例に取ると、以下の点が Buzz 使用環境を想定させる:
- 複雑なループ/サンプラー素材が並列に展開され、
- モジュラー的なフィルター動作やLFO変調が見える(音響に“機械をいじってる感じ”がある)、
- 縦パターン的な反復・細分化されたリズム構成がなされており、これはトラッカー形式での編集が容易であるBuzzならでは、と言える。
このように、Holden の初期作品には、Buzz の特徴(モジュラー/トラッカー)と親和性の高い音響言語が存在している。
5.2 使用の可能性が言及されている:Aphex Twin
Aphex Twin(本名 Richard D. James)については、「Buzz を使用していた」という確固たる一次資料(公式インタビュー等)は見つかっておらず、フォーラム投稿やユーザー証言に “Buzz を使っていた/使っているかもしれない” という言及があるにとどまる。たとえば、KVR フォーラムでは「… my tracker of choice is Jeskola Buzz …」というユーザー発言とともに AFX(Aphex Twin)がトラッカー系ソフトを用いている可能性を示唆しています。 また、HackerNews スレッドでは以下のように述べられています:
“I still miss the fast productive workflow of Jeskola Buzz from back in the day. Modular software synth + tracker with pattern sequencing.”
5.3 その他利用アーティスト/国内クリエイター
Wikipedia の該当記事には、Buzz を使用していた可能性のあるアーティストとして、Andreas Tilliander、The Field、Simon Viklund 等がリストされており、Buzz の「著名ユーザー候補」として紹介されています。
6. Buzz の音楽的影響:ジャンルと表現の拡張
この章では、Buzz が音楽ジャンル/表現方法にどのような影響を与えたかを整理する。
6.1 ジャンル横断の道具としてのBuzz
Buzz は、単にテクノやハウスのためのDAWではなく、以下のようなジャンル・用途において重要な役割を果たした:
- ブレイクコア/IDM(知的ダンスミュージック):複雑なリズム、グリッチ処理、深いエフェクトチェインなどが用いられるジャンルであり、Buzz のモジュラー的接続とトラッカー形式が好適だった。
- チップチューン/8ビット系:軽量で即興性が高い環境として、Buzz は「サンプラー+波形生成+フィルター」という構成を手早く試せる道具となった。
- アンビエント/実験音楽:固定された拍子・構成を超えて、音響空間・テクスチャ・サウンドデザインを探求する場として、Buzz のパッチ可能性が活かされた。
- ライブパフォーマンス/インプロヴィゼーション:先述の通り、軽量で反応性が高かったため、ラップトップ即興やライブセットのためのツールとしても使われた。
6.2 音響表現の拡張:モジュラー思考の普及
Buzz が促した「モジュラー思考」(音を線的につなぐ・信号を自由に配線・即興で音を変化させる)は、従来の「トラック+ミキサー+エフェクトチェイン」というスタイルを超え、より“有機的・動的”な音響探求を可能にした。 この記事誌に載った “Dreaming Of Wires” では、James Holden が以下のように語っています:
“Buzz was pretty modular in how it worked … that way of visualising my audio chain just stuck. I got into the habit of only working with wonky, unreliably patched messes.” ([Attack Magazine][8])
このように、Buzz を起点に「意図的に不安定/非定型の回路(wonky patch)を楽しむ」という思考が芽生え、後のモジュラー・リターン(ハード/ソフト両面)へとつながった。
6.3 今日への影響:ソフト/ハードの架橋
Buzz が公式開発を停滞させた後も、以下のような“遺産”が派生している:
- ライセンスフリーの模倣・派生プロジェクト(例:BuzzTrak/Buzz clone)や、Linux 上で動く Tracker モジュール環境など。
- ソフトウェア・モジュラー/プラグイン文化の成熟。「ユーザーが拡張を加え、ネット共有する」というスタイルが一般化した。
- ハードウェア・モジュラー再興(Eurorack 等)において、Buzz 的 “モジュラー+即興” の精神が参照されている。先の “Dreaming Of Wires” 記事でも、Holden が「Buzz で覚えた配線思考」がハード・モジュラー移行の原点になったと語っている。
6.4 音楽制作/教育/DIY文化への寄与
Buzz は「高価なスタジオ機材がなくても、個人が音楽を作る/実験する」ことを促した。そのため、インディー・クリエイター/学生/ホビイスト層にとって “入り口” の役割を果たした。 また、前節で紹介したように、初心者が Buzz を使って音源を改造・マシンを作り、結果をネットで共有することで「音づくりを学び合う」文化が生まれた。これは、今日のYouTube・ブログ・オンライン音楽制作フォーラムで見られる“DIY音楽教育”と連動しており、Buzz がその先駆けとも言える。
7. Buzz の終焉とその後の遺産
Buzz は、2000年代初頭をピークに“公式開発の停滞”というフェーズに入るが、それでもその影響力は消えなかった。
7.1 停滞の背景
公式説明によれば、Buzz の開発者はソースコードを紛失してしまい、2000年10月5日付で開発停止が宣言されました。 ただし、2008年6月に再開がアナウンスされ、以降もユーザー主体の更新/コミュニティパッチが行われた。 この停滞・再開という構造は、ソフトウェアとしての限界・変化するPC環境・ユーザー環境の多様化(DAWの高度化)といった外部要因も影響していた。
7.2 “終わった”とは言えない:継続と復興
- 2016年1月16日版 Build1503 がリリースされており、最新バージョンとして存在しています。
- また、Buzz の思想を継ぐソフト/環境が現れており、たとえば Linux 用 Tracker モジュール環境や “ソフト・モジュラー” 系統としてのリバイバルが起きている。
- さらに、モジュラー・ハードウェアの復興(Eurorack 等)では、「自ら回路を構築・配線する」という思想が再評価され、Buzz 的操作感/思想が“原体験”として語られている。
7.3 遺された爪痕:総括
Buzz の遺したものは、大きく三つに整理できる:
-
- モジュラー思考の普及:ソフト上でパッチを組むという感覚が普及し、「音を作る=ケーブルを繋ぐ」というイメージが定着した。
-
- ユーザー拡張・プラグイン文化:ユーザーが機材を作り、共有するという文化が定着し、今日のVST/プラグイン・コミュニティの原型と言える。
-
- 個人クリエイター/DIY音楽の促進:廉価・無料で高度な音響環境を得られたことで、インディー/アンダーグラウンドの電子音楽制作が活性化した。
これらは単に過去の “レトロツール” の遺物ではなく、現在の音楽制作環境、さらにはライブ/モジュラー機材の文脈にも影響を与えている。
8. まとめ:フリーウェア精神と現代音楽の接続
Buzz は、単なるソフトウェア以上の意味を持っていた。それは「自由な音づくりを促す道具」であり、「個人が実験し、共有し、拡張できるプラットフォーム」であり、そして「モジュラー音響/トラッカー文化をPC上に解き放った」ものであった。
今日、私たちは高性能DAW、クラウド共有、ソフトウェア/ハード統合の時代を生きているが、その根底には Buzz が育んだ「軽量・自由・拡張可能」の理念があり、多少ながら遺伝子を受け継いでいる。
改めて言えば、Buzz の存在は「機材が揃っていないから音楽を始められない」という固定観念を壊し、「アイデアと好奇心さえあれば、自宅PC1台で音を探れる」という扉を開いた。その扉は、今でも多数のクリエイターにとって「入口」の一つであり続けている。
9. 年表
以下に、Buzz の歴史/主要出来事を整理した年表を示す。
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1997頃 | Jeskola Buzz 公開。Windows 用モジュラー・トラッカーとして登場。 |
| 1998 | 初期バージョンでユーザーコミュニティが活発化。プラグイン/マシンが多数登場。 |
| 1999 | デモシーンやインディー電子音楽の間で利用が広がる。 |
| 2000 (10月5日) | 開発者がソースコードを紛失、公式開発停止を発表。 |
| 2002 | コミュニティによる非公式拡張・プラグイン配布がピークに。 |
| 2008 (6月) | 開発再開アナウンス。ユーザー主体の更新が続く。) |
| 2012頃 | Build 1400代がリリースされ、フォーラムでは「James Holden が使ってた」といった証言も広がる。 |
| 2016 (1月16日) | Build 1503 がリリース。正式 “最新” 版として記録。 |
| 2020年代 | ハード/ソフト・モジュラーの復興とともに、Buzz の思想が再評価される。 |
10. 図解:Buzz の信号フロー例
以下、Buzz における典型的なマシン接続(信号フロー)を図式化してみます。
解説:
- A:音源(波形生成 or サンプラー)
- B:フィルター(ハイパス/ローパス)
- C:エンベロープ/LFO (時間変化・周期変化)
- D:ディレイ(空間・タイミング加工)
- E:リバーブ(残響空間)
- F:出力(ミキサー→ステレオ)
- G:モジュレータ(LFO等)をフィルター等に掛けて変調を加えている
このよう に、Buzz ではマシン間を自由に接続できるため、従来の “音源→ミキサー→エフェクト” という固定的な流れでは得られない「回路的」「パッチ的」「探索的」な音響構造が可能となった。
