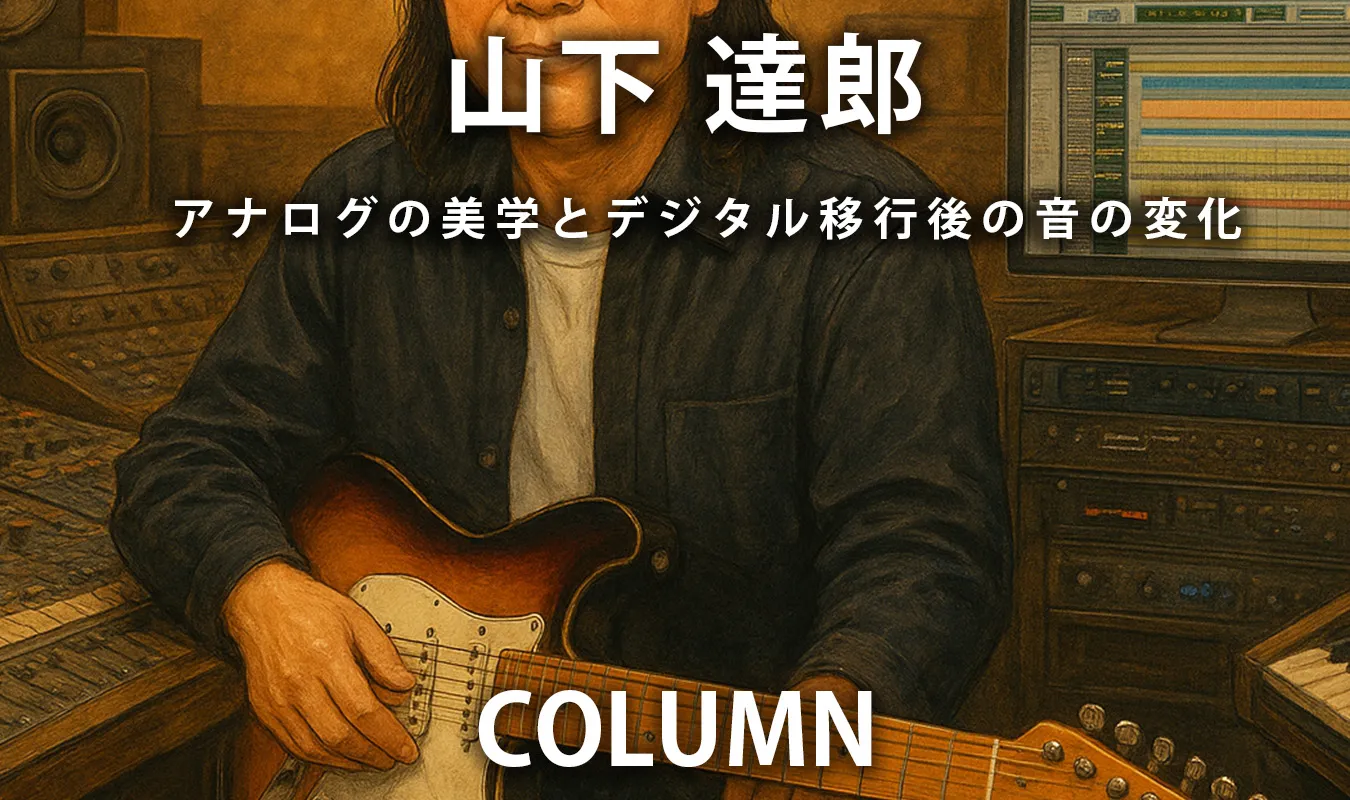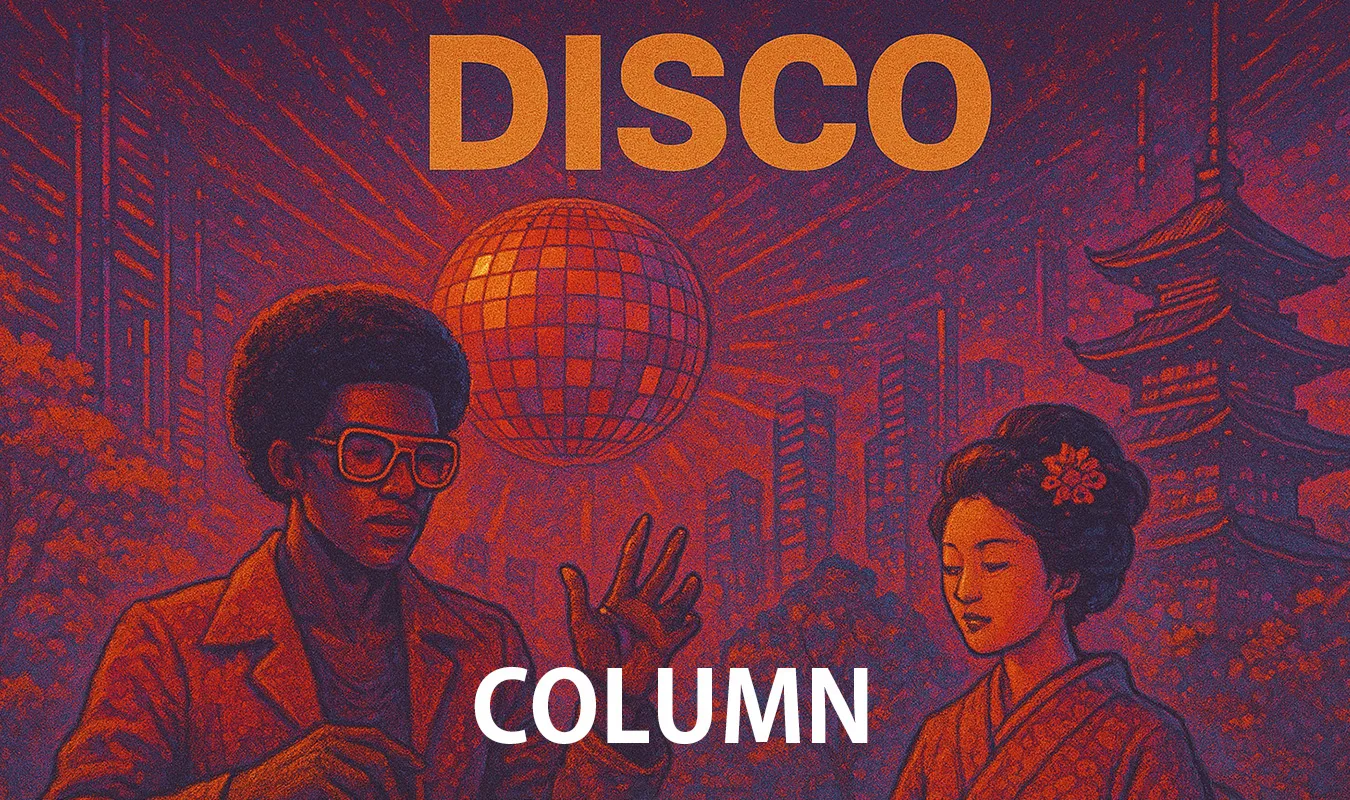1. 序章:なぜ今、シティポップなのか
文:mmr|テーマ:1980年代の日本都市ポップス“シティポップ”が、YouTube世代と海外DJにより再発見。都市の夜景と郷愁を映すサウンドは、今や世界で共鳴する文化的現象
1980年代の終わり、日本の音楽界では「シティポップ」という言葉が一度その役割を終えたはずだった。
だが2020年代に入って、このジャンルは世界のストリーミングチャートを賑わせている。YouTube上では「Plastic Love」が数千万回再生され、Spotifyでは“Tokyo Night Drive”“Japanese City Pop”といったプレイリストが常に上位を維持する。
この現象は単なる懐古ではない。アルゴリズムが偶然導いた再発見の裏に、都市的洗練と郷愁が共存する音楽への普遍的欲求が潜んでいる。
海外の若いリスナーにとって、これらのサウンドは「レトロ・フューチャー」の象徴だ。ネオンの光、雨上がりの舗道、アナログ録音の温度感――彼らは自国の音楽では得られない“異国の過去”に未来のロマンを見ている。
DJ Night Tempoは「この音楽は未来のノスタルジアだ」と語った。つまり、過去を消費するのではなく、“もう一つの未来”として日本の80年代を受け取っているのだ。
2. シティポップの定義:都市のサウンドスケープ
「シティポップ」とは、都市の光景を音に変換した文化装置である。
その音楽性は多層的だ。AOR、ソウル、ファンク、ジャズ、ディスコ――西洋の黒人音楽を下敷きに、日本語の旋律美と詩情を融合させた。山下達郎の緻密なヴォーカル・ハーモニー、竹内まりやの甘くも切ないメロディ、大滝詠一の構築的プロダクション。どれもが「日本人によるポップの再定義」として機能していた。
この音楽の主題は、恋愛や夜の街、孤独、移動といったモチーフに集約される。都市を舞台にしながら、どこか“取り残された感情”が流れているのだ。
それは高度経済成長が生んだ豊かさと空虚さを、個人の感覚として描いた“私的な風景画”だった。だからこそ、現代の海外リスナーにも共鳴する。都市化とデジタル化が進んだ今、彼らもまた同じ孤独を抱えているからだ。
3. 歴史的背景:高度経済成長とカセット時代
1970年代末から80年代にかけて、日本社会は急速に豊かさを手に入れた。
家電や車、ファッション、そして音楽が“都市的ライフスタイル”を象徴した。
Sonyのウォークマン(1979)は「音楽を持ち歩く」という革命をもたらし、シティポップはその理想的なサウンドトラックとなった。
FM局が次々と開局し、DJが英語交じりに最新ヒットを流す。アメリカ西海岸の風を感じさせるコード進行が、東京・横浜・神戸といった都市イメージと結びついた。
当時のリスナーは、シティポップを通じて「都会に生きる自分」を演出していたともいえる。
この時期、日本の録音技術は世界最高水準に達し、レコードの音質も極めて高かった。まさに、音響的にも社会的にも“都市”が鳴っていた時代だった。
4. 音楽的特徴:コード、グルーヴ、録音美学
シティポップの心臓部は、ハーモニーの洗練とリズムの柔軟性にある。
コード進行はMajor7や9thを多用し、浮遊感を生む。ディミニッシュで不意に転調する瞬間のメランコリーは、聴き手を“夜の都市”へと誘う。
リズムはAOR的でありながら、当時流行のディスコやソウルを吸収しており、BPM110前後の軽やかなグルーヴが特徴だ。
録音面では、当時のアナログ機材と熟練エンジニアによる“空間の美学”が光る。
スタジオのリバーブ処理や、EQの精密さが「透明感」と「湿度」を同時に実現した。
特に山下達郎の『SPACY』(1978)は、スタジオ録音の芸術性を極限まで高めた金字塔として語り継がれている。
このサウンドの完成度こそ、40年以上後に海外で“発掘”される理由のひとつだ。
5. 消費と忘却:90年代以降の沈黙
90年代、バブル経済の崩壊は音楽の価値観を根底から変えた。
都市の輝きは失われ、シティポップは“古臭い”“軽薄”とみなされた。
代わって台頭したのは、J-Popやヴィジュアル系、ヒップホップなど、“より個人主義的な自己表現”の音楽だった。
だが、地下では別の流れが生まれていた。クラブカルチャーの中で、DJたちがレアグルーヴとして80年代の日本音楽を再発見していたのだ。
DJ MUROやDJ Nori、Gilles Petersonらがコンピレーションを作り、世界中のレコードバイヤーが日本盤を探し求めた。
つまり、シティポップは完全に死んだわけではなく、“記憶の底”で静かに生き続けていたのである。
6. 再評価の起点:YouTubeと“Plastic Love”現象
2017年、YouTube上に一つの動画が静かに投稿された。
竹内まりやの「Plastic Love」。レコードの一枚画像と、淡い女性の横顔をサムネイルにしたシンプルな投稿。
しかしその動画はアルゴリズムに乗り、数年で数千万回再生を記録した。
なぜ拡散したのか?
第一に、YouTubeの自動推薦が“聴覚的連鎖”を生み、偶然海外リスナーの耳に届いた。
第二に、そのメランコリックな響きがVaporwaveやLo-fi HipHopと親和性を持っていた。
そして第三に、コメント欄が国際的な“ノスタルジア共同体”として機能したのだ。
こうして「Plastic Love」は、デジタル時代の偶像となった。
彼らは80年代を知らないが、この曲の“記憶の質感”をデータ越しに共有している。
7. 海外DJの視点:リスニングからダンスフロアへ
フランス、韓国、ロンドン、LA――各地のDJがCity Popをクラブに持ち込んだ。
Night Tempo、Yung Bae、Macross 82-99などが象徴的だ。
彼らはシティポップをサンプリングし、再構築して“Future Funk”という新ジャンルを生み出した。
この音楽は、単なる懐古ではなく、80年代の明るさと現代のテンポ感を融合したもの。
DJにとってシティポップは、BPM110〜115の「心地よく踊れるテンポ」であり、
サンプリング素材としても完璧な音質を備えている。
クラブの照明に照らされると、竹内まりやや角松敏生のサウンドが、まるで現代のダンスチューンのように響く。
それは“過去を再演する”のではなく、“過去と共に未来を踊る”という新しい体験だった。
8. Vaporwave/Lo-fi HipHop文化との接続
シティポップの再評価を語る上で欠かせないのが、インターネット発のVaporwave文化である。
このジャンルは、過去の広告音楽や日本語サンプルを切り貼りし、デジタルノイズとノスタルジーを融合した。
結果として、1980年代の日本文化が“匿名の未来”として再利用された。
Lo-fi HipHopも同様に、YouTubeのBGMカルチャーと結びつき、“Japanese 80s vibes”として拡散。
勉強用BGMとして流れるシティポップの断片が、数億回の再生を記録している。
つまり、音楽の文脈が完全に解体された上で、日本のポップスはグローバルな感情の素材となった。
ここにこそ、文化の翻訳を超えた「デジタル郷愁」の本質がある。
9. 現代アーティストへの影響
2020年代の日本では、シティポップのDNAを受け継いだ新世代が登場している。
SuchmosやLucky Tapes、cero、Nulbarichはもちろん、iriや向井太一、Vaundyといった若手もその系譜に連なる。
彼らは80年代のコード感やグルーヴを現代的に再構築し、“都市に生きる感情”を新しい言語で描く。
海外でもKhruangbin、Men I Trust、Crumbなどが“Japanese Aesthetic”を意識的に取り入れている。
Spotifyのデータでは、シティポップの聴取はアメリカ・ブラジル・韓国・フランスで特に増加。
つまりこのジャンルは、“ローカルな日本文化”ではなく、“ポストグローバルな感情共有装置”へと変貌したのだ。
10. 結論:ノスタルジアが輸出品になる時代
かつて日本人が“都会の夢”として作り上げた音楽が、40年後の地球の裏側で共感を呼んでいる。
それは単なる懐古ではなく、「過去が未来になる」逆転現象である。
AIが生成する映像、メタバース上の都市、NFTアート――どれもシティポップの延長線上にある。
音楽は時代の鏡であると同時に、時代を超える共感装置でもある。
シティポップが世界に愛されるのは、その音が「過去を再現する」のではなく、「失われた未来を夢見る」からだ。
都市の夜は、再び世界の耳に灯りはじめている。