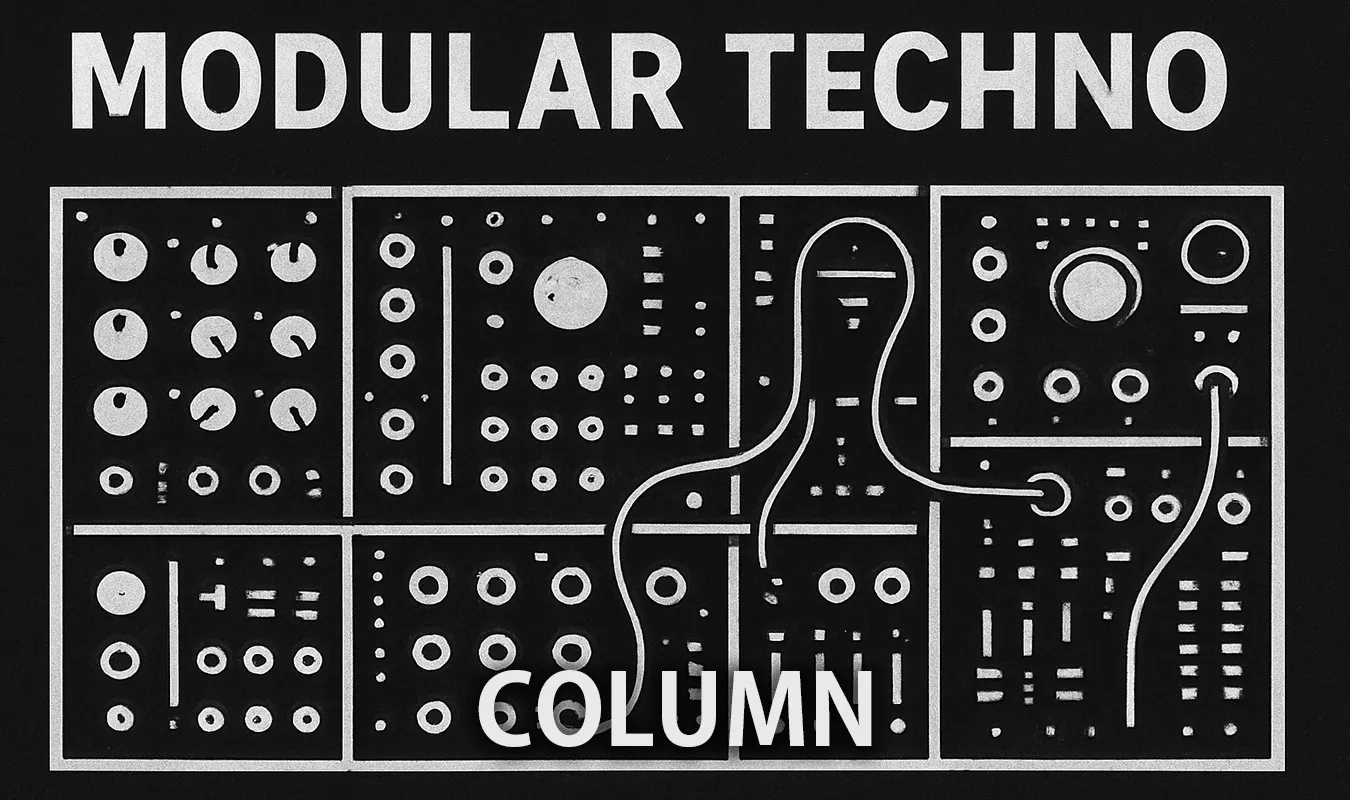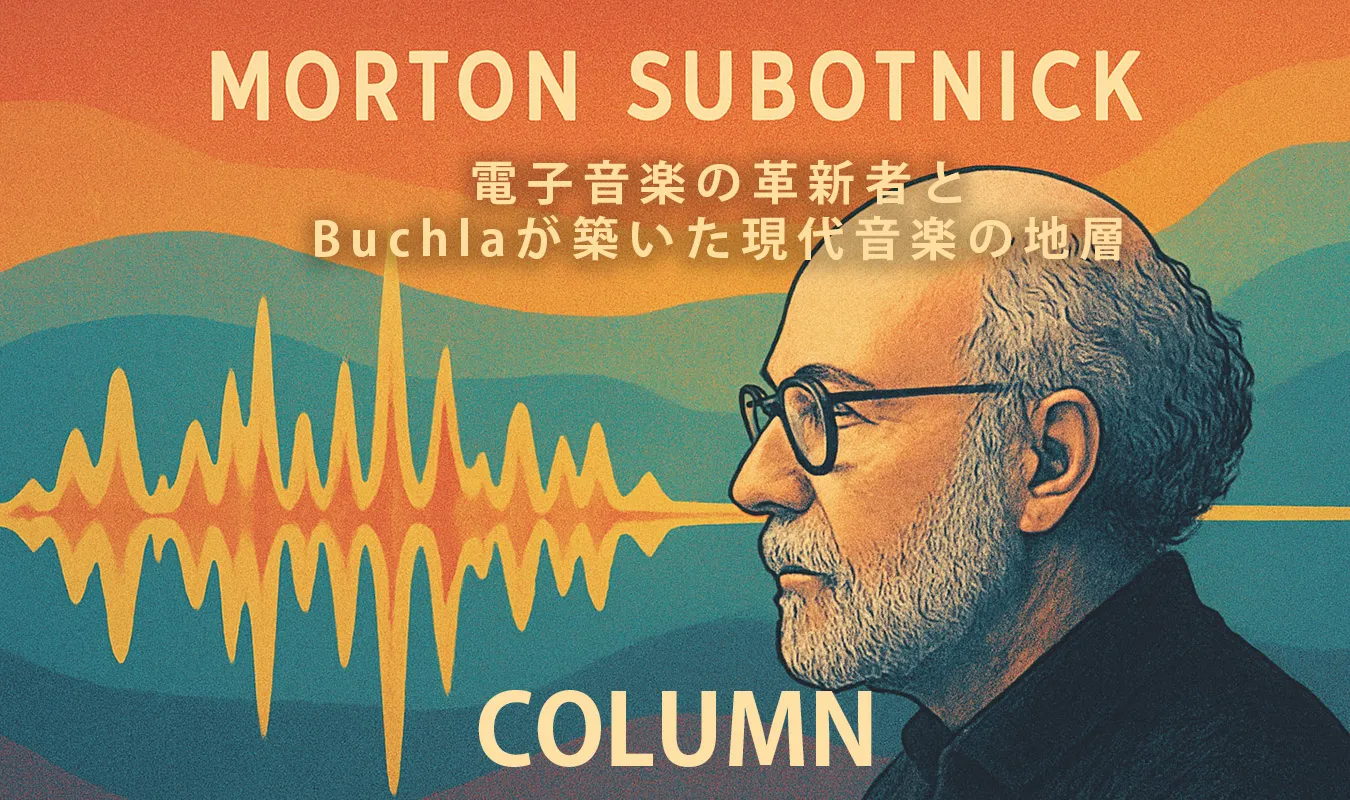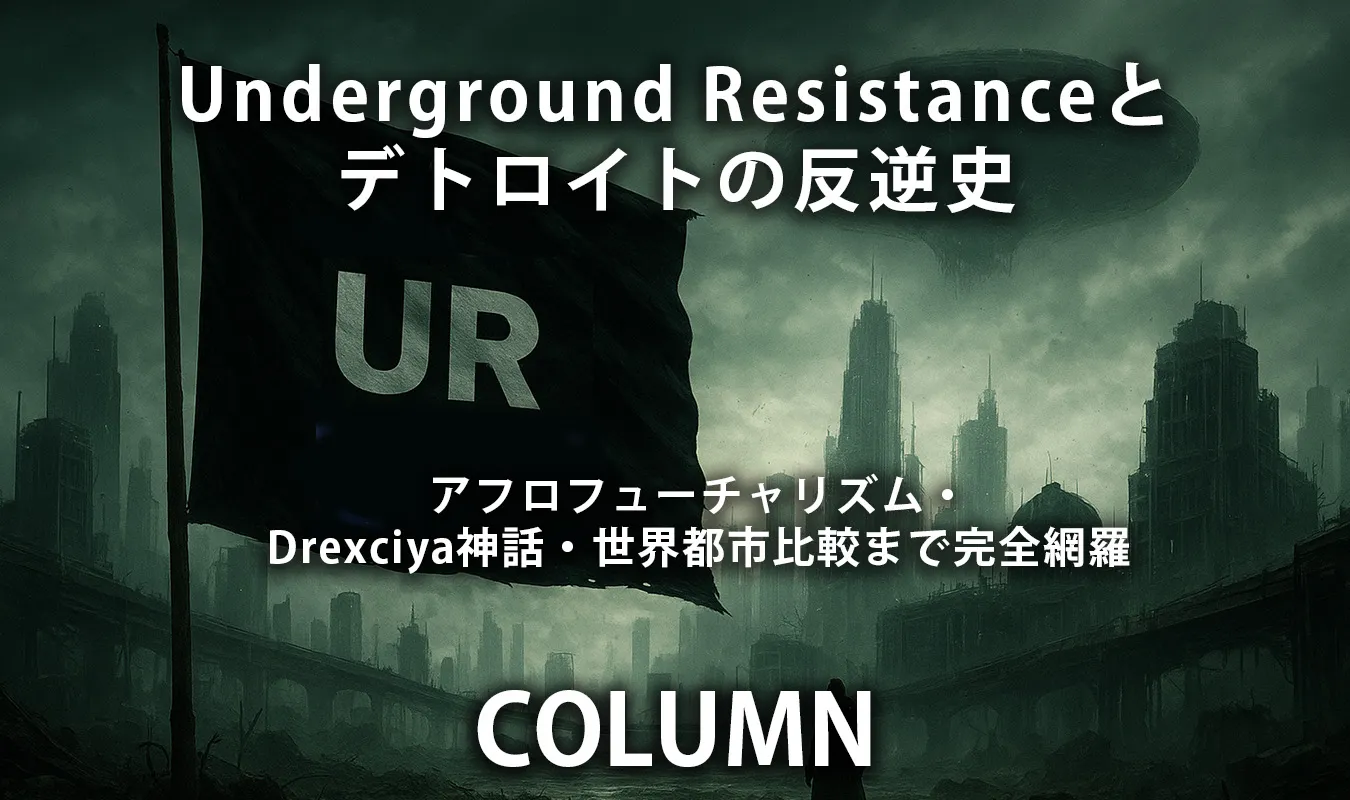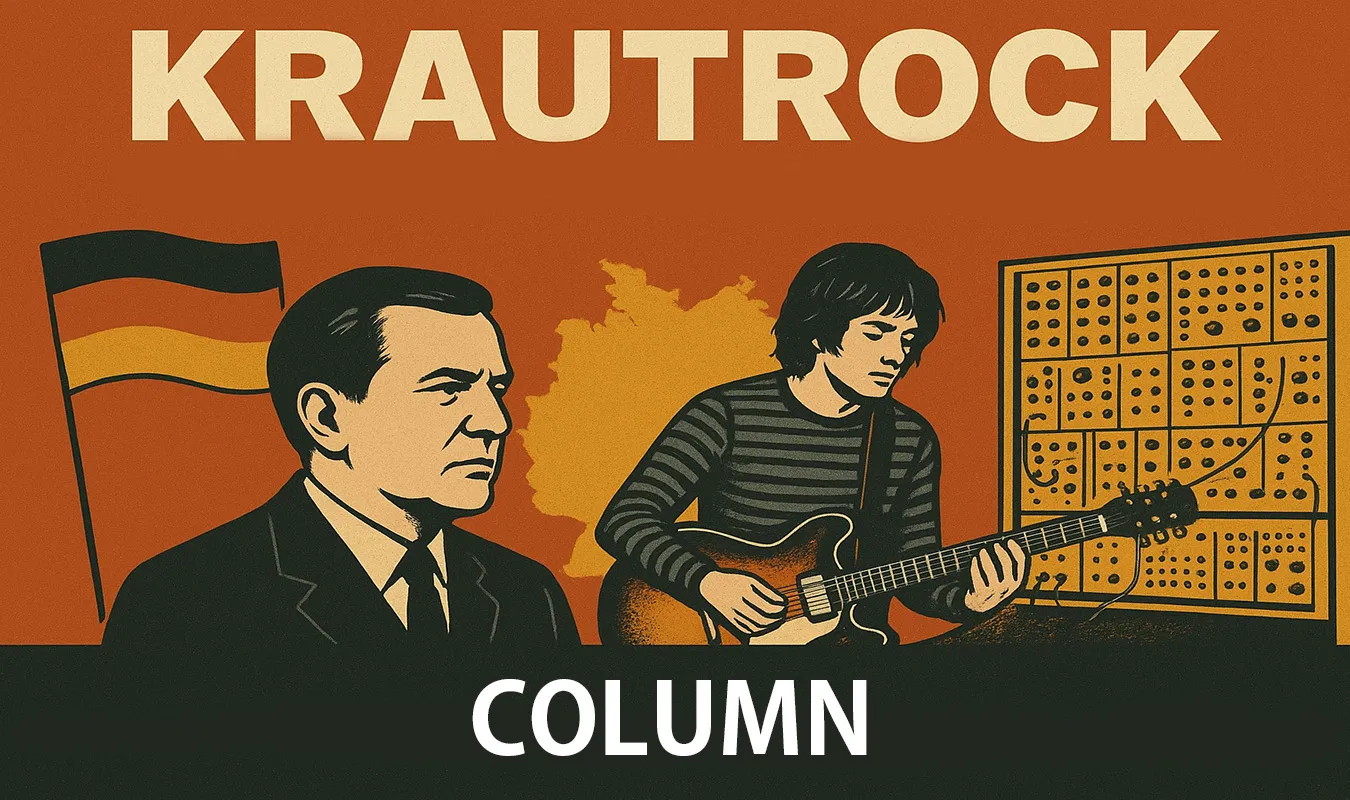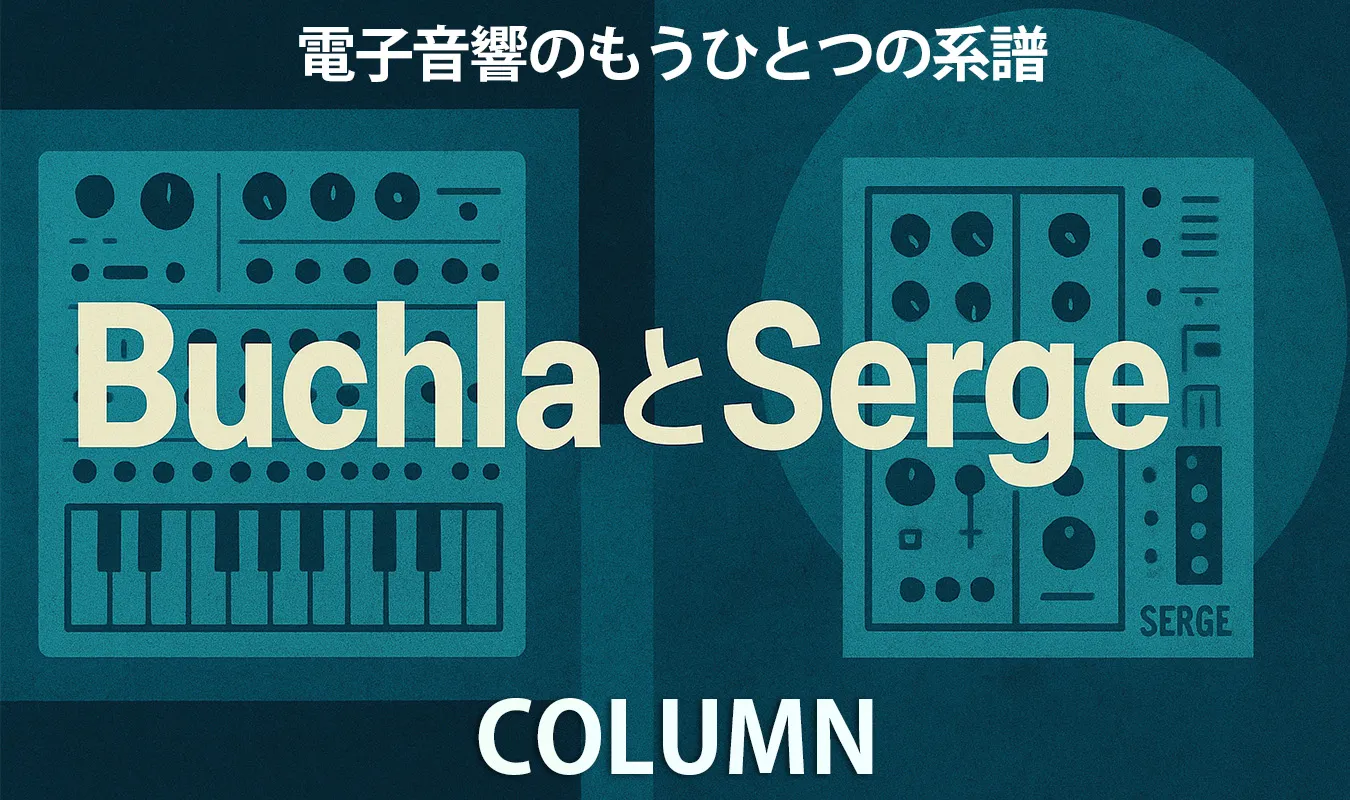
「はじめに — モジュラーとは何か」
文:mmr|テーマ:西海岸モジュラーシンセの精神史。ドン・ブックラとサージ・トチェーニーの思想が、どのように今日のサウンドデザインへ継承されたのか
1970年代初頭、アメリカ西海岸。
大学の電子音楽スタジオを離れ、「音をデザインする装置」を個人の創造空間へと持ち帰ろうとした人々がいた。
彼らの名前は Don Buchla(ドン・ブックラ) と Serge Tcherepnin(サージ・トチェーニン)。
BuchlaとSergeは、いわゆる「モジュラーシンセの始祖」として語られることが多いが、実際には商業楽器ではなく、哲学的な道具を作ろうとした点で異彩を放っている。
彼らの設計思想は、今日のEurorackやMax/MSP、あるいはAIを用いた生成音楽にも通底する“反・規範的”な音響観を宿していた。
1. ドン・ブックラ:電子音の詩学
1-1. サンフランシスコ・テープ・ミュージック・センターから
1960年代初期、サンフランシスコのテープ・ミュージック・センターでは、Morton Subotnick や Pauline Oliveros らが、実験音楽とテクノロジーの新しい関係を模索していた。
彼らが求めたのは、「ピアノやギターの延長ではない楽器」だった。
Subotnickの依頼に応えて登場したのが、Buchla Series 100(1963–1966)である。
ノブとパッチケーブルによる音響回路の構成、タッチプレート式キーボード(実際には「音階を持たない電圧入力デバイス」)など、従来の楽器的操作性を意図的に排していた。
“No black and white keys.” — Don Buchla
1-2. Buchlaの思想:Performative Electronics
Buchlaは楽器を「制御と生成が同居する生態系」として設計した。
音は演奏者の身体から直接出るのではなく、電圧変化という抽象的な振る舞いによって生成される。
そのため、演奏は即興的な“行為”となり、音は流動する。
(コントロール電圧)"] --> MOD["Modulation Bus
(変調経路)"] MOD --> OSC["Complex Oscillator
(複雑発振)"] OSC --> LPG["Low Pass Gate
(音色・音量連動)"] LPG --> OUT["Audio Out"] end style Buchla_System fill:#f0f8ff,stroke:#003366,stroke-width:1px;
この構造こそが、「音を操作するのではなく、音を触媒する」というBuchlaの世界観を象徴している。
Low Pass Gate(音量と音色を一体制御する素子)は、後にEurorack文化でも定番の哲学装置となった。
2. サージ・トチェーニン:民主化されたモジュール
2-1. “The People’s Synthesizer” の誕生
1970年代後半、ドン・ブックラの設計思想に感銘を受けた若き音楽家サージ・トチェーニンは、UCLAで電子音楽を学びながら「より多くの人が手にできるBuchla的装置」を構想した。
それが Serge Modular Music System(1974–)である。
ブックラが芸術家のための特注機を作ったのに対し、SergeはDIY文化と大学コミュニティに根ざし、「回路図を公開し、誰でも作れる」という精神を掲げた。
このオープンソース的な姿勢は、後のEurorack普及に先駆けた概念的革命だった。
2-2. Sergeの哲学:Patch Programmability
Sergeの根本思想は、“One module, many functions”。
つまり、単一の回路が接続方法次第で無数の動作モードを持つという考えだ。
たとえばDual Universal Slope Generator(通称「DSG」)は、
- エンベロープ
- LFO
- トリガーディレイ
- クロックディバイダ
- カオスモジュール
と、パッチ構成次第で機能が変容する。
この思想は今日のMax/MSPパッチング、Reaktor Blocks、あるいはEurorackのMake Noise「Maths」へと直系で受け継がれている。
3. BuchlaとSergeの比較:構造と思想
| 要素 | Buchla | Serge |
|---|---|---|
| 出発点 | 芸術家向け実験楽器 | 教育・DIY文化 |
| 操作思想 | Performative(行為としての音) | Functional(構造としての音) |
| 機能設計 | 専用モジュール構成 | 汎用モジュールを組み合わせ |
| コントロール | 抽象的電圧動作 | 具体的信号操作 |
| 音響傾向 | 有機・動的・滑らか | 線形・明快・高速レスポンス |
| 文化的影響 | アートサウンド、インスタレーション | ノイズ、テクノ、DIY電子音楽 |
4. 技術年表
| 年 | 出来事 | 備考 |
|---|---|---|
| 1963 | Buchla Series 100 開発開始 | Subotnick委託による最初のモジュラー |
| 1966 | Buchla Music Easel 原型登場 | ポータブル・シンセの始祖 |
| 1974 | Serge Modular 発表 | “People’s Synthesizer”のスローガン |
| 1980 | Serge Dual Slope Generator 登場 | パッチ哲学の完成形 |
| 1990s | Serge再評価期 | アナログリバイバルと再発 |
| 2004 | Eurorackブーム開始 | Doepfer, Make Noiseなどに継承 |
| 2020s | Buchla USA / Serge復刻 | オリジナル思想の再文脈化 |
5. モジュラー文化への影響
ブックラとサージの哲学は、音響そのものを“社会的行為”として再定義した。
つまり、「楽器」から「環境」「インターフェース」へと視点を移したのだ。
Eurorackにおけるモジュラーの“無限の組み合わせ”は、単にパーツの自由ではなく、意味の再構成そのもの。
Buchlaの「身体性」、Sergeの「構造性」が融合し、今日の電子音楽はますます“非中心的”になっている。
6. 現代への接続:アルゴリズムと身体のあいだで
Max/MSPやVCV Rack、さらにはAI生成音楽ツールにおいても、Buchla/Sergeの精神は生きている。
それは単なる“モジュールの組み合わせ”ではなく、時間・空間・身体・確率を接続するアート的フレームである。
モジュラーシンセは、音を作るための「道具」ではなく、
音と人とのあいだに生まれる「出来事」を生成するメディアだ。
BuchlaとSergeの設計思想は、まさにそのメディア哲学の萌芽であり続けている。
結語 — “Control Voltage” の詩学
ドン・ブックラは生前、こう語ったという。
“Voltage is not a number — it’s a gesture.”
サージもまた言う。
“Every patch is a composition.”
彼らにとって、電圧とは単なる信号ではなく、
「人間の意志と機械のあいだを結ぶ詩的な言語」だった。
2025年の今もなお、私たちはその電圧の詩を聴き続けている。