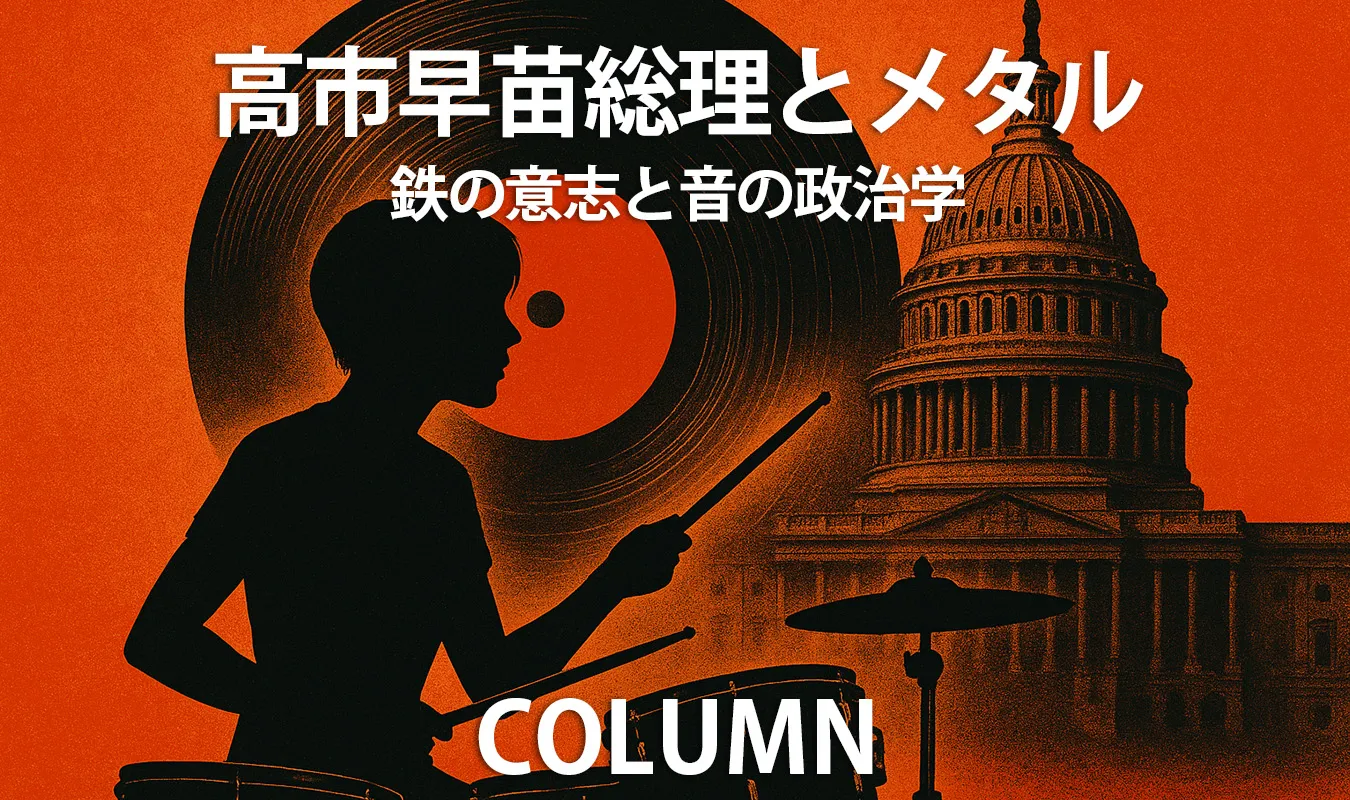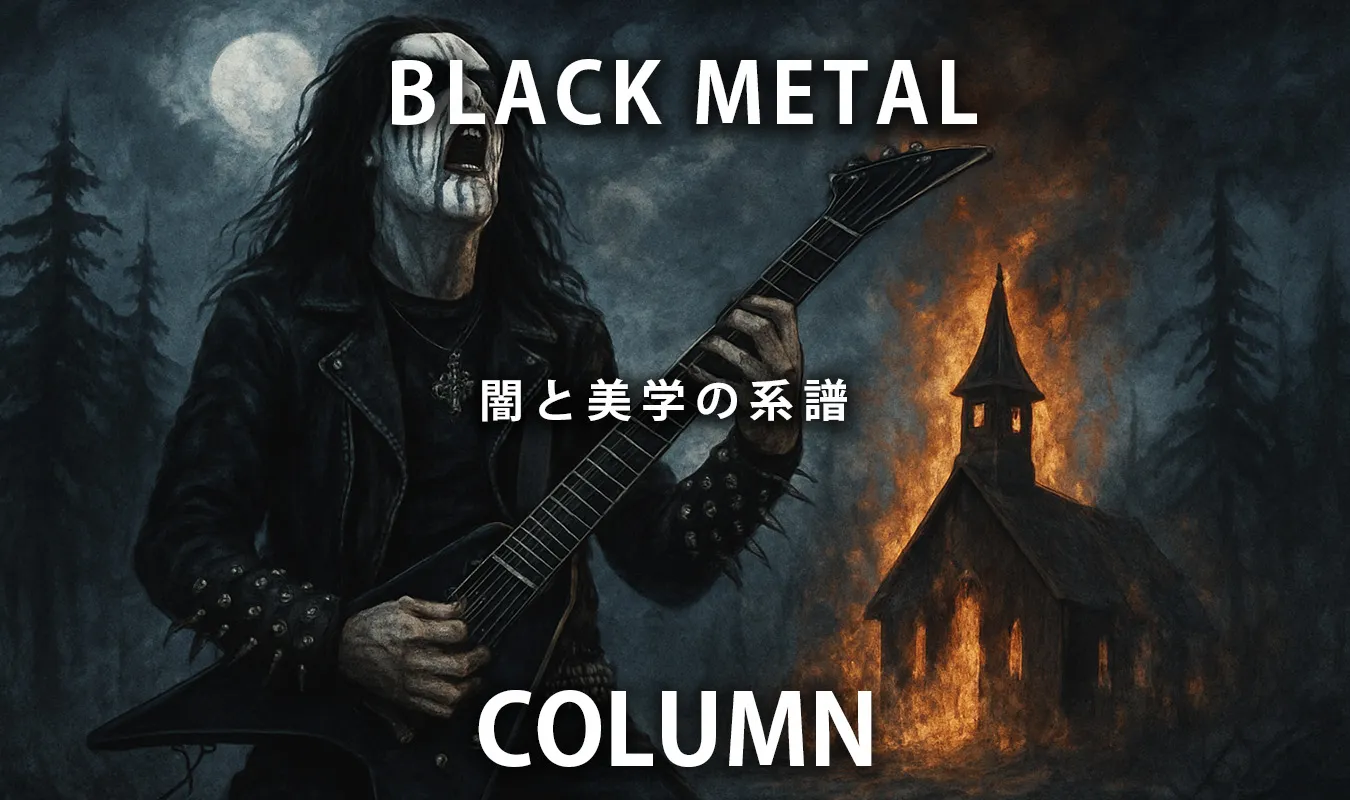
ブラックメタル —— 暗黒音楽の進化史
文:mmr|テーマ:ブラックメタルの地域別詳細分析・個別バンドセクション・細分化年表・図解を備えて包括的に辿る
ブラックメタル(Black Metal)は、極限の表現・反体制・美学的破壊を抱えながら独自の進化を遂げてきた。音楽性だけでなく、思想、文化、地域性、芸術表現まで総合的に絡み合う本ジャンルは、金属音楽史のなかでも最も複雑な体系をもつ。
序章:なぜブラックメタルは“特別”なのか
ブラックメタルは、ヘヴィメタルの中でも最も“概念的”で、最も“美学的”で、 そして最も“文化的背景の影響を受ける”ジャンルである。
音の特徴だけでは語れない。 宗教観、地理環境、民族文化、哲学、政治状況、自然環境、録音技法、アンダーグラウンド倫理。 それらすべてが結びつき、ブラックメタルは他ジャンルとは異なる独自の存在となった。
本稿では、その全体像を史実にもとづき包括的に整理し、 さらに地域別分析・個別バンド深掘り・年表細分化まで統合した 決定版の長編ブラックメタル論を構築する。
第1章:起源 — 1970年代の暗黒美学の萌芽
ブラックメタルは1980年代に生まれたと思われがちだが、 その基盤は1970年代のヘヴィメタル黎明期に確立されていた。
■ Black Sabbath の“暗黒性”
1970年の Black Sabbath のデビューは、 オカルティズム・不吉さ・陰鬱なムードといった“ダーク”の概念をメタルの中心に据えた。
■ Venom 出現前の重要要素
- オカルト文学の影響
- 悪魔学的表現の拡大
- 反宗教的アートの普及
- ストリート文化と極端音楽の近接化
ブラックメタルの“精神的起源”はこの段階で既に芽生えている。
第2章:第一波(1981〜1989)— 荒々しい暗黒性の確立
1981年、Venom が誕生する。 1982年のアルバム 『Black Metal』 はジャンル名の起点となった。
■ 第一波の特徴
- スラッシュ/スピードメタル的
- 荒い演奏
- 悪魔崇拝・反キリストを全面化
- ローファイ録音
- ライブ重視の暴力性
■ キーとなるバンド
- Venom(英国)
- Bathory(スウェーデン)
- Hellhammer → Celtic Frost(スイス)
- Sarcófago(ブラジル)
- Tormentor(ハンガリー)
第一波の音楽は荒々しく、 のちの「冷たい・霊的・氷のような」第二波ブラックとは質感がまったく異なる。
しかし、美学の骨格(悪魔、反宗教、暗黒録音、反商業主義)は確立した。
第3章:第二波(1990〜1998)— ノルウェーが世界を変えた
ブラックメタル史でもっとも重要な時代が1990〜1998年である。 中心はノルウェーの若いアンダーグラウンド・ミュージシャンたちだった。
■ キー概念
- ローファイ録音を“美学“として確立
- トレモロリフ
- スクリーム Vo
- 反復と速度による“氷の荒野”の表現
- コープスペイント
- 冬・森林・孤独の自然観
■ 代表バンド
- Mayhem
- Darkthrone
- Burzum
- Emperor
- Immortal
- Satyricon
■ 重大事件
- 1991:Mayhem の Dead が死去
- 1992:教会放火事件
- 1993:Euronymous 殺害事件
- 1993–1994:主要アルバム一斉リリース
ノルウェーのシーンは暴力事件と美学の結びつきにより 世界的議論を巻き起こし、ブラックメタルを単なる音楽ではなく 文化現象へと押し上げた。
第4章:第三波(1998〜2005)— 世界的拡散と変異
第二波の音像を継承しながら、 1998年以降は国際化と多様化が急速に進む。
■ 主な潮流
- USBM の台頭(Leviathan, Xasthur)
- フランス DSÔ・LLN 系の哲学化
- プログレ化(Enslaved)
- アトモスフェリック志向
- 民族音楽との融合
ブラックメタルは“思想・音楽・文化圏ごとの多様化”という 新たなフェーズへ移行する。
第5章:第四波(2005〜2025)— ポストブラックと多文化化
2005年以降は、従来の美学を継承しながらも “新しい光”“新しい感情”“新しい自然観”が導入され、 ブラックメタルは再定義されていく。
■ 代表的潮流
- ポストブラック/ブラックゲイズ(Alcest, Deafheaven)
- 自然霊性を基盤とする北米系(WITTR)
- アトモスフェリック系の世界的普及
- 東欧の民族主義・自然詩学系の拡大(Drudkh)
- 東アジアの新世代(Zuriaake ほか)
ブラックメタルは、もはや欧州だけのものではなく、 “世界各地の文化が反応して生まれる概念音楽”へと変化した。
第6章:個別バンド詳細セクション(主要バンドの思想・音楽性・社会的影響)
ここでは、ブラックメタル史上の要となったバンドを、時代・地域・潮流ごとに体系的に掘り下げる。
Venom(UK):ジャンル名称を決定づけた始祖
活動開始:1979年 代表作:Black Metal (1982), Welcome to Hell (1981)
- Venom は、ブラックメタル特有の「理念」や「美学」の多くを持っていないが、 “Black Metal” という語を作品タイトルとして初めて強く提示したバンドである。
- 音楽的にはスラッシュ・パンク・NWOBHM の中間を突き進む荒削りなサウンド。
- Chronos らメンバーは、宗教的な神秘思想を真剣に標榜していたわけではなく、 ショック要素としての悪魔主義/反宗教を利用。
- その結果、後世の北欧ブラック勢が Venom を“音楽ではなく姿勢”の源流と位置づける。
Bathory(Sweden):音楽的ブラックメタルの基礎を確立
中心人物:Quorthon 代表作:Bathory (1984), The Return…… (1985), Under the Sign of the Black Mark (1987)
- 北欧ブラックメタルの「音楽的フォーマット」を最初に明確化したのが Bathory。
-
特徴
- ノイズの壁のようなギター
- エコーが深く広い絶叫ヴォイス
- リフのミニマル構造
- リズムの高速化(特に1985〜87)
- スウェーデン特有の“冷気”と“湿気”を思わせるメロディラインは以後のムーヴメントに直結。
- 90年代にはヴァイキングメタル期へ移行し、ブラックメタルの範疇を超えた北欧神話美学の再創造へ。
Mayhem(Norway):ノルウェー・サークルの中心
代表作:Deathcrush (1987), De Mysteriis Dom Sathanas (1994)
- メンバー構成、事件、思想、すべてがブラックメタル第二波の象徴。
- Dead(Per Ohlin)のステージ・パフォーマンス(死体化粧・生肉など)は ブラックメタルに「死と非人間性」の儀式的要素を持ち込む決定的出来事。
- Euronymous は Helvete(オスロのレコード店)を活動拠点として、 ブラックメタル・インナーサークル(密な少人数コミュニティ)を形成。
- 後に Euronymous 殺害事件(1993)と教会放火事件群で世界的な注目を浴びる。
Burzum(Norway):ミニマリズムと神秘主義の確立
中心人物:Varg Vikernes 代表作:Burzum (1992), Det Som Engang Var (1993), Hvis lyset tar oss (1994)
- 音楽は徹底したミニマリズムを志向し、 反復によるトランス性・時間感覚の崩壊を意図した作風。
- 1990年代前半のノルウェー文化・宗教論争において強い発信を続け、 メディアの過剰報道によりブラックメタルの「危険イメージ」が定着。
- 事件(Euronymous 殺害)と逮捕以降、Burzum 音源はよりアンビエント志向に向かう。
Darkthrone(Norway):ローファイの美学を定義
代表作:A Blaze in the Northern Sky (1992), Under a Funeral Moon (1993), Transilvanian Hunger (1994)
- 1991年までデスメタル志向だったが、 Bathory に強く影響され、北欧ブラックメタルの“最純形”を確立。
-
録音は極端にローファイで、
- 垂直なギターの壁
- ハイハットとスネアのモノトニックな連打
- 極端に軽いベース が“北欧黒金属の音”=「コールド・サウンド」の決定版となる。
Emperor(Norway):シンフォニックな広がりの創造
代表作:In the Nightside Eclipse (1994)
- キーボードの大規模使用により、 ブラックメタルをオーケストラ的な音響へ拡張したパイオニア。
- Samoth、Ihsahn の二軸で構築された構造は、後のシンフォニックBM 全体の原型となる。
Immortal(Norway):北極神話の独自路線
代表作:Battles in the North (1995), At the Heart of Winter (1999)
- “Blashyrkh” と呼ばれる架空の氷雪世界観を構築し、 暴力性ではなく架空神話性を押し出した点で異色。
- ギター・ドラムの速度と、フィクション世界の濃度が後年の“ファンタジーBM”の源流に。
第7章:地域別の専門的分析(国・文化背景ごとに体系化)
ノルウェー:第二波の神殿
- 主軸:Mayhem / Burzum / Darkthrone / Emperor / Immortal / Satyricon ほか
-
文化背景
- 国教としてのキリスト教(ルター派)と、北欧古層文化の断絶
- 90年代初頭の若者文化の閉塞
- 政教関係の歴史的摩擦
-
音楽的特徴
- ローファイ志向
- メロディの北欧民俗的下降フレーズ
- 極寒の空気感を持つトレモロリフ
スウェーデン:メロディと秩序の国
- 主軸:Bathory / Marduk / Dark Funeral / Dissection
-
特徴
- スウェーデンは録音技術において安定しており、 “冷たさと高解像度の両立”という独特のサウンドを生む。
- Dissection のデス・メロディ導入は、全世界のメロディックBMに波及。
フィンランド:異形系の温床
- 主軸:Beherit / Impaled Nazarene
-
特徴
- ノイズ、プリミティブ、ロウ・サタニズムなど 最も“異端寄り”のブラックメタルが集中。
- 録音の質よりも“儀式性”を重要視。
フランス:ポスト・ブラックの先駆地
- 主軸:Deathspell Omega / Blut Aus Nord
-
特徴
- 哲学的、反教義的、アヴァンギャルドな表現が突出。
- 2000年代以降は世界のブラックメタルの中心潮流のひとつを形成。
アメリカ(USブラックメタル):多様性の坩堝
- 主軸:Leviathan / Xasthur / Wolves in the Throne Room
-
特徴
- カスカディアンBM(自然崇拝系)
- DSBM(鬱系)
- アンビエントBM と各スタイルが細分化し、世界展開を主導。
東欧:ペイガンと民族主義の磁場
-
ロシア、ウクライナ、ポーランド
- Drudkh, Nokturnal Mortum, Graveland など
- フォークロア・神話・土着文化の比重が高い。
第8章:年表
— 主要出来事+年ごとの名盤リスト —**
下記は 事実ベースの時系列。事件や作品は公式リリース年・発生年を基準とする。
1980–1984(原初相)
1981
- Venom Welcome to Hell 1982
- Venom Black Metal(ジャンル名が確立する契機) 1984
- Bathory Bathory(北欧BMの音楽的基礎を定義)
1985–1989(音楽的フォーマット成立)
1985
- Bathory The Return…… 1987
- Bathory Under the Sign of the Black Mark
- Mayhem Deathcrush EP
名盤
- Celtic Frost(スイス)Into the Pandemonium (1987) — アヴァンギャルド方向性の原型。
1990–1993(第二波勃興・事件の時代)
1990
- Immortal 形成
- Emperor 形成
1991
- Mayhem:Dead 死去(事実)
- Darkthrone:デスメタルからブラックメタル方向へ転換決定
1992
- Burzum Burzum
- Darkthrone A Blaze in the Northern Sky
1993
- 複数の教会放火事件の発生(事実)
- Euronymous 殺害事件(事実)
- Burzum Det Som Engang Var
1994–1999(ジャンルの拡張・成熟)
1994
- Mayhem De Mysteriis Dom Sathanas
- Emperor In the Nightside Eclipse
- Burzum Hvis lyset tar oss
- Darkthrone Transilvanian Hunger
1995
- Immortal Battles in the North
- Gorgoroth デビュー
1996–1999 名盤
- Satyricon Nemesis Divina (1996)
- Immortal At the Heart of Winter (1999)
2000–2010(ポスト・ブラック/DSBM/US勢の台頭)
2003
- Xasthur The Funeral of Being(DSBMの礎)
2006
- Wolves in the Throne Room Diadem of 12 Stars(カスカディアンBMの確立)
2010
- Deathspell Omegaの哲学的三部作が世界的評価へ。
2011–2020(グローバル化とクロスオーバー)
- 日本、東欧、北米、南米を中心に地域性が織り込まれる時代へ
- ブラックゲイズ(黒轟音+シューゲイザー)系が欧米で拡大
- Raw Black Metal の再ブーム(特にBandcamp文化と連動)
第9章:図:ブラックメタル潮流系統図
総括:ブラックメタルとは何か
ブラックメタルは、金属音楽の一派でありながら、宗教・美学・哲学・録音文化・地域社会など多方面に根を張る“総合文化現象”である。 単なる破壊的音楽ではなく、各地で異なる方向へ進化し、時に芸術・文学・映像文化にも浸透してきた。
冷気、闇、精神性、反逆、孤独、祝祭、儀式。 そのすべてがブラックメタルの中に同時に存在している。
- ブラックメタルの音楽は 特定地域の気候・文化・歴史の反映として成長した。
- 1990年代以降は 多極化(ノルウェー中心から世界へ)が進行。
- 事件・思想・社会背景はジャンルの評価やイメージ形成に強く影響したが、 音楽史的には各バンドの作品構造・録音美学の変遷こそが本質である。
- 2000年代以降は アヴァンギャルド化・自然崇拝型・DSBM・ポストBMのように細分化し、 2020年代まで拡張が続いている。