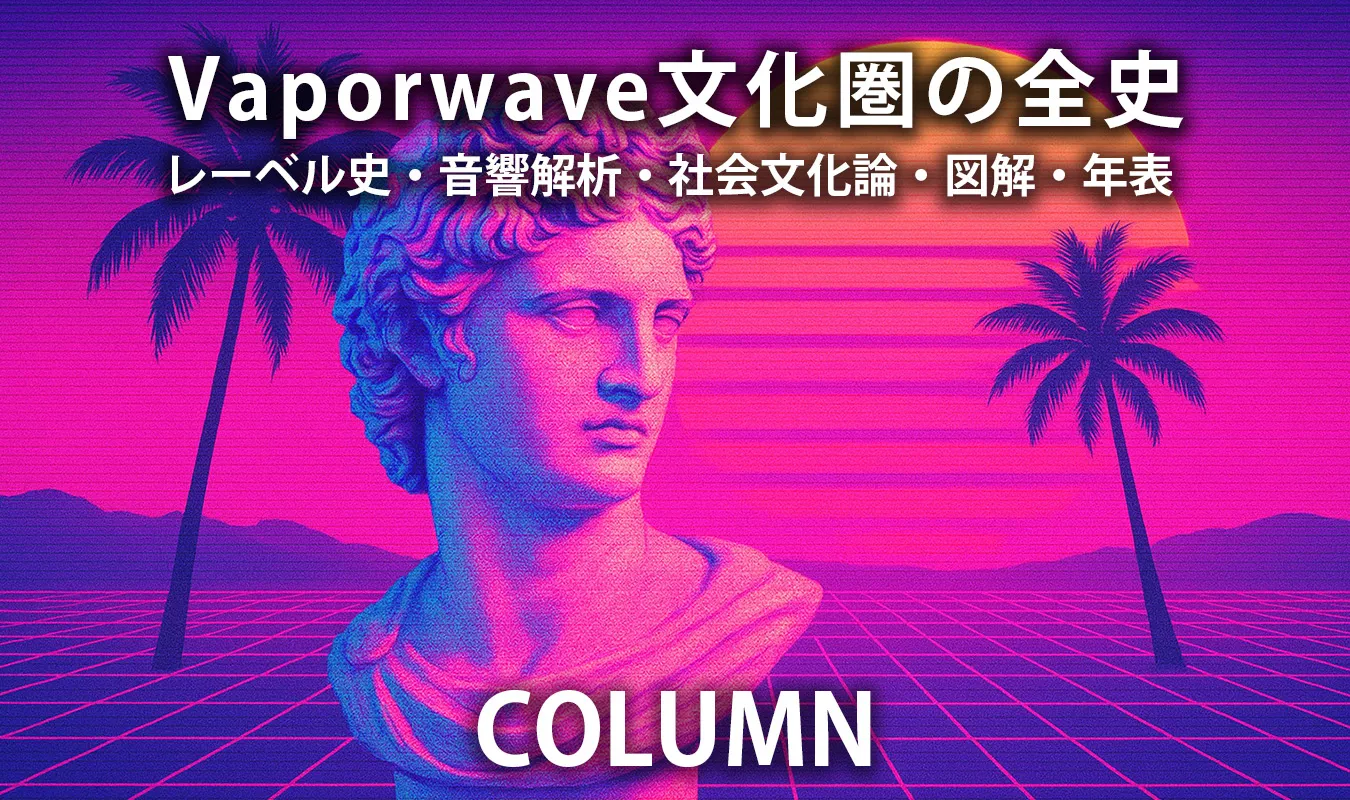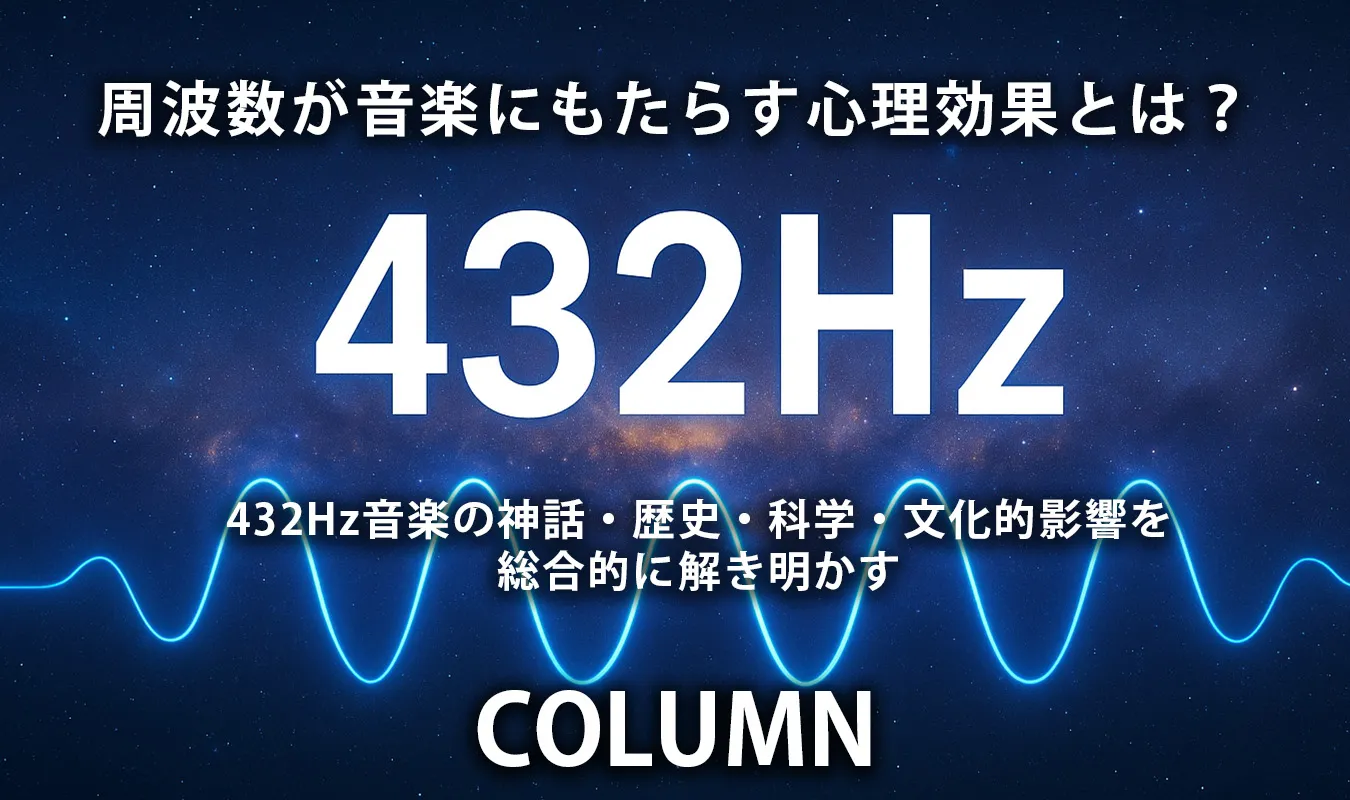序章:耳という感覚の詩学
文:mmr|テーマ:耳は小さな宇宙だ。聴覚の研究・予防・再生を支援するHHFの活動を通して、“聴く”という行為の神秘と未来を探る
「沈黙こそ、音楽の最も大切な一部である」
— マイルス・デイヴィス
耳は、単に音を拾うための器官ではない。
それは記憶を運び、世界とつながるための“詩的装置”だ。
Hearing Health Foundation(HHF) は、この“聴く力”を守り、取り戻すために活動している。
米国最大の聴覚・平衡感覚研究基金として、彼らは聴覚障害や耳鳴りの原因究明から、再生医療・遺伝子治療の最前線までを支援している。
1. 聴くことの科学──耳の中の宇宙
「音は空気を震わせ、心を震わせる。」
— ブライアン・イーノ
外耳で拾われた音は鼓膜を震わせ、耳小骨を通って蝸牛へ。
内耳の有毛細胞がその振動を電気信号に変え、脳が“音”として認識する。
HHFのサイトには、この精妙なシステムの破綻によって引き起こされる感音性難聴やメニエール病、過敏聴覚のメカニズムがわかりやすく解説されている。
外耳で集められた音は、鼓膜を経て中耳の耳小骨に伝わり、内耳の蝸牛へ。 そこから電気信号へ変換され、聴覚神経を通じて脳幹・聴覚野に届く。 音を聴くことは、物理的現象から神経的・認知的プロセスまでが連なる、まさに“生命の音楽”である。
2. 聴覚障害の風景──静寂の中のリズム
歌手グライムスは、耳鳴りに悩まされながらも楽曲制作を続けている。
「ノイズの中にも秩序がある」と彼女は語る。
聴覚障害は、失うことではなく“再構築”の過程かもしれない。
HHFは、耳鳴り(Tinnitus)やバランス障害の研究支援を続けている。
その対象は、単なる医学研究にとどまらず、「聴覚と脳の相互作用」を解き明かすニューロサイエンス領域にも及ぶ。
3. 再生の科学──音を取り戻すという夢
「耳は回路であり、音楽は電流だ。」
— 坂本龍一
HHFが支援するHearing Restoration Project(HRP)では、
失われた有毛細胞を再生するための細胞療法・遺伝子治療の研究が進む。
これは、“聴くこと”の回復を現実のものとする未来への実験だ。
人工内耳や新型補聴器の技術革新も目覚ましい。
“音を増幅する”から“脳に直接届ける”へ。
サウンドデザインの領域でも、脳波を利用した“聴覚的UI”研究が加速している。
▶︎ 図:聴覚信号経路(音波から聴覚野まで)
簡易版
この経路は“聴覚の旅”である。 物理的な空気の震えが、やがて感情や記憶と結びついた「音楽」へと昇華していく。 その複雑な階層構造の研究は、人工知能の音声認識モデル設計にも応用されている。
4. 騒音と沈黙のあいだ──予防のカルチャー論
ロック・コンサートの爆音、イヤホンの過剰使用、都市の騒音。
これらは現代の“聴覚汚染”といえる。
HHFのキャンペーン「#KeepListening」は、音量と距離の関係を再考する社会的ムーブメントだ。
実際、デイヴィッド・ボウイは耳の健康を非常に気にかけ、
ツアー時にはステージのモニタ音量を通常の半分に設定していたという。
聴覚を守ることは、表現を長く続けるための“芸術的セルフケア”でもある。
5. 音楽家と耳の運命──逸話で読み解く「聴覚の文化史」
- ベートーヴェン:難聴の絶望の中で《第九》を完成。
- ピート・タウンゼント(The Who):ライブの爆音で聴力を失い、聴覚保護の啓発活動を開始。
- フィル・コリンズ:片耳難聴を抱えながらもツアーを敢行。
- レディオヘッドのトム・ヨーク:耳鳴りを抱えつつ、“内なる音”を楽曲に昇華。
これらの逸話が示すのは、耳が壊れても音楽は終わらないということだ。
HHFの理念は、その精神を科学的に支えるものでもある。
6. 社会と支援──耳の未来をつくるコミュニティ
HHFは寄付・研究助成・教育を通じて、聴覚健康の“文化的リテラシー”を育てている。
例えば、毎年選出されるEmerging Research Grants受賞者たちは、
遺伝子編集から人工知能まで、多様な角度から“聴く未来”を描いている。
また、一般向けのオンライン誌「Hearing Health Magazine」では、
実際の体験談や専門家のコラムが掲載され、耳の健康をライフスタイルとして提案している。
7. 結語:聴くという行為の未来
「音楽は“聴くこと”の芸術であり、聴くことは“生きる”ことだ。」
— ジョン・ケージ
聴覚の科学は、私たちの感性の科学でもある。
音の再生とは、人間の“存在の再生”なのかもしれない。
Hearing Health Foundationの活動は、医学とアートの境界を超え、
“聴くこと”をめぐる文化の未来を静かに照らしている。