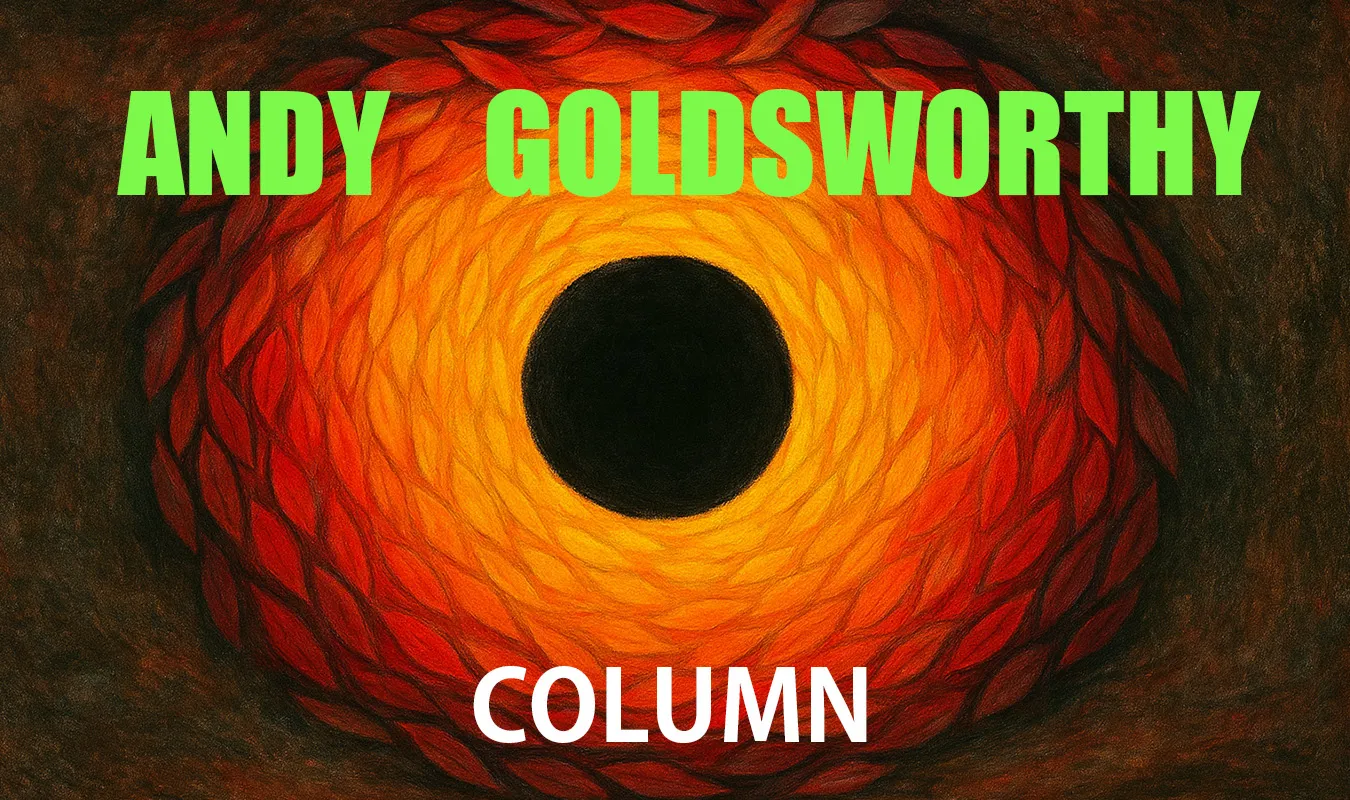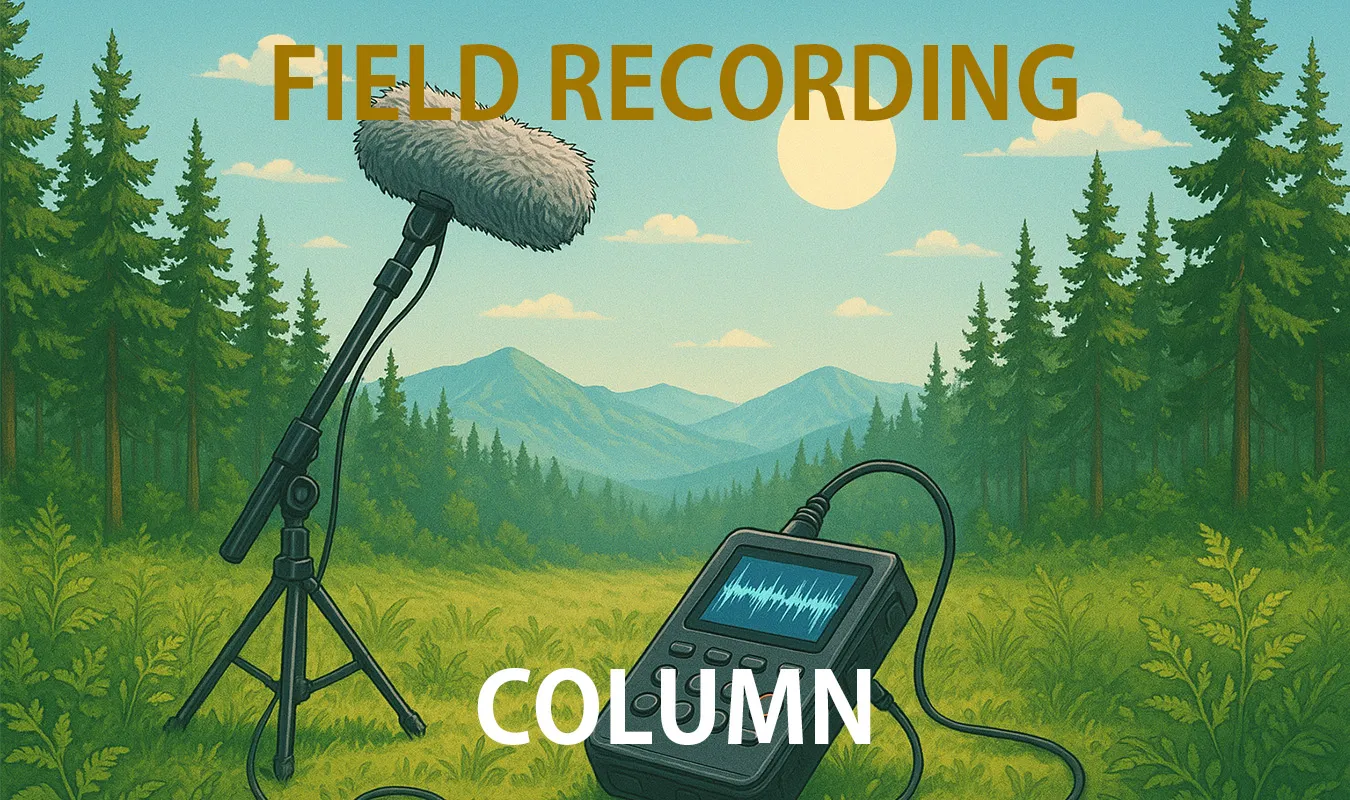
なぜフィールドレコーディングか
文:mmr|テーマ:フィールドレコーディングの歴史、主要機器の特徴、代表的な録音作家・プロデューサー、年代別おすすめアルバムを網羅
フィールドレコーディング(field recording)は、スタジオを離れ“現場の音”をそのまま記録する行為です。自然音、都市の環境音、民俗歌唱、鉄道や工場の機械音──これらは単なる効果音にとどまらず、文化のアーカイブであり音楽的素材でもあります。映画・ゲーム・音楽制作・サウンドアートのいずれにも不可欠な技術です。
年表(概観)
機材ガイド:主要メーカーとモデル
現場録音は「マイク+レコーダー+電源」の三位一体です。ここでは多用途に使える定番とその特徴を簡潔に示します。
| ブランド | モデル | 特徴 | 時代 |
|---|---|---|---|
| Zoom | H6 / H6essential | 交換式マイクカプセル、多トラック | 2010s〜現在 |
| Tascam | DR-100MKIII | プロ仕様、外部マイク入力 | 2010s |
| Sound Devices | MixPreシリーズ | 32-bit float、高品位プリアンプ | 2010s〜現在 |
| Sony | PCM-D100 | ハイレゾ対応、堅牢性 | 2010s |
| Roland | R-09 / R-26 / R-07 | 小型&多機能、Bluetooth対応モデルあり | 2000s〜現在 |
| NAGRA | アナログ/デジタル機 | 映画・放送の定番 | 1960s〜現在 |
フィールドレコーディング・アーティストと使用機材リスト
| アーティスト | 活動概要・代表作 | 使用機材(代表的なもの) |
|---|---|---|
| Alan Lomax | 20世紀の民俗音楽アーカイブ。米国〜世界のフィールド録音を記録。代表作:The Alan Lomax Collection | Ampexテープレコーダー、Nagra(1950s以降)、各種ダイナミックマイク |
| Chris Watson | 元Cabaret Voltaire。BBCやドキュメンタリー制作で自然音の録音を担当。代表作:El Tren Fantasma (2011) | Sound Devices 7シリーズ、Nagra、Sennheiser MKHシリーズマイク |
| Bernie Krause | 自然環境音(バイオフォニクス)の第一人者。代表作:The Great Animal Orchestra | Nagra IV、Sound Devices レコーダー、Neumann & Sennheiser マイク |
| Hildegard Westerkamp | サウンドウォーク/アコースティック・エコロジー運動。作品:Kits Beach Soundwalk | 初期はNagraテープ、現在はデジタル機材全般 |
| Toshiya Tsunoda(角田俊也) | 日本のサウンドアーティスト。コンテナや街中の微細音を録音。代表作:Extract from Field Recording Archive | DATレコーダー、コンデンサマイク、接触マイク |
| Francisco López | 世界各地で環境音を無加工〜加工して作品化。代表作:La Selva | DATレコーダー(初期)、現在はSound Devices系、Schoepsマイク |
| Annea Lockwood | 自然と環境をテーマにした作品多数。代表作:A Sound Map of the Hudson River | フィールドレコーダー(Nagra → デジタル)、水中マイク(Hydrophone) |
| Ryuichi Sakamoto(坂本龍一) | 晩年は環境音を採取し作品に反映。代表作:async | Zoom Hシリーズ、DPAマイク、水中マイク |
フィールドレコーディングを彩るアーティストの逸話
Alan Lomax
-
「フィールド録音」という言葉の前に「民俗録音」を広めた人物。
-
アメリカ南部の農場で労働歌を録音する際、カメラよりも大きなリール式録音機を抱えて移動。
-
生活音(食器の音や人の笑い声)まで収録し、それを「その文化のリアリティ」とした。
Annea Lockwood
-
「川のサウンドマップ」シリーズは、科学調査のように徹底的にフィールドを歩き回って記録。
-
長時間録音のため、録音機材の電源や耐候性を工夫しながら制作。
-
作品を聞くと「地理的移動を耳で旅する」体験が得られる。
Hildegard Westerkamp
-
サウンドウォークのワークショップでは「今聞こえている音に耳を澄ませてください」と案内。
-
都市騒音を「騒がしいゴミ」ではなく「現代都市の詩」として捉え直す思想を広めた。
Toshiya Tsunoda
-
音の存在を「空間の共鳴」としてとらえる。
-
例:道路のアスファルト下の空洞にマイクを設置し、微細な振動を記録。
-
科学実験のような手法だが、その結果は美的体験へと変換される。
Francisco López
-
聴衆に「アイマスク」を配り、真っ暗闇で音を聴かせるパフォーマンスを行う。
-
「音楽と環境音の境界を消す」ことを目指す。
-
作品『La Selva』では熱帯雨林をそのまま録音し、編集も最小限に留めた。
Chris Watson
-
バンド時代は電子音楽を探求。その後BBCに所属し、自然番組の録音を担当。
-
『El Tren Fantasma』では廃線の鉄道を旅し、列車の走行音と風景音を緻密に収録。
-
鳥類録音では、野生のハヤブサの巣近くで数日間動かずに待機した逸話が残っている。
Bernie Krause
-
元はThe ByrdsやDoorsとも関わったシンセ奏者。
-
その後、自然録音に転向。
-
「自然界の合唱団(Biophony)」という概念を提案し、環境保護のために録音を活用。
Ryuichi Sakamoto
-
晩年の作品では「音楽は環境と切り離せない」という思想を明確化。
-
2011年以降、東日本大震災の現地音も記録し、環境音への関心を深めた。
-
『async』では「時間の断片を残すための音楽」と語った。
各アーティストと機材の逸話
Alan LomaxとAmpex
-
1950年代のAmpexは非常に大型で重量も数十kg。
-
Lomaxはこれを車ごと移動スタジオにして録音。
-
電源の確保が最大の課題で、発電機を使用。
Chris WatsonとNagra / Sound Devices
-
「Nagraが動かなくなったのを見たことがない」と語るほど信頼。
-
鳥や動物の録音では超指向性マイク(Sennheiser MKH 416/816)を愛用。
-
砂漠で機材を砂から守るために「防水袋+砂よけ布」を自作。
Bernie KrauseのNagra
-
初期の自然録音で背負ったバッテリーは10kg以上。
-
「疲労よりも録り逃すことの方が恐怖」と語った。
-
その後DATレコーダーや軽量機材の普及で活動が飛躍的に効率化。
Francisco LópezのDAT
-
DATレコーダーは高音質で人気だが、湿気に弱かった。
-
熱帯雨林でカビによりテープが劣化、収録が失敗することも。
-
Lópezは「自然環境に機材を預ける」という発想で挑戦。
Toshiya TsunodaのDIYマイク
-
空間そのものの振動を録るため、センサーやコンタクトマイクを自作。
-
「音を聴く」のではなく「空気と物体の共鳴を測る」という発想。
-
市販機材の「想定外の使い方」を常に試みている。
Ryuichi Sakamotoと日常機材
-
晩年はポケットサイズのZoom H2nやSony PCMレコーダーを常に携帯。
-
街の雑踏、雨音、電車の音などをそのまま素材化。
-
「生活と作品をつなぐための道具」として機材を扱った。
フィールドレコーディング史と代表アルバム
| 年代 | アーティスト | 代表アルバム | コメント | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1950s–1960s | Alan Lomax | *The Alan Lomax Collection | 20世紀中葉の民俗録音を体系化。録音機材はAmpex/Nagra。フィールドレコーディングの礎。 | Amazon |
| 1980s | Annea Lockwood | A Sound Map of the Hudson River (1989) | ハドソン川を「音」で地図化。アコースティック・エコロジーの先駆的作品。 | Amazon |
| 1990s | Hildegard Westerkamp | Transformations (1996) | サウンドウォーク理論を作品化。都市・自然のリスニングを体験化。 | archive.org |
| 1990s | Toshiya Tsunoda(角田俊也) | Extract from Field Recording Archive (1997–2001) | 港湾や街中の微細音を緻密に記録。日本のフィールド録音を国際水準へ。 | archive.org |
| 1990s | Francisco López | La Selva (1998) | コスタリカ熱帯雨林をそのまま音楽作品化。世界のサウンドスケープ研究に衝撃。 | Amazon |
| 2010s | Chris Watson | El Tren Fantasma (2011) | メキシコ鉄道の旅を「音で追体験」させるBBC制作の傑作。 | Amazon |
| 2010s | Bernie Krause | The Great Animal Orchestra (2012) | 自然音を「交響楽」として提示。バイオフォニクスの理論的裏付け。 | YouTube |
| 2010s | Ryuichi Sakamoto(坂本龍一) | async (2017) | 環境音と電子音が融合する晩年の到達点。都市の音を詩的に再構成。 | Amazon |
フィールドレコーディングの現在と未来
フィールドレコーディングは単なる技術ではなく「音の記憶」を作る行為です。高性能なポータブル機器の普及とデジタル・アーカイブ技術の進展により、誰でも高品質な現場録音を行える時代になりました。一方で、倫理(被写体の同意、文化的帰属)や保存フォーマットの選択といった課題も残ります。フィールド録音を趣味や仕事に取り入れるなら、まずは信頼できる機材で現場に出ること、そして記録した音を正しく管理・共有するワークフローを作ることをおすすめします。
YouTube Podcast
※このPodcastは英語ですが、自動字幕・翻訳で視聴できます
関連コラム
🔗 【コラム】 David Toopとジャンルレスな音楽思考 ― 年代別にたどる音の探究
🔗 【コラム】 アンビエント:「聴く音楽」から「感じる音楽」へII