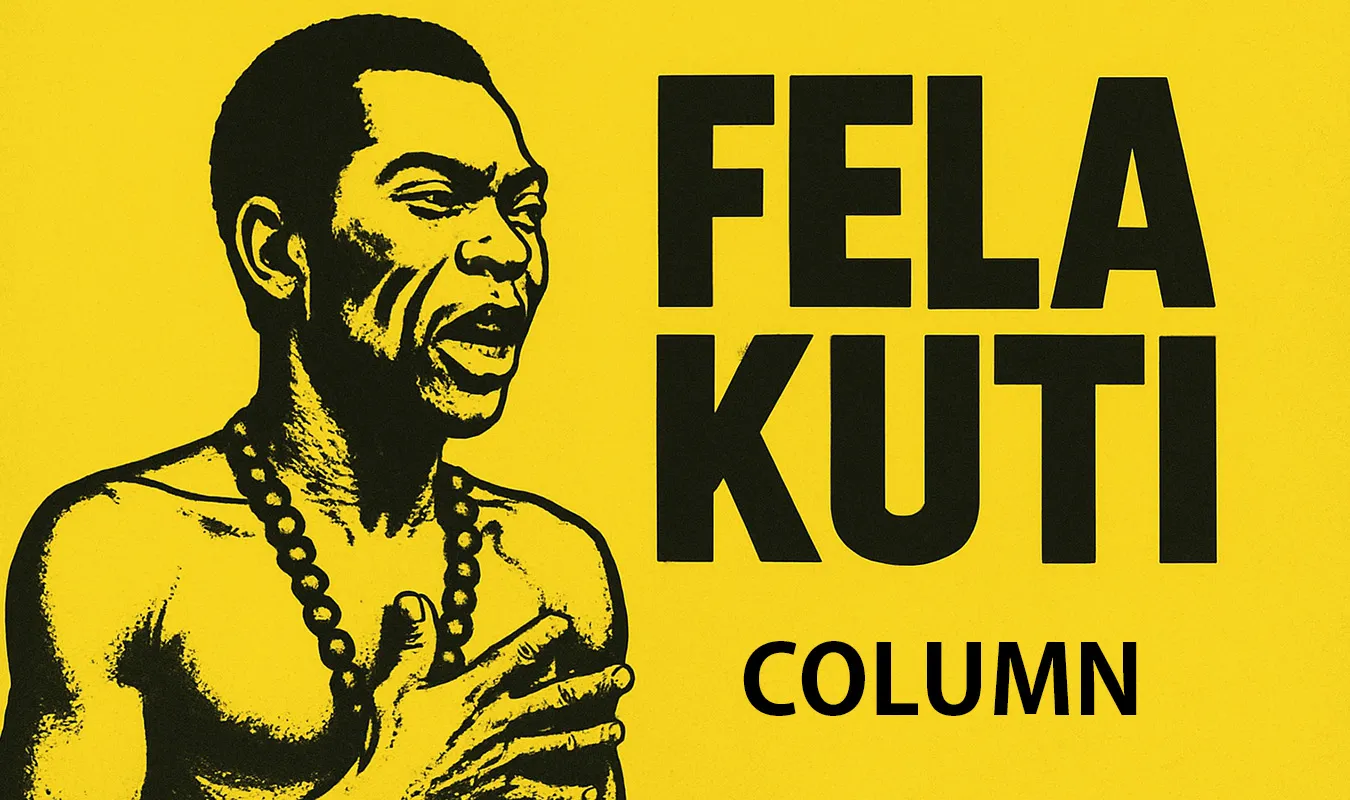
アフリカ音楽の巨人──フェラ・クティとは誰か
文:mmr|テーマ:フェラ・クティ(Fela Kuti)の生涯と音楽
フェラ・アニクラポ・クティ(Fela Aníkúlápó Kútì, 1938–1997)は、ナイジェリア出身の音楽家、活動家、そしてアフロビートの創始者です。ジャズ、ファンク、ハイライフ、ヨルバ音楽を融合させた独自のサウンドは、20世紀後半の世界音楽に計り知れない影響を与えました。
彼の音楽は単なるエンターテインメントではなく、軍政や不正を告発する「政治的声明」であり、数々の逮捕や暴力にも屈しない抵抗の象徴でした。
生涯と音楽的変遷
Fela Aníkúlápó Kútì は1938年にアベオクタで生まれ、ロンドンで音楽教育を受けた後、1960年代後半にナイジェリアへ戻り、ブルース/ジャズ/ファンク/ハイライフと伝統リズムを結びつけて独自の音楽言語を築いた。1960年代のKoola Lobitos期、1970年代にAfrica ’70で政治性を強め、後にEgypt 80などの編成へと発展していった。
Felaの音楽は、長尺(10分〜30分)の反復的グルーヴ、力強いホーン・セクション、ポリリズム、そしてピジン英語による直接的なメッセージで特徴づけられる。ドラマーのトニー・アレンはアフロビート形成に不可欠な存在であり、彼のドラムはジャンルの基礎を作った。
政治・カルチャーとしての活動
フェラは自身の邸宅を「Kalakuta Republic(カラクトゥ共和国)」と宣言し、共同体、スタジオ、劇場的空間として運営。軍政への痛烈な批判が繰り返され、警察や軍による襲撃や拘束、拷問エピソードも多く残る(有名な事件の一つが“Expensive Shit”の逸話)。これらの闘争的な姿勢が彼をナイジェリアの「声なき者の声(voice of the voiceless)」にした一方、肉体的代償も伴った。
代表的な時代区分と音楽的ハイライト
ロンドン期→米録音→Africa ’70での確立→1970年代中盤の政治的ピーク→80年代以降の活動と弾圧を経て1997年に没(死因は合併症/エイズ関連と報告される)。
関わったバンド・プロデュース/周辺の人物
Koola Lobitos(初期)→ Africa ’70(最も象徴的な編成)→ Egypt 80(80年以降の編成)。各期でメンバーが入れ替わりつつも、ホーン隊・コーラス・リズム隊の大所帯編成が特徴。
トニー・アレン(Tony Allen):共同でアフロビートのリズムを構築したドラマー。彼の死(2020年)はジャンルにとって大きな損失だったが、アフロビートの核は残る。
逸話・伝説
“Expensive Shit” の事件:警察が逮捕の口実としてマリファナ(ジョイント)を仕掛けたとされる事件を、フェラは逆手にとって曲にした(アルバム『Expensive Shit』)。この物語はフェラの反体制的イメージを象徴する逸話として語り継がれる。
Kalakuta襲撃と母の死:Kalakutaが軍に襲撃された際、フェラの母が被害を受けたとされる事件は、後の楽曲や活動の原動力にもなった。
年代別フェラ・クティのアルバム解説
1960年代:Koola Lobitos期
- 『The ’69 Los Angeles Sessions』
ロンドン留学後の初期作で、ジャズとハイライフが中心。アフロビート以前の萌芽が聴ける作品。
1970年代前半:アフロビート確立期
- 『Gentleman』(1973)
植民地主義を批判した名作。ファンク的なグルーヴに社会的メッセージが加わる。 - 『Confusion』(1975)
ラゴスの都市混乱を比喩的に描いた20分超の大曲。
1970年代後半:政治的ピーク
- 『Expensive Shit』(1975)
警察による大麻冤罪事件を逆手にとった名盤。代表曲「Water No Get Enemy」収録。 - 『Zombie』(1977)
軍を“ゾンビ”と呼び批判した挑発作。結果としてKalakuta Republicが襲撃される引き金に。 - 『Sorrow Tears and Blood』(1977)
軍による弾圧と流血を告発した強烈な楽曲。
1980年代:Egypt 80期
- 『Underground System』(1989)
長尺のリズムとホーンセクションが冴える後期代表作。 - 『Beasts of No Nation』(1989)
世界の指導者を痛烈に批判。国際的にも注目を浴びた。
1990年代:最晩年
- ライブ盤や編集盤を中心に活動。健康悪化の中でも音楽的メッセージを発信し続けた。
おすすめアルバム(購入リンク付き)
| 年代 | アルバム | 解説 | リンク |
|---|---|---|---|
| 1969 | The ‘69 Los Angeles Sessions | 初期ジャズ+ハイライフ色が強い実験作 | Amazon |
| 1973 | Gentleman | 植民地主義批判とアフロビートの完成度 | Amazon |
| 1975 | Expensive Shit | 有名な冤罪事件を逆手にとった代表作 | Amazon |
| 1977 | Zombie | 軍政を痛烈批判、結果的にKalakuta襲撃を招く | Amazon |
| 1989 | Underground System | Egypt 80期の成熟したアフロビート | Amazon |
Kalakuta襲撃の年表
アルバム『Zombie』発表
軍を“ゾンビ”呼ばわりし話題に"] B["1977-02
軍隊がKalakuta Republic(フェラの共同体兼スタジオ)を襲撃"] C["1977-02
母が建物から投げ落とされ重傷(後に死去)"] D["1977-03
フェラが棺を軍本部へ運び抗議"] E["1978-1980
その後も繰り返し逮捕・弾圧を受ける"] A --> B B --> C C --> D D --> E
フェミ・クティとスーン・クティ — 遺産を継ぐ者たち
フェミ・クティ(Femi Kuti)
1962年生まれ。フェラの長男。
ソロ作『Shoki Shoki』『Africa for Africa』などで現代的アフロビートを展開。
ジャズ要素を深化させつつ、父の政治性を受け継いでいる。
スーン・クティ(Seun Kuti)
1983年生まれ。フェラの末子。
Egypt 80を率いて父のスタイルを直接継承。
『Black Times』(2018)ではヒップホップやロックとも交差。
現在の遺産と評価
Kalakuta Museum(ラゴス):フェラの旧邸宅を博物館化。遺品・楽器が展示。
Felabration:毎年10月に開催される音楽祭。世界中からアーティストが集まり、フェラを讃える。
国際的影響:アメリカのAntibalasや、ヒップホップでのサンプリング、さらにはビヨンセやJay-Zらもフェラのリズムを引用。
まとめ
フェラ・クティは「アフロビートの父」であるだけでなく、音楽を通じた政治的抵抗の象徴でした。その遺産は、息子フェミ・クティやスーン・クティを通じて、また世界中のアーティストの作品に反映され続けています。 アフロビートを深く知りたいなら、『Gentleman』『Expensive Shit』『Zombie』の3枚から始めるのがおすすめです。
フェラの言葉とリズムは、今もラゴスの風に響き、世界のステージで鳴り響いているのです。
YouTube Podcast
※このPodcastは英語ですが、自動字幕・翻訳で視聴できます
